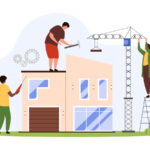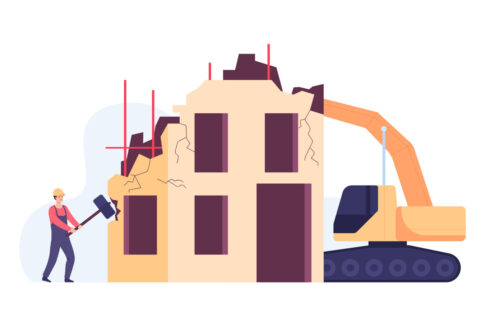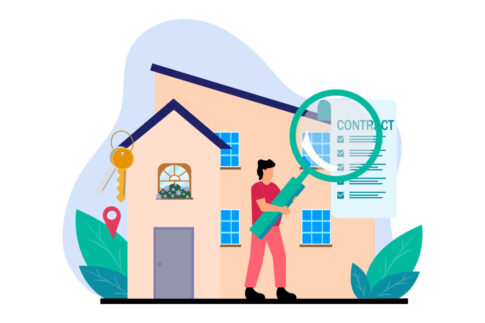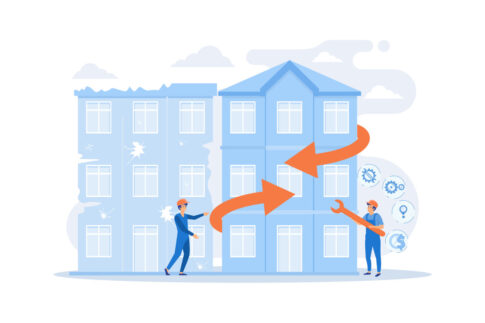再建築不可のボトルネックは“接道”。本記事では〈接道2mの有効幅〉〈法42条道路の種類〉〈幅員測定と最狭部〉〈私道の通行・掘削承諾〉を一次情報に沿って整理。
さらに〈セットバック・位置指定・持分取得・地役権・長期賃貸借・43条許可〉まで、解消策と段取りをひと目で分かる手順で解説します。
目次
まず知る|再建築不可と接道の基本
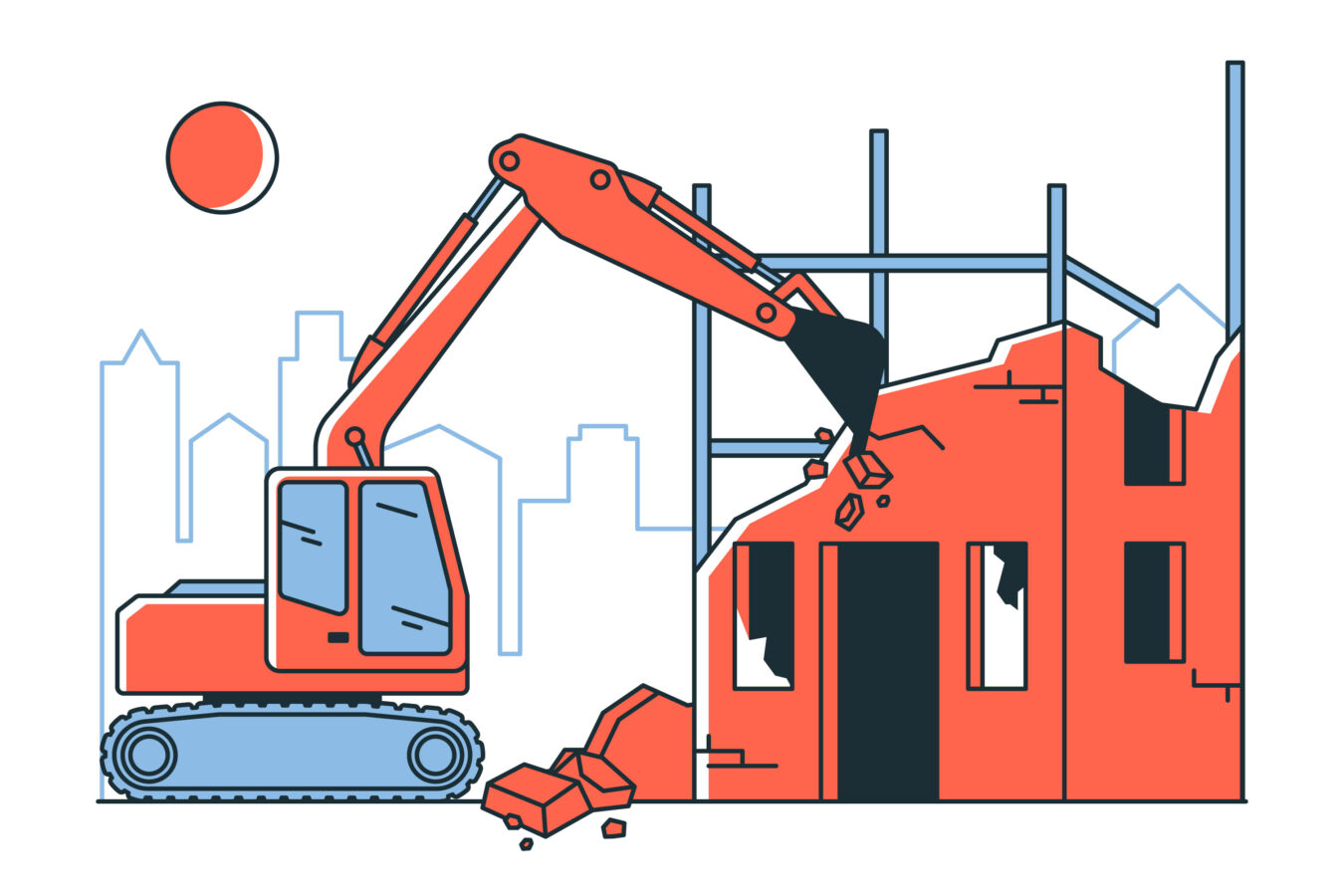
再建築不可の根っこにあるのが“接道”です。建築基準法上の道路に、敷地が有効に2m以上連続して接していないと、新築や建替えの建築確認が原則とれません。
ここで重要なのは「見えている道」ではなく「法上の道路」かどうか、そして門塀や電柱などを差し引いた“有効幅”です。
前面が狭あいで4m未満の道路(いわゆる2項道路)の場合は、中心線からのセットバックが求められることがあり、後退部分は原則として建築不可の扱いになります。
私道に面するなら、通行や掘削といった承諾の有無・範囲が工事やインフラ引込の可否を左右します。投資の観点では、接道の明確化は〈評価・融資・売却〉の三点に直結します。
最初に、道路種別・接道2m・後退要否・私道承諾・境界と最狭部を資料と実測で二重に確認し、次に、解消策(セットバック・位置指定・持分/地役権・43条許可)の成立性と費用・期間を同じ物差しで比較すると、失敗が減ります。
| 観点 | 確認すること | 影響する場面 |
|---|---|---|
| 道路種別 | 法42条のどれか、幅員、中心線 | 建替え可否・配置計画・是正方法 |
| 接道2m | 連続2mの有効幅、旗竿の路地部分 | 確認申請の前提、再販時の説明 |
| 私道承諾 | 通行・掘削・占用の書面範囲 | ライフライン更新・工事動線 |
- 「法上の道路」か→道路台帳・位置指定図などで根拠化
- “有効幅”で2mを確認→門塀・支線等を控除して最狭部を実測
- 私道は承諾の有無と範囲(通行/掘削/再掘削/工事車両)を文書で確認
接道2m要件と「有効幅」の考え方
接道2mとは、敷地が建築基準法上の道路に「連続して」2m以上接していることを指します。
旗竿地では路地状部分の全長にわたり2mを確保するのが出発点で、途中のくびれや曲がりで2mを割り込むと、連続性がないと判断されることがあります。
ここで実務上の落とし穴が“有効幅”。門柱・袖壁・塀の控え・階段・電柱・支線・消火栓ボックス・ガードレールなど、恒常的に通行を妨げる要素が幅を圧迫していないかを、最狭部で確認します。
測定は〈道路境界から直角に〉が基本ですが、現地では境界杭が欠損しているケースも多いため、道路管理者の資料(台帳・中心線)と現況測量で両面から裏取ります。
旗竿の場合は、敷地進入車両の内輪差・歩行通路の安全(段差・照度)も合わせて確認し、計画段階での支障を洗い出しておくと後戻りが減ります。
【測定と整理のコツ】
- “連続2m”を崩すくびれがないか→路地状部分は全長で2m確保が目安
- 最狭部を写真+寸法で保存→障害物は名称・位置・寸法をメモ
- 門塀・植栽・ポスト等の移設で有効幅が増えるかを検討
| ケース | 起こりがちな状況 | 初期判断・対処の方向 |
|---|---|---|
| 旗竿地 | 路地途中で1.9m程度にくびれる | 連続性が崩れる恐れ→塀の控え見直し・地役権で補正を検討 |
| 角地前面 | 電柱・支線で有効幅が不足 | 管理者に移設可否を照会、困難なら代替の接道確保を検討 |
| 門塀・階段 | 敷地側の造作で幅が不足 | 造作の切り詰め・位置変更で有効幅の回復を検討 |
- 「見かけ2mあれば足りる」は危険→最狭部の“有効幅”で判断されます
- 一部だけ2m不足でも“連続2m”を満たさない可能性があります
- 旗竿の路地はカーブや出入口の開き方でも有効幅が変わることがあります
法42条道路の種類と確認の手順
接道の可否は、まず敷地が接する道が「法42条のどの道路か」で決まります。
実務では、〈42条1項道路〉(道路法の道路、都市計画事業で築造された道路、法施行時からある幅員4m以上の道路、位置指定道路など)と、〈42条2項道路〉(幅員4m未満の既存道路で、将来4mとみなすため中心線から後退を求める道路)を区別して確認します。
次に、台帳・位置指定図・中心線・幅員証明・境界確認書等の一次資料を収集し、現地の実測(幅員・最狭部・障害物)と突き合わせ、後退線の位置や私道の権利関係(通行・掘削・占用)を整理します。
位置指定道路であれば、指定図や告示番号・指定年月日の有無が重要で、古い私道は指定図が見当たらないこともあるため、役所と管理者双方に確認を取るのが安全です。
最後に、セットバックの要否と量、後退後の有効宅地の減少、外構・排水の再設計までを一枚の図で可視化すると、関係者の合意形成が進みます。
【確認フロー(書類→現地→整理)】
- 書類収集:道路台帳、幅員証明、位置指定図・告示情報、境界・中心線資料
- 現地確認:幅員を複数点で実測、最狭部を写真+寸法で記録、障害物の位置を特定
- 整理:後退線の位置図、私道承諾(通行/掘削/占用)範囲、外構・排水の再配置案
| 道路種別 | 根拠資料の例 | 実務ポイント |
|---|---|---|
| 1項道路 | 道路台帳、幅員証明、境界確認書 | 接道2mを“連続”で満たすか、後退要否を併せて確認 |
| 位置指定道路 | 指定図・告示番号・指定年月日 | 指定範囲と実測のズレ、私道承諾の運用を把握 |
| 2項道路 | 中心線図・後退指導図 | 後退量と外構・排水の移設範囲を図示し、工程・費用を試算 |
- 「台帳・中心線・指定図」と「現況測量」を必ずセットで照合する
- 私道は承諾の常時性(通行/掘削/占用/再掘削)を文書で整理する
- 後退が必要な場合は、後退後の有効宅地・外構・排水の再設計を先に描く
現地確認|幅員・最狭部・私道承諾

接道の成否は、図面だけでは判定できません。現地で「道路幅員」「最狭部の有効幅」「私道承諾(通行・掘削・占用)」を同一ルールで採寸・記録し、第三者が見ても同じ結論に至れる資料を作ることが第一歩です。
幅員は境界に直角で複数点を測り、最小値を“最狭部”として寸法入り写真で保存します。有効幅とは、門柱・袖壁・階段・電柱・支線・消火栓ボックス・植栽の張り出しなど恒常的な障害を控除した値です。
旗竿地では、路地状部分の“連続2m”の確保が焦点になるため、カーブ・くびれ・門扉の開閉方向まで確認します。
私道に面する場合は、通行・掘削・占用・再掘削・工事車両進入の可否を所有者・管理者と擦り合わせ、書面化の見込みを同時に整理します。
これらを「台帳・中心線・位置指定図」+「現地実測(採寸表・スケッチ)」+「寸法入り写真台帳」+「承諾書案」に束ねると、役所協議・見積・融資・売却説明が一気に進みます。
| 確認項目 | チェック内容 | 資料化のコツ |
|---|---|---|
| 道路幅員 | 中心線有無、複数点の直角測定 | 測点を図示、幅員証明と値の整合を取る |
| 最狭部 | 障害物の位置・寸法・恒常性 | 寸法入り写真、障害名と距離をキャプション化 |
| 私道承諾 | 通行/掘削/占用/再掘削・工事車両 | 条項雛形を添えて面談、可否と条件を議事録化 |
- 昼夜で撮影→夜間照度と段差の見落としを防ぐ
- 最狭部は“有効幅”で判定→障害物を控除した値を採用
- 写真名=測点番号に統一→図面・採寸表と突合しやすくする
幅員測定と最狭部の寸法をそろえる
幅員・最狭部の数字は、同じ採寸ルールで取らないと比較・説明ができません。基本は〈境界に直角で測る〉〈複数点で測る〉〈最小値を“最狭部”とし寸法入り写真で保存〉の三本立てです。
まず、道路台帳・中心線図・境界確認書(または境界標)で“どこからどこまでが道路か”を先に確定します。境界杭が欠損している場合は、管理者へ示方依頼を行い、暫定測線は必ず“仮”と明記します。
次に、直線・曲線・交差点寄り・敷地正面など少なくとも数点を選び、レーザー+メジャーの二重測定で値を確定。
障害物(門柱・袖壁・花壇・階段・電柱・支線・消火栓等)は位置と寸法を採寸し、有効幅=幾何学的幅員−障害控除として計算します。
旗竿地では路地状通路の全長にわたって“連続2m”を満たすかが焦点です。曲がり角の内側で2m割れしやすいため、内外壁の控え、門扉の開閉方向、ポール・植栽の根鉢の張り出しまで確認しておきます。
最後に、測点番号をスケッチに落とし、各写真のファイル名に番号・方位・寸法を付し、採寸表と突合できるよう整えると、役所・金融・買主いずれの説明もスムーズになります。
【採寸をそろえる手順】
- 前提整備→台帳・中心線・境界の把握(境界不明時は“仮測線”表記)
- 幅員測定→境界に直角・複数点・レーザーとメジャーで二重測定
- 最狭部特定→障害物の名称・寸法・恒常性を確認し、有効幅で記録
- 資料統合→スケッチ(測点番号)+採寸表+寸法入り写真台帳で一体管理
| よくある狭窄 | 典型パターン | 対処の方向性 |
|---|---|---|
| 敷地側の造作 | 門柱・袖壁・階段が張り出す | 切り詰め・位置変更で有効幅を回復 |
| インフラ設備 | 電柱・支線・消火栓・分電盤 | 管理者に移設照会、不可なら接道解消策へ切替え |
| 路地状通路 | カーブや曲折部で2m割れ | 内側控え・曲率補正・通路形状の見直し |
- 斜め測定は不可→必ず境界に直角で測る
- 勾配・段差でメジャーが浮くと誤差→レーザーで補正し二重確認
- “一部だけ2m未満”でも連続2mが崩れれば不適合になり得る
私道の通行・掘削承諾を書面化する
私道に面する物件では、接道の判定だけでなく「通行・掘削・占用・再掘削・工事車両進入」の権利を、合意者・範囲・期間・復旧方法まで含めて文書化することが不可欠です。
まず、私道の権利関係(所有者・共有者・管理者)を把握し、連絡先一覧を作成します。次に、計画の骨子(通路幅員・延長・勾配・段差・夜間照度・車両の種類・配管ルート・復旧仕様)を1枚図にまとめ、承諾に必要な論点を先回りで提示します。
合意書の条項は、通行範囲(幅・延長・時間帯)、車両通行(工事車両・緊急車を含む)、掘削・再掘削(上下水・ガス・電気等の敷設/更新)、占用期間と対価、舗装・側溝の復旧基準、損害賠償と保険、維持管理の責任分担、承継(所有者が変わっても効力維持)、期間更新・解約、紛争解決の方法までを最低限セットにします。
対抗要件を確保するためには、可能であれば地役権設定や長期賃貸借の登記に格上げすると、金融機関や買主への説明が安定します。
面談記録は議事録化し、誰が・どの範囲を・いつまでに承諾するのかを明確化。承諾が“通行のみ”で終わると、将来の配管更新で行き詰るため、必ず掘削・再掘削・工事車両についても条文化してください。
【承諾取得の進め方】
- 当事者洗い出し→所有者・共有者・管理者の一覧と連絡経路を作成
- 提案資料→通路図(幅員・延長・勾配・照度)と配管ルート・復旧仕様を1枚化
- 条項ひな形→通行/掘削/再掘削/工事車両/復旧/承継/期間更新を明文化
- 対抗要件→地役権・長期賃貸借の登記で恒久性を担保(可能であれば)
| 条項 | 押さえるポイント | 資料の添付例 |
|---|---|---|
| 通行範囲 | 幅・延長・時間帯・歩車区分の明示 | 通路平面図、夜間写真(照度付き) |
| 掘削・再掘削 | 配管種別、更新時の手順・通知期限 | 配管系統図、復旧仕様書 |
| 復旧・維持管理 | 舗装/側溝の復旧基準、費用負担 | 舗装断面図、標準単価表 |
| 承継・期間 | 所有者変更後も効力維持、更新・解約 | 登記事項証明書、ひな形合意書 |
- “1枚図+条項ひな形”を先に提示→合意論点を可視化する
- 復旧は写真基準(Before/After)を契約に添付→齟齬を防ぐ
- 通行だけでなく掘削・再掘削・工事車両まで範囲を拡張して合意
解消策|接道を満たす現実的ルート

接道を満たすための現実的なルートは、大きく〈セットバックで有効幅を確保〉〈位置指定道路で私道を“法上の道路”へ昇格〉〈私道や隣地の持分を取得して接道2mを連続化〉〈地役権・長期賃貸借で通路権原を恒久化〉〈43条但し書き許可で個別審査〉の五系統に整理できます。
どれを選ぶかは、道路種別・不足幅・関係者数・費用/期間・金融機関評価のバランスで決まります。
まず現況測量と台帳類で〈中心線・境界・後退線・最狭部〉を確定し、次に権利(通行/掘削/占用/再掘削)の“将来の安定性”を書面化できるかを検討します。
工程は「図と数量→当事者合意→登記→必要なら舗装・排水整備」の順で進めると手戻りが減ります。
| ルート | 成立条件の要点 | 期間/費用・評価の傾向 |
|---|---|---|
| セットバック | 中心線と後退量の確定、外構・排水の移設合意 | 中コスト・中期間/後退後の評価は段階的に改善 |
| 位置指定道路 | 幅員・排水・転回等の基準適合、関係者同意 | 高コスト・長期間/評価改善が大きい |
| 持分取得 | 分筆・売買合意、境界確定、登記 | 中〜高コスト/接道2m連続で評価安定 |
| 地役権・長期賃貸借 | 通行/掘削/車両/再掘削の条項、登記 | 低〜中コスト・短期間/条項の強さで評価が変動 |
| 43条但し書き | 通路幅員・勾配・照度・消防活動・権原の説明 | 中期間/資料次第で可否が分かれる |
- 恒久性:登記で権利と形状を担保できるか
- 実行性:関係者数・合意難度・工事可否と期間
- 金融評価:融資・売却時に“換価性”を説明しやすいか
セットバック・位置指定・持分取得
セットバックは、幅員4m未満の細街路で中心線からの後退により将来の有効幅を確保する手段です。
実務では、〈中心線・後退線の確定〉〈後退量の数量化〉〈外構・門塀・植栽・側溝の移設設計〉〈寄附採納か無償使用かの扱い〉を先に決めます。
後退部分は原則建築不可となるため、有効宅地が減ることを前提に配置計画を再設計し、排水の勾配・集水桝・舗装仕様まで図で示すと、役所協議と見積がスムーズです。
位置指定道路は、私道を基準に合わせて築造し“法上の道路”として指定を受ける重装備のルートです。
幅員(多くは4m以上)・排水・転回広場・路盤・構造など標準仕様に適合させ、関係者(所有者・通行人)との同意、築造後の維持管理ルールまで文書化します。
費用と期間は大きい一方で、金融や売却の評価はもっとも改善しやすい選択肢です。持分取得は、接道2mの“連続性”があと少し足りない旗竿地や袋地で有効です。
分筆登記→売買→境界復元→舗装/排水の復旧を段取り、承諾と違い将来の恒久性を所有権で担保できるのが強みです。
【段取りの実務ポイント】
- 測量→中心線・境界・後退線を同一図に統合し数量(m/㎡)を確定
- 費用内訳→測量/設計/登記/舗装・排水/外構復旧を分解して相見積
- 関係者合意→後退・寄附/無償使用、維持管理、工事動線を文書化
| 手段 | 主な作業 | 留意点 |
|---|---|---|
| セットバック | 後退線確定、外構撤去、舗装・側溝設置 | 有効宅地減と排水計画の整合、寄附/無償使用の選択 |
| 位置指定道路 | 設計協議、築造、告示、管理規約整備 | 高コスト・長期化の想定、維持管理体制の明確化 |
| 持分取得 | 分筆・売買、境界復元、復旧工事 | 価格合意と工事範囲の特定、接道2mの連続性確認 |
- “1枚図”に中心線・後退線・復旧範囲・数量を集約し全員で共有
- 外構復旧は写真基準(Before/After)を契約書に添付
地役権・長期賃貸借・43条許可の要点
地役権は、他人地を通行する権利を登記で恒久化する方法です。
実務では〈通行幅員・延長〉〈車両通行の可否〉〈掘削・再掘削の可否〉〈工事車両の一時占用〉〈夜間照度・安全配慮〉〈維持管理と復旧責任〉〈承継(所有者が変わっても効力維持)〉を条項として明文化し、地役権図面とともに登記します。
長期賃貸借は、用地を借りて通路利用する手段で、初期費用を抑えつつスピードを確保できますが、更新・解約・承継・賃料改定・掘削/車両の可否を契約で強固にしておかないと、金融評価が安定しません。
いずれも「通行はOKだが掘削はNG」といった限定条件が多いため、上下水やガスの引込・更新計画と整合させることが肝心です。
43条但し書き許可は、法上の道路に2m接していなくても、安全・防災・衛生上支障がないと認めれば建築を認める個別審査の枠組みです。
通路の有効幅・距離・勾配・段差・夜間照度、消防活動(ホース延長・梯子設置)、通行権原(契約・登記)の恒久性、近隣影響などを、図面・写真・同意書で説明します。
許可は「資料の粒度」で可否が大きく分かれるため、事前相談→必要書式の確認→通行経路の実測→承諾原本の取得→避難・防火の説明図作成、の順で詰めると通過率が上がります。
【比較表(権利整備と許可のちがい)】
| 手段 | 強み | 弱み/注意点 |
|---|---|---|
| 地役権 | 登記で恒久化しやすい/掘削・車両通行を条項化可 | 設定交渉が難航しやすい/条項の甘さは金融評価が不安定 |
| 長期賃貸借 | 初期費用が抑えやすい/スピーディ | 更新・解約・承継の条項次第で安定性が左右 |
| 43条許可 | 短期で打開できる余地/工事計画に直結 | 資料と運用基準に左右/条件付き許可や不許可のリスク |
- 「通行のみ」の合意は配管更新で行き詰る→掘削・再掘削・車両を必ず条文化
- 賃貸借は対抗要件(登記または引渡し)と承継条項を整備
- 43条は夜間照度・勾配・段差など“現場の数値”を写真と併記して示す
影響と判断|評価・融資・売却への波及

接道の充足度は、評価・融資・売却の三領域にそのまま波及します。
評価では「建替え可能性」「配置計画の自由度」「将来の是正コスト(後退・承諾・舗装/排水)」が価格の芯になり、融資では「換価性(売り切れる見込み)」と「法令適合(接道2m・道路種別・私道承諾)」が与信の前提となります。
売却では、買主の裾野が“実需+金融利用層”まで広がるか、それとも“現金+専門家”に狭まるかが、接道の明快さで決まります。
したがって現地では、最狭部の有効幅・台帳上の道路種別・中心線/後退線・私道の通行/掘削承諾・境界の確実性を同一フォーマットで可視化し、是正案(セットバック・地役権・持分取得・位置指定・43条許可)の費用と工程を表に並べます。
資料が揃えば、評価は下振れしづらく、融資は比較対象として検討土俵に乗り、売却は説明負荷が下がりスピードが上がります。
| 領域 | 接道が効くポイント | 実務の打ち手 |
|---|---|---|
| 評価 | 建替え可否・配置自由度・是正コスト | 後退量・承諾の有無・復旧範囲を数量で提示 |
| 融資 | 換価性・法令適合・権利の安定性 | 道路台帳・測量・承諾書・工程表をセット化 |
| 売却 | 買主層の広さ・説明負荷・指値幅 | 是正案つき募集(費用帯/工期)で不確実性を圧縮 |
- 道路台帳+中心線/後退線の図示(図番・更新日付き)
- 最狭部の寸法入り写真台帳(障害物名・位置・寸法)
- 是正案の費用帯・工程・合意ルート(誰と、何の同意を)
換価性とローン審査で見られる点
金融機関は「返済能力」に加えて「換価性(売れる見込み)」を重視します。再建築不可でも、接道の論点が資料でクリアなら、審査は“検討に値する案件”として扱われやすくなります。
具体的に見られるのは、①法42条の道路種別と接道2mの連続性、②最狭部の“有効幅”と障害物の恒常性、③私道の通行/掘削/占用/再掘削の承諾(将来の配管更新が可能か)、④後退量・復旧範囲・排水計画など是正コストの見通し、⑤出口(売却・賃貸・是正後の再評価)まで含む説明の一貫性、の5点です。
ここが曖昧だと、LTVは下がり、審査時間が延び、条件が厳しくなる傾向があります。逆に、中心線図と測量、寸法入り写真、承諾書案、工程と費用帯をひとまとめにした“評価パック”を提出できれば、換価性の説明が短時間で通ります。
【審査で効く提示順(短時間で通す型)】
- 前提:道路種別・接道2m・最狭部の有効幅(写真+寸法)
- 権利:私道の通行/掘削/占用/再掘削の承諾可否と条項案
- 是正:後退量・復旧範囲・排水仕様・費用帯・工程(誰の合意が必要か)
- 出口:売却/賃貸/是正後の再評価の収支スケッチ(保守的前提で)
| 審査観点 | チェックされる中身 | 資料化のヒント |
|---|---|---|
| 法令適合 | 42条区分、接道2m連続、後退要否 | 台帳・中心線図・後退線を1枚図に統合 |
| 権利安定 | 通行/掘削/占用/再掘削の権利 | 承諾書案(条項)と関係者一覧・連絡ルート |
| 是正コスト | 外構・舗装・排水・寄附/無償使用 | 数量表(m・㎡)と写真基準、相見積の幅 |
| 出口設計 | 売却/賃貸/是正後の再評価 | 収支表(感度:単価±・工期±)を添付 |
- 「通行のみ承諾」で止まる例が多い→掘削/再掘削/工事車両まで条文化
- “見かけ2m”は不可→最狭部の有効幅(障害物控除後)で説明
- 後退は“量と復旧範囲”を数量で提示→写真だけだと費用根拠が弱い
隣地売却・一部譲渡の判断基準
接道を満たせない、是正の合意が難しい、費用対効果が合わない――そんなときは「隣地売却・一部譲渡」が選択肢になります。
判断の軸は、①相手側の便益(建替え可になる/配置自由度が増す/駐車が可能になる等)の大きさ、②こちら側の残地に与える影響(有効宅地の減少・動線・排水・外構や門塀の再設計)、③手続の難度(分筆・地役権・後退・私道承諾・境界復元)、④時間価値(保有コスト・税・機会損失)の4つです。
実務では、現況測量→筆界確認→越境の是正→復旧範囲(塀・舗装・排水・植栽)の図示→費用分担と工程の合意、という順に進めます。
価格は“相手の便益”を数値化し、復旧コストとセットで対比表に落とすと合意が前進します。
【判断を早める比較表(例)】
| 観点 | 隣地売却(一括) | 一部譲渡(分筆/地役権) |
|---|---|---|
| 便益の大きさ | 接道2m確保・建替え可で上振れ大 | 通路幅の連続化・動線改善で中〜大 |
| 手続/期間 | 売買のみで比較的シンプル | 分筆・地役権・復旧合意で中〜長期 |
| 残地への影響 | 残地ゼロ→出口確定 | 有効宅地減・外構/排水の再設計が必要 |
| 価格の決め方 | 相場±是正不要の上振れ | 相手の便益−復旧費(+当方の機会費用) |
- “1枚図”で境界・後退・復旧範囲・数量(m・㎡)を共有する
- 復旧仕様は写真基準(Before/After)を契約書に添付する
- 代替案(通行地役権のみ・賃貸借による通路設定)も同時提示する
資料と段取り|失敗しない進め方

接道の可否や解消策は、最初の資料整備と段取りで勝負が決まります。ポイントは、〈同じルールで測る〉〈一次資料で裏付ける〉〈第三者が追認できる形で残す〉の3つです。
まず、道路台帳・中心線・位置指定図・幅員証明・境界確認書と、現地の採寸(幅員・最狭部の有効幅)・寸法入り写真をワンセット化します。
次に、私道の場合は通行・掘削・占用・再掘削・工事車両の承諾の可否と条件を確認し、合意の見込みをメモ化します。
最後に、後退量・復旧範囲・排水勾配などの数量を表計算に落とし込み、是正案(セットバック・位置指定・持分取得・地役権・43条許可)ごとに費用帯と工程を横並び比較にします。
資料は「図番・更新日・担当・撮影位置・寸法」の5点を必ず記載し、PDFと紙で二重保存。これだけで、役所協議・見積取得・金融機関への説明・売却時の開示まで一気通貫で進めやすくなります。
| 資料群 | 中身 | 管理のコツ |
|---|---|---|
| 道路関係 | 道路台帳・中心線図・幅員証明・位置指定図 | 図番・作成年月・担当課を明記→更新日を表紙に記入 |
| 現地実測 | 幅員複数点の値・最狭部の寸法入り写真 | 測点番号をスケッチに落とし、写真名に番号を付す |
| 権利関係 | 通行/掘削/占用/再掘削・工事車両の承諾 | 条項案の雛形を添付し、可否と条件をメモ |
- 同一フォーマットで採寸・撮影→ばらつきを無くす
- 一次資料で裏取り→図番・更新日・担当を必ず記録
- 是正案は数量・費用・工程を横並びで比較する
道路台帳・測量・承諾の揃え方
道路台帳・測量・承諾は、順番と粒度をそろえるだけで進み方が変わります。最初に「道路側の一次資料」を揃えます。
道路台帳で道路種別を特定し、中心線の有無・幅員証明・位置指定図(告示番号・指定日)を取得。
次に「現地側の実測」を行い、境界杭の有無を確認しつつ、境界に直角に幅員を複数点測定、最狭部の有効幅を寸法入り写真で保存します。
旗竿地は路地状通路の全長で“連続2m”を満たすかを通しで確認し、カーブ・門扉・袖壁の控えで割り込まないかを点検します。
最後に「私道の承諾」を精査します。通行・掘削・占用・再掘削に加え、工事車両の一時占用や舗装復旧の責任分担、承継条項(所有者が変わっても有効)を雛形条項に落とし、可否と条件を一覧化。
可能なら、通行地役権設定や長期賃貸借で権利を登記に格上げし、将来の換価性説明を安定させます。
【収集→実測→承諾の実務フロー】
- 収集:道路台帳・中心線・幅員証明・位置指定図(あれば告示番号)を取得
- 実測:幅員を複数点で直角測定、最狭部を写真+寸法で保存(障害物名も記載)
- 承諾:通行/掘削/占用/再掘削/工事車両の可否をヒアリング→条項案に整理
| ドキュメント | チェックポイント | 不備時の対処 |
|---|---|---|
| 道路台帳・中心線 | 道路種別・幅員・中心線の位置 | 管理者へ照会し、幅員証明・指導図の写しを追加取得 |
| 現況測量図 | 境界標・筆界・最狭部・高低差 | 簡易測量→境界不明は立会い測量の可否を検討 |
| 承諾(私道) | 通行/掘削/占用/再掘削・工事車両の範囲 | 条項案を提示して合意形成、可否は議事録化 |
- 写真・図面・承諾を“同じID”で紐づけ→検索性を上げる
- 承諾は口頭NG→条項(掘削/再掘削/工事車両/復旧/承継)を文書化
- 境界不明の測定値は“仮”と明記し、後で差し替える前提で使う
工程・費用・リスクの見える化手順
工程・費用・リスクは、是正案ごとの「横並び表」と「クリティカルパスの図解」で可視化します。
工程は〈収集→実測→役所協議→同意形成→登記→整備〉の6段階を基本に、関係者数と役所回答に応じて余白を設定します。
費用は、測量/設計/登記/舗装・排水/外構復旧/寄附・無償使用手続といった共通項目に分解し、数量(m・㎡・本数)を母数に単価×数量で積み上げます。
リスクは、法適合(後退量確定・承諾不足)・権利(同意遅延)・工事(搬入・排水不良)・財務(資金ショート)・近隣(騒音・通行)の5分類で管理し、回避策と担当を明記。
金融機関・買主向けには、後退後の有効宅地や復旧範囲を“1枚図”で示し、費用帯と工期を表に添えれば、判断が早まります。
【横並び比較の作り方】
- 列:セットバック/位置指定/持分取得/地役権・賃貸借/43条許可
- 行:工程(週)/費用帯(万円)/合意先/権利の恒久性/金融評価への効き
- クリティカルパス:同意→登記→舗装・排水→検査、を太線で可視化
| 管理軸 | 見える化のポイント | 指標・アラート |
|---|---|---|
| 工程 | 6段階(収集→整備)で週数と依存関係を記載 | 各段階の最大許容週数、回答待ちの期限 |
| 費用 | 共通内訳で単価×数量の積上げ表に統一 | ±10〜20%の幅を設定、相見積の中央値を採用 |
| リスク | 法適合・権利・工事・財務・近隣の5分類 | 発生確率×影響度、回避策と担当・期限を記載 |
- “1枚図+横並び表”で意思決定を短時間化する
- 中間金の支払い時期=資金実行日に調整→資金ショートを防ぐ
- 是正後の写真・数量・登記事項をセットで保存→融資・売却で効く
まとめ
要点は①道路種別の確定②接道2mの実測③承諾の書面化④解消策の比較です。道路台帳→現況測量→承諾取得→費用と工程の見える化、の順で進めれば判断が速くなります。
セットバックや地役権等は根拠資料を添えて同時並行で検討。最短経路を選び、評価・融資・売却の条件改善につなげましょう。