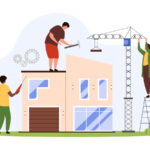再建築不可でも、救済措置を使えば建替えや価値向上の道が開けることがあります。本記事は、投資初心者向けに〈判断フロー〉と〈実務の型〉を整理。
43条2項許可、位置指定道路、通行地役権、隣地一部取得、セットバック、私道承諾の要点をやさしく解説します。費用・期間・優先順位の考え方まで俯瞰でき、買う前に何を確認すべきかが一目で分かります。
救済措置の全体像と判断フロー

再建築不可の救済は、個々の事情に応じて「法律上の例外活用」と「物理・権利の是正」を組み合わせて進めます。
代表例は、43条2項許可(ただし書許可)、位置指定道路の確認・整備、接道確保(隣地の一部取得・通行地役権の設定・セットバックの実施)、私道の通行・掘削・占用承諾の整備などです。
最短距離で結論に近づくコツは、見た目ではなく「法上の道路か」「接道2mあるか」「幅員4mを満たすか」という客観条件を先に固めることです。
そのうえで、可能なルートを洗い出し、費用と期間、合意形成の難易度、価値向上の度合いを比較します。
投資目的の場合は、救済後の活用(建替え・増改築・賃貸化・売却)まで逆算し、出口で再評価される資料(図番付きの台帳写し、測量成果、承諾書、事前相談記録)を揃えておくと意思決定がぶれません。
- 事実確認→道路種別・接道長さ・幅員・後退線の有無を役所と図面で確定。
- ルート設計→43条2項許可/位置指定/接道確保の代替案を横並び比較。
- 実行条件→承諾・合意・工程・復旧水準を文書化し、後日の根拠化を徹底。
| フェーズ | 目的 | 主なアウトプット |
|---|---|---|
| 事実確定 | 法上の道路・接道2m・幅員の確定 | 道路台帳写し、位置指定図、照会メモ、実測写真 |
| ルート選択 | 救済手段の可否と優先順位の決定 | 比較表(費用・期間・合意難度・価値向上) |
| 実行準備 | 承諾・境界・設計の整備 | 承諾書、測量成果、配置計画、復旧仕様 |
- 役所照会→図番・作成年月日・担当を必ず記録。
- 書類→現地→再照会の順で整合を取る(見た目では判断しない)。
対象可否を見極める基本ステップ
救済措置の可否は、敷地が法上の道路に接しているか、接道2mを有効幅で満たすか、前面道路の幅員が4m以上か(不足なら2項道路として後退で是正できるか)といった根本条件でおおむね決まります。
位置指定道路であれば、指定番号・図面・端部接続・有効幅が現況と一致しているか、私道なら通行・掘削・占用の承諾を文書で整えられるかが分岐点です。
43条2項許可を狙う場合も、通行経路の幅・距離・段差・視認性、消防活動上の支障有無を図面と写真で説明できるかが鍵になります。
実務では、下のステップで可否を早期に判断し、通りにくいルートは早めに撤退して、実現性の高い選択肢に資源を集中します。
- 道路の適否→42条1項か2項か、位置指定の有無を台帳で確定。
- 接道2m→門塀・設備を差し引いた有効幅で複数点実測、最小寸法を特定。
- 幅員→4m未満は中心線と後退線を確定、後退後の有効宅地を試算。
- 承諾→私道の通行・掘削・占用の可否と同意者の範囲を特定。
- 代替→隣地一部取得・通行地役権・通路新設の実現性と合意難度を比較。
| 論点 | 見るポイント | 次のアクション |
|---|---|---|
| 法上の道路 | 道路台帳・位置指定図・中心線の根拠 | 図番と作成年月日を控え、現地と照合 |
| 接道2m | 最小寸法、門塀・電柱等の障害 | 写真+寸法で可視化、移設・拡幅の可否確認 |
| 幅員4m | 最狭部の幅、2項道路の指定有無 | 後退線確定→配置・外構計画を再設計 |
| 承諾関係 | 通行/掘削/占用の要件 | 同意者の範囲と復旧水準を文書化 |
- 舗装端=境界と思い込み→台帳の境界線で裏取りが必要です。
- 「見かけの2m」で判断→有効幅の最小値で判断します。
書類整備と役所相談の進め方
救済の成否は「根拠の質」に左右されます。まず、建築指導課で法上の道路種別(42条1項・2項・位置指定)、中心線、後退線の有無を確認します。
道路管理課では道路台帳・境界・幅員と占用・掘削の取扱い、都市計画課では用途地域や道路予定線などの制限を把握します。
法務局では登記事項・公図・地積測量図を入手し、私道や地役権の有無、筆界と現況の齟齬を確認します。
相談は口頭に依存せず、図面名・図番・作成年月日・担当部署・回答要旨をメモし、写しを取得できるものはファイリングします。
これらを現地の実測写真と突合し、整合が取れない箇所は再照会か測量士・調査士への相談に進みます。
- 持参物→地番・案内図・現地写真・登記事項・公図・既存図面の写し。
- 照会メモ→図番・更新日・担当名・回答の要点を同じ書式で管理。
- ファイル化→「道路」「境界」「承諾」「配置」の4つに分類すると再利用が容易。
| 書類 | 主な内容 | 入手先・相談先 |
|---|---|---|
| 道路台帳/位置指定図 | 境界・幅員・中心線・指定番号 | 道路管理課/建築指導課 |
| 登記事項/公図/地積測量図 | 権利・筆界・寸法の根拠 | 法務局 |
| 都市計画図 | 用途・地区計画・道路予定線 | 都市計画課 |
- 「図面で話す」→口頭説明ではなく写しに書き込みながら確認。
- 不一致はその場で再照会→現地写真と図面を並べて論点を特定。
費用・期間・優先順位の考え方
救済は「通せるルート」を選ぶ戦略です。評価軸は、可否(通る/通らない)、合意難度(承諾者数・利害の複雑さ)、工期(季節・工事規制・審査時期)、総コスト(設計・測量・工事・復旧・諸経費)、価値向上(建替え可・配置改善・賃料上昇見込み)です。
はじめに“可否が高い順”に並べ、次に“価値向上が大きい順”、最後に“コスト/期間が許容内か”で絞り込みます。
金額を無理に当てにいくより、費用の“性質”を把握し、増減要因(共有者数、障害物の有無、後退長、配管距離、復旧水準、電柱移設の要否等)を洗い出すと予算ブレを抑えられます。
期間は、照会→合意→設計→申請→工事→復旧の直列工程になりやすいため、前段の役所照会と合意形成を先行させると短縮効果が大きいです。
- 優先順位→可否の高い案→価値向上が大→コスト/期間が許容内の順。
- コストの性質→固定費(設計・申請)と変動費(後退長・復旧範囲)を分けて管理。
- 工程短縮→承諾取得と役所照会を先行、復旧仕様は早期に合意。
| 項目 | コストの性質 | 期間・依存関係の例 |
|---|---|---|
| 測量・境界 | 案件の不確実性を下げる投資 | 隣地立会いに依存→早期着手で全体短縮 |
| 承諾取得 | 通行・掘削・占用の可否を左右 | 共有者数に依存→書面テンプレで並行取得 |
| セットバック/復旧 | 後退長・舗装仕様で増減 | 天候・占用物移設に依存→余裕日程を確保 |
| 電柱・配管 | 移設・引込距離で増減 | 管理者協議に依存→早期照会が有効 |
- まず可否→通らない案は深追いしない。
- 価値→建替えや配置改善でリターンが大きい案を優先。
- 期間→承諾と照会を前倒しで走らせる。
43条2項許可の基礎と自治体運用
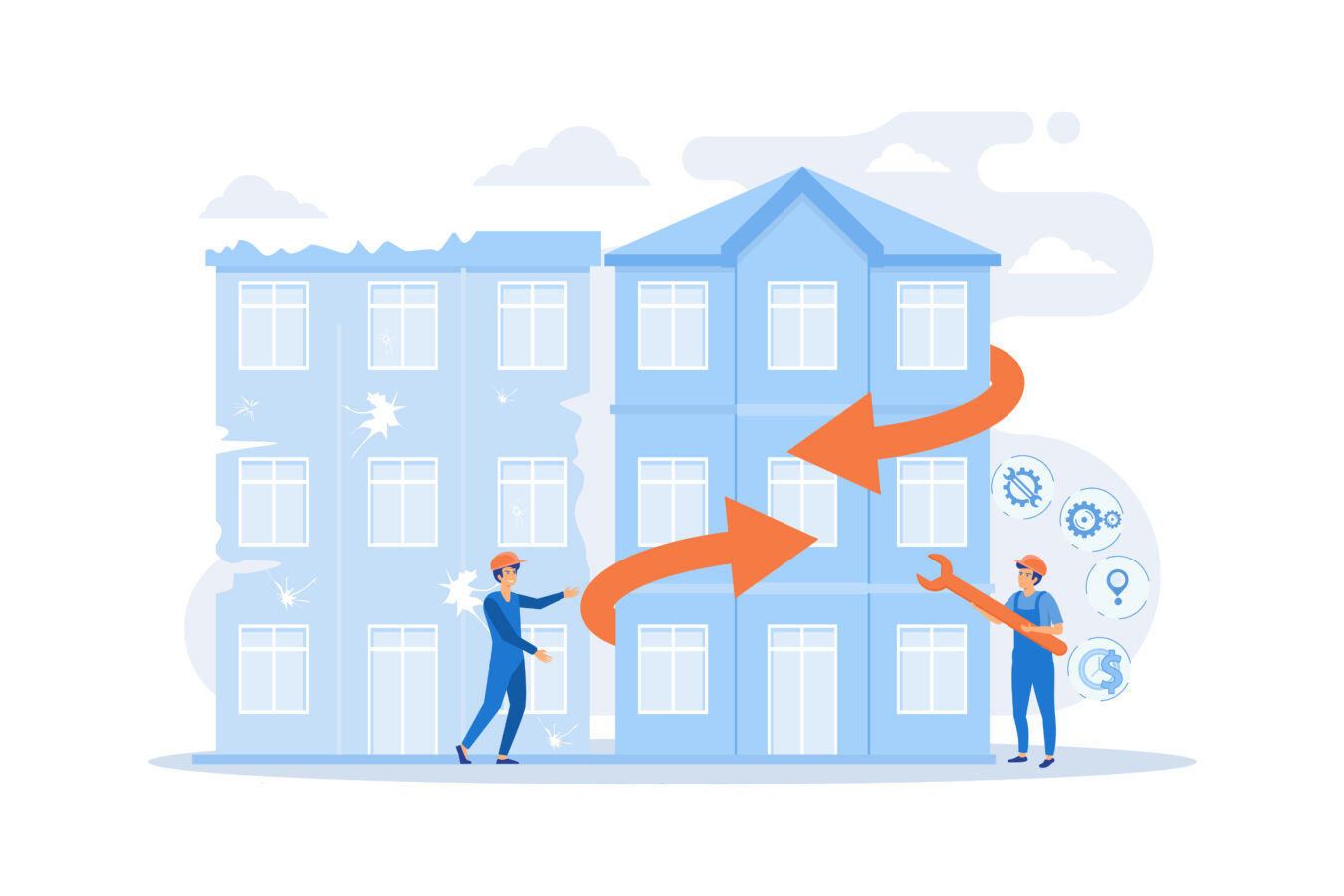
建築基準法の接道要件(原則→敷地は建築基準法上の道路に2m以上接する)を満たせない敷地でも、一定の安全・通行・防火上の配慮が確保できると特定行政庁(自治体)が例外的に建築を認める仕組みが「43条2項許可(いわゆるただし書許可)」です。
実務では、自治体が定める運用基準に沿って審査され、標準的な要件を満たすものはあらかじめ建築審査会が包括的に同意した「一括同意基準」に該当するか、あるいは個別に審査会の同意を要する「個別審査」に回るかで手続と難易度が変わります。
判断材料は、通行経路の有効幅・距離・勾配・見通し・夜間照明、避難動線と消防活動の確実性、私道の通行・掘削・占用の承諾、境界・後退線の確定などです。
まずは役所の事前相談で、想定する経路と安全対策、承諾取得の見込み、配置計画の概略を示し、適用可能性と必要資料をすり合わせます。
自治体により呼称や基準の細部が異なるため、名称ではなく「求められる実質(通行の常時性、安全上の確実性、近隣影響の低減)」で準備することが近道です。
- ポイント→名称や慣行は自治体差あり。まずは事前相談で適用可否と必要資料を確認。
- 根拠→通行の常時性・安全性・防災上の配慮を図面と写真で可視化する。
- 承諾→私道の通行/掘削/占用は口頭でなく書面化して添付する。
| 論点 | 見るべき内容 | 準備・証拠の例 |
|---|---|---|
| 通行経路 | 有効幅・距離・段差・見通し・夜間照明 | 現況測量図、写真・動画、照明計画 |
| 消防・避難 | 進入口・可搬機材搬入可否・避難動線 | 配置図、動線図、消防との協議記録 |
| 権利承諾 | 通行・掘削・占用の可否と条件 | 承諾書(範囲/期間/復旧/連絡先) |
- 適用可否は自治体運用で差→必ず事前相談で方針確認。
- 根拠は図面・写真・承諾書で可視化→口頭前提にしない。
- 安全・通行・近隣配慮をセットで提示→代替案も用意。
1号認定と2号許可の違い
実務では、43条2項の運用で「1号」「2号」という区分を用いる自治体が多く見られます(呼称は自治体により異なります)。
整理の目安として、1号は標準要件が明確に定められ、それに適合すれば建築審査会の「一括同意」対象となる類型、2号は個別の事情(経路が狭い・距離が長い・見通しが悪い・避難計画に工夫が必要等)を伴い、建築審査会で個別審査・同意を要する類型、と理解すると準備の軸がぶれません。
いずれも“特定行政庁が安全上支障なしと認めること”が前提で、通行の常時性や承諾の確実性、消防活動上の支障の有無を、図面・写真・承諾書・計画書で説明できるかが合否を分けます。
したがって、用語の違いよりも、どの観点で評価されるか(通行・安全・周辺影響)に合わせて資料を組み立てることが重要です。
- 1号(基準適合型の目安)→標準的な幅員・距離・視認性が確保され、承諾や管理方法が明確。審査は迅速になりやすい。
- 2号(個別審査型の目安)→幅・距離・勾配等に難がある、避難・消防で追加措置が必要。代替案や改善案を複数提示する。
- 共通要件→通行・安全・承諾・近隣配慮の4本柱を“証拠付き”で示す。
| 区分(目安) | 特徴 | 準備の勘所 |
|---|---|---|
| 1号認定 | 一括同意基準に適合しやすい標準ケース | 要件表への適合根拠を整理→不足は早期に是正 |
| 2号許可 | 個別事情により追加対策・同意が必要 | 安全代替策(照明・段差解消等)を図面化して提示 |
- “1号=必ず可”ではありません。自治体基準への適合と実態の一致が前提です。
- “2号=必ず不可”でもありません。代替措置と承諾の実効性で可否が動きます。
一括同意基準と個別審査
多くの自治体では、建築審査会が予め標準的な条件を承認しておく「一括同意基準」を定め、これに合致すれば審査会の都度開催を省略し、特定行政庁の許可で進められる運用があります。
一括同意基準の典型は、通行経路の有効幅・距離・段差・見通しの目安、夜間照明や鍵管理の方法、避難動線の確保、承諾書の様式や必要範囲など、客観的に再現可能な条件です。
一方、地形や敷地条件が特殊、経路が長い・狭い、避難・消防上の懸念が残る、周辺影響(騒音・プライバシー)が大きい等のケースは、審査会での「個別審査」となり、提出資料も厚くなります。重要なのは、どちらの経路でも“評価者が迷わない資料構成”にすることです。
- 一括同意基準→標準条件の充足を表形式でチェックし、裏づけ資料を紐づける。
- 個別審査→懸念点に対する代替案(照明追加・路肩整備・緊急時開放等)を複数提示。
- 共通→通行承諾は目的・期間・復旧方法・連絡先まで明記し、常時性を担保。
| 審査形態 | 想定される条件 | 資料の作り方 |
|---|---|---|
| 一括同意 | 標準的な幅員・距離・視認性、承諾の整備 | チェックリスト+該当ページ付箋付きの写し |
| 個別審査 | 特殊条件・安全配慮の追加措置が必要 | 改善案の比較表、代替経路・運用規程の提示 |
- “基準→証拠→配置図”の順でファイル化し、誰が見ても同じ結論になる構成にする。
- 写真は昼夜/晴雨を揃え、通行の実態が分かる動画リンクを用意する。
事前相談で準備する図面と証拠
事前相談は許可可否の方向性を左右します。ここで重要なのは、口頭説明ではなく“図面と証拠”で「安全・通行・承諾」を可視化することです。
まず、現況測量図(敷地・道路・高低差・障害物)と通行経路図(有効幅・距離・曲がり角・段差)を準備し、最狭部の寸法を赤字で明示します。
次に、避難・消防の観点を反映した配置図・動線図(進入口、消火活動の導線、非常時開放方法)を添付。夜間の視認性や足元の安全は、照明計画や写真・動画で示します。
権利関係は、通行・掘削・占用の承諾書案(目的・範囲・期間・復旧・費用負担・連絡先)を同封し、誰が同意すべきか(私道共有者・隣地所有者等)の一覧を付けます。
最後に、想定される指摘に対する代替案(照明追加・段差解消・路肩整備・鍵管理)を“Before/After”の図で用意すると、協議がスムーズです。
- 図面類→現況測量図、通行経路図、配置図・動線図、後退線の根拠図。
- 証拠→最狭部の実測写真、昼夜の視認性写真・動画、騒音配慮の計画。
- 承諾→通行・掘削・占用の承諾書案、同意者一覧、連絡先、想定スケジュール。
| 資料 | 目的 | 内容のポイント |
|---|---|---|
| 通行経路図 | 通行の常時性の立証 | 有効幅・距離・曲率、最狭部の明示、写真対応表 |
| 安全計画図 | 避難・消防上の配慮 | 進入口、避難ルート、照明・段差対策 |
| 承諾書案 | 法的・運用的な実効性 | 目的/期間/復旧/費用/連絡先、鍵運用規程 |
- 最狭部の寸法・位置が不明確→赤字で位置と数値を図面と写真両方に記載。
- 承諾の範囲が曖昧→誰の同意が必要かを一覧化し、目的別に書式を分ける。
位置指定道路・特定通路の活用

再建築不可の救済では、「法上の道路に接していない」「接道2mが足りない」などの弱点を、①位置指定道路(建築基準法42条1項5号)の新設・再確認、②各自治体が43条2項許可の運用で求める通路(いわゆる“特定通路”“避難通路”等と呼ばれることがある)の確保、③私道の通行・掘削・占用承諾の整備という三本柱で是正します。
実務の順番は、まず役所で道路種別・中心線・後退線の有無を確認→現況測量で通路幅・最狭部・障害物を把握→位置指定や43条運用の適用可否を事前相談→必要に応じて工事・承諾・契約で通行の常時性と安全性を担保、が効率的です。
投資の観点では、工事費や承諾取得の難易度だけでなく、救済後の配置改善・賃料上昇・出口の取りやすさまで数値化し、費用対効果で比較することが重要です。
- 位置指定道路→図面・工事・完了検査で「法上の道路化」を狙う。
- 特定通路(43条運用)→安全・通行・承諾を満たす計画で例外許可を狙う。
- 私道承諾→通行/掘削/占用を文書化し、常時性と復旧方法を明確化。
| 選択肢 | 狙い | 鍵となる資料・手当て |
|---|---|---|
| 位置指定道路 | 42条1項道路として接道を確立 | 位置指定図、工事仕様、完了検査記録 |
| 特定通路(43条) | 安全配慮で例外的に建築可 | 通行経路図、承諾書、照明・段差対策 |
| 私道承諾整備 | 通行・配管・復旧の実行性を担保 | 通行/掘削/占用承諾、管理規程 |
- 「法上の道路化」→位置指定で恒久解を優先、難しければ43条運用を検討。
- 承諾・安全・証拠を三位一体で準備→図番付き写しと写真で根拠化。
位置指定の要件と指定手順の流れ
位置指定道路は、民間の敷地内通路を、一定の技術基準と手続を満たすことで建築基準法上の道路(42条1項5号)として扱う仕組みです。
要件・手順は自治体ごとに運用差がありますが、概ね〈有効幅の確保(多くは4m基準)〉〈行き止まりの場合の転回・隅切り〉〈排水・側溝・舗装仕様の整備〉〈両端の接続や見通し〉〈電柱・工作物が有効幅を圧迫しない配置〉などが求められ、計画→事前協議→図面審査→工事→完了検査→位置指定の告示・台帳記載、という流れが一般的です。
実務では、境界確定と用地の帰属(持分/地役権/共有ルール)、維持管理の主体、将来の道路後退や占用の扱いまで先に取り決めておくと、申請・運用が安定します。
既設の通路を位置指定として“再整備”するケースでは、花壇・ポール・門扉・メーター等の移設計画と、近隣の合意形成が肝心です。
- 計画段階→現況測量図を基に中心線と有効幅、排水計画を作成。
- 協議段階→建築指導課・道路管理部局と仕様・検査項目をすり合わせ。
- 工事・検査→舗装・側溝・転回部・見通しを整備し、完了検査に合格。
| 項目 | 目安・留意点 | 実務ポイント |
|---|---|---|
| 有効幅 | 多くは4m基準(自治体差あり) | 最狭部で確保、電柱/門塀の移設可否を先行確認 |
| 排水・舗装 | 側溝・集水桝・舗装厚などを指定 | 勾配と集水位置を図面化→雨天時の写真を添付 |
| 転回・隅切り | 袋路は車両転回や隅切りを求められる | 実車軌跡を図示→内輪差を考慮 |
| 管理・承諾 | 維持管理者と占用ルールを明確化 | 協定書で通行/掘削/復旧の範囲を定義 |
- 「最狭部」を赤字で明示、日中・夜間の見通し写真を添付。
- 管理・復旧ルールを協定書で先に合意→後日のトラブルを予防。
特定通路の考え方と適用の目安
「特定通路」は法律上の正式名称ではなく、自治体の43条2項許可の運用で、避難・消防・通行の安全が確保できる経路を指す通称として用いられることがあります(呼び方は“特定通路”“避難通路”“防災通路”等さまざま)。
狙いは、法上の道路に2m以上接していない敷地でも、常時通行と安全措置が担保できるなら例外的に建築を認めることです。
適用の目安として、〈有効幅の下限(例:2m以上など自治体基準による)〉〈経路の距離と曲がり角の処理〉〈段差・勾配の緩和〉〈夜間照明や見通しの確保〉〈鍵・ゲートの運用ルール〉〈私道や隣地の承諾の実効性〉などが重視されます。
重要なのは、名称に拘らず「通行の常時性」と「安全上の確実性」を図面・写真・承諾書で立証することです。
懸念(狭窄部、路肩の欠損、見通し不良、夜間の暗さ等)がある場合は、照明追加・路肩整備・段差解消・ミラー設置などの改善案を併記し、代替通路の有無も含めて説明すると前進しやすくなります。
- 評価の柱→通行の常時性、安全対策、承諾の確実性、周辺影響の低減。
- 資料→通行経路図(最狭部を赤字)、写真・動画、照明計画、承諾書案。
- 運用差→幅や距離の目安は自治体で異なる→必ず事前相談で確認。
| 論点 | 見るポイント | 改善・証拠の例 |
|---|---|---|
| 最狭部 | 有効幅の最小値と位置 | 実測写真、障害物の移設計画 |
| 視認性 | 夜間・雨天の見通し | 照明配置図、反射材、ミラー |
| 常時性 | 鍵・ゲート・時間制限の扱い | 鍵運用規程、常時開放区間の明示 |
| 承諾 | 通行/掘削/占用の文書化 | 承諾書(目的/期間/復旧/費用) |
- 呼称に引きずられない→実質(安全・常時性)で準備し、基準は自治体で確認。
- 口頭同意のまま提出しない→承諾は目的・範囲・復旧まで明記した書面で。
私道の通行・掘削承諾の整え方
私道に依存する計画では、〈通行承諾〉〈掘削承諾〉〈占用承諾〉を分けて、必要な範囲の同意を“書面で”確保することが重要です。
通行承諾は、日常および工事中の車両・歩行者の通行可否と条件(時間帯・車両サイズ・誘導員等)を定めます。
掘削承諾は、上下水・ガス・電気等の引込や更新に伴う掘削と復旧の方法・費用負担を明確にします。占用承諾は、仮設足場・資材置場・後退部分の復旧など“占用状態”を一時的に認める合意です。
共有私道では全共有者の同意が必要になる場合が多く、連絡先の把握と説明資料(配置図・通行経路図・工期・復旧仕様・保険証書)の同封が有効です。
承諾の実効性を高めるため、目的・範囲・期間・復旧・費用負担・損害賠償・連絡窓口を明記し、図面と写真を添付して「どこを・どの程度」使うのかを可視化します。
- 通行承諾→日常・工事時の通行条件(時間帯・車種・誘導)を明文化。
- 掘削承諾→配管経路・掘削幅・復旧仕様・費用負担を合意。
- 占用承諾→足場・資材・後退復旧などの占用位置と期間を特定。
| 承諾の種類 | 主な内容 | 添付・根拠資料 |
|---|---|---|
| 通行承諾 | 常時通行/工事通行の条件 | 通行経路図、時間帯表、誘導計画 |
| 掘削承諾 | 上下水・ガス・電気の掘削と復旧 | 配管図、復旧仕様、工期、保険証書 |
| 占用承諾 | 足場・資材置場・後退復旧 | 占用位置図、期間、写真付き復旧計画 |
- 目的/範囲/期間/復旧/費用/賠償/連絡先→抜けなく明記する。
- 図面・写真を添付→位置・幅・長さ・最狭部を赤字で示す。
接道確保の実務策(隣地・地役権・後退)

接道を確保する実務は、大きく「物理策(隣地の一部取得・通路新設・セットバック)」と「権利策(通行地役権・私道承諾の整備)」の組合せで進めます。
まずは役所で道路種別(42条1項・2項・位置指定)、中心線、後退線の有無を確認し、現況測量で有効幅・最狭部・障害物を把握します。
そのうえで、費用、期間、合意の難易度、価値向上(建替え可・配置改善・車両動線の確保等)を横並びで比較し、実現性が高い順に着手します。
投資目線では「恒久解(隣地取得・位置指定)→準恒久(通路新設・地役権)→暫定(セットバックのみで配置最適化)」の順に、出口の取りやすさが変わる傾向があります。
承諾や契約は口頭で進めず、目的・範囲・期間・復旧・費用負担を明記した書面に落とし込み、図面・写真で位置と寸法を可視化しておくと、後のトラブルを避けやすくなります。
- 全体像→物理策と権利策をセットで検討し、可否・価値・コストで整理します。
- 手順→役所照会→現況測量→案の比較→承諾・契約→工事・復旧の流れです。
- 記録→図番付き写し、測量成果、承諾書、写真台帳を一式保管します。
| 手段 | 狙い・向いている状況 | 主なリスク・留意点 |
|---|---|---|
| 隣地一部取得 | 間口2m以上を恒久的に確保したい | 取得費と復旧費、越境・塀の調整、売主合意の難易度 |
| 通路新設 | 敷地配置を改善し車両動線を確保したい | 設計・排水・舗装仕様、近隣合意、工期の長期化 |
| 通行地役権 | 所有を移さず接続を確保したい | 掘削や占用は別合意が必要、将来の運用ルール |
| セットバック | 2項道路で後退して幅員を確保したい | 後退地は原則建築不可→有効宅地が減少 |
- 役所照会→図番・作成年月日・担当を記録し、現況と突合する。
- 案の比較→可否→価値→コスト/期間の順で優先順位を決める。
隣地一部取得と通路新設の比較
隣地の一部取得は、法的・物理的に「間口2m以上」を恒久的に確保しやすい強力な手段です。境界確定(筆界確認)と価格合意、塀や基礎・排水の復旧条件を明確にし、売買契約書・境界確定図・復旧合意書をセットにするのが安全です。
通路新設は、既存の敷地内や取得地を組み合わせ、排水・舗装・見通し・隅切りを整えて車両動線を改善する方法です。
位置指定道路化まで進められれば「法上の道路」としての価値を得られますが、仕様協議や完了検査が必要になり、費用と時間は増えやすくなります。
どちらも実務では、現況測量→配置案→近隣合意→工事→復旧の順で進みます。投資判断では「確実性」と「価値向上(建替え可・レイアウト改善・駐車可)」を数値で比較し、割引現在価値で評価するとブレが減ります。
- 隣地一部取得→恒久的な接道確保。越境・塀・排水の復旧範囲を契約書に明記します。
- 通路新設→動線と見通しを改善。排水・舗装・段差処理・照明まで設計に含めます。
- 双方共通→境界確定・近隣合意・工事後の復旧写真をセットで保管します。
| 項目 | 隣地一部取得 | 通路新設 |
|---|---|---|
| 確実性 | 所有権取得で恒久性が高い | 設計・合意・工事品質に左右 |
| 費用・期間 | 取得費+測量・復旧費、交渉次第 | 設計・排水・舗装・照明・検査で増加 |
| 価値向上 | 建替え可・売却時の評価に直結 | 位置指定化できれば評価が伸びやすい |
| 主なリスク | 合意決裂、越境処理、復旧範囲の争い | 排水不良、隅切り不足、近隣苦情 |
- 「復旧範囲」を図面と写真で特定→塀・舗装・側溝の仕様を明記。
- 雨天時の動画・写真を取得→排水計画の妥当性を説明できるようにする。
通行地役権で接続確保する方法
通行地役権は、所有権を移転せずに「通行する権利」を設定して接続を確保する方法です。
契約では、通行の目的(居住・搬入・工事等)、範囲(幅・延長・位置)、常時性(時間制限の有無・鍵の運用)、車両の種類(軽・普通・工事車両)、維持管理(除草・清掃)、損傷時の復旧、費用負担、第三者への対抗力(登記)を明記します。
掘削や占用(上下水・ガスの引込、仮設足場・資材置場)は通行と別の同意が必要になることが多いため、通行地役権設定契約と合わせて「掘削承諾」「占用承諾」の書式も準備しておくと実務が進めやすくなります。
私道が共有の場合は、同意が必要な共有者の範囲を先に確定し、説明資料(通行経路図、時間帯、復旧仕様、保険証書)を添付します。
将来の更新・譲渡・建替え時の扱いは紛争になりやすいため、条項に「工事中の一時占用」「緊急車両の通行」「鍵の管理者と連絡先」を入れて運用を明確にします。
- 契約の軸→目的・範囲・常時性・車両条件・復旧・費用・登記の7点です。
- 図面添付→位置・幅・最狭部を赤字で表示し、写真対応表を付けます。
- 承諾の拡張→掘削・占用は別承諾でカバーし、セットで締結します。
| 書面の種類 | 主な内容 | 添付・根拠 |
|---|---|---|
| 通行地役権設定契約 | 目的、範囲、常時性、車両条件、費用、賠償 | 通行経路図、写真、登記事項要約 |
| 掘削承諾書 | 配管経路、掘削幅、復旧仕様、費用負担 | 配管図、復旧仕様書、工期・保険証書 |
| 占用承諾書 | 足場・資材・後退復旧の占用位置と期間 | 占用位置図、復旧写真の提出方法 |
- 通行承諾と掘削/占用承諾を混同しない→別書式で明確化します。
- 口頭合意は不可→登記まで行い第三者対抗力を確保します。
セットバック計画と復旧のポイント
前面道路が幅員4m未満の「2項道路」の場合、道路中心線から2mの位置まで敷地を後退(セットバック)して建築ラインを整えるのが基本です。
はじめに建築指導課で当該道路の種別・中心線・後退線の根拠を確認し、現況測量で境界・最狭部・高低差・占用物(塀・花壇・電柱・メーター・側溝)を洗い出します。
後退部分は原則建築不可の扱いとなるため、門塀・駐車・ポーチ・屋外機の配置を先に見直します。
復旧は舗装・縁石・排水・段差処理をセットで計画し、雨天時の水はけ、既設配管・桝の位置、隣地や私道管理者の合意を確認します。
電柱・支線・メーター類の移設は管理者協議に時間がかかるため、早めに照会し、移設費と工期を見積に反映します。
完了後は丁張図・完了写真・復旧仕様書を台帳化しておくと、申請や将来の売買・融資で根拠資料として機能します。
- 後退線の確定→役所の根拠図と測量成果でダブルチェックします。
- 外構再設計→門塀・駐車・屋外機・ポストの位置を後退後基準で再配置します。
- 復旧計画→舗装・排水・段差の仕様、電柱・メーター移設の工程を明記します。
| 工程 | ポイント | 必要な資料 |
|---|---|---|
| 事前照会 | 道路種別・中心線・後退線の根拠確認 | 道路台帳・照会記録・位置図 |
| 現況測量 | 境界・高低差・占用物・配管位置の把握 | 現況測量図・写真・最狭部の寸法 |
| 設計・合意 | 外構・排水・段差・占用移設の計画 | 配置図・復旧仕様書・承諾書 |
| 施工・記録 | 天候と交通に配慮、復旧品質を写真で記録 | 丁張図・完了写真・検収書 |
- 「後退地=原則建築不可」を前提に、門塀や機器類の位置を先に確定する。
- 舗装端=境界ではないことがある→台帳で境界線を必ず裏取りする。
投資判断の目安と注意点

再建築不可の投資判断は、「救済の通る可能性」と「通った後の価値向上」をセットで見極めることが大切です。
まずは法上の道路・接道2m・前面道路幅員の事実確定を行い、救済ルート(43条2項許可、位置指定、隣地一部取得、通行地役権、セットバック等)の実現性、費用、期間、関係者の合意難易度を比較します。
次に、救済後の賃料や出口(売却・再融資)の改善幅を試算し、総投資額に対する利回りやキャッシュフロー、DSCRなどで採算を判定します。
金融は保守的になりやすいため、借入比率は控えめに見積もり、承諾失敗・工事長期化・復旧追加費といった“ズレの源”に予備費を置きます。
出口は、救済の根拠資料(図番付き台帳、測量成果、承諾書、事前相談記録)を揃えるほど評価が安定し、買い手説明も容易になります。
- 「可否→価値→コスト/期間」の順で意思決定を組み立てると迷いにくいです。
- 最狭部の寸法・承諾の有無など、価格に効く事実は写真と図面で可視化します。
- 利回りは表面だけでなく、修繕・承諾・復旧・税コストを含む実質で判断します。
| 指標 | 目安・読み方 | 注意点 |
|---|---|---|
| 実質利回り | 家賃−空室−運営費−修繕を投資総額で割る | 救済費・復旧費・承諾取得費用を必ず含める |
| キャッシュフロー | 税前CFが安定的にプラスかを確認 | 固定資産税・保険・点検を過小見積りしない |
| DSCR | 年間CF/年間元利支払の比率 | 保守的に見て1.2以上を目標に検討 |
- 可否→救済が現実に通るか(根拠資料と承諾の実効性)。
- 価値→建替え・配置改善・賃料増がどれだけ見込めるか。
- コスト/期間→予備費と余裕工程を必ず確保する。
収益性・出口・リスクの見立て方
収益性は「救済前後のキャッシュフロー差」を軸に評価します。現況賃料・駐車場収入・物置/倉庫賃料などの“今取れる収入”と、救済後に見込める賃料改善・稼働改善・空室縮小を分けて積み上げます。
費用は、測量・承諾取得・後退復旧・通路新設・電柱/メーター移設・設計/申請・外構や排水のやり替えまで、工程別に見積を取り、将来の修繕(屋根/外壁/設備)や保険も含めて実質利回りを算出します。
出口は、救済の根拠書類が揃っているかで評価差が出やすく、図番付きの写し・承諾書・完了写真が揃うほど買い手の不確実性が下がります。
リスクは「承諾不成立」「幅員/接道の最小値不足」「排水/勾配の不備」「審査長期化」「近隣合意難航」「金利上昇」など。
各リスクに対し、代替案(別経路・別配置・仮設案)や代替用途(駐車・ストレージ等)を用意しておくと、損失の下振れを抑制できます。
- 収入面→現況収入と改善後収入を分け、家賃・付帯収入・稼働で試算。
- 費用面→救済費+復旧費+運営費+将来修繕を全て含めた実質で評価。
- 出口面→根拠資料の厚みが価格に直結。図番・作成年月日・担当を併記。
| 項目 | 試算のポイント | リスク低減のヒント |
|---|---|---|
| 賃料 | 近隣成約と差分を仮説化、救済後の間取り/駐車可否で補正 | 複数シナリオ(保守/中立/楽観)で感度分析 |
| 空室/稼働 | 立地×動線×駐車の有無で補正 | 駐車区画や物置を追加して需要を広げる |
| 修繕/保守 | 屋根・外壁・配管・外構の年次サイクル | 初年度に重点修繕→保険特約と点検で平準化 |
- “現況”と“救済後”を別表にし、差額で投資効果を見る。
- 感度分析で賃料−5%、費用+10%を同時に当てて安全域を確認。
使えない救済措置とよくある誤解
救済は万能ではありません。まず、43条2項許可は“権利”ではなく、通行の常時性・安全・承諾・周辺影響を満たす個別審査の結果として与えられる“許可”です。
標準基準に合わなければ、代替案(照明追加・段差解消・別経路)を出しても不許可の可能性は残ります。
位置指定道路も、私道に線を引けば自動で成立するものではなく、幅員・排水・舗装・転回・見通しなどの仕様を整え、完了検査を経て初めて「法上の道路」になります。
通行地役権も、通行の権利は確保できても、掘削や占用(上下水・ガス・足場等)は別の承諾が必要です。
セットバックは幅員不足の是正に有効ですが、接道2mが足りない旗竿通路を“後退だけで”満たすことはできません。
さらに、「舗装端=境界」と誤認し、実は境界が内側にあって有効幅が不足していた事例は多く、必ず台帳と測量で裏取りが必要です。
- 43条2項許可=必ず通る、ではない→個別審査と実態一致が前提です。
- 位置指定=誰でも出せる、ではない→仕様・検査・告示が必要です。
- 地役権=掘削も自由、ではない→通行と掘削は別合意です。
- セットバック=接道2mも満たせる、ではない→別の是正策が必要です。
| 誤解 | 実際 | 投資への影響 |
|---|---|---|
| 43条は申請すれば通る | 個別審査。通行・安全・承諾の実効性が鍵 | 不許可リスク→代替案と予備費が必須 |
| 位置指定は通路に線を引けば良い | 仕様整備と完了検査・告示が前提 | 費用と期間が増える→工程に余裕を持つ |
| 地役権で配管も当然OK | 掘削・占用は別承諾が必要 | 工事止まりの恐れ→書面で先行合意 |
- 境界・中心線・最狭部は図面と写真で二重に確認する。
- 承諾は通行/掘削/占用を分け、目的・範囲・復旧まで明記する。
専門家への依頼範囲と進行管理
再建築不可の救済は、法務・測量・設計・施工・近隣調整が絡む“チーム戦”です。はじめに課題を分解し、誰に何を頼むか(成果物の形式・図面名・図番・作成年月日)まで明確にします。
土地家屋調査士/測量士は現況測量・境界確定・筆界確認、建築士は配置・動線・安全計画と役所事前相談、司法書士/弁護士は地役権や承諾契約・登記、不動産事業者は相場・出口戦略と近隣調整、施工者は後退復旧・舗装・排水・占用移設を担当します。
進行管理は、照会→合意→設計→申請→工事→復旧を一本の工程表に落とし込み、会議体(週次など)で進捗・課題・承諾の状況を更新。
書類は「道路」「境界」「承諾」「配置/復旧」にフォルダ分けし、図番と更新日を必ず記録します。見積は“比較可能な形”で揃え、仕様・数量・復旧基準の差を可視化してから発注すると、手戻りを抑えられます。
- 課題分解→法上の道路/接道2m/幅員/承諾/復旧の論点に分ける。
- 担当割当→専門家の役割と成果物フォーマットを決める。
- 工程表→照会・合意・設計・申請・工事・復旧を日付入りで可視化。
- 検収→完了写真・復旧仕様・承諾原本をチェックリストで確認。
| 専門家 | 主な役割 | 成果物の例 |
|---|---|---|
| 土地家屋調査士/測量士 | 現況測量・境界確定・筆界確認 | 現況測量図、境界確定図、筆界確認書 |
| 建築士 | 配置・動線・安全計画、事前相談同席 | 配置図、通行経路図、安全計画図 |
| 司法書士/弁護士 | 地役権設定・承諾契約・登記 | 契約書案、登記関係一式 |
| 施工者 | セットバック・舗装・排水・占用移設 | 復旧仕様書、完了写真、検収書 |
- 「図番・作成年月日・担当」を全資料に記載し、更新履歴を残す。
- 承諾取得と役所照会を前段で走らせ、設計と並行化して全体期間を短縮する。
まとめ
救済措置の鍵は、①法上の道路・接道状況の事実確認→②可否を分ける要件の特定→③図面・承諾・根拠資料の整備→④費用と期間の見積→⑤投資判断の順で進めることです。
43条2項許可や位置指定、通行地役権・隣地取得・セットバックは“使い分け”が重要。
根拠を揃えれば、価格交渉や出口戦略の精度が上がります。まずは役所の事前相談と専門家への早期打診から着手しましょう。