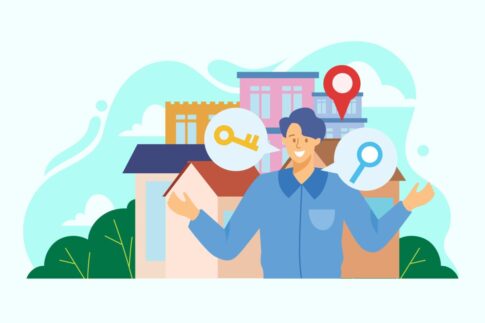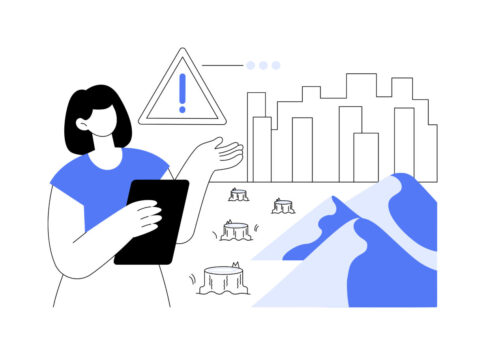再建築不可の物件は一見お手頃でも、扱いを誤ると手戻りが大きくなります。
本稿では、実務で使われる意味合いと接道3条件、道路区分の確認ルート、再建築不可に陥りやすい要因、価格と融資の実際、改善策(43条2項許可・セットバック・隣地調整 など)、活用時の着眼点までを初学者でも追える順で再構成。要点を一気に把握できるようにまとめ直しました。
目次
再建築不可物件の基礎知識

再建築不可は法令上の用語ではなく、建替えを想定したときに建築確認が原則通らない見込みが高い状態を示す実務用語です。
代表的な背景は、敷地が建築基準法の「道路」(42条道路)に2m以上連続して接していない、または前面道路の幅員が足りないこと。
建替えの選択肢は狭まりますが、価格が相対的に抑えられる場面もあります。とはいえ、増改築や大規模修繕でも要件を踏む必要があるため、まずは「道路の種別」「接道の長さ」「道路の幅」を事実で確かめることが肝心です。
以下、定義・エリア・数値基準・確認窓口の順に把握しましょう。
- 基本軸→接道2mの連続+前面道路4mが目安。崩れると新築が難しくなります。
- 価格は下がりがちですが、融資・工事・売却で条件面の制約が出やすいです。
- 最初の一歩は役所の建築指導窓口で道路の種別・幅員の裏取りです。
| 用語 | やさしい説明 |
|---|---|
| 42条道路 | 法で「道路」と扱われる道。ここに2m以上接していれば原則建築しやすい。 |
| 2項道路 | 4m未満でも条件により「みなし道路」。中心線からの後退(セットバック)が前提。 |
| 接道義務 | 敷地は道路に2m以上接するのが原則。満たせないと建替えは原則不可。 |
- 接面長→敷地と道路の連続接面が2m以上か
- 道路幅→4m以上か、2項道路で後退が必要か
- 道路の性質→公道/私道/位置指定など区分の特定
定義と対象区域をやさしく理解する
再建築不可という表現は便宜上の呼び方で、趣旨は「現行基準に照らすと新築の建築確認が原則得られない見込み」。多くは接道義務未充足ですが、区域指定や用途、敷地形状が絡む場合もあります。
対象になりやすいのは都市計画区域・準都市計画区域の建物で、これらでは原則、法上の道路に2m以上接することが求められます。区域外でも規模・用途によって同趣旨の扱いになるため、個別の確認が欠かせません。
【確認観点】
- 接している「道」は法上の道路か→名称が道路でも対象外のことがあります。
- 接道長さ→2m未満なら建替えは原則困難。
- 道路幅員→4m未満なら2項道路の可能性。後退が前提になります。
| 項目 | 概要 | 確認先 |
|---|---|---|
| 区域指定 | 都市計画区域・準都市計画区域は道路要件が原則必要 | 都市計画課・建築指導課 |
| 接道長さ | 2m以上の連続接面が原則 | 測量図・現地実測・道路位置の照会 |
| 道路幅員 | 4m未満は後退・隅切りの検討が必要 | 道路台帳・道路種別の回答書 |
- 「再建築不可=ゼロ活用」ではないが、新築は原則不可の前提で考える。
- 結論は用語ではなく要件の充足で確定。書面での裏付けを優先。
接道義務の4m・2m基準を図解で把握
接道義務は、敷地が法上の道路に2m以上連続して接するという考え方です。ここでの2mは「有効幅」。
門柱・塀・メーターボックス・給湯器・植栽・段差などで実効幅が削られると基準に届かない扱いになりえます。前面道路の標準幅員は4m。
4mに満たない場合でも、古くからの道であれば2項道路として扱われ、中心線から2m後退して将来的な4mを確保する運用になります。
【状況別の考え方】
- 間口2m未満→原則、接道義務を満たさず新築は困難。
- 幅員3.6mの生活道路→2項道路であれば中心線から2m後退し建築ラインを調整。
- 角地→各道路の幅員・接道長さを個別に点検。
| 条件 | 概要 | 実務ポイント |
|---|---|---|
| 接道2m | 有効幅で2m以上の連続接面 | 旗竿通路は出っ張り込みで測る |
| 道路4m | 原則4m以上が基準 | 不足時は後退線の根拠を確認 |
| 障害物 | 電柱・工作物・段差で有効幅が縮む | 実測写真と図面で突合し記録化 |
- 私道の門扉などで1.9mに→有効幅不足で接道不成立となることがあります。
- 後退部分は原則建築不可→有効宅地が減ります。
道路の種類と調べ方・確認先を知る
呼称は道路でも、法上の道路に当たらない通路は珍しくありません。道路法の道路、都市計画事業等による道路、古くからの4m以上の道、事業予定の道路、位置指定道路などが「42条1項道路」。
幅員不足でも条件を満たすと「2項道路」と扱われます。外観では判定しづらいため、建築指導窓口で「法の道路か」「中心線・境界の位置」を資料で確認するのが確実。
私道の場合は通行・掘削の承諾の要否も合わせてチェックしましょう。
【実務フロー(目安)】
- 建築指導課→42条1項/2項/位置指定の有無を確認
- 道路管理者→道路台帳・幅員・境界の確認
- 私道→通行・掘削承諾の有無を点検
- 測量→現況測量で図面と現地の整合をとる
| 道路種別 | 特徴 | 確認書類・窓口 |
|---|---|---|
| 1項道路 | 道路法・都市計画等で整備/指定、原則4m以上 | 道路台帳・都市計画図・道路判定 |
| 2項道路 | 4m未満の既存路をみなし道路化 | 後退線の指定図・窓口回答の写し |
| 位置指定道路 | 私道でも告示・図面で指定される道 | 位置指定図・告示番号・台帳 |
- 「見た目」ではなく「資料根拠」で判断する。
- 私道は承諾・管理の確認までセットで行う。
なぜ再建築不可になる?原因を具体例で整理

再建築不可の主要因は、法上の道路に有効幅2m以上接していないか、前面道路の幅員が不足していることです。
外見は道路でも法上の道路に当たらない通路しか接していない、門柱や電柱で2mを切っている――といった事例も対象。
袋地・旗竿地、分筆で間口が細くなった敷地、古い細街路沿い、承諾関係が未整備の私道沿いなどで生じやすいです。
対処は、セットバックで幅員確保、通路拡幅や隣地調整で2m接道の実現、位置指定や通行承諾の整備、43条2項許可の検討など。まずは接道長さ・道路種別・幅員を役所資料と現況の双方で確認しましょう。
- 見た目の道路=法の道路ではない→資料で裏付け。
- 旗竿通路は有効幅が2m未満だと原則建替え不可。
- 4m未満の道路はセットバックが前提になる場合あり。
| 原因類型 | 起こりやすい状況 | 確認・対処のヒント |
|---|---|---|
| 2m未満の接道 | 旗竿の竿が細い・門塀で圧迫 | 有効幅を実測→工作物移設や隣地一部取得を検討 |
| 道路幅員不足 | 古い細街路・生活道路 | 2項道路の可否・後退線の位置を確認 |
| 法の道路でない | 農道・私設通路など | 道路判定・位置指定・承諾の有無を照会 |
| 私道承諾未整備 | 掘削不可・通行合意なし | 管理者・共有者の同意取得→書面化 |
- 法の道路か→書類で立証。
- 有効幅2mか→工作物で削れていないか。
- 4m確保か→2項道路なら後退線を確定。
袋地・旗竿地と道幅不足のパターン
袋地(道路に接していない敷地)や旗竿地(細道の奥に敷地が広がる形)は、接道基準を満たしづらい代表例です。
旗竿地では竿部分の「有効幅」が2m以上必要で、門柱・塀・メーター類・植栽・段差・隅切りなどが重なると、実測で2mを下回ることがあります。
袋地は道に無接面のため、通路新設や一部取得、通行地役権の設定が要る場合があります。
前面道路が4m未満なら、2項道路としてセットバックを求められ、実質の建築可能面積が減る点にも注意。現況と図面を突合し、道路種別と後退線を早めに確定させましょう。
- 旗竿1.9m→原則建替え不可。塀位置の見直しや隣地の一部譲受を検討。
- 角部の隅切り・電柱で圧迫→管理者と移設可能性を事前に協議。
- 3.6mの生活道路→2項道路なら中心線から2m後退でライン調整。
| 型 | 影響 | 対処 |
|---|---|---|
| 袋地 | 道路に無接面→建築不可 | 通路新設・地役権・隣地一部取得 |
| 旗竿の不足 | 有効幅2m未満→接道不成立 | 工作物撤去・拡幅・塀後退 |
| 幅員不足 | 後退で有効宅地が減る | 後退線確定→配置再検討 |
- 図面上は2mでも、現地工作物で実効が不足という事例が多い。
- 後退部分は原則建築不可→通路や駐車に充てる前提で計画。
私道・位置指定道路で起きやすい注意点
私道や位置指定道路は、承諾や維持管理が曖昧だと建替え時に詰まります。
典型は、通行承諾が口頭のみ、掘削承諾が得られない、指定時の幅員から実幅が細っている、境界が不明確、共有者に連絡が取れない――など。
位置指定道路は図面と公告番号で根拠化できますが、路肩の占用や工作物で有効幅が足りないこともあります。
持分がなくても通行が認められる場面はありますが、掘削は別途承諾が要るのが通例。建替え前に「種別・幅員・境界・承諾・管理者」を書面で整理しておきましょう。
- 位置指定→指定図と現況を照合し、占用物で細っていないか確認。
- 共有私道→全員同意が求められることがある。代表者のみでは不足。
- 掘削→上下水・ガスの引込や後退工事で事前承諾が鍵。
| 論点 | 例 | 対応の目安 |
|---|---|---|
| 通行/掘削 | 配管新設の同意が得られない | 書面依頼・代替ルートの検討 |
| 指定条件 | 花壇・ポールで実幅縮小 | 指定図と現況を照らし移設交渉 |
| 境界 | 舗装線と境界杭のズレ | 測量で確定→後退線を再確認 |
- 「持分なし=常に不可」ではないが、掘削は別問題→書面承諾を確保。
- 共有者が多いほど時間がかかる→早期に合意形成を開始。
43条2項許可の考え方と基本の流れ
43条2項許可(ただし書許可)は、法の道路に接しない敷地でも、通行・防災・衛生上の支障がないと特定行政庁が判断すれば例外的に建築を認める制度です。
基準や必要図書は自治体や敷地の状況で異なるため、事前相談が出発点。経路の有効幅・距離・段差、非常用進入口、照明・見通し、隣地承諾、排水経路などを具体図書で示します。
まず適用可能性と必要条件を聞き取り、現況測量図・経路図・承諾案・配置計画を整え、指摘に応じて修正しながら詰めます。
- 事前相談→実測・写真・動画で経路を可視化し、審査観点を確認。
- 通行確保→隣地・私道の承諾、鍵・ゲートの扱いを明確化。
- 安全措置→段差解消・照明・見通し確保などの改善を盛り込む。
| 審査の視点 | 例 | 準備書類 |
|---|---|---|
| 通行の恒常性 | 有効幅・距離・常時利用の担保 | 測量図・写真、通行承諾、管理規約 |
| 防災・安全 | 消防活動への配慮 | 配置・避難動線、改善工事計画 |
| 周辺影響 | 通行増・騒音への配慮 | 説明資料・合意記録 |
- 自治体ごとに基準が違う→事前相談で可否と条件を把握。
- 承諾と改善工事の合意を先行→審査のスピードが上がります。
売買・価格・融資の現実的な目安を理解

再建築不可は流通性の弱さや将来不確実性が価格に反映されます。評価では、近隣の建築可との比較に加え、セットバックの要否、私道承諾・掘削可否、インフラ・解体・測量などの追加費用を見込みます。
買い手は「取得価格」だけでなく「残る有効宅地面積」「資金調達の難度」「出口の取りやすさ」を同時に検討。
売り手は道路種別・接道長さ・後退線の根拠資料を整え、説明不足によるディスカウントを抑えます。
融資は厳しめですが、自己資金や担保追加で成立する事例もあります。以下の観点で価格と条件をセットで考えましょう。
- ロジックは「近隣相場→制約・追加費用→残存価値」。
- 調査の質が評価を左右→根拠資料の先出しで不確実性を縮小。
- 融資の方針は金融機関次第→早期打診と代替ルートの確保を。
| 論点 | 価格への作用 | 確認資料 |
|---|---|---|
| 接道・幅員 | 建替え可否・有効面積に直結 | 道路種別通知・後退線図・実測図 |
| 私道・承諾 | 工事・配管不可なら価値低下 | 通行/掘削承諾・管理規約 |
| 追加費用 | 解体・測量・インフラ等で負担増 | 見積・工程・許認可の要否 |
| 出口 | 再売却のしやすさに影響 | 周辺事例・需要層の想定 |
- 相場→制約→費用→残る価値の順で一貫させる。
- 役所の回答と書面化で不確実性を小さくし、交渉材料にする。
相場の傾向と評価の考え方の基本
相場は「建替え難→換価性が低い」分だけ調整されます。もっともシンプルな手順は、近隣の建築可事例から始め、セットバックによる面積減、拡幅や隣地交渉の難度、私道承諾の取得可否、重機進入など工事制約をコスト・リスクに置き換えて差し引く方法。
土地値のみで評価する場合も、現況建物の賃貸や駐車場・置場などの収益・節約効果が見込めるなら、収益還元を加えると整合性が増します。
重要なのは「不確実性の具体化」。承諾未取得・後退線未確定・配管経路不明は、いずれも割引要因です。
- 可比事例は道路条件を一致させて抽出。
- 面積の実効性→後退後の有効地や車両動線まで評価に反映。
- 承諾者数・利害で時間と費用が上下する点を見込む。
| 視点 | 具体化のヒント | 価格作用 |
|---|---|---|
| 物理制約 | 有効間口・後退量・進入可否 | 動線難が強いほどマイナス |
| 権利・承諾 | 持分・通行/掘削承諾の有無 | 未整備はディスカウント |
| 工事・費用 | 解体・測量・インフラ・仮設 | 見積で数値化して反映 |
| 代替活用 | 駐車場・倉庫・賃貸の余地 | 収益が取れれば下支え |
- 「可比事例+制約コスト」の二段構成で考える。
- 不確実項目は図面・見積・書面で可視化し、主観を排す。
住宅ローンが難しい理由と代替策
住宅ローンは「長期利用に耐え、担保価値と換価性が見込めること」が前提。再建築不可は建替え自由度と流通性が弱く、担保評価が伸びにくいため、比率や審査が厳しめになりがちです。
老朽が進むほど保全コストや保険条件の面でもハードルが上がります。とはいえ、自己資金の厚み、安定収入、他不動産の担保余力、用途(賃貸併用 など)で余地が変わるため、早期に複数行へ相談し、成立確度と総コストで比較するのが基本です。
- 難しい主因→担保評価・換価性・保全条件の不確実性。
- 可能性を上げる工夫→自己資金増、担保追加、用途・計画の明確化。
- 判断は金利だけでなく総支払額と柔軟性で。
| 代替策 | 概要 | 留意点 |
|---|---|---|
| 現金+少額ローン | 自己資金を厚くして借入を抑える | 流動性と予備費を確保 |
| 担保追加 | 別不動産で信用補完 | 設定費用・売却時制約を確認 |
| リフォームローン | 改修資金を別枠で調達 | 金利が高め→費用対効果を精査 |
| プロパー/事業性 | 収益化前提で融資相談 | 返済原資と実行計画を提示 |
- 金融機関の姿勢は地域・案件で差→早期ヒアリングが近道。
- 出口時の制約も含め総額で比較する。
リフォーム可否と工事時の留意点
再建築不可でも、内装の更新や軽微な修繕は進めやすい一方、増築や構造に影響する工事、用途変更は適法性の確認が必要。
2項道路のセットバック未了なら外構・搬入計画に制限が出やすく、私道沿いでは掘削承諾がないと上下水・ガス更新が止まります。
工事が外周に及ぶ場合は、足場・搬入・仮設電気/水・車両動線・近隣説明を具体化し、写真と図面で記録を残すとトラブルが減ります。
- 法令適合→確認の要否や後退線の扱いを事前相談で確認。
- 承諾関係→通行・掘削・占用の可否を文書で取得。
- 工程計画→進入・資材置場・時間帯・騒音配慮を明確化。
| チェック領域 | 内容 | 実務ポイント |
|---|---|---|
| 法令適合 | 増改築要件・後退の扱い | 後退部は原則建築不可→外構を調整 |
| 権利・承諾 | 私道掘削・占用、電柱移設 | 書面承諾で工程遅延を回避 |
| 安全・工程 | 足場・搬入・動線・騒音 | 近隣説明と時間帯調整・記録化 |
| 費用・予備費 | 解体/処分・仮設・復旧 | 複数見積・予備費の設定 |
- 役所の事前相談で確認要否と後退線を確定。
- 私道書面承諾(通行/掘削/占用)を先行取得。
再建築可へ近づける方法と手順の選択肢

多くの案件は「接道2m不足」「幅員不足」が起点です。現況を正確に掴み、物理策(拡幅・後退・通路新設)と権利策(通行/掘削承諾・位置指定確認・地役権設定・隣地一部取得)を組み合わせます。
まず道路種別・後退線・接道長さを資料と実測で確定し、費用・期間・合意形成の難度を比較。建替えが難しい場合は代替活用も並走し、投入コストに対する価値向上を評価します。
- 道路種別・後退線→役所照会で確定し、測量で整合。
- 物理策+権利策→セットで案を作り、費用・期間・難度で比較。
- 複数案を並べ、最も実現性と効果が高い道を選ぶ。
| 選択肢 | 狙い | 鍵資料・合意 |
|---|---|---|
| セットバック | 将来4m確保に合わせ建築ライン是正 | 後退線根拠、境界確定、復旧計画 |
| 隣地一部取得 | 有効間口2m以上の確保 | 測量成果、売買契約、越境の処理 |
| 通路新設/地役権 | 道路への確実な接続 | 契約、実測図、公図、維持管理合意 |
| 私道承諾整備 | 通行/掘削/後退の実行性確保 | 同意書、管理規約、占用物移設合意 |
- 役所照会→道路種別/後退/位置指定の有無を確認。
- 測量→境界・有効幅・障害物を可視化。
- 案比較→費用・期間・難度・価値向上で評価。
セットバックや道路後退の進め方
幅員4m未満の道が2項道路なら、中心線から2m後退して建築ラインを整えるのが基本。
建築指導窓口で種別・中心線・後退線の根拠を確認し、現況測量で境界・高低差・占用物(花壇・塀・ポール・電柱 等)を洗い出します。
後退予定部は原則建築不可・外構制限がかかるため、門塀や駐車計画を見直します。私道側の後退や占用物移設には管理者・共有者の合意が必要。
復旧は舗装・排水・段差解消をワンセットで検討し、写真・図面で記録します。
- 後退線の確定→役所根拠+測量成果で二重確認。
- 占用物の移設→後退ライン外へ再配置。
- 復旧計画→舗装・排水・段差の方法と費用を事前見積。
| 工程 | 内容 | 実務ポイント |
|---|---|---|
| 事前確認 | 種別・中心線・後退線の確定 | 図面番号・回答記録を控える |
| 現況測量 | 境界・高低差・占用物の把握 | 有効幅の障害を特定→移設計画へ |
| 合意形成 | 管理者・隣接地と調整 | 排水・管理の分担を文書化 |
| 復旧工事 | 舗装・縁石・排水・段差処理 | 完了写真・丁張図を保存 |
- 「後退部=原則建築不可」を前提にプランする。
- 電柱・メーターの移設可否は早期照会。
隣地取得・通路新設などの選択肢
有効幅が2m未満なら、隣地の一部購入で間口を広げるか、通行地役権で道路接続を確保する方法があります。
前者は恒久的に確実性を高めやすい一方、取得費・測量費・復旧費を総額で判断。後者は所有権は移さずに通行権を確保できますが、幅員・位置・車両条件、工事・掘削の取り決めを明確に。
通路新設は測量・設計・近隣合意・排水計画が鍵で、建築計画と一体で検討します。
- 隣地一部取得→2m以上の確保。塀・基礎の復旧条件を明記。
- 通行地役権→幅員・車両・時間帯を明文化し、掘削条件も別記。
- 通路新設→排水・舗装・段差まで含めた実施設計が必要。
| 方法 | メリット | 留意点 |
|---|---|---|
| 一部取得 | 恒久的に2m以上を確保しやすい | 取得費+測量・復旧の総額で判断 |
| 地役権 | 低コストで接続を確保 | 掘削・工事条件を契約で補完 |
| 通路新設 | 使い勝手と視認性の向上 | 合意・工期・費用の見通しが前提 |
- 境界・面積・越境の有無を測量で確定し、図面で共有。
- 復旧範囲(塀・舗装・排水)と費用負担を事前合意。
共有私道の承諾・掘削の実務ポイント
共有私道に接する場合、建替えや配管引込、後退工事には通行・掘削・占用の承諾が必要になることがあります。
まず持分割合・共有者一覧・管理者の有無・規約の有無を把握。承諾は口頭でなく書面で、目的・範囲・期間・復旧・費用・連絡窓口を明記します。
共有者が多いほど時間がかかるため、図面・工程・騒音/車両動線の配慮案を添付して合意形成を進めると通りやすいです。
占用物(花壇・車止め 等)が有効幅を圧迫している場合は、移設先と費用負担を事前に決めておきます。
- 権利関係の把握→共有者名簿・持分・規約の確認。
- 承諾の書面化→目的・範囲・復旧・費用・期間。
- 工程配慮→時間帯・動線・清掃・騒音対策を提示。
| 承諾種別 | 主な内容 | 添付例 |
|---|---|---|
| 通行承諾 | 工事車両含む通行条件 | 配置・動線図、時間帯・幅員条件 |
| 掘削承諾 | 上下水・ガス・電気の更新/新設 | 配管図、復旧断面、工期、写真記録 |
| 占用承諾 | 足場・資材置場・後退復旧 | 占用位置図、保険証書、原状回復方法 |
- 一部同意では不足のケース→必要範囲の同意者を特定。
- 復旧水準の齟齬→舗装・排水・清掃まで具体化し書面化。
活用方法とリスク管理を初心者向けに整理

再建築不可でも、建物を新築しない使い方なら実用性があります。駐車場・資材置場・簡易ストレージ・看板・菜園などは、手続を確認しつつ運用できる可能性があります。
要は、用途ごとの許認可・近隣調整・通行確保を事前に整えること。私道沿いなら承諾、2項道路なら後退部の扱い、既存建物の安全・保守、保険設計が論点になります。
災害リスクや適法性、契約時の説明・資料化まで含めて準備すると、収益とトラブル回避の両立が図れます。
- 建築を伴わない活用→駐車場・看板・置場・菜園など。
- 既存建物の活用→軽微修繕で安全性と利便を確保。
- 承諾と合意→私道通行/掘削、近隣説明を文書化。
| 観点 | チェック要点 |
|---|---|
| 法令適合 | 建築の要否、用途許可、後退部の扱い |
| 安全・環境 | 動線・騒音・粉じん・照明・防犯 |
| 承諾・合意 | 私道承諾、近隣説明、看板の許可 |
- 用途と手続を役所で確認し、記録を残す。
- 動線・騒音・照明の配慮案で早期合意。
- 保険と点検計画を整え、事故・災害に備える。
駐車場・物置など現実的な活用例
車両進入可否・地盤・勾配で適した活用が変わります。簡易舗装で月極/時間貸の駐車場に転用すれば、初期費用を抑えつつ収益化が可能。
搬入が厳しいなら、軽・二輪専用や駐輪場、小口ストレージ、家庭菜園など「小さく回す」選択が現実的です。
既存建物は安全点検の上、倉庫や作業スペース、レンタル物置として活用する例も。看板は視認性・許認可・落下防止・夜間照明に配慮します。
どの用途でも「使い勝手→安全→近隣配慮→保険」の順で詰めると実装が早いです。
- 駐車場→区画割・車止め・照明・精算方式を設計。
- 物置/倉庫→防水・施錠・湿度管理、搬入動線の確保。
- 看板→許認可・構造・照明の確認。
| 活用例 | 実務ポイント | 留意点 |
|---|---|---|
| 月極駐車場 | 動線設計・区画サイズ・舗装仕様・管理方式 | 出入口の視距・夜間照明・騒音配慮 |
| レンタル物置 | 防水・施錠・湿度・搬入幅/段差 | 火災/盗難への備えと規約整備 |
| 小規模ストレージ | 棚荷重・床耐力・避難動線 | 危険物・臭気物の持込禁止を明記 |
- 需要が強い用途から着手し、区画を柔軟に設計。
- 管理負担を数値化し、月額損益に織り込む。
災害時の安全配慮と保険の基本
狭い通路や袋地は避難・消防の遅れに直結しやすい点に留意します。まずハザードマップ(浸水・土砂・高潮 等)で立地リスクを把握し、夜間も含めた避難導線を確保。
既存建物は屋根・外壁・基礎、電気・ガス・水道の健全性を定期点検し、飛散しやすい設備や看板は補強。
保険は火災+地震を基本に、風災・水災、動産、施設賠償などを用途に合わせて選びます。補償額(再調達/時価)・免責・連絡フローを平時に文書化しておくと復旧が早まります。
- ハザード→浸水深・到達時間・避難所ルートの確認。
- 点検→屋根/外装/配管/電気盤・倒木・掲示物の固定。
- 保険→補償範囲・免責・特約を用途に合わせて設定。
| 項目 | 要点 | ヒント |
|---|---|---|
| 避難・消防 | 夜間でも安全な導線と集合場所 | 照明・表示・鍵の管理を共有 |
| 設備保守 | 漏電・ガス漏れ・雨漏り・腐食の防止 | 年次点検・写真記録・交換周期の管理 |
| 保険設計 | 火災+地震+水災等の組合せ | 再調達/時価、賠償要否を確認 |
- 狭隘通路は消防活動の遅延要因→簡易消火設備の整備も検討。
- 看板・掲示物は強風で飛散しやすい→固定金物と定期点検を徹底。
契約不適合・境界確定の確認事項
売買では、道路種別・接道長さ・後退の要否、私道の通行/掘削承諾、既存建物の状態など、買主にとって重要な事実の開示と証拠化が肝。説明不足は契約不適合の火種となり、境界未確定や越境の放置は将来の工事に支障を来します。
売主は道路判定・後退線の根拠、承諾関係、測量成果(現況測量・境界確定・筆界確認書)、インフラ状況、既存建物の不具合履歴を整理。
買主は引渡し前に現地と書類の突合を行い、規約類があれば写しを添付。合意事項は極力書面化し、図面と写真で可視化すると安全です。
- 重要事項→道路種別・接道長さ・後退線・私道承諾の有無。
- 測量・境界→筆界確認書・越境の有無・復旧範囲の合意。
- 既存建物→雨漏り・シロアリ・配管劣化などの履歴。
| 書類 | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 道路判定/後退線 | 種別・中心線・セットバック範囲 | 役所の根拠図・照会記録を添付 |
| 測量成果 | 現況測量・境界確定・筆界確認 | 越境・欠損の有無、復旧方法の合意 |
| 承諾関係 | 通行/掘削/占用、管理規約 | 同意者範囲・期間・復旧負担を明記 |
- 役所照会+測量+承諾を三点セットで提示し、不確実性を極小化。
- 合意内容は図面・写真で可視化して、引渡し後の認識差を防ぐ。
まとめ
再建築不可は、接道や幅員の要件を満たさないことなどから新築が原則難しい一方、割安取得や暫定利用の余地があります。
定義と接道3条件、道路確認の進め方、価格・融資の見方、改善策(セットバック・隣地調整・43条2項許可)を押さえ、事実ベースで判断すれば、無駄なリスクを避けつつ価値向上へ道筋を描けます。
迷ったときは所管窓口や専門家に照会し、書面で根拠を残す運用を徹底しましょう。