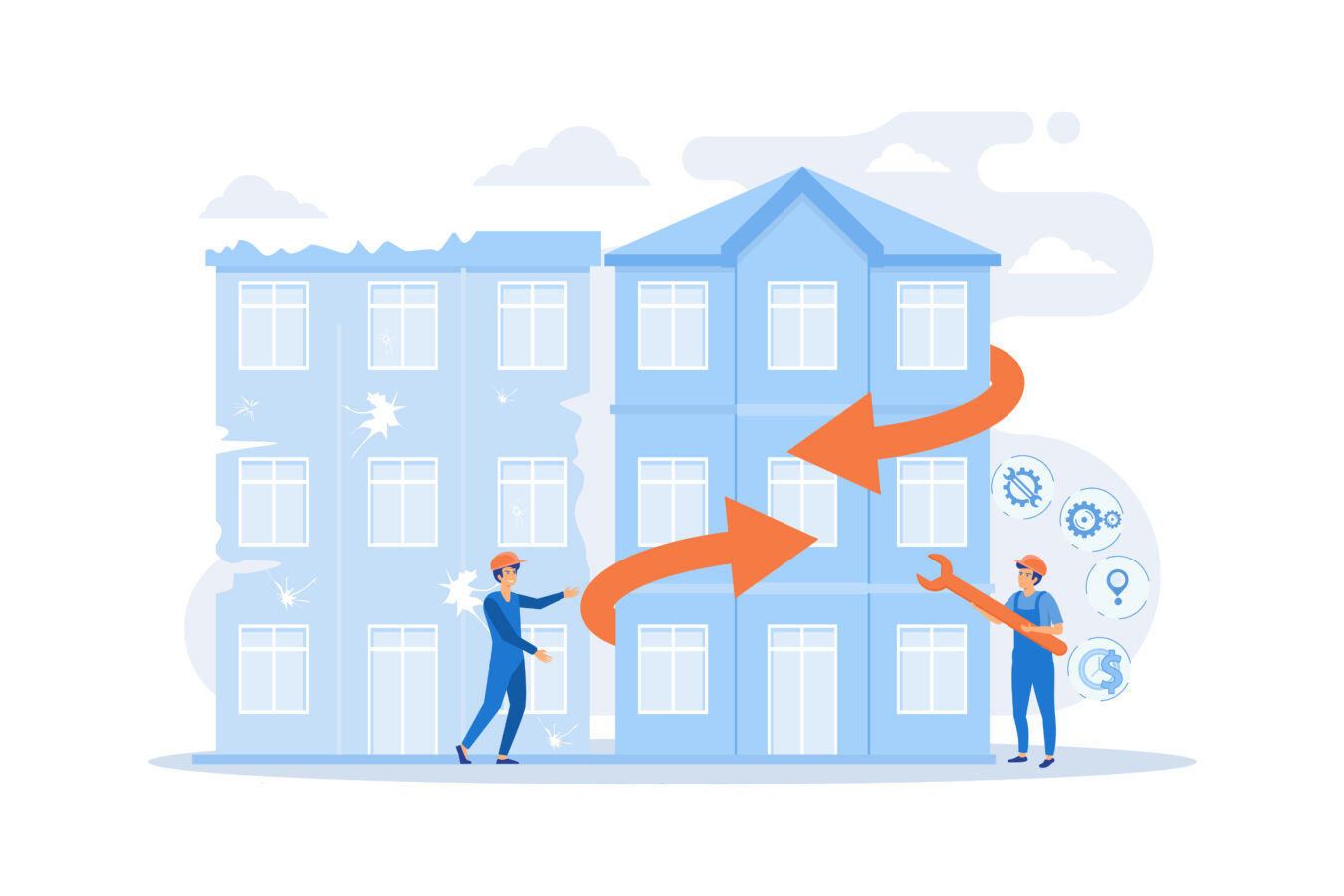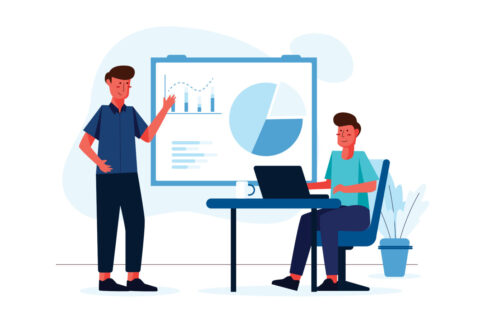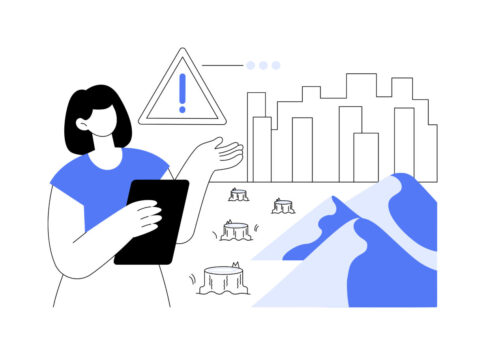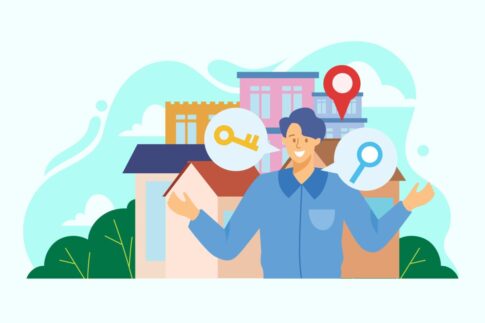再建築不可かどうかは、価格・融資・活用に直結します。本記事は、初めてでも迷わない7ステップで、役所での道路判定の確認、登記・公図・道路台帳の取り方、接道2mと幅員の簡易実測、位置指定道路・43条2項許可の要点までを整理。調査の順番と必要書類が一目で分かります。
再建築不可の調べ方の全体像

再建築不可かどうかは、道路の種別・接道長さ・幅員などの客観情報を順番に確認すれば整理できます。
流れとしては、役所で道路判定や都市計画の前提を把握→法務局で登記事項・公図・地積測量図を取得→現地で接道2mと前面道路幅員を簡易実測→私道なら通行・掘削の承諾の有無を確認→必要に応じて測量士・調査士へ依頼、という順が効率的です。
判断は「見た目の道」ではなく「建築基準法上の道路」かどうかで行います。書類と現地を突合し、記録を写真・メモ・図面で残すと、売買・融資・活用の説明資料として再利用しやすくなります。
- 役所で道路種別・後退線・位置指定の有無を確認する→根拠図面の所在も控える。
- 法務局で登記・公図・地積測量図を取得→境界・面積・越境の有無を確認。
- 現地で接道2m・道路幅員・障害物を実測→写真と寸法をセットで保存。
| 目的 | 確認すること | 主な窓口・資料 |
|---|---|---|
| 道路の適否 | 法上の道路種別、中心線、セットバック要否 | 建築指導課、道路管理課、道路台帳・位置指定図 |
| 権利・境界 | 地番・地目、筆界、面積、越境の有無 | 法務局(登記事項、公図、地積測量図) |
| 現地実態 | 接道長さ2m、前面道路幅、障害物 | 現地実測、写真、簡易スケッチ |
- 書類→現地→専門家の順で精度を上げる。
- 「法上の道路か」で判断→見た目では決めない。
役所窓口の確認手順と必要書類
最初に建築指導課で「当該接道が建築基準法上の道路か」「道路種別(42条1項・2項・位置指定など)」「中心線や後退線の位置」を照会します。
次に道路管理課や土木事務所で道路台帳・境界の情報を確認し、都市計画課では用途地域・地区計画・道路予定線などの制約を把握します。
上下水道局・ガス事業者では配管台帳や引込の可否を確認しておくと、後の工事計画が立てやすくなります。
持参物は地番・家屋番号、位置が分かる地図、可能なら登記事項や公図の写しです。照会は口頭だけにせず、図面名・図番・担当部署名・日付をメモに残すと、売買や融資での説明が確実になります。
- 建築指導課→道路種別・中心線・後退線の有無を確認。
- 道路管理課→道路台帳・境界・幅員、占用物の扱いを確認。
- 都市計画課→用途地域・地区計画・道路予定線などの規制を確認。
- 上下水道・ガス→配管経路・引込可否・掘削条件を確認。
| 窓口 | 確認事項 | 持参・準備 |
|---|---|---|
| 建築指導課 | 法上の道路、中心線、2項道路の後退線 | 地番・案内図、登記事項・公図の写し |
| 道路管理課 | 道路台帳、幅員、境界、占用の可否 | 対象位置が分かる図面、写真 |
| 都市計画課 | 用途地域・地区計画・高度/防火の指定 | 地図・住所・地番、計画の概要 |
| 上下水道等 | 配管台帳、引込条件、掘削承諾の要否 | 位置図、既設メーター情報 |
- 「図面名・図番・担当」を控える→後で根拠提示がしやすい。
- 写真・簡易図を持参→説明が伝わりやすく確認が早い。
登記事項・公図・測量図の入手と確認
法務局では、登記事項証明書(所有者・地目・権利関係など)、公図(筆の配置)、地積測量図(境界標や寸法が記載)を取得できます。
公図は概略図で誤差を含むため、境界や寸法の根拠は地積測量図や確定測量成果で確認するのが安全です。
複数筆で一体利用している場合は、筆界が通路部分と重ならないか、越境(塀・庇・排水)がないかを必ず点検します。
建物がある場合は家屋番号の登記や、過去の建築確認台帳記載(役所)も併せて確認し、現況と不整合があればメモに残します。
これらの書類は、接道2mの根拠提示やセットバック範囲の説明、私道承諾の交渉材料としても有効に使えます。
- 登記事項→権利・地目・持分・地役権の有無を確認。
- 公図→筆の位置関係の把握に利用(概略図である点に注意)。
- 地積測量図→境界標・辺長・座標などの根拠。なければ現況測量を検討。
| 書類 | 主な内容 | 確認ポイント |
|---|---|---|
| 登記事項証明 | 所有者、地目、持分、地役権等 | 通行地役権・私道持分の有無、地目の整合 |
| 公図 | 筆の配置・形状の概略 | 筆界の位置、通路部分との重なり、有無の把握 |
| 地積測量図 | 境界点、辺長、面積 | 境界標の現況一致、越境・欠損の有無 |
- 公図は概略図→寸法や境界確定の根拠にはならないことがある。
- 地積測量図がない地番もある→現況測量や筆界確認書を検討する。
現地チェックと接道2mの簡易確認
現地では、敷地が「法上の道路」に2m以上接しているかを、有効幅で確認します。門柱・塀・ポール・メーター・植栽・電柱・段差などがあると、見かけの寸法より狭くなることがあります。
旗竿地では竿部分の通路が有効2m以上か、角地なら各道路の接道長さと幅員をそれぞれ測ります。
道路幅が4m未満なら2項道路の可能性があり、後退線の位置は役所の確認が必要ですが、中心線推定のため道路の対向側寸法も控えておくと後の照会がスムーズです。
測定はメジャーやレーザー距離計で行い、測った位置が分かるように写真に寸法を書き込み、障害物の位置とサイズも併記すると再確認が容易になります。
- 敷地と道路の接するラインを特定→開始点と終点を決める。
- 有効幅を実測→門塀・設備で狭まる箇所は最小寸法を記録。
- 前面道路の幅員を実測→対向側までの距離を複数箇所で採る。
- 障害物(電柱・看板等)の位置を写真+寸法で記録。
| 確認項目 | 具体的な見方 | 記録方法 |
|---|---|---|
| 接道2m | 敷地の有効間口が2m以上か | メジャー実測、最小値の位置を写真に追記 |
| 道路幅員 | 4m以上か、狭い箇所はどこか | 複数点で計測、簡易スケッチに寸法を書込 |
| 障害物 | 門塀・電柱・花壇・段差の有無 | 位置とサイズ、移設可否のメモ |
- 「最小寸法」を重視→一番狭い箇所を特定して記録する。
- 現地の寸法は役所資料で後日照合→不一致は要再確認。
道路種別の確認と地図サービスの使い方

道路が建築基準法上の「道路」かどうかを確かめるには、役所の台帳類と地図サービスを組み合わせ、書類→現地→再照会の順で突合するのが効率的です。
まず建築指導課で道路種別(42条1項・2項・位置指定)や中心線、後退線の有無を確認し、道路管理課で道路台帳・境界を確認します。
次に自治体の都市計画情報提供サービスや地理院系の基盤地図で位置関係を俯瞰し、航空写真・地形図・ゼンカイ地図等で路肩や通路の連続性、幅員のムラを把握します。
最後に現地でメジャー等を用いて有効幅を測り、写真に寸法を書き込みます。紙図とウェブ地図は縮尺や更新日が異なるため、必ず原典(台帳の図番・作成日)を控え、疑義があれば担当課に再確認します。
- 書類→台帳・位置指定図・中心線の根拠を把握する。
- 地図→航空写真と地形図で連続性や幅員の変化を確認する。
- 現地→有効幅と障害物の最小寸法を測り、写真に記録する。
| ツール | 主な用途 | 実務のコツ |
|---|---|---|
| 都市計画情報 | 用途地域・道路予定線・地区計画 | 表示縮尺と更新日を確認→台帳と整合 |
| 道路台帳 | 道路境界・幅員・管理区分 | 図番を控える→写しの保存で根拠化 |
| 基盤地図/航空写真 | 通路の連続性・実態の把握 | 影・植栽で狭窄部を推測→現地で実測 |
- 役所台帳で道路種別と中心線を特定→図番と日付を記録。
- 地図で全体像を把握→狭い箇所をマーク。
- 現地で最小寸法を実測→写真+寸法で保存。
42条1項・2項道路の見分け方と要点
42条1項道路は、道路法による道路や都市計画事業で整備された道路、既存の幅員4m以上の道、位置指定道路(1項5号)などが該当します。
原則として幅員4m以上で、敷地がこれらの道路に2m以上接していれば接道義務を満たします。
一方、42条2項道路は、幅員4m未満でも一定の要件を満たす「みなし道路」で、将来4m確保を前提に道路中心線から2mの位置まで敷地を後退(セットバック)する考え方です。
見分けの第一歩は、名称や見た目ではなく、台帳や道路判定での「法上の道路」かどうかの確認です。
幅員が場所によって変わる細街路は、最も狭い箇所で判断が左右されるため、複数点で実測し、中心線の位置を台帳で裏取りします。
- 1項道路→原則4m以上。接道2m以上で建替えの前提を満たしやすい。
- 2項道路→4m未満。中心線から2m後退が必要で有効宅地が減る。
- いずれも最小幅と有効接道を重視→障害物で2mを下回らないか確認。
| 区分 | 特徴 | 確認ポイント |
|---|---|---|
| 42条1項 | 道路法等の道路、4m以上、位置指定を含む | 台帳の路線名・幅員、境界・中心線の根拠 |
| 42条2項 | 4m未満の既存道をみなし道路とする | 中心線の位置、後退線、将来の拡幅前提 |
- 「町内道路」「農道」等の名称=法上の道路とは限りません。
- 実測は最小幅で判断→電柱・塀・植栽が有効幅を圧迫しやすいです。
位置指定道路の確認手順と台帳の読み方
位置指定道路は、開発時に個別の図面・番号で指定を受けた私道で、42条1項5号に含まれます。
確認の基本は、建築指導課で「位置指定番号・指定年月日・幅員・延長・両端の接続先・側溝や用地の内外」などが記載された図面を取得し、現地と照合することです。
図面記載の有効幅が、現況の花壇・車止め・ポール・工作物で狭まっていないか、路肩の越境がないかを確認します。
また、私道の管理主体や共有者、通行・掘削・占用の承諾要件も併せて整理しておくと、将来の建替えや配管更新でのトラブルを避けられます。
端部が公道につながっていない袋状の指定道路は、避難・通行の観点で追加条件が付く場合があるため、事前相談が有効です。
- 図面の必須項目→幅員、中心線、延長、端部の接続先、指定番号・日付。
- 現地照合→占用物で有効幅が縮んでいないか、境界杭の有無を確認。
- 承諾整理→通行・掘削・占用条件を文書化し、共有者の範囲を確定。
| 確認項目 | 台帳で見る点 | 現地で見る点 |
|---|---|---|
| 幅員 | 有効幅と測定基準の記載 | 花壇・車止め等で狭窄していないか |
| 端部接続 | 公道への連続性・接続方法 | ゲート・段差・鍵の運用有無 |
| 境界 | 境界線・側溝の内外 | 杭の存否、舗装と境界のズレ |
- 「番号・図番・指定日」を必ず記録→根拠提示に直結します。
- 承諾条件は早めに合意→掘削・復旧の費用と範囲を明文化。
道路幅員とセットバック線の確認
道路幅員は、建替え可否や配置計画に直結する重要項目です。現地では複数箇所で道路の反対側まで距離を測り、最小幅を特定します。
幅員が4m未満の場合は2項道路の可能性があり、道路中心線から2mの位置まで敷地を後退させるセットバックが必要になります。
中心線の位置は台帳・図面で確定し、現地の側溝や縁石、舗装端と一致しないことがあるため、必ず役所の根拠と照らし合わせます。
後退部分は原則として建築不可の扱いとなり、門塀・駐車・ポーチ計画に影響します。写真・寸法・後退線のスケッチをまとめ、設計者や役所の事前相談で整合を取ると、申請や工事がスムーズです。
- 複数点で幅員を測る→狭い箇所の数字を重視する。
- 中心線は台帳で確定→舗装端や側溝位置は目安に過ぎません。
- 後退部分は原則建築不可→外構・駐車計画を先に見直す。
| 状況 | 確認・計画の要点 | 資料 |
|---|---|---|
| 4m以上 | 接道2mを満たせば基本は良好 | 道路台帳、中心線、実測写真 |
| 4m未満 | 2項道路の後退線を確定→配置を再計画 | 中心線根拠図、後退線図、測量成果 |
| 不明・不整合 | 役所で道路判定→図番と担当を記録 | 照会記録、追補実測、スケッチ |
- 電柱・ボラード等が有効幅を狭める→最小値で判断する。
- セットバック後の舗装・排水の復旧費を見積→総コストに織り込む。
接道2mの確認と実測・境界確定の基本

接道2mの要件は、敷地が「建築基準法上の道路」に有効幅2m以上で接しているかを確認することです。見た目の幅ではなく、門柱・塀・ポール・メーター・植栽・電柱・段差などを差し引いた「有効幅」が基準になります。
まずは役所で道路種別・中心線・後退線の有無を把握し、法務局の公図・地積測量図で敷地の形と筆界を理解します。そのうえで現地にて、接道ラインの始点・終点を決め、複数箇所で幅を実測し、最小寸法を特定します。
測った位置が分かるよう写真に寸法を書き込み、障害物の種類と位置を併記すると、後日の照会・比較がスムーズです。
境界が不明確な場合や図面と現況に差がある場合は、測量士・土地家屋調査士への相談で「現況測量」や「境界確定」に進むと確実です。
- 役所で道路種別・中心線・後退線の有無を確認→根拠図の図番・日付を控える。
- 法務局で登記事項・公図・地積測量図を入手→筆界と寸法の根拠を確認。
- 現地で有効幅を複数点計測→最小値を重視し、写真+メモで記録。
| 段取り | 内容 | 記録・資料 |
|---|---|---|
| 事前確認 | 道路種別・中心線・後退線の有無 | 道路台帳、位置指定図、照会メモ |
| 図面収集 | 公図・地積測量図・登記事項 | 写しの保管、要点の付箋 |
| 現地実測 | 接道2m、前面道路幅、障害物 | 写真に寸法追記、スケッチ |
- 「最小寸法」を必ず押さえる→最も狭い箇所で判断。
- 門扉・塀・電柱などは有効幅を圧迫→位置とサイズを記録。
旗竿通路の有効幅と障害物のチェック
旗竿地の通路は、敷地が道路と接する「生命線」です。要件は「有効幅2m以上」で、門柱・塀・ポール・メーター類・植栽・計器ボックス・段差・側溝のフタのはみ出しなどを除いた幅で判断します。
計測は通路の始端から終端まで数メートルおきに行い、最も狭い箇所を特定します。門扉の開きしろや、車両が曲がる角度で内輪差が生じる箇所も要注意です。
1.9mなど僅差で不足する場合は、塀の移設や工作物の撤去、隣地の一部取得、通行地役権の設定など、複数の改善案を比較します。
私道の場合は、通行・掘削・占用の承諾条件が別途必要になることが多いため、早めに管理者・共有者の条件を確認し、書面化しておきましょう。
- 通路全長を複数点で計測→最小寸法とその位置を写真に明記。
- 門扉の開閉・メーター箱の出っ張り・花壇・車止めを個別に計測。
- 曲がり角・勾配・段差で有効幅が実質的に縮まる点をチェック。
| 障害物 | 影響 | 対処の方向性 |
|---|---|---|
| 門柱・塀 | 有効幅を直接圧迫 | 位置移設・幅詰め、隣地協議 |
| メーター・ポール | 局所的に狭窄を発生 | 管理者と移設可否を協議 |
| 植栽・花壇 | 根張り・越境で通路を圧迫 | 剪定・撤去・境界復旧の合意 |
| 段差・側溝 | 通行時の実効幅が減少 | 蓋交換・縁石加工・復旧計画 |
- 始端・中間・終端+曲がり角で計測→最小値を記録。
- 門扉の開き/内輪差を再現→写真に動線と寸法を追記。
袋地・隅切り・電柱など現地確認の要点
袋地(道路に面していない敷地)は、そのままでは接道を満たしません。通行地役権の設定、隣地の一部取得、通路新設などで道路への接続を確保できるかを検討します。
角地の隅切りは見た目の幅より有効幅が小さくなることがあり、曲線部や斜辺部で最小寸法を測ることが重要です。
電柱・支線・車止め・消火栓・ガードレール等の占用物は、通行や工事の実行性を下げるため、位置と占用幅を実測し、管理者の移設条件を確認します。
側溝の縁石や段差、舗装のズレが境界と一致しないケースも多く、図面(道路台帳・地積測量図)との照合作業を丁寧に行うと誤認を防げます。
- 袋地→通行権の確保(地役権・一部取得・通路新設)の可否を整理。
- 隅切り→曲線部・斜辺部で有効幅の最小値を実測し、写真に記録。
- 電柱など→占用物の幅と位置、移設可否・費用負担の原則を確認。
| 対象 | よくある影響 | 確認・対処の要点 |
|---|---|---|
| 袋地 | 接道ゼロ→建替え不可 | 通行地役権/一部取得/通路新設の実現性を比較 |
| 隅切り | 内輪差で実効幅が不足 | 曲線部の最小寸法、見切り線を実測 |
| 電柱・支線 | 有効幅・車両動線を阻害 | 管理者に移設条件を照会、代替位置を検討 |
| 側溝・縁石 | 境界と舗装端の不一致 | 台帳・測量図で位置を裏取り、復旧範囲を整理 |
- 最小寸法の位置を特定→写真・スケッチに反映しておく。
- 「舗装端=境界」とは限らない→必ず図面で照合する。
測量士・調査士に依頼する判断基準
接道の成立は、数センチの差で結果が変わることがあります。公図が古い、地積測量図がない、現地に境界標が見当たらない、道路中心線や後退線の位置に疑義がある、私道の境界が不明確、といった状況では、測量士・土地家屋調査士への依頼が有効です。
依頼メニューには、現況測量(現地形状の把握)、境界確定(関係者立会いのうえ筆界を確定)、確定測量に基づく図面作成(将来の売買・申請の基礎)などがあります。
成果物は「現況測量図」「境界確定図」「筆界確認書」等で、役所照会記録とセットで保存すると、売買・融資・申請の根拠として強力です。
費用・期間・関係者数は案件により大きく異なるため、複数社からの見積取得と工程表の比較をおすすめします。
- 境界標が欠損/不一致→境界確定を検討。
- 公図・地積測量図が不十分→現況測量で現地形状を把握。
- 道路中心線・後退線に疑義→役所照会+測量成果で裏付け。
| 依頼メニュー | 目的 | 主な成果物 |
|---|---|---|
| 現況測量 | 敷地形状・高低差・工作物の把握 | 現況測量図、写真・座標リスト |
| 境界確定 | 筆界を関係者立会いで確定 | 境界確定図、筆界確認書 |
| 申請用図面 | 売買・申請・設計の基礎資料 | 座標付き図面、復旧範囲の明示 |
- 過去図面・役所照会記録・現地写真を一式共有できるよう整える。
- 関係者(隣地・私道共有者)の連絡先をリスト化→立会い調整を容易にする。
役所での照会先と必要書類の取り方

再建築不可かどうかを正確に見極めるには、関係窓口で「道路の法的な位置づけ」「中心線・後退線」「境界や幅員」の根拠資料をそろえることが大切です。
基本の順番は、建築指導課で道路種別と中心線・後退線の有無を確認→道路管理課(または土木事務所)で道路台帳・境界・幅員を確認→都市計画課で用途地域や地区計画などの制限を確認、です。
並行して法務局で登記事項・公図・地積測量図を取得し、書類と現地実測を突合します。照会は口頭だけにせず、図面名・図番・作成日・担当部署をメモし、写しを可能な範囲で取得して保管しましょう。
上下水道・ガス等のインフラ窓口で引込や掘削の条件を確認しておくと、のちの設計や工事計画がスムーズになります。
- 窓口ごとに聞く内容を分ける→建築指導課は「法上の道路」、道路管理課は「境界・幅員」。
- 地番・案内図・現地写真を持参→説明が伝わりやすく確認が早いです。
- 取得した図面は図番と日付を必ず記録→根拠の一貫性を確保します。
| 窓口 | 主な確認内容 | 持参・入手するもの |
|---|---|---|
| 建築指導課 | 42条1項/2項の別、中心線、後退線、位置指定の有無 | 地番・案内図、登記事項・公図の写し、現地写真 |
| 道路管理課 | 道路台帳、幅員、境界、占用・掘削の取り扱い | 対象位置図、過去の図面番号、占用物の写真 |
| 都市計画課 | 用途地域、地区計画、道路予定線、各種指定 | 住所・地番、都市計画図の写し |
- 地番・家屋番号・案内図(Google印刷可)・現地写真。
- 登記事項・公図・(あれば)地積測量図の写し。
建築指導課・道路管理課での確認事項
建築指導課では、まず対象の接面道路が「建築基準法上の道路」かどうかを確認します。
42条1項道路(道路法の道路、都市計画事業の道路、既存4m以上の道、位置指定道路等)なのか、42条2項道路(みなし道路)なのかで、求められる要件が変わります。
中心線の位置と後退線(セットバック)の要否、位置指定道路なら指定番号・指定日・幅員・延長・端部の接続先も控えます。
道路管理課(または土木事務所)では、道路台帳をもとに境界・幅員・管理区分・占用や掘削の可否を確認します。
舗装端や側溝が境界と一致しないことがあるため、台帳の線と現地の線を混同しないよう注意が必要です。
- 建築指導課→法上の道路種別・中心線・後退線・位置指定の有無を特定。
- 道路管理課→幅員・境界・占用/掘削の扱い・復旧基準を確認。
- 不一致があれば現地写真と図面で再照会→図番・担当・日付を記録。
| 窓口 | 確認項目 | 記録ポイント |
|---|---|---|
| 建築指導課 | 42条1項/2項、中心線、後退線、位置指定番号 | 図面名・図番・作成日、担当者名、参照台帳 |
| 道路管理課 | 道路境界、幅員、占用・掘削の手続 | 道路台帳のページ番号、復旧仕様、連絡窓口 |
- 「舗装端=境界」と思い込みやすい→必ず台帳で境界線を確認。
- 口頭回答のみは危険→図番・日付・担当をメモ、写し取得を検討。
道路台帳・都市計画図・公図の読み方
道路台帳は、道路の幅員・境界・管理区分などを確認する資料で、境界線や中心線の位置を把握するのに有効です。都市計画図は、用途地域・道路予定線・地区計画など、建築や開発に関わる規制を俯瞰できます。
公図は筆の配置を示す概略図で、隣接地との位置関係の把握に役立ちますが、縮尺の歪みや古さがあるため、寸法や境界確定の根拠としては地積測量図や確定測量成果を優先します。
これらを相互に照らし、現地写真・実測メモと突合することで、接道2mや後退範囲の判断がぶれにくくなります。
- 道路台帳→境界・幅員・中心線の根拠。舗装端とズレることあり。
- 都市計画図→用途・地区計画・道路予定線などの制限を俯瞰。
- 公図→筆の位置関係の把握用。寸法根拠は地積測量図を優先。
| 資料 | 内容 | 読み方・注意点 |
|---|---|---|
| 道路台帳 | 境界線、幅員、中心線、管理情報 | 図番と作成日を確認→境界と舗装端の差を意識 |
| 都市計画図 | 用途地域、地区計画、道路予定線 | 縮尺に注意→最新更新日を確認し台帳と整合 |
| 公図 | 筆の配置・形状の概略 | 概略図で誤差あり→寸法判断は測量図を用いる |
- 台帳の線→現地の構造物と必ずしも一致しない→写真と重ねて確認。
- 図ごとに更新日が違う→作成年月を併記して保管。
建築確認台帳・位置指定図面の取得方法
建築確認台帳は、過去に建築確認を受けた建物の概要を記録する資料で、建築指導課や保管部署で閲覧・写し交付の可否や手続が定められています。
申請者名や年代、所在地(住所・地番)が分かると特定が早まります。位置指定道路の図面は、指定番号・指定年月日・幅員・延長・端部の接続先などが記載され、同じく建築指導課で閲覧・写しの相談をします。
いずれも個人情報や非公開部分があるため、閲覧に制限がかかるケースがあります。事前に電話等で必要情報と手数料、閲覧日時の予約可否を確認すると効率的です。
取得後は図番・作成日・担当部署を明記し、現地写真と一緒にファイル化すると、売買・融資・設計時の根拠として活用できます。
- 建築指導課に連絡→建築確認台帳・位置指定図面の閲覧可否と手続を確認。
- 必要情報(住所・地番・申請者名・おおよその年代)と身分証、手数料を準備。
- 閲覧・写し取得→図番・作成日・担当をメモし、現地写真と突合して保存。
| 資料 | 入手先・手続 | 実務ポイント |
|---|---|---|
| 建築確認台帳 | 建築指導課等で閲覧・写し(可否は自治体規定) | 申請者名・年代が分かると特定が早い |
| 位置指定図面 | 建築指導課で番号・指定日をもとに検索 | 幅員・端部接続・側溝の位置まで確認 |
- 個人情報保護で一部閲覧不可のことあり→事前確認が安心。
- 写しは図番・作成日を必ず併記→後日の根拠提示が容易。
例外許可と専門家への相談の基本

再建築不可の判定に近い状況でも、法の枠内で建築を認める例外制度や、調査の精度を高める専門家の関与によって計画の可能性が変わることがあります。中心となるのは、建築基準法43条2項許可(いわゆるただし書許可)の検討です。
これは「法上の道路に2m以上接していない」などの不利条件がある敷地でも、避難・通行・消防活動に支障がないことを具体的な措置で示すことで、例外的に建築を認めるかを個別審査で判断するものです。
実務では、役所の事前相談→現況測量や通行経路の成否確認→承諾書や配置計画の整備→申請という流れを、建築士・土地家屋調査士・測量士らとチームで進めます。
通行・掘削・占用など私道の承諾関係は早めに書面化し、台帳・図番・根拠図をそろえて提出根拠を明確にすると、審査がスムーズです。
- 役所の事前相談で審査観点を把握→必要資料と改善項目を確定する。
- 専門家と計画を分解→通行・消防・安全・周辺影響の各論点を図面化。
- 承諾関係・後退線・境界の根拠を整理→写しと図番を添付して可視化。
| 論点 | 主な確認内容 | 関与が想定される専門家 |
|---|---|---|
| 通行の確実性 | 有効幅・距離・常時通行の担保 | 建築士、土地家屋調査士、弁護士(契約) |
| 防災・安全 | 消防進入口・避難動線・視認性 | 建築士、消防との協議 |
| 権利・承諾 | 私道通行/掘削/占用の書面化 | 不動産業者、弁護士、管理者 |
- 「事前相談→測量・図面→承諾→申請」の順で整える。
- 根拠は図面名・図番・作成年月日まで記録して一式保管する。
43条2項許可の検討と事前相談のポイント
43条2項許可は、通常の接道要件を満たさない敷地であっても、安全性や通行確保の措置を講じることで建築を例外的に認める仕組みです。
審査は自治体ごと・敷地ごとに個別判断となるため、事前相談が不可欠です。
まず、現況測量と写真・動画で通行経路の幅・勾配・段差・見通し・夜間照明の有無を可視化し、必要に応じて隣地や私道の通行承諾案を用意します。
消防活動の観点(進入口の確保、可搬式資機材の搬入可否、延焼遮断など)を図面で説明できるよう、配置計画に逃げ経路・非常動線を反映させます。
審査中の指摘に対応できるよう、改善案(照明追加・段差解消・路肩整備・鍵管理の明確化等)を複数用意しておくと前進しやすいです。
- 経路の実態→幅・距離・段差・見通し・夜間照明を数値と写真で提示。
- 承諾の整備→隣地・私道の通行/掘削/占用承諾書案を準備。
- 安全計画→消防進入口と避難動線を配置図・断面図で説明。
| 審査視点 | 具体例 | 準備資料の例 |
|---|---|---|
| 通行の確実性 | 常時開放、鍵管理、幅の確保 | 通行承諾書、鍵運用規程、実測図 |
| 安全・防災 | 消防ルート、夜間の視認性 | 配置計画、照明計画、写真 |
| 周辺影響 | 通行量・騒音・プライバシー | 説明資料、合意形成メモ |
- 見た目の道を根拠にしない→台帳と図番で中心線・境界を裏付け。
- 口頭合意のまま進めない→承諾は目的・期間・復旧方法まで書面化。
不動産調査の依頼先と費用・納期
再建築可否の判断は、書類と現地の突合が要となるため、専門家への依頼で精度と説明力を高めます。
一般に、土地家屋調査士・測量士は境界や現況測量、建築士は配置・避難・消防対応を含む計画図、司法書士は権利関係の登記、弁護士は通行・掘削・占用承諾の契約整備、不動産事業者は相場把握や近隣調整に強みがあります。
費用・納期は、関係者の人数(共有者・隣地所有者)、境界の難易度、図面・書類の有無、自治体の審査プロセスで大きく変動します。
まずは課題を分解し、必要業務の範囲と成果物(図面・承諾書・写真台帳など)を明確化したうえで複数見積を取り、工程と提出物のチェックリストで進行管理を行うと、手戻りを抑えられます。
- 業務範囲を明確化→測量範囲・図面種別・承諾書の有無を合意。
- 成果物を定義→図面名・図番・作成年月日・写真台帳の形式を指定。
- 工程を可視化→事前相談日程・立会い・提出締切をカレンダー化。
| 依頼先 | 主な役割 | 成果物の例 |
|---|---|---|
| 土地家屋調査士/測量士 | 現況測量・境界確定・筆界確認 | 現況測量図、境界確定図、筆界確認書 |
| 建築士 | 配置・避難計画・事前相談対応 | 配置図、動線図、許可対応の修正案 |
| 司法書士/弁護士 | 権利・承諾・契約の整備 | 通行/掘削/占用承諾書、合意書 |
| 不動産事業者 | 相場資料・近隣調整・販売計画 | 需要データ、説明資料、販売戦略案 |
- 費用と納期は案件条件で変動→複数社の提案を比較し根拠を確認。
- 提出物チェックリストで検収→不備は早期に差戻し是正する。
売買前の重要事項と表示を読み解くコツ
売買段階では、「重要事項説明」と広告表示を丁寧に読み解くことが、トラブル回避と妥当な価格判断につながります。
特に、建築基準法上の道路種別、接道長さ2mの成否、前面道路幅員とセットバック要否、私道の通行/掘削/占用承諾、位置指定道路の番号・指定日、後退部分の取り扱い(原則建築不可)、インフラ引込の可否、既存建物の不具合履歴(雨漏り・腐食等)は確認の要です。
表示に「再建築不可」「要セットバック」等の文言がある場合は、その根拠図面と照会記録の写しを求め、図番・作成日・担当部署を控えます。
現地写真と図面の不一致があれば、その場で追加照会や再測を依頼し、合意内容は図面に反映して保存すると安全です。
- 道路・接道→種別・中心線・後退線・接道長さ2mの成否を根拠付きで確認。
- 私道→通行/掘削/占用承諾と管理者の連絡先を特定し、期間・復旧方法を合意。
- 既存建物→不具合履歴・修繕記録・設備年式を資料で確認。
| 項目 | 見るべき表示 | 根拠・確認資料の例 |
|---|---|---|
| 道路・接道 | 再建築不可、要セットバック 等 | 道路台帳、位置指定図、照会記録、実測写真 |
| 私道関係 | 私道負担、承諾の有無 | 通行/掘削/占用承諾書、管理規約の写し |
| 建物・設備 | 不具合履歴、改修の有無 | 点検記録、修繕報告書、設備仕様書 |
- 広告の短い文言だけで判断しない→根拠図面と照会記録の写しを取得する。
- 口頭説明は必ず書面化→合意内容は図面・写真に反映して保管する。
まとめ
再建築不可の調査は、役所での道路種別の確認→登記・公図・道路台帳の収集→接道2mと幅員の実測→位置指定・セットバックの確認→必要に応じて測量士等と43条2項許可の事前相談、の順が効率的です。
根拠資料をそろえれば、購入判断や価格交渉の精度が高まり、無用なトラブルを避けられます。