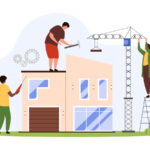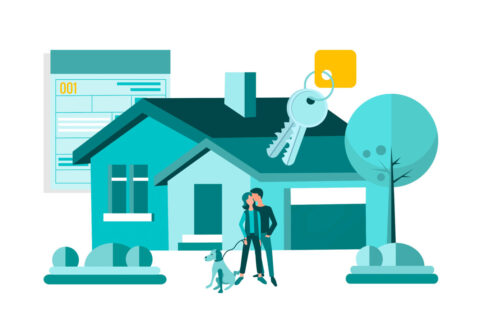再建築不可でフラット35は原則むずかしい一方、条件を満たせば可能性が残る場合があります。この記事は〈接道2mなど技術基準〉〈43条2項・位置指定による接道確保〉〈適合証明の取得手順〉〈区域やマンションの取扱い〉〈不適合の典型〉を整理。
さらに民間・プロパー等の代替ローン比較まで、購入前に確認すべき順番と必要書類を“実務の型”で解説します。
目次
フラット35の基本要件と再建築不可の関係

フラット35は「機構(住宅金融支援機構)が定める技術基準に適合していること」を前提に、第三者の物件検査を受けて「適合証明書」を取得する必要があります。
技術基準には、原則として敷地が一般の道に2m以上接すること(接道2m)、住宅の規模(目安:戸建70㎡以上・マンション等30㎡以上)、(中古の場合)新耐震相当の耐震性などが含まれ、検査に合格してはじめて融資対象になります。
新築は建築基準法の検査済証の確認も行われます。また、資金使途は「自ら居住する住宅等」に限定され、投資目的の取得は認められていません。
これらの前提から、接道を満たしにくい再建築不可は原則として適合証明の取得が難しく、フラット35の利用も難しくなります。
一方で、接道確保(位置指定・セットバック・43条2項許可に基づく通路確保等)により要件を満たせば、適合の可能性が生まれます。
- 技術基準→適合証明(第三者検査)に合格することが必須です。
- 接道2m・面積・(中古)耐震などを満たさないと不適合になります。
- 居住要件→投資目的(自己居住なし)は不可です。
| 要件 | 概要 | 確認・根拠 |
|---|---|---|
| 接道 | 原則、一般の道に2m以上接する | 技術基準ページ・適合証明の有無 |
| 面積 | 戸建70㎡以上/共同住宅30㎡以上(目安) | 技術基準の規模要件 |
| 耐震(中古) | 昭和56年6月1日以後の建確、または耐震評価基準適合 | 中古技術基準の耐震要件 |
| 居住要件 | 自ら居住(投資目的は不可) | 不適正利用の注意喚起 |
- 技術基準の該当性→接道・面積・耐震を一次資料で確認。
- 適合証明の取得可否→検査機関に事前相談。
技術基準の要点(接道2m・耐震・面積)
まず「接道2m」は、敷地が原則として一般の道に2m以上接していることを求めるものです。フラット35の技術基準自体が明記しており、接道不足の宅地は適合証明が出ない可能性が高まります。
なお、建築基準法の接道義務は「幅員4m以上の道路に2m以上接すること」が原則で、これを満たさず再建築不可となるタイプは、技術基準の接道要件にも抵触しやすい点に注意が必要です(2項道路の後退で是正できる場合は別途確認)。
次に「耐震」。中古住宅は新耐震相当が要件で、建築確認日が昭和56年6月1日以後であること、または耐震評価基準に適合することが求められます。
最後に「面積」。戸建はおおむね70㎡以上、共同住宅は30㎡以上が目安です。これらは適合証明の審査項目であり、満たさないとフラット35の利用はできません。{index=5}
- 接道2m→一般の道に2m以上接することが原則(技術基準)。{index=6}
- 耐震(中古)→新耐震相当(昭和56年6月1日以後)か、耐震評価基準適合。
- 面積→戸建70㎡以上・共同住宅30㎡以上(目安)。
| 項目 | 主要ポイント | 確認書類の例 |
|---|---|---|
| 接道 | 2m以上の接道が原則。2項道路は後退の扱いに注意 | 適合証明書、道路台帳、位置指定図 |
| 耐震 | 中古は新耐震か耐震評価基準適合 | 建築確認通知書、評価報告書 |
| 面積 | 戸建70㎡以上/共同30㎡以上 | 登記事項証明書、図面 |
- 「最小値」を重視→接道は最狭部で2mを満たすかを写真+寸法で確認。
- 中古の耐震は年式だけで判断せず、評価基準適合の可否も検討。
なぜ再建築不可は対象外になりやすいか
再建築不可の多くは、建築基準法上の接道義務(幅員4mの道路に2m以上接する原則)を満たしていないことが原因です。
この状態では、フラット35の技術基準が求める「原則、一般の道に2m以上接すること」に抵触しやすく、適合証明が出ずに融資対象外となる可能性が高くなります。
さらに、中古で旧耐震のまま耐震性が確認できない、面積が基準未満、私道承諾が未整備で実務上の通行や掘削が担保されない、といった要因が重なると、審査の前提を満たせません。
投資目的での取得は制度趣旨に反し、フラット35自体の利用が認められていない点も押さえておくべき論点です。
接道確保(位置指定・後退・43条2項許可に基づく安全な通路)や耐震の評価・補強で基準を満たし、適合証明の取得可否を検査機関に事前相談することが、唯一の現実的アプローチになります。
- 接道不備→技術基準の「接道2m」に抵触しやすい。
- 耐震・面積→中古の新耐震要件や面積基準を満たせない例がある。
- 承諾未整備→私道の通行・掘削の実効性が示せず不適合要因に。
| 原因 | 融資審査への影響 | 打ち手の方向性 |
|---|---|---|
| 接道不足 | 技術基準の接道要件を満たせず適合困難 | 位置指定・通路新設・セットバックの検討 |
| 耐震不明/不足 | 中古の耐震要件に適合しない | 耐震評価・補強の可否を専門家に確認 |
| 承諾未整備 | 通行・掘削の常時性が担保できない | 承諾書の取得・復旧条件の明文化 |
- 「舗装端=境界」とは限らない→台帳で境界線を裏取りして接道2mを判定。
- 投資目的の利用は不可→自己居住要件を満たさないと制度外です。
使える可能性のあるケースと確認手順

フラット35の利用可否は「技術基準に適合しているか」を第三者が確認できるかどうかに尽きます。再建築不可でも、接道条件の是正や例外許可により実質的に要件を満たし、適合証明が取れる見込みがあれば道は残ります。
現実的な順番は、役所で道路種別・中心線・後退線を確定→現地で接道2mと最狭部の実測→私道の承諾(通行・掘削・占用)の整備可否を確認→救済ルート(位置指定、43条2項2号、セットバック、隣地一部取得・地役権)の実現性を比較→検査機関に事前相談→適合証明の本審査という流れです。
投資目的のみではフラット35は使えないため、自己居住の計画と入居時期の見通しも同時に整理します。
- 最初に事実を確定→接道2m・道路幅員・中心線・後退線の有無を裏付ける。
- 救済の実行力→承諾書・工事・復旧の計画を“書面で”揃える。
- 検査機関に早期相談→不足資料と改善点を明確化し、手戻りを抑える。
| 段階 | 確認・整備する内容 | アウトプット |
|---|---|---|
| 事実確定 | 道路種別・接道2m・幅員・後退線 | 道路台帳写し、実測写真、照会記録 |
| 救済選定 | 位置指定・43条・セットバック等の可否 | 比較表(費用・期間・合意難度) |
| 証拠整備 | 承諾書・配置/復旧図・工程 | 通行/掘削/占用承諾、復旧仕様書 |
| 適合相談 | 技術基準への適合見込み | 不足資料リスト、改善指示メモ |
- 「接道の最狭部」「承諾の有無」「後退線の位置」を先に特定する。
- 救済は可否→価値→費用/期間の順で優先付けし、検査機関へ根拠付きで相談。
43条2項2号・位置指定・接道確保
接道確保の王道は〈位置指定道路(42条1項5号)〉で、通路を所定の仕様で整備し、完了検査・告示により「法上の道路」として扱ってもらう方法です。恒久性が高く、接道2mを満たせば建替え・配置計画が一気に現実味を帯びます。
次に〈43条2項2号許可〉は、法上の道路に2m接していなくても、通行の常時性と安全を具体策(有効幅の確保、照明、段差解消、承諾書等)で担保できる場合に、特定行政庁が例外的に建築を認める仕組みです。
もう一つの実務策が〈物理的な接道確保〉で、隣地一部取得・通行地役権・通路新設・セットバックなどを組み合わせ、最狭部で有効2mを確保します。
いずれのルートでも「承諾の実効性」「復旧仕様」「写真・図面の整合」を可視化できるかが鍵で、適合証明の審査でも根拠資料として重視されます。
- 位置指定→仕様整備+完了検査で「法上の道路」化。恒久性が高い。
- 43条2項2号→通行の常時性・安全確保を個別審査。資料の厚みが勝負。
- 物理確保→隣地取得・地役権・後退で最狭部2mを達成。承諾と復旧を明記。
| 手段 | 強み | 留意点 |
|---|---|---|
| 位置指定道路 | 恒久解で再販・設計自由度が高い | 仕様・工事・検査・告示が必要→費用/期間は重め |
| 43条2項2号 | 既存条件でも許可の可能性がある | 自治体運用差・個別審査→証拠の充実が必須 |
| 接道2mの物理確保 | 比較的シンプルに達成できる場合あり | 承諾・復旧・越境処理がボトルネック |
- 恒久性(位置指定)か即効性(43条/物理確保)かを用途と予算で選ぶ。
- どのルートでも“承諾+復旧+最狭部2m”の三点セットを揃える。
適合証明の手順と検査機関への相談
適合証明は、技術基準への適合を第三者が確認し、「適合証明書」を発行するプロセスです。効率よく進めるには、事前相談で不足資料と改善点を洗い出すことが不可欠です。
まず、道路台帳写し・位置指定図・43条関連の協議記録、写真付きの現況測量図(最狭部の寸法を赤字)、通行/掘削/占用の承諾書案、後退線の根拠図、配置/復旧図、(中古なら)耐震評価や建築確認関係の写しを束ねます。
検査機関では、接道2mの最狭部、道路幅員と中心線、承諾の常時性、救済による是正後の状態、自己居住要件の充足などを総合的に確認します。
指摘が出たら、照明追加・段差解消・経路変更・承諾の追補で再提出。書類はページ番号と図番、撮影日を入れて“同じ結論にたどり着く”構成にすると合格率が高まります。
- 事前相談→不足資料を特定し、提出順と書式を合わせる。
- 測量・写真→最狭部の寸法と場所を写真+図で二重表示。
- 承諾→目的/期間/復旧/費用/連絡先まで明記し、常時性を担保。
| ステップ | 目的 | 主な書類 |
|---|---|---|
| 事前相談 | 適合見込みと不足の把握 | 照会記録、現況図、写真、承諾書案 |
| 本申請 | 技術基準適合の立証 | 位置指定図/43条資料、後退根拠、配置図 |
| 是正対応 | 指摘事項の解消 | 追加写真、修正図、追補承諾 |
- “基準→証拠→図面”の順でファイル化し、ページ見出しを統一。
- 昼夜・晴雨の写真を用意→通行の常時性と安全性を客観的に示す。
都市計画区域内外・戸建とマンションの違い
区域や建物種別で「確認先」と「判定の視点」が変わります。都市計画区域・準都市計画区域では、建築指導課や道路管理課の台帳で道路種別・中心線・後退線の確認が要です。
区域外でも、フラット35の技術基準は原則同じ視点(接道2m、面積、耐震等)で見られるため、結局は“第三者が客観資料で適合を判断できるか”がポイントです。
戸建は個別敷地で接道2mが問われ、旗竿地や私道承諾など“現地の最狭部”がボトルネックになりがちです。
一方マンション等の共同住宅は、敷地全体の接道・避難性・耐震性が主眼で、専有面積の下限(目安30㎡)や共用部の避難動線がセットで評価されます。
接道は管理組合や土地共有関係の書類で立証する場面が多く、私道の承諾範囲や鍵運用の常時性を、規約や覚書で補強しておくと審査がスムーズです。
- 区域内外→技術基準の視点は同様だが、確認窓口や台帳の形式が異なる。
- 戸建→個別敷地の最狭部2mと私道承諾が焦点。復旧仕様まで明記する。
- マンション→敷地全体の接道・避難動線・専有面積の下限を確認。規約類で補強。
| 区分 | 確認の主眼 | 資料の例 |
|---|---|---|
| 都市計画区域内 | 道路種別・中心線・後退線の台帳確認 | 道路台帳、位置指定図、照会記録 |
| 区域外 | 同様の視点で適合性を資料化 | 現況測量図、実測写真、承諾書 |
| 戸建 | 最狭部2m、私道承諾、配置・復旧 | 通行/掘削承諾、配置/復旧図 |
| マンション | 敷地全体の接道、避難、専有面積 | 管理規約、敷地利用権、避難計画図 |
- マンションは“敷地全体の接道”で判断される→個別住戸の玄関前の幅だけで判断しない。
- 区域外でも根拠は同じ→写真・図面・承諾の厚みが適合可否を左右する。
使えないケースの判断基準と注意点

フラット35は「技術基準に適合していること」を第三者が書面と現地で確認してはじめて利用できます。
したがって、接道2mを満たせない、法上の道路に接していない、私道の通行・掘削承諾が取れない、耐震の裏付けがない(旧耐震で評価未実施・補強計画なし)、面積が基準未満、違反建築状態が残っている(無確認の増改築・未是正)、自己居住要件を満たさない(投資のみ)などは、原則として適合証明が発行されにくい状況です。
判断を誤らないコツは、書類(道路台帳・位置指定図・登記・測量)と現地(最狭部の実測・障害物)の突合を最初に行い、満たせない項目がある場合は「是正できるのか」「代替資金に切り替えるのか」を早期に決めることです。
特に接道は数センチの差で可否が変わるため、門塀・電柱・メーターなどの突出物を控除した“有効幅”で判定します。
- 接道・道路→法上の道路か、最狭部で有効2m以上か、後退線の確定があるか。
- 私道承諾→通行・掘削・占用を目的別に書面化できるか。
- 耐震・面積→中古は新耐震相当か評価適合か、面積が下限以上か。
| 論点 | 使えない判断の典型 | 確認・是正のヒント |
|---|---|---|
| 接道 | 法上道路でない/有効2m不足/後退未了 | 道路台帳・中心線・最狭部写真→位置指定・後退・通路新設を検討 |
| 私道承諾 | 通行は口頭のみ/掘削・占用の同意が取れない | 承諾書(目的・範囲・復旧)を整備、同意者の範囲を確定 |
| 耐震・面積 | 旧耐震で評価なし/戸建70㎡未満等 | 耐震評価・補強の可否確認、面積不整合は図面・登記を修正 |
| 違反・居住 | 違反建築の是正未了/自己居住なし | 是正完了の証憑を整備、資金計画は自己居住前提で組立て |
- 法上の道路に接していない+救済が実現困難(承諾不可・用地取得不可)。
- 旧耐震で補強不能、または面積基準を満たせない構造的制約がある。
接道・私道承諾・耐震で不適合の典型
不適合の大半は「接道」「私道承諾」「耐震」でつまずきます。
接道では、見た目は2mあっても門柱・塀・電柱・メーター・支線・花壇などで“有効幅”が2mを割り込む例が多く、最狭部の実測と写真が決定打になります。
法上の道路でない通路(農道・通路扱いの私道等)は、位置指定や後退での是正検討が不可欠です。
私道承諾は、通行の承諾があっても掘削(上下水・ガス・電気)や占用(足場・資材置場・後退復旧)が別承諾の対象となる点を見落としがちで、工事段階で止まる典型例です。
耐震では、旧耐震の中古で評価未実施、もしくは評点不足・補強不能(構造上の制約・コスト過大)が壁になります。
これらは「書類での裏付け」が弱いほど適合証明が出にくくなるため、道路台帳・位置指定図・現況測量図・承諾書・耐震評価報告などを“同じ結論に収束する構成”で束ねることが重要です。
- 接道→最狭部の有効幅が2m未満、または法上の道路でない通路のみ。
- 私道承諾→通行は可だが掘削不可、占用不可でインフラ更新ができない。
- 耐震→旧耐震で評価未実施、または評点不足・補強計画なし。
| 論点 | 不適合の典型 | 代替策・是正案 |
|---|---|---|
| 接道 | 有効2m不足/法上道路でない | 隣地一部取得・地役権・通路新設・位置指定・後退 |
| 私道承諾 | 掘削承諾が得られず配管更新不可 | 承諾書の再交渉(復旧仕様・費用負担を明記) |
| 耐震 | 旧耐震で評点不足・図面不整合 | 耐震評価→補強案(費用対効果を比較) |
- 「舗装端=境界」と誤認→台帳・測量で境界線を裏取りせず最狭部が不足。
- 通行承諾だけで安心→掘削・占用の別承諾がなく工事が止まる。
接道ありでも適合証明が出ないケース
形式上は“接道あり”でも、適合証明が発行されない事例があります。典型は「有効幅の最狭部が2mを割る」ケースで、門柱・電柱・メーターボックス・支線・花壇・植栽・段差などが接道の有効幅を局所的に狭めているタイプです。
2項道路では、後退線が未確定・未実施で、後退後の有効宅地が大きく減る、外構・機器類が後退部分にかかる、といった設計上の不整合も不適合要因になります。
私道の場合は、接道していても通行は可・掘削不可でインフラ更新ができない、鍵・ゲートの運用で常時性が担保できない、といった運用面の課題でNGになることがあります。
さらに、図面と現地の不一致(位置指定図と現況の幅員差、道路中心線の取り違え)、違反建築の是正未了、マンションでは敷地全体の接道証拠や管理規約が不十分、専有面積が下限未満等も該当します。
- 最狭部が不足→障害物で実効幅が2m未満(写真・寸法で判明)。
- 2項道路の後退未了→後退線不明、後退後の配置不整合で不適合。
- 私道の常時性不足→掘削不可・鍵管理不明で通行の実効性が担保できない。
- 図面不整合→位置指定図・道路台帳と現況が一致せず、根拠が弱い。
| 症状 | なぜNGになるか | 是正・対応の方向性 |
|---|---|---|
| 最狭部不足 | 基準の「有効2m」を満たさない | 障害物移設、隣地一部取得、地役権、通路拡幅 |
| 後退未実施 | 2項道路で後退線不明・未了 | 中心線確定→後退線設定→外構・機器再配置 |
| 承諾未整備 | 通行は可でも掘削・占用不可 | 承諾別紙(目的・範囲・復旧)で追補合意 |
| 図面と現況のズレ | 根拠資料と実態が一致しない | 現況測量で再作図、写真台帳で一致を証明 |
- 最狭部の実測値を写真に追記→障害物の寸法・位置も記録。
- 私道は常時性と掘削の可否まで書面化→鍵・復旧・費用の取り決めを明確に。
資金計画と代替ローンの現実的選択

再建築不可の物件は、フラット35の利用が難しくなるため、最初から「複線の資金計画」で臨むのが現実的です。
具体的には、接道や適合証明の見通しを追いながら、同時並行で民間住宅ローン・プロパーローン(事業性)・リフォームローン等の代替手段を比較し、どの条件でも最終決定できる“出口の確保”を意識します。
重要なのは、自己資金の厚み(頭金+予備費)、担保余力(他不動産の活用可否)、資金用途(購入・改修・後退復旧・測量費など)の切り分け、そして審査スピードと金利水準のバランスです。
承諾の取得や後退工事は予定外の費用が出やすいため、見積の上下振れを前提とした予備費(目安として工事・復旧費の上乗せ)を最初から組み込みましょう。
- 複線化→フラット35が難航しても「民間/プロパー/リフォーム」で決められる設計に。
- 費用の棚卸→購入・測量・承諾取得・後退復旧・インフラ移設・設計/申請を分離計上。
- 時間軸→承諾取得→設計→審査→工事の順でボトルネックを先行処理。
| 選択肢 | 向いているケース | 主な留意点 |
|---|---|---|
| 民間住宅ローン | 自己居住前提で適合証明が見込める/軽微な是正で済む | 評価厳格化の可能性→頭金厚め・属性で補完 |
| プロパーローン(事業性) | 賃貸化・複数物件保有・担保追加で柔軟に組みたい | 計画・返済原資の説明力、金利は相対的に高め |
| リフォーム/リノベ | 耐震・外構・後退復旧など改修費の一部を別枠で調達 | 金利高め/期間短め→費用対効果を精査 |
- 可否の見極め→接道・承諾・適合証明の見通しを先に判定。
- 複線の用意→民間/プロパー/リフォームを同時比較して“最終案”を確保。
民間ローン・プロパー・リフォームの比較
民間住宅ローンは、自己居住を前提に審査が行われ、金利水準は比較的低めで長期固定や変動など選択肢も豊富です。
一方で、再建築不可や接道不備の疑いがある物件では担保評価が伸びづらく、頭金の上積みや他担保の追加が求められる場合があります。
プロパーローン(事業性)は、賃貸化・複数物件保有・法人化など、事業としての返済原資が説明できるときに選択肢となり、審査の自由度が高い反面、金利は相対的に高く、返済期間やLTVの設定も個別交渉になります。
リフォーム(リノベ)ローンは、耐震補強・外構のやり替え・セットバック後の復旧など、工事費の一部を機動的に賄えるのが利点ですが、無担保型は金利が高め・期間短め、有担保型は手続が増えるなど一長一短です。
実務では、購入資金は民間住宅ローンかプロパーで確保し、工事部分をリフォームローンで分離する「二本立て」も検討対象になります。
- 民間住宅ローン→低金利・長期可。適合証明や自己居住の条件を満たす前提。
- プロパーローン→用途や返済原資の説明が鍵。担保追加や短期リファイナンス戦略も視野。
- リフォームローン→改修費を機動的に手当て。金利と期間のバランスを吟味。
| 項目 | 民間住宅ローン | プロパー/リフォーム |
|---|---|---|
| 金利・期間 | 低め/長期可(属性・物件次第) | やや高め/中短期が中心(個別交渉) |
| 審査の視点 | 自己居住・適合証明・担保評価 | 返済原資(賃料・事業CF)・担保余力 |
| 使い分け | 購入資金のメイン枠 | 不足分や工事費の補完/機動的な改修 |
- 同時進行の申込は「条件付与・期限」を整理→時期のズレで失効しないよう管理。
- 工事見積は内訳を細かく→購入資金と改修資金を金融機関ごとに説明可能に。
自己資金・担保追加・金利感度の考え方
再建築不可の資金計画では、自己資金の厚みが交渉力を左右します。頭金の上積みは審査を通しやすくするだけでなく、承諾取得や後退復旧など“現金でしか動かない工程”の遅延を防ぎます。
加えて、他不動産の担保追加や保証人の活用は、LTV(融資割合)の調整と金利条件の改善に有効です。
金利感度は「家賃や返済原資が想定よりブレた場合に、返済がどこまで耐えられるか」を測る重要な視点で、表面利回りだけではなく、空室・修繕・承諾取得費・復旧費・保険・税を含めた実質キャッシュフローで試算します。
簡易には、金利+0.5%・+1.0%のシナリオ、工事費+10%のシナリオ、賃料−5%のシナリオを同時に当て、年間の返済余力(年間CF)とDSCRの下振れを確認すると安全域が把握しやすいです。
予備費は、工事・復旧・承諾関連の想定外コストを吸収できるサイズで確保しましょう。
- 自己資金→頭金+予備費+初年度修繕費まで含めて設計する。
- 担保追加→別物件の余力や共同担保でLTV・金利を調整。
- 金利感度→金利上昇・費用増・賃料減の同時ショックで耐性を確認。
| 論点 | 実務ポイント | チェックの着眼点 |
|---|---|---|
| 自己資金 | 頭金の厚みで審査/条件が改善 | 承諾・復旧など現金決済工程の資金を確保 |
| 担保追加 | 共同担保で評価補完・条件緩和 | 設定費用・売却時の制約も同時に確認 |
| 金利感度 | 複数シナリオで年間CF/DSCRを試算 | 金利+1.0%、費用+10%、賃料−5%でも黒字か |
- 予備費は“工事・復旧・承諾”の合計見積に上乗せして確保する。
- 金利・費用・賃料の感度を同時に当て、赤字化ラインを事前に把握する。
まとめ
フラット35の可否は、技術基準の充足→接道確保(43条・位置指定・後退)→適合証明の取得可否で決まります。
まず図面と役所照会で事実を確定し、検査機関へ早期相談。並行して民間・プロパー・リフォーム等の代替資金も比較し、自己資金や担保追加を含めた複線化で実現性を高めましょう。根拠資料を整えるほど交渉と出口が安定します。