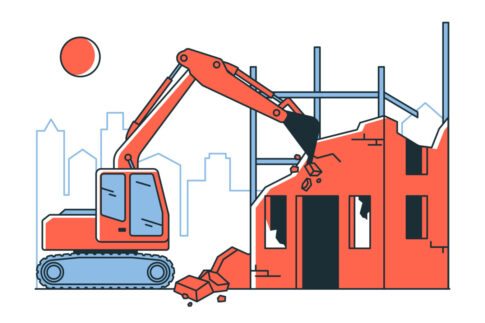再建築不可は「住宅ローンが通らない」「接道不足で需要が限定」ため売れにくい物件です。
本記事は、相場の見極めと値付け、隣地セット・接道解消、仲介/買取の使い分け、最小投資の整備、売却期間設計まで―失敗を避ける具体策5選を簡潔に解説します。
まず知る|売れない原因と市場の前提

再建築不可が「売れない」と言われる主因は、買主の多くが利用する住宅ローンが通りにくいこと、接道や適法性の不確実性で購入判断が遅れること、そして出口(将来の売却や建替え)が取りづらいことです。
市場では、実需層(自ら住む人)よりも、現金または自己資金比率の高い投資家・買取事業者が主な買い手になります。よって、価格形成は「利便性や広さ」よりも「換価性の低さや制約」を強く織り込みます。
売却準備の第一歩は、接道・道路種別・私道承諾・建築確認の履歴・図面・検査済証・越境や境界の状況などを可視化し、買い手が判断できる資料を整えることです。
情報が欠けているほど検討は先送りされ、結果として価格が下がりやすくなります。
以下の表で、買い手タイプごとの目線と必要資料を整理し、誰に・どの条件で売るのが合理的かを見極めましょう。
| 買い手タイプ | 資金手段・重視点 | 準備すべき資料 |
|---|---|---|
| 実需 | ローン前提/安全性・生活利便性 | 接道・法令の整理、図面・検査済証、修繕履歴 |
| 投資家 | 現金比率高め/賃料と出口の見通し | 賃貸想定収支、修繕計画、契約不適合の開示 |
| 買取業者 | 短期再販・再生前提/手離れの良さ | 権利関係・越境・私道承諾・測量の確度 |
【売れにくくなる典型要因】
- 接道2m未満や道路種別不明→建築確認の見通しが立たない
- 私道・通行・掘削承諾が未整備→再生工事の障害になる
- 書類不足(図面・検査済証・境界)→買い手の審査・判断が遅い
- 道路・接道・私道承諾の現況確認→役所照会と書面化
- 基本資料の整備(図面・検査済証・測量・越境是正方針)
- ターゲット買い手の選定→価格条件と引渡条件をセットで設計
住宅ローン・接道・適法性の重要点
売れにくさの核心は「住宅ローンの通過確度」と「法令・接道の明確さ」です。住宅ローンは、返済能力に加えて担保価値(換価性)と適法性を重視します。
再建築不可は建替えが難しく、将来の買い手もローンを組みにくいため換価性の評価が厳しくなります。
さらに、接道義務(敷地が一定の道路に2m以上接すること)を満たさないと、建築確認が難しいため、買い手は「用途変更や増改築の見通し」を描きづらくなります。ここで重要なのは、売主側で不確実性を減らすことです。
道路種別(法定道路・位置指定・私道)や有効幅員、私道の通行・掘削承諾の有無、既存建物の「既存不適格」か「違反」か、過去の確認申請・検査済証の有無などを、役所照会や書面で可視化しましょう。
書類の整備は価格を直ちに上げる保証ではありませんが、検討停止や指値の根拠を減らし、売却期間の短縮に寄与します。
【実務で整えておきたい事項】
- 道路・接道:道路台帳・種別・有効幅員、セットバック要否
- 私道関係:通行・掘削承諾、管理者・所有者の同意関係
- 適法性:確認申請図・検査済証・増改築履歴、是正の要否
| 項目 | 売れにくくなる理由 | 実務対応のヒント |
|---|---|---|
| 接道不明確 | 用途変更・改修の不確実性→買い手が敬遠 | 役所照会で道路種別・幅員を確定→資料添付 |
| 私道承諾未整備 | 工事や配管の更新が不安→再生コスト上振れ | 通行・掘削承諾を文書化→将来の工事条件を明記 |
| 書類不足 | 金融機関・投資家の審査が進まない | 図面・検査済証・測量・越境の是正方針をセット化 |
- 「柱一本残し」はリフォーム扱いとは限らない→新築相当と見なされ得る
- セットバック済=即建替え可とは限らない→運用確認が必要
- 私道は接していれば十分ではない→通行・掘削の承諾内容が重要
相場の目安と下落要因と売却期間
相場を見誤ると、内見はあっても申込に至りません。
再建築不可の相場は、周辺の「再建築可」物件の成約単価を起点に、買い手層(投資家中心)、資金手段(現金・高自己資金)、法的制約(接道・私道承諾・用途)、書類の整備度、再生コストの見込みなどを差し引きして形成されます。
具体的な数字は立地・条件で大きく変わるため、一律の割引率を当てはめるのではなく、売却前に「資料の整備で不確実性を減らす→再生コストを見積る→出口(賃貸・再販)の収支を可視化する」という順でロジックを固めると、買い手の評価が揃いやすくなります。
売却期間は、価格設定と情報開示の濃度に強く影響されます。初期露出で反応が薄い場合は、2〜3週間ごとに反響と内見フィードバックを数値化し、価格・条件・資料の不足を改善します。
【相場と期間を読むための着眼点】
- 周辺の再建築可の実例→基準単価を把握し、制約分をロジカルに控除
- 再生コストの見込み→見積で裏付け、指値の根拠を先回り
- 買い手層の想定→投資家向けの収支表(賃料・空室率・出口)を提示
| 要因 | 下落につながる理由 | 対処の方向性 |
|---|---|---|
| 法的制約 | 建替え困難・改修制限→需要が限定 | 接道解消の可否・私道承諾・許可の見込みを明示 |
| 情報不足 | 不確実性が高く審査が止まる | 図面・検査済証・測量・越境の開示で遅延を防ぐ |
| 再生コスト | 買い手がリスク上乗せ→指値が強くなる | 相見積と仕様の明確化→不確実性の幅を縮小 |
- 初期2週間で反応を評価→資料補強や写真差替え、説明文を改善
- 想定買い手別に資料セットを用意→実需・投資家・買取で説明を切替え
- 期限と価格調整の基準を事前合意→迷いを減らし、機会損失を回避
売る道筋|出口戦略の基本と選び方

再建築不可を売るときの基本は、「誰に」「どの条件で」「いつまでに」を同時に設計することです。買い手は主に実需・投資家・買取業者に分かれ、それぞれ評価軸が違います。
まずは接道や私道承諾、図面・検査済証・測量・越境の有無など、不確実性を下げる資料を整え、現況有姿で売るか、軽微整備を加えて売るか、あるいは隣地とセットや接道解消と組み合わせるかを比較します。
価格は「周辺の再建築可の成約単価」を起点に、制約分をロジカルに控除し、初期の露出期間で反応が薄い場合は、一定の基準で条件調整を行います。
出口は一つに限定せず、仲介・買取・隣地交渉を並走させ、最短で決まる経路を常に確保しておくことが、期間短縮と価格の下振れ防止につながります。
| 買い手像 | 重視点 | 向く売り方 |
|---|---|---|
| 実需 | 生活利便・安全・書類整備 | 軽微整備+書類充実で不安低減 |
| 投資家 | 賃料と再生コスト・出口 | 収支表提示・現況有姿・短期決済 |
| 買取 | 手離れ・瑕疵の見通し | 現況有姿・瑕疵開示・迅速決済 |
- 資料整備→不確実性を可視化
- 価格と期限→調整基準を事前に設定
- 仲介・買取・隣地交渉を並走→最短経路を確保
隣地とセット売却・接道解消の可否と進め方
「隣地とセット売却」や「接道解消(隣地の一部取得・地役権設定・セットバック)」は、再建築不可のボトルネックを外し、買い手層と価格帯を広げる有力な選択肢です。
実務では、現況測量と境界確認で不足幅を数値化し、通路案を図面で示したうえで、隣地所有者に交渉します。
用地取得なら分筆登記と売買、通行地役権なら契約と登記、賃貸借なら長期契約と承諾条項が鍵です。
交渉は価格だけでなく、舗装・排水・維持管理の分担、車両通行や掘削承諾、更新条件まで具体化すると合意しやすくなります。成立性が読めない場合は、セット売却(自物件+隣地)で一括募集するのも有効です。
どの案も、自治体の運用(後退線・寄附採納・私道扱い等)や金融機関の評価のされ方に差があるため、役所照会と金融機関への説明資料を同時に準備し、期間・費用・効果を同じ物差しで比較しましょう。
| 選択肢 | メリット | 留意点 |
|---|---|---|
| 隣地一部取得 | 恒久性が高く評価改善につながりやすい | 測量・分筆・費用が大きい→工程管理が必要 |
| 通行地役権 | 初期費用を抑えつつ通行を恒久化 | 契約条項と登記の強さが命→更新・掘削は明記 |
| セット売却 | 2物件一括で接道問題を同時解決 | 関係者調整と契約設計が複雑→スケジュール余白を確保 |
- 不足幅と通路計画を図面化→幅員・勾配・舗装・排水まで提示
- 費用・管理・承諾の分担を文章化→合意は登記で担保
- 並行案(取得・地役権・賃貸借)を提示→合意の余地を広げる
買取と仲介の使い分けと出口設計
買取は「価格は控えめだが速い・確実」、仲介は「時間はかかるが高く売れる可能性」のトレードオフです。
再建築不可では、書類不足や私道承諾未整備だと仲介での停滞が長引き、結果的に価格を下げるケースが少なくありません。そこで、最初から「二本立て」で設計します。
具体的には、仲介で通常募集しつつ、同時に買取業者へも査定依頼し、一定期間で反応が薄ければ条件調整または買取切替えを行う方式です。
さらに、買取再販事業者向けには、現況有姿のままでも判断できる資料(道路・私道承諾・測量・越境・概算再生見積・想定賃料と出口案)をパッケージ化すると、指値の幅が狭まりやすくなります。
出口は「即現金化(買取)」「価格最大化(仲介)」「接道解消後に再評価」の三段構えで、資金・期間・手離れの希望に応じて優先順位を決めます。
| 出口 | 向いている状況 | 運用のポイント |
|---|---|---|
| 買取 | 早期現金化・書類不足・リスク回避を優先 | 瑕疵開示を徹底→現況有姿・迅速決済で調整 |
| 仲介 | 価格最大化・時間に余裕・資料が充実 | 初期2〜3週間の反応で価格と条件をチューニング |
| 接道解消後 | 隣地協議に見込み・再評価で上振れ狙い | 期間・費用・成功率を数値化→同時に買取線も確保 |
- 初期から買取査定も取得→最終ラインを把握
- 仲介は期限・調整幅・条件変更の基準を設定
- 隣地交渉は別線で進行→成立時は即座に方針を切替え
価格戦略|査定と値付けの実務

再建築不可の値付けは「周辺の再建築可の実勢→制約分を控除→資料整備で不確実性を圧縮」という順でロジックを固めることが基本です。
まず、近隣の成約事例・路線価・賃料相場を集め、建替え困難・私道承諾・越境・再生コストなどのマイナスを、見積や役所照会で数値化します。
次に、想定買い手(実需・投資家・買取)の3類型に合わせ、説明資料を切り替えます。実需には安全性と書類整備、投資家には賃貸収支と出口、買取には手離れの良さを示すのが効果的です。
初期は反応を見極める「観測価格」で出し、2〜3週間ごとに反響・内見・指値の内容でチューニングします。
値引きだけに頼らず、引渡時期・残置物・測量・境界・私道承諾などの条件調整で“実質価格”を最適化すると、総額の下振れを抑えられます。
| 指標 | 意味 | 値付けへの活かし方 |
|---|---|---|
| 成約単価 | 周辺の成立価格の中央値 | 基準単価→制約控除の出発点にする |
| 再生コスト | 修繕・承諾取得等の総費用 | 見積で裏付け→指値の根拠を先回りで吸収 |
| 反響率 | 掲載閲覧→問い合わせの比率 | 2〜3週で基準値未達なら条件・写真・文面を改善 |
- 基準単価を確定→制約控除を数値化→観測価格を設定
- 買い手別の資料パッケージを用意→説明の一貫性を担保
- 反響KPIで定期見直し→値引き前に条件調整を優先
複数査定と条件交渉の実務ポイント
複数査定は「同一条件の資料」を配って比較可能性を高めるのが鉄則です。現況図面・検査済証・道路種別と有効幅員・私道承諾の有無・測量/越境の状況・再生概算見積・想定賃料や出口案をひとつのパッケージにし、仲介2〜3社と買取2〜3社に同時提示します。
提示条件がバラつくと、査定差は実力差ではなく情報差になり、意思決定を誤ります。
交渉では「価格」だけでなく、「引渡時期」「残置物」「境界確定の実施」「私道承諾の取得」「契約不適合責任の範囲」「手付解約条項」など、支払以外のレバーを積極的に使います。
再建築不可は買い手の不確実性が高いため、売主が先に資料で不確実性を潰すほど、指値幅は縮小します。
内見フィードバックは必ず定量化し、同じ指摘が3件以上繰り返される項目(臭気・雨漏り跡・動線など)は、軽微整備や写真差替えで対応すると歩留まりが改善します。
| 交渉項目 | 買い手の関心 | 売主の実務ポイント |
|---|---|---|
| 価格 | 再生コストとリスクの上乗せ | 見積と役所照会で根拠提示→指値の幅を限定 |
| 引渡時期 | 資金手当・工期の最適化 | 短期可なら上乗せ要求/長期要なら価格譲歩と交換 |
| 私道承諾 | 工事・配管更新の実行可能性 | 書面取得・更新条件を明記→評価アップを狙う |
| 契約不適合 | 予期せぬ修繕負担の回避 | 開示を徹底→免責範囲は代替条件とセットで提案 |
- 同一仕様・同一資料で査定→「情報差」由来のブレを排除しましょう。
- 指値は金額だけでなく条件の組み替えで吸収すると総額が守れます。
- 買取査定は常にキープ→仲介停滞時の撤退線として機能します。
- 資料一式を統一→PDF化して即時共有できる状態に
- 価格以外の譲歩条件(時期・残置・測量)を事前に決める
- 同質問への回答テンプレを作成→対応スピードで優位に
期限設定と撤退ラインの決め方と注意点
売却は「時間」との戦いです。初期露出の鮮度が高いほど、質の良い問い合わせが集まりやすく、ここでの設計ミスは取り返しにくくなります。
推奨は、初期30〜45日の「集中販売期間」を設定し、2〜3週間ごとに反響・内見・指値・問い合わせ質をKPIで評価します。
基準未達なら、①写真と物件説明の改善→②条件調整(引渡時期・残置物・私道承諾対応など)→③価格調整の順に手を打ちます。
撤退ラインは、買取の最低ライン・資金繰り・次の投資機会を踏まえて、金額と期限を先に決めておくことが重要です。
ズルズル延ばすと、保有コスト(固定資産税・維持修繕・機会損失)が累積し、実質の回収率が悪化します。
季節要因(繁忙/閑散)も考慮し、反応が薄い時期は短期お休み→再出稿で鮮度を回復させる戦術も有効です。
| 期間設定 | 主なアクション | 判定の基準 |
|---|---|---|
| 初期0〜2週 | 媒体最適化・写真強化・資料整備 | 閲覧→問い合わせ率が基準値以上か |
| 2〜4週 | 内見導線・説明強化・条件調整 | 内見→申込率、指値幅が縮小しているか |
| 4〜6週 | 価格再評価・買取線との比較 | KPI未達なら価格or出口の切替え |
- 「先に決めた順序」で打ち手を実行→感情での値下げを避けます。
- 保有コストと時間価値を可視化→長期化の損失を数値で認識します。
- 買取の事前査定をキープ→撤退ラインの実効性を担保します。
- 値引き一択は非効率→条件調整→写真・説明改善→価格の順で検討
- KPI未設定は迷走の元→2〜3週ごとに定量評価して方針を更新
- 季節・金利・税負担の変化を無視しない→期限と撤退線を守る
見せ方・整備|最小投資で印象改善

「売れない」を「検討したい」に変える最短ルートは、費用の大きい全面改修ではなく、第一印象を底上げする“最小投資”の整備です。
内見者は玄関から5分以内で購入可否の印象を固めやすく、匂い・明るさ・清潔感・動線のわかりやすさが評価を左右します。
再建築不可は構造や接道のハンデがあるため、室内外の“見え方”で不安を減らし、資料でロジックを補うのが効果的です。
具体的には、徹底清掃・脱臭、照明器具の増設や電球色の統一、カーテンの開放と窓清掃、動線を妨げる大型家具の撤去、玄関と水回りのピンポイント補修(コーキング・パッキン・水栓の簡易交換)など、半日〜数日の軽作業で印象は大きく改善します。
写真・間取り図・動線説明(どこが居室で、どこが収納か)が揃っているだけでも離脱が減ります。売主側で「将来の再生コストが読める状態」を作ることが指値の幅を狭める近道です。
【まず手を付けたい改善ポイント】
- 匂い対策:換気→脱臭→カーテン洗濯→下駄箱の消臭
- 明るさ確保:電球の統一・増設、窓ガラスとサッシの清掃
- 清潔感:キッチン・浴室・トイレの水垢/カビ除去、コーキング打ち直し
- 動線の可視化:不要家具の撤去、通路幅の確保、収納の整理
| 整備箇所 | 具体アクション | 期待できる効果 |
|---|---|---|
| 玄関 | 照明交換・土間清掃・消臭・靴の撤去 | 第一印象の改善→滞在時間が延び説明が通る |
| 水回り | カビ取り・コーキング補修・水栓簡易交換 | 「すぐ住める」印象→不安感と指値の根拠を減少 |
| 居室 | 照明増設・カーテン開放・床ワックス | 面積感が増す→写真のクリック率・内見率が向上 |
- 清掃→照明→写真→資料(図面・動線メモ)の順に整える
- 匂いは最優先で対処→内見の滞在時間が伸びる
- 大型の工事は後回し→まずは印象と資料で離脱を抑える
検査と書類整備で不確実性を低減する方法
買い手が一番嫌うのは「見えないリスク」です。再建築不可では建替えや増改築の自由度が低いため、現況を数値と書類で見える化するほど、購入判断が早まります。
ポイントは〈軽検査+資料パッケージ〉です。軽検査は、雨漏り兆候・配管の滲み・シロアリ痕・床の傾き・電気/給排水の動作確認など、半日〜1日のチェックで十分です。
結果は写真つきレポートにまとめ、補修が必要な箇所は「想定費用のレンジ」を併記します。
資料パッケージは、道路種別と有効幅員、私道の通行/掘削承諾、図面・確認申請の履歴、検査済証、測量図・越境の有無、固定資産税課税明細、過去の修繕履歴などを一体にして、内見前に共有できる状態にします。
これだけで「どこに費用がかかるか」が早期に共有でき、指値の幅が狭まりやすくなります。
【資料パッケージの基本構成】
- 法令・道路:道路台帳、法定道路の区分、セットバック要否
- 権利・承諾:私道の通行/掘削承諾、管理規約や同意書
- 建物・図面:確認申請図、検査済証、増改築履歴、現況図
- 測量・境界:現況測量図、越境有無と是正方針
- 維持修繕:過去の工事明細、軽検査レポート、写真
| 書類/検査 | 目的 | 提示のポイント |
|---|---|---|
| 道路・承諾 | 再生や配管更新の実行可能性の確認 | 幅員・延長・承諾の範囲を図で明示→不安を先回りで解消 |
| 確認・検査済証 | 適法性の把握と違反疑いの排除 | 不足は役所照会の記録を添付→対応方針を併記 |
| 軽検査レポート | 劣化箇所と費用レンジの見える化 | 写真・位置図・対処案をセット→交渉の土台を統一 |
- 写真は「前→問題→対処案」を1枚に集約して説明しやすくする
- 費用は幅で示す(例:◯◯〜◯◯万円)→過度な断定を避ける
- 不足書類は役所照会の控えで補完→“何が、いつ”揃うかを明記
軽微リフォームと現況有姿提示のコツ
最小投資で成果を出すには、「軽微リフォーム」と「現況有姿(手をかけず現状での売却)」を上手に使い分けます。
軽微リフォームの狙いは、構造や間取りをいじらず、匂い・明るさ・清潔感・安全性の体感値を上げることです。
代表例は、徹底清掃、クロス部分補修、床補修ワックス、照明増設、簡易な水栓交換、建具の調整、網戸・戸車の交換、屋外の雑草除去と高圧洗浄など。
いずれも短工期で効果が見えやすく、写真品質の向上にも直結します。現況有姿で行く場合は、メリット(着工待ち不要・即決可能)とデメリット(買い手の不安が残り指値が強め)を理解し、代わりに「資料の厚み」で補います。
具体的には、前項の資料パッケージに加え、簡易の再生見積(A案:最低限、B案:標準、C案:推奨)を用意して、買い手の“想像コスト”を現実の数字に変えるのが有効です。
【費用対効果が高い軽微リフォーム例】
- 水回り:カビ取り・コーキング打ち直し・水栓/シャワーヘッド交換
- 内装:部分クロス貼替え・巾木補修・建具調整・照明増設
- 外回り:高圧洗浄・雑草除去・表札/ポスト清掃・玄関アプローチ整備
| 選択肢 | 向いている状況 | 注意点 |
|---|---|---|
| 軽微リフォーム | 内見は来るが申込に至らない/匂い・暗さの指摘が多い | 構造や主要設備の大改修は避ける→短工期で写真改善を狙う |
| 現況有姿 | 時間優先・資金制約あり/買取や投資家向け | 瑕疵の開示を徹底→軽検査レポートと見積の併用で不安を低減 |
| 併用型 | 水回りと玄関のみ整備→他は現況で提示 | 「手をかけた理由」を説明文に明記→価格根拠を補強 |
- 中途半端な壁撤去・造作で動線が悪化→目的と整合しない改変は逆効果
- 色合わせの悪い部分貼替え→写真で違和感が出て評価が下がる
- 見えない不具合の先送り→後日の交渉材料になるため軽検査で可視化
【運用のコツ】
- まずは現況有姿で公開→反応を見て軽微リフォームを追加する順番が安全
- 写真・説明文は“ビフォー/アフター”を分かりやすく→改善点を強調
- 内見フィードバックを3件単位で集計→次の整備箇所を定量で決める
法と手続き|接道解消と許可の基本
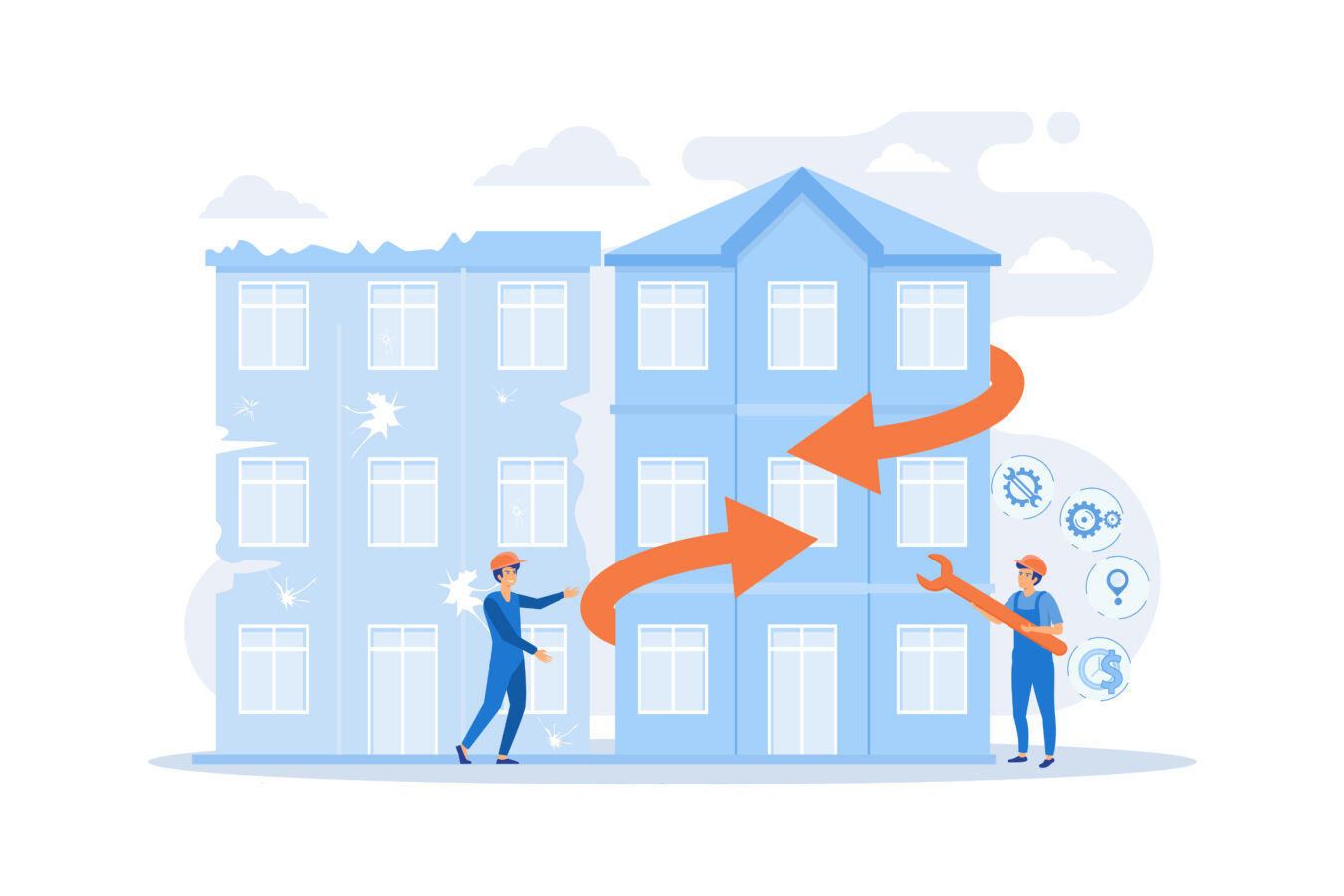
再建築不可の最大の壁は「接道」と「許可」です。
売却・再生・賃貸のいずれでも、まず敷地がどの道路にどの長さで接しているか(有効幅員・2m以上の確保)、私道であれば通行・掘削承諾が整理できるか、将来的にセットバックで条件を満たし得るかを確認します。
さらに、接道の要件を満たさなくても個別審査で建築を可能にする「43条但し書き」の成立性を検討し、許可→確認申請までの工程と必要書類を逆算します。
これらは単独で進めるより、〈隣地交渉(取得・地役権・賃貸借)/セットバックの運用確認/43条但し書きの事前相談〉を同時並行で進め、費用・期間・成功率・銀行評価への効果を同じ物差しで比較するのが実務的です。
【基本の整理ポイント】
- 道路種別と有効幅員→不足量を数値化し、セットバック要否を確認
- 私道の権利関係→通行・掘削承諾の内容と更新条件を文書化
- 許可・確認の流れ→事前相談→申請→審査→許可→確認申請の工程を把握
| 目的 | 主な手段 | 実務ポイント |
|---|---|---|
| 建替え・再生 | 隣地一部取得/通行地役権/長期賃貸借/セットバック | 測量・境界確定→契約・登記で恒久性を担保→銀行評価に反映 |
| 個別許可 | 43条但し書き(避難・防災・通行の安全確保) | 通路幅員・勾配・照度・承諾書等を図面・写真で示す |
| 売却 | 資料パッケージ化→現況有姿/許可前提での募集 | 可否とコストの見通しを明示→指値の幅を縮小 |
- 現況測量・道路台帳・役所照会→不足量と運用ルールを把握
- 隣地交渉(取得/地役権)と43条事前相談を並走→最短経路を確保
- 工程・費用・成功率を1枚に集計→銀行・買い手への説明を統一
43条但し書きとセットバック
43条但し書きは、敷地が建築基準法上の道路に2m以上接していない場合でも、避難・防災・交通上支障がないと認められれば個別審査で建築を可能にする仕組みです。
実務では、通路の幅員・長さ・勾配・段差、夜間の安全(照度)、消防活動の可能性(はしご・ホース延長の可否)、通行権原(地役権・賃貸借・承諾書)の恒久性などを総合評価されます。
一方、前面道路の有効幅員が4m未満であれば、道路中心線からの後退により将来的に条件を整える「セットバック」も重要な手段です。
セットバックは即時の建替え可を保証するものではなく、自治体の運用(後退線指定、寄附採納の要否、私道扱い、舗装・排水の整備水準)により扱いが異なります。
したがって〈43条但し書き〉と〈セットバック〉は対立概念ではなく、目的(いつ、どの規模で、どの用途に)に応じて併用・比較する発想が必要です。
【手続の流れの目安】
- 事前相談→計画・敷地・通行経路を説明し必要資料の粒度を確認
- 申請→位置図・公図・経路図・承諾関係・配置/平面/断面・避難説明を提出
- 審査→安全・防災・通行権原・近隣影響を総合判断(必要時に審査会)
- 許可→条件付きの場合あり→その後、建築確認申請へ
| 手段 | 成立の鍵 | チェックポイント |
|---|---|---|
| 43条但し書き | 安全・防災上の合理性/通行権原の恒久性 | 幅員・勾配・段差・照度の実測、承諾書の更新条件、夜間写真 |
| セットバック | 後退線の確定/公共協議の整合 | 寄附採納の可否、舗装・排水の仕様、境界杭の復元 |
- 通路条件は“数値+写真+図面”で提示→主観表現は避ける
- 承諾は口頭NG→契約・登記で恒久性を担保(更新・掘削・車両通行)
- セットバックは「後退=即建替え可」ではない→運用差を事前確認
契約不適合責任と免責範囲の考え方
再建築不可の売買では、物件の「制約」をどう開示し、どこまで売主が責任を負うのかを明確にすることが、価格とスピードの両立に直結します。
契約不適合責任は、引渡時に目的物が契約内容に適合していない場合の売主の責任で、故意・重過失があれば免責合意があっても責任を免れにくく、開示の精度が極めて重要です。
具体的には、接道の不足量、道路種別、有効幅員、私道の通行・掘削承諾、越境の有無、雨漏り・給排水・白蟻等の既知不具合、確認申請・検査済証・増改築履歴、測量結果などを、事前に書面と添付資料で開示し、現況有姿の前提(修補義務の範囲)を明文化します。
免責は万能ではありません。買主に誤認を与える表示や重要事項の不告知は、後日の紛争や請求のリスクを高めます。
したがって、売主の戦略は「隠す」のではなく、「事実を先に全部出して、責任の範囲と代替条件(価格・承諾取得・残置処理・引渡時期)で合意形成」を図ることです。
【開示と免責を設計する視点】
- 事実の特定→接道・承諾・越境・不具合等を文書化し根拠資料を添付
- 範囲の明確化→現況有姿・修補対象外の線引き、売主の知り得た事実の列挙
- 代替条件→価格調整、承諾取得の実施、境界確定、残置処理などの選択肢
| 項目 | 実務上の目的 | 契約・書面での要点 |
|---|---|---|
| 重要事項の開示 | 誤認・紛争を予防し交渉を円滑化 | 道路・承諾・越境・既知不具合を一覧化し証拠を添付 |
| 免責の合意 | 売主の予見不能リスクの限定 | 現況有姿の範囲、除外対象、買主調査の前提を明記 |
| 代替条件の提示 | 価格だけに頼らず総額最適化 | 承諾取得や境界確定、引渡時期・残置での調整案を併記 |
- 「知らない」は通用しにくい→役所照会・測量・軽検査で裏取り
- 免責条項は魔法ではない→故意・重過失・説明不足は免れにくい
- 交渉は“事実セット”を先出し→価格と条件の合意を早める
まとめ
要は「需要を広げるか、価格で決めるか、出口を切り替えるか」です。
接道・適法性を確認→相場と期間を把握→値付けと期限を設定→隣地セットや買取も同時検討→軽微整備と書類整備で不確実性を下げましょう。複数経路を同時並行で走らせ、機会損失を最小化します。