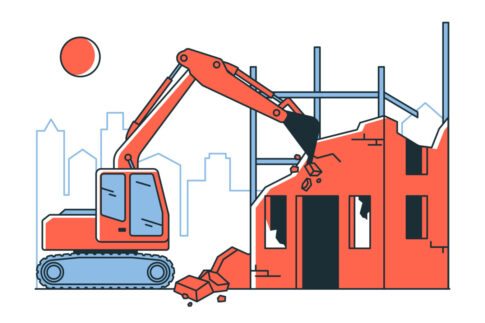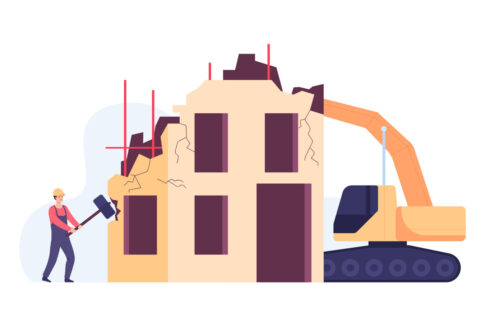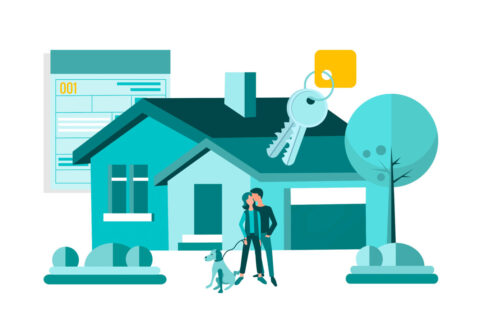再建築不可でも火災保険は“不可”と決まっているわけではありません。
この記事では、審査で見られる項目(構造・築年・空き家/賃貸の別)、補償範囲と主要特約、水災・地震の判断軸、保険金額(再調達価額/時価)の選び方、保険料に効く要因、事故時の請求手順までを実務目線で整理します。
再建築不可と火災保険の基本整理

再建築不可でも、火災保険は「加入不可」と決まっているわけではありません。保険会社は“建て替え可否”そのものではなく、火災・風水害・盗難等に対するリスクと管理状況を見ます。
具体的には、建物の構造(木造・鉄骨等)や老朽度、配線・屋根・外壁の傷み、空き家か居住中か、賃貸か自用か、放火や水漏れの発見遅延リスク、地域のハザード(浸水・土砂)などが評価対象です。
老朽化が強い、長期無人で管理が乏しい、違法増改築が残ると、引受制限(補償削減・免責拡大・保険料割増)や引受不可の判断もありえます。
一方で、見回り・防犯照明・警報器の設置、屋根や配線の補修、施錠・雨漏り対策などを実行し、写真・点検記録で管理実態を示せば、加入可能性は高まります。
まずは「建物状態の是正」と「用途(自用・賃貸・空き家)の明確化」を行い、商品選択(一般住居用/空き家向け)と補償の範囲・金額を組み立てましょう。
- 評価の中心→建物の安全性・管理状況・用途・立地ハザードです。
- 再建築不可でも、管理が行き届けば引受余地はあります。
- 事前点検と記録(写真・修繕領収・巡回メモ)が説得材料になります。
| 観点 | 確認の要点 |
|---|---|
| 建物状態 | 屋根・外壁・配線・雨漏り・腐朽・傾きの有無。一次補修の実施状況。 |
| 管理実態 | 巡回頻度、施錠、庭木・雑草、漏水・害獣対策、防犯灯・警報器の設置。 |
| 用途 | 居住・空き家・賃貸の別(商品・特約が変わる)。 |
| ハザード | 浸水・土砂・風雪の地域特性(補償の要否と保険料に影響)。 |
- 点検と軽微補修→屋根・配線・雨仕舞いの不安を先に潰す。
- 管理計画→巡回頻度と写真記録、施錠・照明・警報器の有無を明示。
- 用途の明確化→自用/空き家/賃貸で商品と特約を選び分ける。
加入可否の考え方と審査ポイント
保険会社の審査は「危険度」と「管理可能性」の2軸で判断されます。危険度は、構造(木造は延焼リスクが相対的に高い)、築年(古いほど配線・屋根・配管の劣化懸念)、立地ハザード(浸水・土砂・強風)、隣接状況(密集地・空き地の管理不良)など。
管理可能性は、常時居住か定期巡回か、防犯・防災設備(火災警報器、消火器、外灯、雨戸)、水抜きや通風、郵便滞留の有無、近隣との連絡体制(緊急時連絡票)などで評価されます。
再建築不可そのものは直接の不承認理由ではありませんが、老朽化や通路狭小による消防活動上の懸念が大きいと、補償限定・免責拡大・保険料割増・引受見送りがあり得ます。
申込前には「点検・是正・証拠化」を済ませ、空き家なら巡回スケジュールと鍵管理を、賃貸なら入居者の使用実態と住宅用火災警報器の設置状況を提示できるよう準備します。
- 危険度→構造・築年・配線/屋根の劣化、立地ハザード、隣接状況。
- 管理可能性→居住/巡回、防犯・防災設備、鍵・郵便・通風の運用。
- 結果の幅→補償限定、免責拡大、割増料率、引受見送りの順で調整されることも。
| 審査項目 | 見るポイント | 準備資料 |
|---|---|---|
| 建物健全性 | 屋根/外壁/配線/雨漏り/腐朽 | 点検写真、修繕見積・領収書 |
| 管理・防犯 | 巡回頻度、施錠、照明・警報 | 巡回記録、設置写真、運用メモ |
| 用途 | 居住・空き家・賃貸の別 | 賃貸借契約、使用実態の説明 |
| ハザード | 浸水・土砂・風雪の想定 | ハザード図の写し、対策計画 |
- 長期無人で郵便滞留・庭木放置→放火・侵入・延焼リスクが高評価に。
- 屋根・配線の不具合放置→申込前の軽微補修を怠ると引受困難に。
補償範囲と主な特約の基礎知識
火災保険の基本補償は、火災・落雷・破裂/爆発に加え、商品により風災・ひょう・雪災、盗難、水濡れ(給排水設備の事故等)、物体の落下・飛来・衝突、騒擾等への損害をカバーします。
再建築不可だからといって補償内容が自動的に狭くなるわけではありませんが、老朽・無人などの事情で免責拡大や補償除外が付く場合があります。
特約は、破損・汚損、残存物片付け費用、臨時費用、失火見舞費用、類焼損害、個人賠償(自用)、施設・管理者賠償(賃貸・貸スペース)、家賃収入の休損特約(商品により有無)、地震火災費用(地震保険とは別枠)、水濡れ見舞い、ガラス・設備修理など。
空き家向け商品では、巡回中の偶然事故の扱いや“空き家限定プラン”の補償範囲が異なるため、用途とリスクに応じて選択します。
重要なのは“必要な事故だけを選ぶ”こと。浸水可能性が低い高台なら水災を外す、漏水リスクが高いなら水濡れ・修理費用特約を厚めにする等、地域・建物・用途で最適化します。
- 基本補償→火災・落雷・破裂/爆発+(風災・ひょう・雪災・盗難・水濡れ等)。
- 主要特約→破損・汚損、臨時費用、片付け費用、類焼損害、(賃貸なら)施設/家主賠償。
- 地震→地震保険は別契約。地震火災費用特約は“延焼時の見舞費用”に近い位置づけ。
| カテゴリ | 代表例 | 着眼点 |
|---|---|---|
| 基本補償 | 火災・落雷・破裂/爆発・風災等 | 免責金額・支払条件(時価/再調達)を確認 |
| 費用特約 | 片付け費用・臨時費用・失火見舞い | 支払限度と支払事由の具体性 |
| 賠償特約 | 個人賠償・施設/家主賠償 | 自用/賃貸で付帯先・限度額が変わる |
- 地域リスク(浸水・土砂・風雪)と建物リスク(老朽・漏水)を分けて考える。
- “なんとなく全部”ではなく、不要補償は外し必要箇所を厚くする。
空き家・賃貸時の取扱いの違い
空き家は、発見遅延や侵入・放火・漏水のリスクが上がるため、一般住居用よりも引受条件が厳しくなりがちです。
専用プラン(空き家向け)では、補償範囲や免責、保険料が別設計のことが多く、巡回・施錠・防犯灯・警報器の設置、郵便転送、見回り記録の提出を条件にされる場合があります。
賃貸では、オーナー側は建物(外周・共用部)に対する火災保険+施設賠償/家主賠償を、テナント側は家財保険+借家人賠償責任を付帯するのが一般的です。
家賃収入特約(休業補償)は商品により有無が分かれ、支払事由(全損・半損・避難指示等)や対象期間が限定されるため、約款の細部確認が不可欠です。
再建築不可の賃貸でも、建物状態の是正と避難・通報体制(警報器・掲示)を整えておくと、引受条件が改善しやすくなります。
空き家から賃貸へ用途変更する場合は、事前に保険会社へ通知し、補償・特約・保険金額を用途に合わせて見直しましょう。
- 空き家→専用プランや免責拡大、巡回・防犯・写真記録が条件化しやすい。
- 賃貸→オーナーは建物+賠償、入居者は家財+借家人賠償が基本構成。
- 用途変更→保険会社へ事前連絡。補償・金額・特約を付け替える。
| 区分 | 主なポイント | 実務のヒント |
|---|---|---|
| 空き家 | 発見遅延・放火・漏水の増加 | 巡回記録・施錠・照明・警報器を写真で提示 |
| 賃貸(家主) | 建物火災+施設/家主賠償 | 共用部の危険箇所点検、掲示・避難導線の明確化 |
| 賃貸(入居者) | 家財+借家人賠償 | 鍵管理・水回りの注意喚起、退去時の原状回復説明 |
- 空き家→巡回頻度・施錠・照明・警報の四点セットを明文化。
- 賃貸→家主賠償/借家人賠償の付け忘れに注意(双方で補完)。
保険金額と評価方法の決め方

再建築不可でも、火災保険の「保険金額(いくらまで補償するか)」は自分で設計できます。
考え方の軸は〈評価方法の選択(再調達価額 or 時価)〉〈対象の切り分け(建物・家財・付帯設備)〉〈過少保険/超過保険の回避〉の3点です。
まず評価方法は、全損時に“同等の家を新たに建てる費用”を基準にするか(再調達)、“現在の価値(劣化を差し引いた額)”を基準にするか(時価)で保険料も支払額も変わります。
次に対象の切り分け。建物本体と一体の設備(浴槽・キッチン・給湯器・屋根の太陽光など)は「建物」に、動産(冷蔵庫・ベッド等)は「家財」に計上します。
最後に回避策。保険金額が再調達価額より小さいと、部分損害でも比例てん補(支払いが按分)になるおそれがあります。
延床面積×再調達単価(㎡単価)+付帯設備+外構の目安を置き、見積や図面で根拠化しておくと、過不足のない設計に近づきます。
- 設計の順序→評価方法の選択→対象の切り分け→金額の根拠化→毎年の見直し。
- 再建築不可でも評価は「建物の再取得費用」をベースに考えるのが基本です。
- 部分損害の按分を避けるには、再調達価額に近い保険金額の設定が有効です。
| 観点 | 実務のポイント |
|---|---|
| 評価方法 | 再調達は復旧重視、時価は保険料抑制重視。築年・用途・資金計画で選定。 |
| 対象の切り分け | 建物(一体設備)と家財(可搬物)を分け、付帯設備はどちらに入れるか整理。 |
| 根拠 | 延床×㎡単価+設備・外構の見積を保管。写真・図面で裏づけ。 |
- 延床面積×再調達単価→建物の基準額を算出。
- 付帯設備・外構の追加見積→建物側へ加算。
- 家財は「買い直しリスト」を作り、合計額で設定する。
再調達価額と時価の違いと選び方
再調達価額は「同等の建物を今あらためて取得・建築するのに必要な金額」が基準で、全損時の復旧をしっかりカバーしたい人向けです。時価は「再調達価額-経年劣化分(減価)」で、築古・投資用で保険料を抑えたい場合に選ばれます。
たとえば再調達2,000万円・経年劣化30%なら時価は1,400万円。全損時の上限も1,400万円に留まる点が最大の違いです。
部分損害でも、保険金額が小さい契約では比例てん補(損害額×保険金額/再調達価額)となる場合があり、復旧費が満額出ないリスクに注意します。
再建築不可の築古でも、屋根・内装・配線を直して運用を続ける前提なら再調達を選ぶ価値はあります。
一方、早期売却や現状維持が前提で“全損でも大規模復旧はしない”なら時価が合理的です。最適化の手順は、〈用途と出口〉→〈復旧方針〉→〈資金余力〉の順に意思決定。
過剰な金額設定は保険料のムダ、過小設定は按分リスクにつながるため、見積・㎡単価・写真で根拠を整えることが実務的です。
- 再調達価額→復旧重視。保険料は高めだが全損時の不足を回避しやすい。
- 時価→コスト重視。全損・大規模損害の自己負担増を許容できるかが鍵。
- 判断軸→出口(保有/売却)・復旧方針(全面/限定)・資金余力(自己負担許容量)。
| 方式 | メリット | 留意点 |
|---|---|---|
| 再調達価額 | 復旧費の不足リスクを抑えやすい | 保険料は相対的に高い→家財・特約を絞って調整 |
| 時価 | 保険料を抑えやすい | 全損時の上限が低い、按分の影響が大きくなりやすい |
- 修繕しながら保有→再調達価額を基本に、免責や年払で保険料を調整。
- 短期保有・解体前提→時価で最小限、賠償系特約を厚めにする選択肢。
建物・家財・付帯設備の線引き
「どれを建物に、どれを家財に計上するか」は保険金額設計の基礎です。
原則として、建物に恒久的に取り付けられ、取り外すと機能や価値が損なわれるもの(浴槽・システムキッチン・洗面台・給湯器・分電盤・屋根の太陽光・ビルトインエアコン・床暖房・シャッター・雨戸・門扉・塀・カーポート等)は「建物」。
持ち運べる動産(冷蔵庫・洗濯機・電子レンジ・テレビ・ソファ・ベッド・衣類・カーテン・カーペット等)は「家財」。
屋外設備や外構は商品により建物付属物として評価されることもあります。賃貸では、オーナー所有の付帯設備(エアコン・照明一体型等)は建物側、入居者持ち込みは家財側と切り分けます。
線引きを曖昧にすると過少保険や支払時の争いにつながるため、契約時に写真とリストで「どちらに計上したか」を明記するのが安全です。
- 建物(例)→浴室・キッチン・給湯器・ビルトインAC・床暖房・分電盤・屋根の太陽光。
- 家財(例)→冷蔵庫・洗濯機・テレビ・ベッド・衣類・可搬式ストーブ・置き型エアコン。
- 外構/付帯(例)→門扉・塀・カーポート・物置・看板は商品約款で扱いを確認。
| 区分 | 代表例 | 実務メモ |
|---|---|---|
| 建物 | 一体型設備・外構(商品により) | 取り外すと建物機能が損なわれるもの |
| 家財 | 可搬性のある生活動産 | リスト化し合計額を保険金額に反映 |
| 付帯設備 | 太陽光・蓄電池・物置等 | 建物扱いか特約扱いかを約款で確認 |
- 「外せば使えない」→建物側、「外しても別に使える」→家財側に置く。
- 写真・品番・設置場所の一覧を契約ファイルに綴じておく。
過少保険・超過保険の回避策
過少保険は、設定した保険金額が再調達価額より小さい状態で、部分損害でも按分支払いになるリスクがあります。
たとえば再調達2,000万円なのに保険金額1,000万円で契約すると、200万円の損害でも支払上限は200万円×1,000/2,000=100万円に縮小される可能性があります。
逆に超過保険は、再調達価額を超えて金額を設定しても、支払いは実損が上限で保険料のムダになります。
回避の実務は、(1)基準額の算出(延床×㎡単価+設備・外構の見積)→(2)家財リストで合計額を作成→(3)契約後の見直しトリガー(リフォーム・設備更新・増築・市場単価の変動)を決め、年1回は点検する、の3段です。
再建築不可で解体前提なら、過大な再調達額は不要ですが、近々の修繕や継続運用を想定するなら、部分損害の按分を避けるレベルに合わせておくのが無難です。
- 過少保険の目安→保険金額/再調達価額の比率が低いほど按分リスクが上昇。
- 超過保険の無駄→実損超の支払いは不可。家財を含め二重計上に注意。
- 年次見直し→増改築・高額設備導入・相場上昇は見直しサイン。
| リスク | 症状 | 対策 |
|---|---|---|
| 過少保険 | 部分損でも按分で不足 | 再調達額の再計算、金額の是正、免責や特約で保険料調整 |
| 超過保険 | 保険料だけ高いが上限は実損 | 家財との重複を除去、付帯設備の扱いを約款で確認 |
- 増改築・屋根外装工事・高額設備の新設・賃貸化/空き家化の用途変更。
- 地価や資材単価の上昇、再調達単価の改定ニュースが出たとき。
保険料に影響する主な要因

再建築不可かどうかに関わらず、火災保険の保険料は「建物の燃えやすさ・壊れにくさ」と「被害が起きやすい場所・使い方」、そして「補償メニューの厚さ」で決まります。
具体的には、構造(木造・軽量鉄骨・鉄筋コンクリート等)や築年、屋根・外壁・配線などの状態、防災設備(火災警報器・屋外照明・消火器)、用途(自用・空き家・賃貸)、管理実態(巡回頻度や施錠)、延床面積、評価方法(再調達価額/時価)、家財の有無、水災・風災・破損汚損などの付帯範囲、免責金額(自己負担)、地震保険の付帯、契約年数(長期割引)、支払方法(年払/月払)といった要素が主に効きます。
加えて、地域のハザード(浸水・土砂・台風・積雪)や地震の地域係数も保険料差を生みます。
まずは〈構造・築年・防災〉〈エリアリスク〉〈補償の厚みと免責〉の三層で整理し、削れない安全と削ってよい贅肉を見分けると、保険料の最適化がシンプルになります。
- 建物側の要因→構造・築年・設備保守(配線・屋根)・防災設備・管理実態。
- 立地側の要因→地域係数(地震)・水災/風雪のハザード・標高や地形。
- 契約側の要因→評価方法・付帯範囲・免責金額・契約年数・支払方法。
| 要因 | 保険料への典型的な影響と見直しのヒント |
|---|---|
| 構造・築年 | 耐火性が高いほど低廉。築古は割高傾向→配線・屋根補修や警報器追加で緩和。 |
| 用途・管理 | 空き家・無人時間が長いと割増→巡回・施錠・照明の仕組み化で改善余地。 |
| 付帯範囲 | 水災/破損汚損/盗難などを厚くすると上がる→地域・建物に合わせて取捨選択。 |
| 免責・年数 | 免責を上げる/長期化で下がることが多い→自己負担許容を前提に調整。 |
- 建物側で下げる→点検・軽微補修・警報器や外灯でリスク自体を小さく。
- 契約側で整える→不要補償は外し、免責で保険料調整。水災はハザード次第。
構造・築年・防災設備の評価軸
保険会社は「燃え広がりにくさ」「延焼・類焼のしづらさ」「初期消火・早期発見のしやすさ」をセットで見ます。
一般に、鉄筋コンクリート(RC)や耐火建築物は保険料が下がりやすく、木造は上がりやすい傾向です。
ただし木造でも、屋根・外壁の健全性、分電盤や配線の更新、コンロ周りの耐火措置、住宅用火災警報器の設置、外周の防犯照明・人感ライト、消火器の配置などで「実質の危険度」を下げられます。
築年は配線・給排水・屋根の劣化リスクを示唆するため、築古ほど保険料は割高寄りですが、更新記録(交換年・工事写真・領収書)があると評価が改善されやすいです。
空き家や再建築不可のように消防活動が入りにくい立地では、施錠・巡回・ポスト転送・植栽管理・不審物掲示など「発見遅延」と「侵入」を抑える管理面の点数が重要です。
- 構造→RC/耐火は低廉、木造は割高傾向。ただし実際の保守と設備で差を埋められます。
- 築年→配線・屋根・給排水の更新有無が鍵。記録の提示で評価改善が可能です。
- 防災→火災警報器・外灯・消火器・消火バケツ・漏水センサーなど小装備も有効。
| 評価軸 | チェックポイント | 保険料への効かせ方 |
|---|---|---|
| 構造 | 木造/鉄骨/RC、屋根材、外壁材 | 不燃材・耐火被覆・延焼遮断の有無を説明 |
| 設備 | 分電盤/配線年式、ガス設備、警報器 | 更新記録・写真・検査票を申込時に提出 |
| 管理 | 巡回・施錠・照明、防犯、郵便転送 | 運用メモ・写真を添付し“無人でも管理中”を可視化 |
- 分電盤・漏電遮断器・給湯器の更新履歴を整理→写真添付で提示。
- 屋根の簡易補修・樋清掃・外灯設置→低コストで危険度を下げる。
エリア係数とハザードの確認
同じ建物でも、立地によって保険料は変わります。地震保険は都道府県ごとの「地震リスク係数」と建物構造(木造/非木造)で保険料ベースが決まり、火災保険でも水災・風災・雪災のハザードが高い地域ほど料率や推奨補償が変わります。
まずは自治体や国のハザードマップで〈想定浸水深・土砂災害警戒区域・高潮〉を確認し、標高・地形・河川からの距離も併せて見ます。
台風通過が多い沿岸部、豪雪地帯、強風が抜ける谷筋では、屋根材・外装・飛来物対策の点検を先に実施し、必要に応じて水災や風災の補償を厚めに。
逆に、高台・内陸・洪水想定0.5m未満などリスクが低い場合は、水災を外す・免責を上げる等で保険料を抑える余地があります。
重要なのは「地図での色」と現地条件(擁壁・排水・周辺建物)を突き合わせ、過去の冠水履歴や近隣の被害情報もヒアリングして実態に合わせることです。
- 地震→地域係数×構造で保険料が変動。耐震補強や非木造は抑制要因。
- 水災→想定浸水深・標高・過去冠水履歴で判断。低リスクなら外す選択肢も。
- 風雪→屋根材・固定具・外装の状態と地域特性を反映して特約の厚みを調整。
| リスク | 判断材料 | 設計のヒント |
|---|---|---|
| 地震 | 地域係数、構造、耐震性能 | 地震保険は上限あり→家財も忘れず検討 |
| 水災 | 浸水深、標高、排水計画、過去事例 | 低リスクなら免責増/付帯除外、逆なら厚めに |
| 風・雪 | 台風頻度、最大風速、積雪深 | 屋根・外壁の補修と写真で“事前対策”を示す |
- 色が濃い=付ける/免責小さめ、色が薄い=外すor免責大きめで最適化。
- 地震は外せない基礎リスク→建物+家財で最低限を確保。
免責金額と契約年数の工夫
免責金額(自己負担)と契約年数は、保険料を左右する実務レバーです。免責は「小口の損害は自分で負担し、大口だけ保険で備える」設定で、1万円→5万円→10万円と上げるほど保険料は下がるのが一般的です。
再建築不可の築古で、軽微な修繕は日常的に発生しやすいなら、免責を高めて保険料を抑える合理性があります。
一方、配線更新直後や水回り新設などで小口故障の発生確率が低いと見込める場合にも、免責高めは有効です。
契約年数は、長期契約(複数年一括)に割引が設定されるケースがあり、保険料の総額を圧縮できます(途中で用途変更・増改築があるなら中途更改の取り扱いも確認)。
支払方法は年払の方が月払より手数料面で有利な場合があり、口座振替割引を用意する会社もあります。
設計のポイントは、〈想定する自己負担許容額〉〈小口事故の発生頻度〉〈中長期の用途計画〉の三つを数字で並べ、免責・年数・支払い方法を一度に最適化することです。
- 免責→小口事故が多いなら低め、自己整備できるなら高めで保険料調整。
- 年数→用途が安定していれば長期割引を活用。用途変更が多い計画なら短期で柔軟に。
- 支払→年払・口座振替の割引有無を確認し、総コストで比較。
| 設定 | 向いているケース | 注意点 |
|---|---|---|
| 免責1万円 | 小口事故も保険で手厚く備えたい | 保険料は上がる→家財や特約のメリハリが必要 |
| 免責5〜10万円 | 軽微修繕は自己負担、保険は大口に集中 | 突発費の予備費(現金)を別途確保 |
| 長期契約 | 用途・賃貸計画が安定、資金計画が明確 | 中途解約や更改の条件を事前確認 |
- 免責を高くしたら「予備費口座」を同時に用意→小口事故に即応。
- 長期契約は“用途固定”が前提。空き家→賃貸など変更時の手続を必ず確認。
水災・風災・地震への備え

再建築不可物件のリスク設計では、火災だけでなく「水災(洪水・内水氾濫・高潮)」「風災(台風・突風)・ひょう・雪災」「地震(本震+火災延焼)」への備えが価格や資金計画に直結します。
水災は立地の標高・想定浸水深・過去冠水履歴の3点を基準に、加入の要否と免責金額を決めます。
風災・ひょう・雪災は、屋根材・外装・固定金物・外構の状態で「壊れやすさ」が大きく変わるため、加入前の点検と写真記録が重要です。
地震は火災保険では原則対象外のため、地震保険(建物・家財)で最低限を確保し、必要に応じて地震火災費用や耐震化による保険料抑制を検討します。
とくに再建築不可の築古は、消防・避難動線の制約から「小さな被害が長期の空室損に発展」しがちです。
補償の厚みは、〈ハザード(発生確率)〉〈建物の弱点(被害規模)〉〈用途(空き家/賃貸)〉〈資金余力(自己負担許容)〉のバランスで決め、不要な補償は外しつつ、致命傷を避ける最低限を厚めにする方針が実務的です。
- ハザード(地図・履歴)×建物の弱点(屋根・外装・設備)×用途で最適化します。
- 写真・点検・見積を先に整え、補償要否と免責金額を数値で決めます。
- 地震は火災保険外→地震保険(+家財)を基礎に、費用特約で補完します。
| 災害 | 判断の主材料 | 設計のヒント |
|---|---|---|
| 水災 | 想定浸水深・標高・冠水履歴 | 高リスク→付帯+免責小、低リスク→除外/免責大 |
| 風・ひょう・雪 | 屋根/外装の健全性・地域特性 | 点検・補修+写真記録で支払実務を円滑化 |
| 地震 | 地域係数・構造・耐震性 | 建物+家財を基本に、費用特約で補完 |
- ハザード確認→点検・補修→写真台帳→補償要否と免責を決定。
- 致命傷(長期空室・全損)は厚く、小口は免責で自己負担に寄せる。
水災補償の要否と加入判断の軸
水災は、洪水・内水氾濫・高潮など「床上浸水や地盤面からの浸水」による損害を対象とする補償です。
要否の判断軸は、①想定浸水深(ハザードマップの色)②標高・地形(谷筋・低地・埋立地)③排水能力(道路勾配・側溝・桝の状況)④過去の冠水履歴(近隣証言・自治体資料)⑤建物の床高・基礎高さ・逆流対策、の5点を重ねて評価します。
想定浸水が0.5m以上、河川から近い低地、過去に床上・床下浸水があれば「付帯が基本」。
一方、高台・内陸・想定浸水浅く冠水履歴もない場合は、免責金額を上げるか水災を外し、保険料を抑える余地があります。
再建築不可の路地奥や袋地は排水・搬出が難しく、同じ浸水でも復旧コストがかさみがちです。雨どい・集水桝・外構の勾配を点検し、止水板・逆止弁・屋外機の嵩上げなどの軽微対策をセットで提示すると、引受・支払の実務がスムーズになります。
- 高リスク(付帯推奨)→想定浸水0.5m以上・低地・冠水履歴あり・床高低い。
- 中リスク→免責5〜10万円で付帯、止水・排水の改善を同時実行。
- 低リスク(削減可)→高台・内陸・履歴なし→水災除外や免責大で最適化。
| 確認項目 | 見るポイント | 対策・設計の例 |
|---|---|---|
| ハザード | 想定浸水深・流域・谷筋 | 色が濃い→付帯+免責小/薄い→免責大or除外 |
| 建物条件 | 床高・基礎・逆流対策 | 外構勾配・逆止弁・屋外機の嵩上げ |
| 履歴 | 過去冠水・排水トラブル | 桝清掃・側溝改修・写真記録 |
- 「地図の色×現地の排水実態×床高」で三重確認し、免責とセットで設計。
- 外構・樋の清掃と写真台帳を年1回更新→支払時の説明力を高める。
風災・ひょう・雪災の注意点
風災・ひょう・雪災は、屋根材(スレート・瓦・金属)、外壁(サイディング・モルタル)、付帯物(樋・フェンス・カーポート・看板)の脆弱性で被害の出方が大きく変わります。
台風・突風では、棟板金の浮き、瓦のずれ、サッシ周りのシーリング切れ、飛来物衝突が典型。ひょうは屋根・樋・外装の凹みや割れ、雪災は軒先のたわみ・雨樋破損・カーポート倒壊が代表例です。
再建築不可の細路地・旗竿地では、足場設置や資材搬入が難しく復旧費が増えやすい点も価格に反映させたいところ。
保険実務では、被害発生からの「時系列写真(全景→近景→損傷部位)」と「応急措置の記録(ブルーシート・養生)」、業者の「見積の内訳(材料・足場・運搬)」が査定のカギになります。
事前には、棟板金のビス増し締め、瓦のラバーロック、シーリング補修、物置・カーポートのアンカー確認、庭木剪定で飛来物化を防ぐ等の低コスト対策が有効です。
豪雪地では、落雪対策の雪止め・庇補強や、除雪時の第三者損害に備えて個人賠償/施設賠償も検討しましょう。
- 点検優先→棟板金・瓦・シーリング・樋・アンカー・看板固定をチェック。
- 記録重視→発生直後の時系列写真+応急養生の領収書を保管。
- 積雪地→雪止め・庇補強・除雪時の賠償(滑落・飛散)まで視野に。
| 災害別 | よくある損傷 | 事前対策/支払のポイント |
|---|---|---|
| 風災 | 棟板金の飛散、瓦ずれ、飛来物衝突 | 増し締め・剪定、時系列写真と応急養生の証跡 |
| ひょう | 屋根・樋・外壁の凹み/割れ | 素材別の損傷写真、同等材の見積根拠 |
| 雪災 | 軒先たわみ、樋破損、カーポート倒壊 | 雪止め設置、庇補強、賠償特約の確認 |
- 年1回の屋根・外装点検+台風前後のスポット点検をルーティン化。
- 物置・看板はアンカー増設、庭木は剪定→飛来物化を防止。
地震保険の上限と付帯の考え方
地震保険は、火災保険の付帯として「地震・噴火・津波」による損害をカバーしますが、保険金額の上限が建物・家財ともに火災保険金額の一定割合(一般に50%)までという制約があります。
つまり、火災保険の設定が低いと、地震保険の上限も自動的に低くなります。
評価は、建物・家財それぞれで「全損・大半損・小半損・一部損」などの区分で支払われ、自己の復旧方針(全面復旧か、最低限の復旧か)と資金余力によって、建物・家財の配分を決めます。
再建築不可の築古では「建物の大規模復旧は想定しないが、家財の買い直しは必要」というケースも多く、家財側を厚めに設定する発想が役立ちます。
付帯の考え方は、①地域係数(地震リスク)②構造・耐震性(木造/非木造、耐震改修の有無)③用途(自用/賃貸/空き家)④資金計画(自己負担許容)の四つで整理。
加えて、地震火災費用(地震後の延焼・避難に関する費用)や、家賃収入の休損特約(商品により有無)で「生活/事業の継続性」を補強します。
- 上限構造→建物・家財とも火災保険金額の一定割合まで(配分設計が重要)。
- 築古×再建築不可→家財厚め+費用特約で生活再建を優先する選択肢。
- 耐震改修や非木造はリスク低減→長期的には保険料抑制にも寄与。
| 設計要素 | 判断材料 | 設計のヒント |
|---|---|---|
| 地域係数 | 発生確率・断層帯・地盤 | 高リスク地域は建物+家財とも最低限を確保 |
| 耐震性 | 構造・築年・改修履歴 | 耐震改修の証跡(報告書・写真)で説明力UP |
| 生活/事業継続 | 家族構成・賃貸運用の有無 | 家財厚め、費用特約、休損の有無を検討 |
- 建物+家財をセットで付帯(家財は実生活に直結)。
- 地震火災費用等の費用特約で初動費用をカバー。
事故対応と請求の実務手順

火災・風水害・盗難などの損害が起きた直後は、「安全確保→記録→応急措置→連絡→書類化→見積→申請」という流れで進めます。
まずは感電・落下・延焼など二次被害の危険を止め、居住者・近隣の安全を確保します。次に、現場の“ありのまま”を写真・動画で記録し、日時・天候・被害の広がり(全景→中景→近景→品番)の順で押さえます。
応急措置は被害拡大を防ぐ範囲(ブルーシート養生・止水・仮撤去)に留め、使用資材や費用の領収書を保存します。保険会社・代理店へは早期連絡し、事故状況と応急措置の内容、立入に適した日時を共有します。
並行して見積は同条件で2~3社から取得し、範囲・数量・単価・足場・運搬・廃材処分まで明示。申請時は「写真台帳」「見積」「修理計画」「所有・使用のわかる書類」を束ね、約款(免責・対象外・期限)に沿って提出すると認定がスムーズです。
- 流れ→安全確保→記録→応急措置→保険会社連絡→見積→申請→検収・保管。
- 記録は“時系列+位置情報+寸法”で第三者が追える形に整えます。
- 修理は原則、保険会社の了承後に本施工。応急は領収書を必ず保存。
| 段階 | 実務ポイント |
|---|---|
| 安全確保 | ブレーカー遮断・ガス止栓・立入規制。感電・落下物・煙の確認。 |
| 記録 | 全景→近景→品番/シリアル、濡れ跡・破断面・飛来物の痕跡を撮影。 |
| 応急 | 養生・止水・片付けは最小限。資材・人件の領収書を保管。 |
| 連絡 | 保険会社に事故日・状況・応急内容・被害箇所・見積予定日を通報。 |
| 申請 | 写真台帳・見積・請求書・所有確認・約款該当条文をセット提出。 |
- 安全→記録→応急→連絡→見積→申請→修理→保管の8ステップ。
- “後から同じ結論になる資料”を作る意識で、時系列と根拠を揃える。
発生直後の記録・写真・応急措置
事故直後は「被害の固定化」が最優先です。まず人の安全を確保し、電気・ガス・水の遮断、倒壊の恐れがある場所の立入規制を行います。
次に記録。撮影は〈全景(建物外観・周囲の状況・足場の必要性)〉→〈中景(被害エリアの範囲・水位ライン・飛散方向)〉→〈近景(破断面・へこみ・裂け)〉→〈品番・シリアル・購入時期〉の順で実施。
水濡れは“濡れたもの・濡れていないもの”の対比、風災は“飛来物・剝離起点”、盗難は“こじ開け痕・破損扉”を必ず押さえます。
動画で排水の逆流や雨漏りの滴下位置も補足すると説得力が上がります。応急措置は、ブルーシート・土のう・止水板・応急パッチ・除水・除湿まで。
応急資材のレシートと作業写真(ビフォー/アフター)を残し、廃材は査定後まで保管が原則です。消防・警察・自治体に通報した場合は、受付番号や指導メモを保存。
保険会社へは事故日・原因の仮説・被害箇所・応急内容・人的被害の有無を通報し、査定立会に備えて現地図・鍵・足場計画を整理します。
- 撮影→全景→中景→近景→品番。濡れ跡・破断面・飛来物の“起点”を写す。
- 応急→養生は最小限、資材と作業の領収書・写真を保存。廃材は原則保管。
- 連絡→保険会社・消防/警察の受付番号、自治体の指導メモを控える。
| 対象 | 撮影の要点 | 応急・記録 |
|---|---|---|
| 水濡れ | 水位線、濡れた床・壁、家具の濡れ境界 | 除水/除湿、カビ防止材の使用、レシート保管 |
| 風災 | 棟板金の剥離起点、飛散方向、破片 | ブルーシート養生、飛散物回収、金物の仮固定 |
| 盗難 | こじ開け痕、壊された錠・窓・扉 | 警察受理番号、修理前写真、被害品リスト |
- 本修理を先に進める(査定前の交換・廃棄で立証が難しくなる)。
- 濡れた家財の即処分(写真と型番がないと支払対象から外れやすい)。
見積・修理・申請書類の整え方
支払の要は「同条件の見積」と「整った台帳」です。見積は2~3社から取得し、対象範囲・数量・単価・足場・運搬・廃材処分・仮設(ブルーシート)・復旧仕様(同等材/同等性能)を統一。
差異は比較表で可視化し、過大/過少な項目を理由付きで整理します。
申請書類は、①事故の概要(日時・天候・原因・被害箇所・応急内容)、②写真台帳(全景→近景→品番、撮影日入り)、③見積書(内訳明細・範囲図)、④所有・使用の確認(登記事項・賃貸借契約等)、⑤請求書・振込先、⑥警察・消防・自治体の受付資料(該当時)を一式。
賃貸なら家主賠償や休損の有無、共用部/専有部の線引きも添えます。
査定時に“補修で直るか交換か”が論点になりやすいため、業者の技術見解(補修不可の理由・メーカー推奨交換)を見積に添付。
空き家は巡回記録や鍵管理メモの提出で「管理中」を証明できます。提出後は、差戻し想定の追補資料(追加写真・材料証明・型番リスト)を準備しておくと再提出が早いです。
- 見積は同条件化(範囲・数量・単価・足場・運搬)→比較表を作る。
- 写真台帳は“図面と対照”できる構成に。撮影日・位置・寸法を明示。
- 技術見解を添付→交換妥当性や安全上の必要性を専門家の言葉で補強。
| 書類 | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 事故概要 | 日時・天候・原因・被害箇所 | 客観表現で簡潔、応急内容も明記 |
| 写真台帳 | 全景→近景→品番/シリアル | 撮影日・位置・寸法・矢印を追記 |
| 見積明細 | 範囲・数量・単価・仮設・処分 | 同条件化し、差異は注記で説明 |
- 写真台帳・見積・請求書・振込先・所有確認・受付番号の6点を一括で提出。
- 賃貸は共有/専有の線引きメモを添付し、賠償や休損の要件を明確にする。
認定されにくい事例と回避ポイント
認定が難航する典型は、①経年劣化・腐朽・サビ・カビ・シーリング劣化など“保険事故でない”損耗、②雨漏りの長期浸み込みや慢性的な漏水、③風災の証拠不足(飛来物・剥離起点が不明)、④盗難での警察届出なし、⑤水災で床上と床下の境界や水位線が不明、⑥申告内容と現場の整合不一致、⑦修理見積が過大/他損混在、です。
再建築不可の細路地・旗竿地では、足場・搬出が難しいため見積の内訳が膨らみやすく、「同等復旧」の範囲超過を指摘されるケースも。
回避の鍵は、〈原因と結果のつながり〉と〈時系列の証跡〉、そして〈同等復旧の根拠〉です。風災なら気象データの日時・最大瞬間風速を控え、剝離起点・飛散物の写真を添付。
水災は水位線と濡れ境界、家財は型番・購入時期を明記。雨漏りは“台風直後の新規浸水”と“経年”の区別を写真で示します。劣化部分は対象外になりやすいので、修繕計画と併せて“事故で悪化した部位”を線引きします。
- 「事故」対「劣化」の線引き→原因・日時・痕跡・気象データで客観化する。
- 同等復旧の範囲→材料・色柄・性能が近い代替案を明示し、過大仕様を避ける。
- 時系列の証拠→発生→応急→見積→修理の順で写真と書類を揃える。
| 難航パターン | よくある理由 | 回避ポイント |
|---|---|---|
| 雨漏り | 経年劣化と混在、気密・防水の寿命 | 台風直後の濡れ跡と旧跡の区別、水位・浸入点を撮影 |
| 風災 | 飛来物/剝離起点の証拠不足 | 破片・剝離部の接写、当日の気象データ添付 |
| 盗難 | 届出なし・こじ開け痕なし | 警察受理番号、破壊痕撮影、被害品リスト |
- 原因→結果のストーリーを図と時系列で作る(誰が見ても同じ結論)。
- 同等復旧の根拠と過大仕様回避を見積書に明記(代替材のカタログ添付)。
まとめ
加入可否は「用途×建物状態×立地」で左右されます。
①評価方式(再調達/時価)を決める→②水災・風災・地震の要否を選別→③免責と契約年数で保険料を最適化→④空き家/賃貸の条件を満たす→⑤事故時は写真・見積・申請書を時系列で整備。
根拠をそろえれば、過不足なく備えられます。