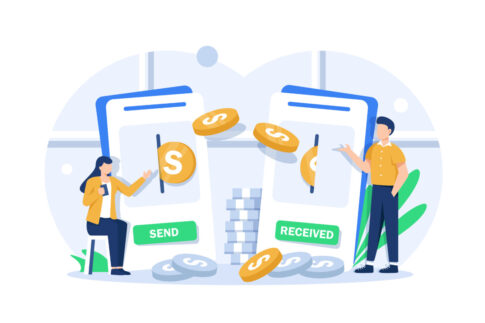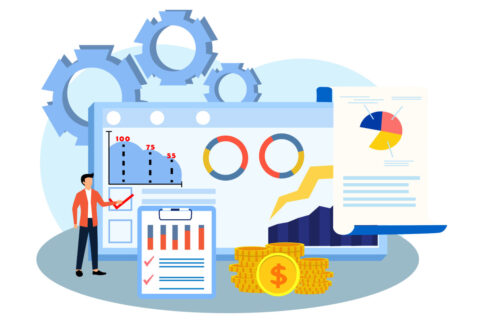測量や境界確定で高収入を得る土地家屋調査士こそ、累進課税で手取りが圧縮されがちです。本記事では給与所得控除から法人化、共済・保険、減価償却を活かした不動産投資まで、実務で使える節税テクニックを体系化。
初心者でもすぐ実践できる具体例付きで、税負担を半減しつつ事務所資金と個人資産を同時に増やすヒントが得られます。
目次
土地家屋調査士が節税で得られる3つのメリット

土地家屋調査士は測量・境界確定の高単価案件が多く、年収が1,000万円を超えるケースも珍しくありません。累進課税によって税負担が年々重くなる一方で、測量機器や出張旅費など業務経費を適切に計上すれば、実効税率を大幅に下げられる可能性があります。
本章では①高累進課税の圧縮効果、②キャッシュフロー向上と事務所成長、③測量機器投資を活かした経費計上という3つの視点から、土地家屋調査士が得られる具体的な節税メリットを整理します。
まず控除や経費で課税所得自体を減らすことで、45~55%に達する最高税率ゾーンを回避可能です。次に浮いたキャッシュをITツールや広告に再投資すれば売上増→追加の経費枠確保→さらに節税という好循環を構築できます。
最後に高額なトータルステーションやドローン測量機を減価償却すれば、会計上の費用が増えて当期の所得を圧縮できるうえ、精度向上により受注単価アップも期待できる点が魅力です。このように節税策と業務成長施策を連動させることで、手取りを守りながら事務所規模を拡大する戦略が実現します。
高累進課税の圧縮効果
土地家屋調査士が最初に取り組むべきは、課税所得を圧縮して累進税率の高い帯を避けることです。個人事業のまま年収1,800万円を超えると所得税40%・住民税10%の合計50%帯に入り、利益の半分が税金で消える可能性があります。
節税の入口として効果的なのは、青色申告65万円控除です。さらに30万円未満の測量備品を少額減価償却資産として一括経費化すると、初年度に費用を全額計上できるため、利益が多い期ほど税負担を抑えやすい仕組みです。
| 節税策 | 具体的な効果 |
|---|---|
| 青色申告特別控除 | 複式簿記と電子申告で65万円を課税所得から控除 |
| 特定支出控除 | 測量研修費・専門書代が給与所得控除額1/2超なら追加控除 |
| 少額減価償却 | 30万円未満のドローンを購入年度に全額経費化 |
- 経費領収書をスマホで即撮影→クラウド保管で紛失防止
- 利益が増えそうな年に測量機器を計画的に更新→即時経費化
これらを組み合わせると、課税所得が数百万円単位で減少し、実効税率を20〜30%台に抑えられる可能性が高まります。
ただし短期的に大型投資をしすぎると資金繰りを圧迫するリスクがあるため、次項で説明するキャッシュフロー戦略と併せて実行してください。
キャッシュフロー向上と事務所成長
節税で確保したキャッシュを「再投資」に回すことで、事務所の成長スピードを高める好循環が生まれます。
たとえばクラウド型測量CADやオンライン申請システムに投資すると、作業時間が短縮され外注費と人件費を圧縮できるうえ、同時に処理件数を増やして売上拡大が期待できます。
【再投資アイデア】
- クラウド測量CAD→作図時間を30%短縮し残業代を削減
- SEO対策付きホームページ→境界確定案件の新規顧客を獲得
- 補助者研修プログラム→現場作業を任せ代表は高単価業務へ集中
| 投資先 | 費用 | 期待ROI |
|---|---|---|
| 測量CAD | 月1万円 | 作業効率1.3倍→人件費10%削減 |
| Web広告 | 月5万円 | 1案件平均20万円×月2件増=+40万円 |
| 研修費 | 年間30万円 | 補助者の生産性20%向上 |
- ROIを必ず試算し、回収期間を6〜12か月で設定
- 設備投資は減価償却と合わせて税負担とCFを両睨み
こうした再投資で売上が増えれば経費計上枠も広がり、さらなる節税原資が生まれます。高収益化→追加投資→節税というループを回すことで、資金繰りに余裕が生まれ、大型のドローンや3Dレーザースキャナ導入など次ステージの成長投資へ進みやすくなります。
測量機器投資を活かした経費計上
土地家屋調査士ならではの節税手段が、高額な測量機器を戦略的に購入し、減価償却費として計上する方法です。トータルステーションやGPS測量器は1台数百万円に上ることも多く、法定耐用年数(機械装置:5年など)で均等に費用化できます。
利益が多い年度に大型機器を購入すると、初年度から償却費が加算され課税所得を圧縮できるため、税率の高い帯を避けやすいです。また、ドローン測量用カメラや3Dスキャナなど30万円未満の周辺機器は一括経費化が可能で、即効性のある節税が見込めます。
- 【耐用年数短縮】中古機器を購入すると残存耐用年数が短く、大きな償却費を早期計上可
- 【リース活用】年度途中で利益が読みにくい場合、リース料を経費化しCF影響を平準化
- 【補助金併用】国交省や都道府県の設備投資補助金を活用し自己資金を抑制
- 年度初に利益予測→償却費を逆算し購入タイミングを決定
- キャッシュ不足時は銀行融資よりリース→資金繰り圧迫を回避
設備投資は節税効果と業務効率化を同時に狙える一石二鳥の手段ですが、購入後の保守費用や保険料も発生します。導入前に5年分のキャッシュフローを試算し、利益が減少する年にも返済が滞らないか確認してから実行すると安全です。
勤務・個人開業・法人化別の節税メニュー

土地家屋調査士は勤務社員として企業や測量会社に在籍するケース、独立して個人事業として測量業務を請け負うケース、そして規模拡大に合わせて土地家屋調査士法人を設立するケースの3段階で課税区分が変わります。
勤務形態では給与所得者として自動計算される給与所得控除が中心になる一方、個人開業形態では青色申告による特別控除65万円と幅広い事業経費計上が可能です。
さらに中小法人等の軽減税率は、年800万円以下の所得に対して「15%」、年800万円超の部分は「23.2%」が適用されます(適用要件あり)。役員報酬や退職金で家族に所得分散ができるため、個人事業よりも大幅な税率低減が狙えます。
ここでは〈給与所得控除と特定支出控除〉〈青色申告と事業経費最大化〉〈測量出張旅費の適正按分〉の3つの視点で、各ステージごとに取り組みやすい節税メニューを解説します。
事務所の成長フェーズごとに最適な制度を組み合わせることで、キャッシュを守りつつ次の設備投資や人材採用へつなげる資金余力を確保できると考えられます。
給与所得控除と特定支出控除
勤務土地家屋調査士がまず意識したいのは、自動的に適用される給与所得控除を踏まえたうえで、特定支出控除を追加活用することです。
給与所得控除は年収に応じて定額・定率で差し引かれるため、課税所得が入り口で圧縮されますが、測量研修費や専門書購入費、遠方現場への旅費など自己負担の業務費用が大きい場合には〈特定支出控除〉が上乗せで適用できる場合があります。具体的には、年間特定支出額が給与所得控除額の1/2を超えた部分が追加控除となる仕組みです。
【対象となりやすい支出】
- 測量士会主催セミナー受講料やCPD講習費
- 境界判例集や最新測量基準書籍の購入費
- 山間部測量のためのレンタカー・宿泊費
- 会社へ証明書発行手続きを早めに依頼→確定申告に必須
- 経費領収書を月ごとにクラウド保管→集計漏れをゼロ化
これにより、年収1,000万円の勤務者でも年間20〜40万円の課税所得を追加で圧縮できる可能性があります。浮いた税金は自己研鑽や資格更新に充てると、長期的な収入増につながる好循環を生みやすいです。
青色申告と事業経費最大化
個人開業土地家屋調査士は、青色申告を行うことで最大65万円の特別控除を受けられます。さらに、測量業務に必要な機材・旅費・外注費・広告費などを幅広く経費計上できる点が強みです。
まずは複式簿記で日々の取引を記帳し、クラウド会計ソフトを利用して月次で利益を確認する仕組みを構築しましょう。
| 主な経費区分 | 具体例と節税効果 |
|---|---|
| 測量機器リース料 | 毎月のリース料を全額経費化→購入よりキャッシュを温存 |
| 地代家賃 | 自宅兼事務所の家賃・ローン利息を専有面積で按分 |
| 通信費・クラウド | オンライン測量CAD・データ保管サービス利用料 |
- 年初に設備更新計画を作成→利益過多期に投資を集中
- 仮払金・未払金を月末で締め→経費計上漏れを防止
青色申告決算書を毎月作成すると、利益が想定より増えた段階で倒産防止共済や長期平準定期保険に資金を振り向け、課税所得を平準化する意思決定がしやすくなります。また、電子帳簿保存法に準拠したスキャナ保存を導入すれば、証憑管理の効率化と税務調査リスク低減を同時に実現できます。
測量出張旅費の適正按分
土地家屋調査士は山間部や離島、都市再開発エリアなど遠隔地での測量依頼が多く、旅費交通費が高額になりがちです。経費として適正に計上するためには「業務実態に即した按分ルール」をあらかじめ定め、証憑と併せて保存することが重要とされています。
- 日当・宿泊費の社内規程を策定→税務調査時に合理性を説明
- 私的観光部分が混在する場合→領収書を分割し業務割合のみ経費化
- マイカー使用時→走行距離×国税庁燃料単価を基に算出
- 観光地で家族同伴→全額経費計上は否認リスク
- ETC・ガソリン明細を保管していない→距離根拠不足
旅費の按分ルールを事前に整備すれば、税務リスクを避けつつ必要経費を最大化できます。さらにクラウド経費精算システムで領収書画像と走行距離を紐づけると、経費申請の手間を削減でき、補助者の生産性向上にもつながります。
こうした仕組み化は法人化後にもそのまま運用できるため、早い段階で規程を整備しておくことがキャッシュフローと監査対応の両面で有効です。
共済・保険を活用した利益平準化

土地家屋調査士は案件ごとの入金額が大きく、期によって利益がばらつく傾向があります。利益が突出した年度にそのまま課税されると、高い累進税率が適用されキャッシュフローが一気に縮小してしまうことがあります。
そこで有効なのが、共済や保険を用いた「利益の平準化」です。たとえば、決算期末に利益が想定を上回りそうな場合は、掛金を全額損金算入できる倒産防止共済や小規模企業共済に資金を振り向けることで、課税所得を翌期以降にスライドさせられます。
また、長期平準定期保険を活用すれば、保険料の一部を損金に計上しつつ解約返戻金で将来の運転資金や退職金原資を準備可能です。
これらの制度を組み合わせると、好況期の税負担を抑えつつ不況期に備える資金バッファーを形成できるため、長期的な事務所経営の安定に寄与します。以下では、①倒産防止共済と小規模企業共済、②長期平準定期保険の二つに分けて、土地家屋調査士が押さえておきたい具体的なポイントを解説します。
倒産防止共済と小規模企業共済
倒産防止共済(経営セーフティ共済)は、掛金を月5,000円〜20万円まで自由に設定でき、年間240万円を上限に全額が必要経費または損金になる制度です。
40か月以上掛金を納付すれば解約返戻率が100%であり、節税と資金準備を同時に行えるメリットがあります。
小規模企業共済は月1,000円〜7万円の掛金が全額所得控除となるため、個人所得税・住民税の即時圧縮に有効です。受取時には退職所得控除が使えるため、将来の税負担も低く抑えられます。
| 制度名 | 主な特徴と活用シーン |
|---|---|
| 倒産防止共済 | 掛金全額損金。40か月以降は100%返戻。好況期の利益圧縮&資金バッファー確保。 |
| 小規模企業共済 | 掛金全額所得控除。20年以上の長期拠出で元本割れリスク解消。退職金準備に最適。 |
- 決算3か月前に利益予測を確認し、掛金を増減して最適化
- 倒産防止共済は40か月を一つの目安に長期運用を計画
- 共済掛金は銀行口座引落しに設定し、支払忘れを防止
- 倒産防止共済の短期解約(12か月未満)は元本割れが生じるため、キャッシュ余力を見ながら掛金を決定することが大切です。
- 小規模企業共済の掛金は、月額1,000~70,000円の範囲で500円単位で設定でき、増額・減額はいずれも可能です(申込時期・前納状況等により適用タイミングの制約あり)。
- 両共済は同時加入できるため、目的別に掛金を振り分けることでリスク分散効果が高まります
長期平準定期保険の損金活用
2019年の税制改正で短期払いの高返戻率保険は大幅に制限されたものの、長期平準定期保険は依然として利益調整に活用しやすい保険商品といわれています。
保険期間を10年以上、返戻率を70〜80%程度に設計することで、保険料の1/2を損金算入できるケースが一般的です。契約期間中は保険料の半分が費用化される一方、残り半分は資産計上されるため、財務バランスを損なわずに節税が可能です。
- 【契約形態】土地家屋調査士法人名義で加入し、保険金受取人も法人に設定
- 【保険料支払】決算直前に前納保険料を支出し、当期利益を圧縮
- 【解約返戻金】退職金支給や測量車更新など、大口支出のタイミングで解約し資金確保
| 活用タイミング | 主なメリット | 注意点 |
|---|---|---|
| 利益急増期 | 保険料損金で課税所得を圧縮 | 資金繰りに影響しない支払額に設定 |
| 退職金支給時 | 解約返戻金で原資を調達 | 返戻益が益金計上されるため他の経費と合わせて調整 |
- 解約返戻金を受け取る年度は益金が発生→退職金や設備投資と同時実行で相殺
- 返戻率が高すぎる商品は税務否認リスクがあるため契約前に税理士へ確認
- 保険期間中に利益が急減する場合は、既払込保険料と返戻率を勘案し、減額や払済変更でキャッシュフローを調整することも検討しましょう。
- 保険料は長期固定費になるため、加入前に5年〜10年先までの資金計画を必ずシミュレーションしてください。
土地家屋調査士法人・資産管理会社で税率を下げる

個人事業で高収益を上げ続けると、所得税45%と住民税10%を合わせた最大55%の累進課税に突入し、せっかくの利益が税金で目減りしやすいとされています。
これを避ける王道策が「法人化」もしくは「資産管理会社」の設立です。中小法人の実効税率は所得800万円以下の部分で約19%、超過部分でも23%台にとどまるため、同じ利益でも税負担が大きく圧縮できる可能性があります。
さらに法人化により〈役員報酬〉〈退職金〉〈福利厚生費〉など多彩な経費化ルートを確保でき、家族を役員に登用して所得を分散すれば世帯単位での税率も引き下げられます。
また、測量業務に付随する不動産の取得や機器リースを資産管理会社側で行えば、法人税率の恩恵を受けながらキャッシュフローを柔軟に調整できる点も魅力です。
本章では①法人税率と所得分散シミュレーション、②家族役員報酬と退職金制度、③インボイス対応と消費税簡易課税という3つの観点から、土地家屋調査士が実践しやすい節税スキームを具体例とともに紹介します。
これらを段階的に組み合わせることで、手取りを守りつつ将来の資産形成と事務所の成長資金を同時に確保する戦略が描けます。
法人税率と所得分散シミュレーション
個人事業で年間利益2,000万円を稼いだ場合、所得税40%+住民税10%で約1,000万円が税金として消える可能性があります。
一方、土地家屋調査士法人を設立し〈法人利益800万円+代表者役員報酬1,200万円〉に配分すると、法人側は軽減税率19%で約152万円、個人側は所得税33%帯+住民税10%で約518万円となり、合計約670万円に圧縮できる試算です。
| 区分 | 課税対象 | 概算税額 |
|---|---|---|
| 個人事業 | 所得2,000万円 | 約1,000万円 |
| 法人+個人 | 法人800万円+個人1,200万円 | 約670万円 |
- 決算3か月前に利益を予測し、法人・個人の最適配分を試算
- 役員報酬で法人利益を800万円以下にコントロール
- 超過利益は共済掛金や設備投資で平準化し追加節税
- 資産管理会社を別途設立し、不動産所得や機器リース料を法人側で受け取れば、さらなる分散効果が期待できます。
- 複数法人化は事務負担も増えるため、顧問税理士と採算ラインを事前に確認しましょう。
家族役員報酬と退職金制度
法人化の節税効果を拡張する鍵は〈家族への役員報酬〉と〈退職金制度〉です。たとえば配偶者を取締役に登用し、年間500万円を支給すれば、配偶者の給与所得控除や基礎控除を活用でき、結果として世帯合算の実効税率を下げられます。
成人した子を業務補助役員として年300万円支給すれば、子の独立資金を準備しつつ法定控除枠も併用可能です。
- 役員報酬は事業年度開始時に定額決定→期中変更は原則不可
- 勤務実態を示す業務日報・出勤簿を保存→税務調査時の証憑
- 扶養控除のラインを超えないよう年額103万円・130万円を意識
退職金については〈報酬月額×功績倍率×勤続年数〉で算定するのが一般的で、功績倍率2.0〜3.0が妥当とされています。
法人側では全額損金算入、個人側では退職所得控除を適用できるため、役員報酬よりも大幅に優遇された税制効果が得られます。
- 役員退職金規程を整備し、支給算定式を明文化
- 長期平準定期保険や共済解約返戻金を原資としてプール
インボイス対応と消費税簡易課税
2023年からのインボイス制度により、免税事業者のままでは取引先が仕入税額控除を受けられず、値下げ要請や取引停止リスクが高まるとされています。
土地家屋調査士法人として課税事業者登録を選択する場合、本則課税か簡易課税かを選ぶ必要があります。測量業務は仕入れや外注が少ない傾向にあるため、みなし仕入率が50%の第5種(サービス業)に該当する簡易課税の方が有利となるケースが多いです。
| 方式 | 適用条件 | 向いている事務所 |
|---|---|---|
| 免税 | 課税売上1,000万円以下 | 顧客が個人や免税事業者中心 |
| 課税・本則 | 仕入控除が多い場合 | 外注費・機器購入が多い年 |
| 課税・簡易 | みなし仕入率50% | 人件費中心で仕入控除が少ない事務所 |
- 簡易課税は2年間継続義務→途中変更不可のため利益予測必須
- 適格請求書発行にはクラウド請求書システム導入が円滑
- 決算前に消費税試算を行い、本則と簡易の納税額を比較して有利判定を行いましょう。
- 免税基準期間1,000万円超が見込まれるタイミングで、いつ課税事業者に移行するかシミュレーションしておくと、キャッシュショックを防げます。
資産運用で広がる節税の可能性

給与所得控除や共済だけでは節税効果に上限が生じると感じたら、次に検討したいのが「資産運用と組み合わせる節税」です。土地家屋調査士は与信力・測量知識・不動産に関する法律理解が高いという3つの強みを持つため、投資と節税を両立させやすい職業といえます。
まず基礎固めとして〈iDeCo〉〈新NISA〉で長期インデックス運用を行い、掛金控除や運用益非課税を享受します。次に〈倒産防止共済〉〈長期平準定期保険〉などで利益が伸びた年度の課税所得を平準化し、キャッシュリザーブを確保します。
そして最終段階として〈不動産投資〉を組み込むと、減価償却費で課税所得を圧縮しつつ家賃収入でキャッシュフローを補強できるため、節税と資産形成を同時に加速できます。
これらを段階的に組み合わせることで、税負担を抑えながら設備投資や人材採用に回せる資金を生み出し、事務所の持続的成長と個人資産の拡大を両立させる好循環が期待できます。
| 資産種別 | 節税メリット |
|---|---|
| iDeCo | 掛金全額所得控除・運用益非課税 |
| 新NISA | 運用益・配当恒久非課税で複利効果最大化 |
| 不動産投資 | 減価償却で所得圧縮・家賃収入でCF安定 |
- 非課税投資枠(iDeCo・新NISA)で基礎固め
- 共済・保険で利益を平準化し資金バッファーを確保
- 不動産投資でキャッシュフローと減価償却を両取り
土地家屋調査士に不動産投資がおすすめな理由
不動産投資が土地家屋調査士に向いている主な理由は「与信力」「測量・登記の専門知識」「減価償却による節税」の3点に集約されます。
まず与信力について、士業は安定した事業収入と社会的信用を評価されやすく、地方銀行や信用金庫から長期固定ローンを低金利で調達しやすい傾向にあります。自己資金を抑えてレバレッジを効かせやすいため、物件数や規模を早い段階で拡大できる可能性があります。
次に測量・登記の専門知識を活かすことで、境界トラブルの有無や越境リスクを自ら調査でき、契約書のチェック精度も高まります。
これにより、一般投資家が見逃しがちな法的瑕疵を事前に回避できる点が大きな優位性です。最後に減価償却による節税効果です。築20年以上のRC造マンションなどを取得すると、残存耐用年数で建物価格を償却できるため、家賃収入が黒字でも不動産所得を赤字化し、給与・事業所得と損益通算できるケースがあります。
【おすすめ投資条件】
- 駅徒歩10分圏内・築古RC造→空室リスク低&高い減価償却
- 長期修繕計画と積立金残高が健全→将来CFを圧迫しにくい
- 固定金利または長期固定ローン→金利上昇リスクを軽減
- ローン返済比率を家賃収入の50%以下に設定
- 測量・境界確認は自ら立会い→瑕疵リスクを最小化
- 減価償却期間終了前に法人へ物件移管し、法人税率でCF最適化
不動産投資で得た家賃収入は、測量機器の買い替えやスタッフ採用など事務所成長の原資にも活用できます。
さらに物件を資産管理会社で保有すれば、法人税率19%帯に抑えたうえで役員報酬や退職金で所得分散が可能となり、個人・法人トータルでの最適化が図れます。土地や建物の専門家だからこそ見抜けるリスクと優位性を最大限に活かし、節税と資産形成を同時に加速させましょう。
まとめ
土地家屋調査士の節税は①給与所得控除・特定支出控除で課税所得を削減②青色申告と経費最大化で利益を平準化③法人化と家族報酬で税率を引き下げ④不動産投資で減価償却と家賃収入を両取り、の四段階が要点です。
まずは年間収支を棚卸し、適用できる控除と共済を確認しつつ、事務所成長に合わせて法人化や資産管理会社設立を検討しましょう。手取りを守りながら長期的な資産形成を進める行動計画が描けるはずです。