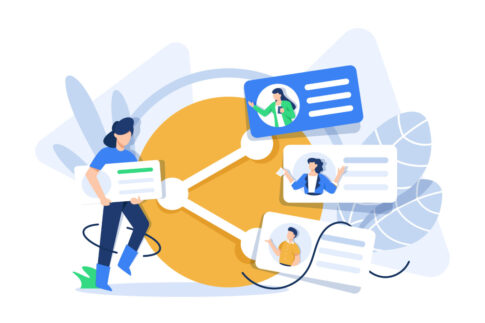高額な設計料や監理料で年収が伸びる一方、累進課税と社会保険料で手取りが減る──そんな悩みを抱える建築士の方へ。
本記事では、報酬構成の見直しや補助金活用による課税ベース削減に加え、減価償却と損益通算を駆使した不動産投資まで、税負担を抑えながら資産を築く具体策を解説します。専門用語を避けたステップ形式なので、忙しい現場でもすぐ実践できるのがメリットです。
目次
建築士が実践する節税戦略の全体像

建築士は設計料・監理料など高額報酬を得られる反面、累進課税と社会保険料の二重負担で手取りが減少しやすいとされています。
本節では、報酬構成を見直して「課税ベース」を下げる、補助金・経費計上で「実質支出」を抑える、減価償却と損益通算を活用する「投資型節税」で長期的に資産を築く——という三本柱の全体像を整理します。
さらに、建築士ならではの技術投資(BIM・省エネ設備)や業務特性(一人親方特例)を組み合わせることで、税負担軽減とキャリア拡大を同時に狙える点もポイントです。
| 領域 | 主な施策 |
|---|---|
| 報酬・保険 | 法人化による報酬分散、非課税手当、新規厚年基金の活用 |
| 補助金・経費 | BIM導入補助金、CAD更新費、講習・CPD取得費の損金算入 |
| 投資型節税 | 築古一棟アパートで短期償却、損益通算で所得圧縮 |
- 年間キャッシュフロー目標を設定し、必要な節税額を逆算
- 制度活用フェーズ→投資導入フェーズの順に段階的に実行
高所得建築士の税負担とリスク
設計プロジェクトが集中すると年収2,000万円超になるケースも珍しくありませんが、この水準では所得税45%・住民税10%が適用され、さらに報酬月額が厚生年金・健康保険の上限等級に到達する可能性があります。
繁忙期の残業単価や成功報酬が4~6月に偏ると標準報酬月額が過大に算出され、翌年度の社会保険料が想定を大きく超えるリスクも指摘されています。
加えてフリーランス契約が中心のため売上波動が大きく、設備更新・研修費など先行投資が重なる年は資金繰りのひっ迫が起こりやすいです。
- 報酬月額上限→4~6月の平均報酬で年額保険料が決定
- 設備投資ピーク→CAD・BIM更新費が重なりキャッシュ流出
- 税制改正リスク→損益通算制限で節税額が減少する可能性あり
- 報酬請求サイクルを月次化し、繁忙期の一括入金を避けると保険料が安定します。
- 大型設備投資は補助金採択後に実行し、無利子融資を組み合わせると資金繰りを守れます。
節税フレームワークと目標設定
節税を成功させる鍵は「現状把握→数値目標→施策選定→モニタリング→出口戦略」というフレームワークで進めることです。まずは年間所得・経費・社会保険料・設備投資・ローン残高を一覧化し、実効税率と可処分所得を計算します。
そのうえで「3年以内に課税所得を25%削減」「5年で家賃収入を年300万円確保」といったSMARTな目標を設定し、報酬最適化・補助金活用・不動産投資の優先順位を決定します。
進捗は四半期ごとに確認し、税制改正やプロジェクト受注の変動に応じてシミュレーションを更新することで、計画と実態のギャップを縮小できます。
- 現状分析シート作成→実効税率とキャッシュフローを算出
- 短期・中期・長期の節税目標を数値化
- 施策ごとの税効果・費用・リスクを比較
- 四半期レビュー→実績→修正→実行のPDCAを回す
- 節税額だけでなく「残る現金」をKPIに入れると意思決定がブレません。
- 家族構成や独立開業プランの変化を毎年反映し、目標をアップデートしましょう。
報酬設計と社会保険料の最適化
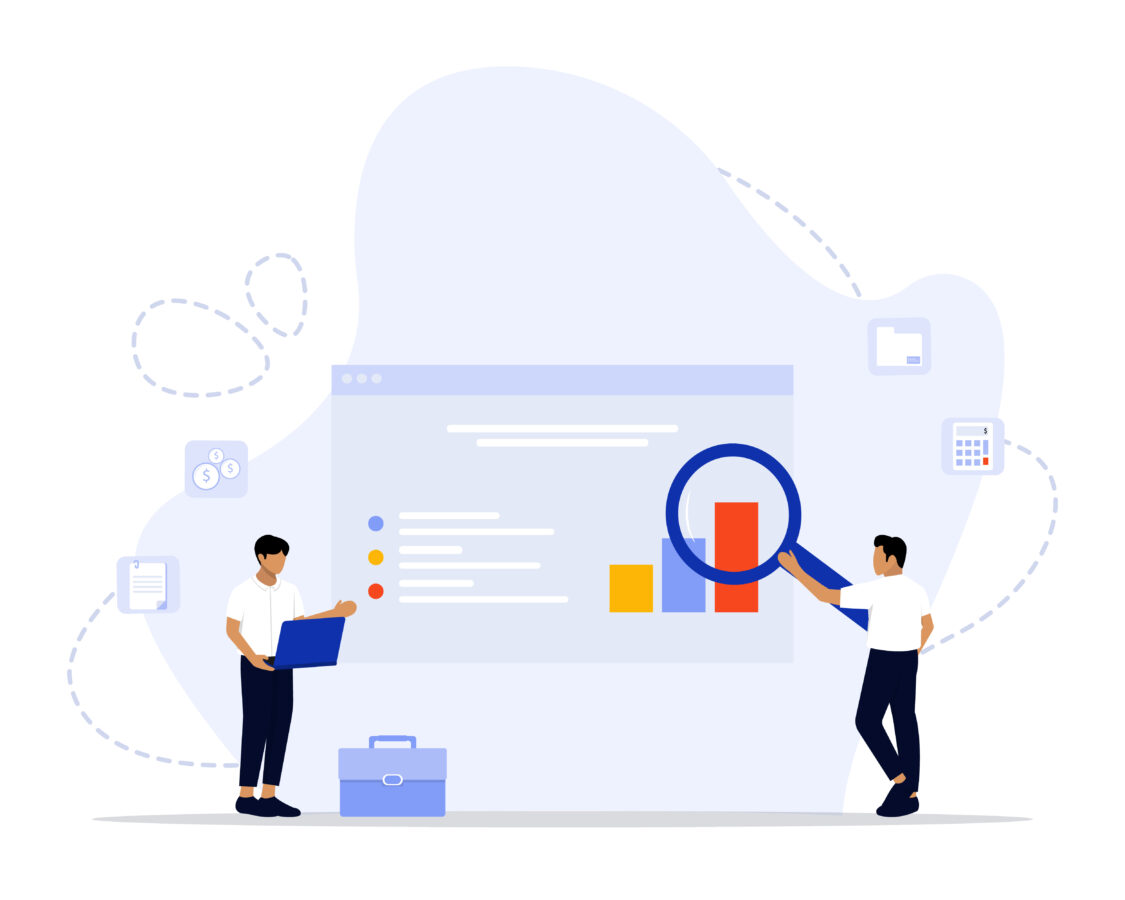
建築士の報酬は、竣工時に一括入金される設計料・監理料と毎月発生する顧問料が混在しやすく、受取時期を誤ると標準報酬月額が急騰し社会保険料が跳ね上がる傾向があります。
特に4~6月の3か月平均で標準報酬月額が決まるため、この期間を「報酬調整ウィンドウ」と捉え、入金スケジュールを平準化すると保険料を抑えられる可能性があります。
また法人化による報酬分散は、①役員報酬を抑え法人税率へシフト、②配当や管理料で家族へ所得分散、③社会保険適用拡大による負担上限のコントロール、といった複数メリットが期待できます。
さらに業務で使用するCADソフトのリース料や現場移動の車両手当を非課税精算に切り替えれば、課税対象を絞りつつ必要経費化が可能です。こうした多層的なアプローチで、可処分所得を増やし資金を投資や研究開発に再投下する循環を構築しましょう。
設計料・監理料の分散と法人化効果
設計料・監理料は着手金・中間金・竣工金の3分割が一般的ですが、実務では竣工金が総額の50〜60%を占めることがあります。この比重を維持したまま4~6月に入金すると、標準報酬月額が最高等級に跳ね上がり、年間社会保険料が100万円単位で増える場合があります。
回避策として「進捗連動分割」へ切替え、工程ごとに請求する方法があります。さらに法人化すれば、役員報酬を定期同額給与として月額に平準化し、法人側で利益を内部留保することで社会保険料と所得税を同時にコントロールできます。
| 区分 | 個人受取 |
|---|---|
| 社会保険料 | 竣工金集中→上限等級へ到達しやすい |
| 所得税 | 累進課税45%ゾーンに入りやすい |
| キャッシュ管理 | 税・保険料納付タイミングと重なると資金繰りが逼迫 |
- 役員報酬・配当・管理料に分散し平均税率を引下げ
- 社会保険の総報酬月額を抑え負担上限をコントロール
【導入ステップ】
- 顧客と契約書を再締結し、進捗連動の請求スケジュールへ変更
- 法人設立時に資本金1,000万円未満で消費税免税期間を確保
- 役員報酬は4~6月の平均が上限等級を超えない金額に設定
一人親方特例と労災保険の負担軽減
現場監理を請け負う建築士は「一人親方」の立場で労災保険に特別加入できます。一人親方特例は労働保険料率が一般労働者より低めに設定されているため、年間保険料を抑えられるとされています。
ただし保険料算定の基礎となる「年間見込賃金額」は自己申告の方式を採るため、過大に設定すると負担増、過小に設定すると給付不足となるリスクがあります。
適正額を見極めるには、過去3年の平均売上と現場日数を参考に算出し、必要に応じて半期ごとに見直す方法が推奨されます。
また自社法人を設立した場合、法人が元請の立場で「事業主特別加入制度」を利用すると、労災対象範囲を拡大しつつ保険料率を最適化できる可能性があります。
| 制度 | メリット | 留意点 |
|---|---|---|
| 一人親方特例 | 労災料率が低く保険給付が受けられる | 年間見込賃金額の設定ミスで給付不足リスク |
| 事業主特別加入 | 法人役員も労災カバー→現場事故リスクに備える | 法人分の労働保険年度更新が追加で必要 |
- 過少申告で給付額が不足すると治療費自己負担が発生する可能性があります。
- 給与と保険料の逆転現象を防ぐため、見込賃金額は定期的に見直しましょう。
【活用フロー】
- 職種コードと料率を確認し、年間見込賃金額を試算
- 特別加入申請書を労働基準監督署へ提出し、概算保険料を納付
- 年度更新で実績売上×料率を清算し、差額を精算
経費計上と補助金活用で課税ベースを削減

建築士が支払う所得税や法人税を圧縮する最も確実な方法の一つが、業務に直結する支出を「経費」として適切に計上し、課税対象となる所得そのものを減らすことです。
とりわけ設計業務では CAD ソフトのライセンス料や測量機器のリース料、最新の構造計算プログラムの利用料など、高額かつ毎年発生するコストが多いため、これらを漏れなく損金算入するだけで税負担を大幅に抑えられる可能性があります。
また、国や自治体が実施する BIM(Building Information Modeling)導入補助金や省エネ関連補助金を活用すれば、設備投資そのものを補助金で軽減しつつ、残額を特別償却や税額控除の対象にできる点も魅力です。
補助金は課税所得に算入されるものの、同時に該当設備の減価償却費が増えるため、実効税率で見れば負担減につながるケースが多いとされています。以下では①日常経費の計上ポイント、②補助金と税制優遇を組み合わせる方法を具体例とともに解説します。
CADソフト・測量機器・研修費の経費化ポイント
CAD や BIM ソフトのライセンス料は毎年更新が必要で、年間数十万円になることも珍しくありません。これらは「ソフトウェア使用料」として全額経費化できるうえ、クラウド型の場合はリース扱いとなるためリース料も損金算入が可能です。
同様に、3D スキャナやドローン測量機器のリース料・保守料も経費に計上できます。なお購入した場合は「30 万円未満の少額減価償却資産」なら一括で即時経費化、それ以上なら法定耐用年数に沿った減価償却となります。
| 支出区分 | 経費化のポイント |
|---|---|
| CAD/BIM ライセンス | クラウド型は使用料として全額経費化。 買取型は30万円未満なら一括償却。 |
| 測量機器リース | リース料・保守料を月次で損金計上。 保守契約は証憑を保存。 |
| 研修・CPD 取得費 | 国内外セミナー参加費・交通費・教材費を合算し、領収書を整理。 |
【経費漏れ防止のコツ】
- サブスクリプション更新時に自動で台帳へ連携するクラウド会計を導入。
- 月末に電子領収書を一括アップロード→AI OCR で費目自動仕訳。
- 測量機器のドローン保険料も「保険料」勘定で損金算入。
- 30 万円未満の備品購入→一括償却を適用していますか?
- 海外セミナー費→移動日も研修日として旅費規程に明記していますか?
BIM導入補助金・省エネ補助金の税優遇枠
BIM 導入補助金は、対象ソフトの購入費や社内研修費を最大 100〜300 万円程度まで助成する制度があり、採択されると初期投資負担を大幅に軽減できるとされています。
さらに補助対象外となった残額は「中小企業経営強化税制」の即時償却または 10%税額控除を選択でき、課税ベースを二重に削減することが可能です。
省エネ補助金では、高効率空調や LED 照明を導入したオフィス改修費の 1/3 前後が補助される上、固定資産の特別償却率 30%が適用されるケースがあり、建築士事務所の環境改善と節税を同時に進められるメリットがあります。
| 補助金 | 主な対象経費 | 併用できる税優遇 |
|---|---|---|
| BIM 導入 | ソフト購入・ハード更新・社内教育 | 即時償却または10%税額控除 |
| 省エネ改修 | 高効率空調・LED 照明・断熱工事 | 30%特別償却・固定資産税1/2 |
【補助金申請フロー】
- 公募要領の確認→対象経費・補助率・採択スケジュールを把握
- 事業計画書作成→投資効果・CO₂削減量・収支計画を数値化
- 採択後→完了実績報告書提出→交付額確定→会計処理へ反映
- 補助金収入は益金算入されますが、同じ設備の償却費が損金になるため実効税率は下がる傾向にあります。
- 補助対象経費を二重に申請すると返還請求のリスクがあります。購入証憑と支払い証明を厳格に管理しましょう。
不動産投資で継続的に節税と資産形成

建築士は設計業務で得た高額報酬をそのまま現金で保有していると、累進課税とインフレの二重リスクに晒される可能性があります。
不動産投資を組み込めば、①減価償却によって課税所得を毎年圧縮しつつ、②家賃収入でキャッシュフローを確保し、③相続時には評価額が下がることで資産移転コストを抑えられる、といった三層のメリットが期待できます。
さらに建築士は物件診断やリノベ設計の専門知識があるため、一般投資家より低コストで物件価値を高められる点が優位といわれます。
本節では減価償却・損益通算を最大化する実務と、リノベ適性物件を選ぶための融資・購入戦略を具体的に解説します。
減価償却・損益通算の実務
減価償却は「建物価格×償却率」で算定し、法定耐用年数で按分する仕組みです。中古物件は残存耐用年数が短縮されるため、木造なら最短4年(鉄骨は材厚等変動)で大きな償却費を計上できる場合があります。
これによりキャッシュアウトがないまま課税所得を圧縮し、所得税と住民税の負担を下げる効果が期待できます。
また不動産所得が赤字になった場合、土地取得の借入金利息を除外した後の赤字は給与所得と損益通算が認められる可能性があります。
ただし赤字幅が大きすぎると金融機関の追加融資にマイナス評価が付く恐れがあるため、ローン返済額と償却費をバランスさせて「税引後黒字」を維持する設計が重要です。
【損益通算の要点】
- 土地利息を除いた赤字のみ通算対象
- 通算しきれない赤字は繰越控除を検討
- 給与所得と相殺する際は扶養控除等が影響しないか確認
- 購入交渉で建物割合を高めると償却費が拡大します。
- 耐用年数終了年に合わせて次の物件取得や繰上返済を準備すると税負担の山谷を平準化できます。
建築士が選ぶリノベ物件投資と融資戦略
物件タイプは「築古区分マンション」「築古一棟アパート」「リノベ済み再販戸建て」など多岐にわたりますが、建築士が持つ構造・法規知識を生かすなら、リノベ前提の築古物件が有力候補とされています。
構造補強や省エネ改修を自ら設計できれば、リフォーム費の見積もり精度が高まり、追加工事リスクを抑えやすいからです。
融資戦略としては〈自己資金20%以上+返済期間は残存耐用年数+5〜10年〉を目安に設定し、返済額と償却費のピーク時でもキャッシュフローを黒字化できるようにします。
| 物件タイプ | メリット | 留意点 |
|---|---|---|
| 築古区分 | 立地重視で空室リスク小 | 建物割合が低めで償却額は限定的 |
| 築古一棟 | 短期償却可・大規模改修で価値向上 | 修繕費と空室が集中しやすい |
| 再販戸建 | 小資本で開始・出口が広い | エリア選定ミスで流動性低下 |
【融資交渉のポイント】
- 設計監理実績を提示し「技術的付加価値」を金融機関にアピール
- 長期固定金利を優先し、金利上昇リスクをヘッジ
- 耐用年数を超える返済期間は金利が上がるため試算が必須
- リノベ工程が伸びると家賃収入ゼロ期間が長期化し、返済原資を圧迫する恐れがあります。
- 赤字決算が続くと追加融資が難しくなるため、初期投資と賃料設定の精度が重要です。
節税効果を守るリスク管理と出口戦略

節税策を実行したあとに最も重要になるのは、それを長期的に維持しながら想定外のリスクに備える仕組みづくりです。
不動産投資であれば空室・修繕・金利上昇、業務収入では景況変動や受注減少がキャッシュフローを直撃し、減価償却が終了する頃には課税所得が一気に増える可能性があります。
さらに税制改正で損益通算や耐用年数のルールが変わると、当初見込んでいた節税額が縮小するリスクも否定できません。そこで①リスクの早期検知、②制度変更時のシミュレーション、③複数の出口を用意する三段階で備えることが重要です。
月次のキャッシュフローレポートと不動産管理会社のレポートを突き合わせ、キャッシュ赤字の兆候が出た段階で修繕計画の前倒しや賃料改定交渉を行うと効果的です。
出口戦略としては「個人売却」「法人移管」「持株会社化」を比較し、譲渡益課税・登録免許税・相続対策を総合評価して最適ルートを選択しましょう。
税制改正と建設業景況変動への備え
税制改正は毎年の税制改正大綱で公表され、赤字通算の制限強化や耐用年数の延長、固定資産税評価の見直しなどが議論されることがあります。これに加え、建設業界は公共工事の発注額や資材価格の変動で景況感が大きく振れやすく、報酬収入が増減しやすい職種といわれています。
したがって「税制シナリオ」と「景況シナリオ」を掛け合わせた感度分析が欠かせません。以下のフレームに沿って、最低でも年1回はポートフォリオを再評価しましょう。
| 想定シナリオ | 備えるアクション |
|---|---|
| 損益通算制限 | 黒字化優先の家賃設定へ移行し、赤字依存型物件は売却を検討 |
| 耐用年数延長 | 短期償却効果が薄れる前に設備投資を前倒しし、新たな償却枠を確保 |
| 資材高騰で工事縮小 | 設計監理の報酬単価を見直し、新築依存からリフォーム市場へ軸足を移す |
- 税制改正大綱は毎年12月に公開→即日で影響度を試算しましょう。
- 公共工事受注統計・建設着工統計を四半期ごとに確認→報酬見通しを更新。
売却・法人スキーム移行で税負担最小化
減価償却が終了するタイミングや大規模修繕の直前は、キャッシュフローと税負担が交差する転換点です。この時期に個人保有物件を長期譲渡で売却すれば、所得税15%・住民税5%の長期譲渡税率で利益確定できる一方、家賃収入はゼロになるため再投資が前提となります。
逆に法人スキームに移行すると、法人税率約30%で所得を封じ込めつつ、役員報酬・配当・退職金で所得分散が可能ですが、登録免許税や不動産取得税が移行コストとして発生します。
持株会社化を選べば、自社株評価引下げや事業承継税制を活用できる反面、設立費用とガバナンス体制の維持コストが増えるため、トータルコストで判断する必要があります。
| 選択肢 | メリット | 留意点 |
|---|---|---|
| 個人売却 | 長期譲渡税率20%→利益確定が容易 | 家賃収入喪失→再投資計画が必須 |
| 法人移行 | 法人税で所得封じ込め+所得分散 | 登録免許税・取得税など初期コストが発生 |
| 持株会社化 | 事業承継と相続税対策を両立 | 管理コストとガバナンス体制構築が必要 |
- 個人→法人売却で市場価格より低い価格設定をすると寄附金認定リスクがあります。
- 現物出資移行では簿価と時価の差額に譲渡益課税が生じる可能性があります。
まとめ
建築士が取るべき節税アプローチを、①報酬・社会保険料の最適化、②経費計上と補助金活用、③不動産投資による長期節税、④リスク管理と出口戦略の四段階で整理しました。減価償却を活かせば課税所得を圧縮しつつ家賃収入を確保できます。
まずは報酬設計を見直し、次に投資シミュレーションを行って行動計画を立てましょう。適切な出口戦略を準備すれば、税制改正や景況変動にも柔軟に対応できます。