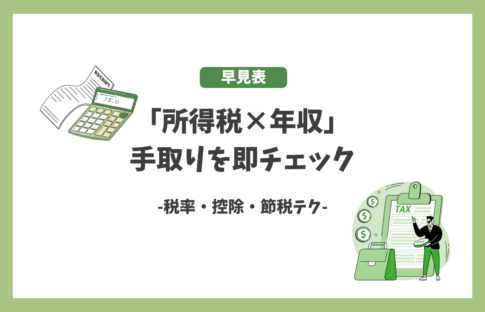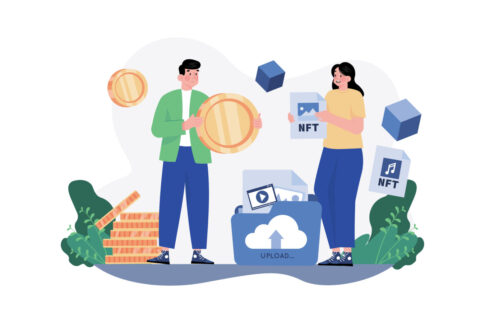年収が高い医師ほど累進課税で手取りが目減りしがちです。本記事では、国税庁データを基に「控除拡大」「医療法人・プライベートカンパニー設立」「減価償却を活用した不動産投資」の3本柱で、合法的に税負担を最大50%圧縮する方法を徹底解説。
キャッシュフロー向上や老後資産形成、働き方の自由度拡大まで得られるメリットを網羅した実践ガイドで、今すぐ使える節税戦略と注意点がわかります。詳細シミュレーション付き。
目次
医師が節税で得られる3つのメリット

医師は高年収ゆえに最大45%の所得税率に10%の住民税が加算されるため、手取りが大きく圧縮されるとされています。しかし適切な節税策を講じることで
- 税率を実効ベースで20〜30%台へ抑えられる可能性
- 浮いた資金を医療スキル向上や設備投資に再投資できる
- 将来の資産形成ペースを加速できる
など多角的なメリットが期待できます。
本章では「高累進課税の圧縮効果」「キャッシュフロー向上と資産形成」「専門職ゆえの控除優遇枠」の3点を詳しく解説し、初心者でも実践しやすい具体例を交えながら医師特有の節税メリットを整理します。
なお、本記事は国税庁や厚生労働省など一次情報を中心に作成し、古い税制を最新情報のように扱わない方針です。
高累進課税の圧縮効果
医師の平均年収は厚生労働省「賃金構造基本統計調査」で1,600万円前後とされ、高所得層に区分されます。
課税所得900万円超の区分では所得税33%、1,800万円超では40%、4,000万円超では45%が適用されるため、住民税10%と合わせると最大55%の税負担になる可能性があります。
- 所得控除(扶養控除・生命保険料控除など)を最大化→課税所得そのものを下げられる
- 医療法人や資産管理会社を設立→所得を分散し、法人税率(15〜23.2%)へシフト
- 青色申告特別控除・事業経費計上→開業医の場合、事業所得に付随する経費で税額軽減
- 法人化は年間利益1,000万円超が目安と言われています
- 損益通算が認められる資産(不動産など)を活用し赤字を作る手法も検討できます
これらの策を組み合わせることで実効税率を20〜30%台へ抑えられると考えられています。ただし法人設立や大規模投資はコストも伴うため、税理士へシミュレーションを依頼してから行動することが推奨されます。
キャッシュフロー向上と資産形成
節税策により可処分所得が増えると、日々の生活費だけでなく将来の資産形成に回せる余剰資金が生まれるとされています。例えば年間所得税・住民税を200万円削減できれば、以下のような好循環を構築できます。
- iDeCoや新NISAに満額拠出→長期運用益は非課税
- 不動産投資ローンの自己資金→レバレッジ効果で資産規模拡大
- 医療スキル向上の自己投資→収入増加に直結
さらにキャッシュフローを改善することで金融機関の融資審査でも総返済比率が低下し、資産拡大スピードが加速する可能性があります。
- 医療法人経由で役員報酬を家族へ分散し、世帯全体で手取り増
- 減価償却が大きい築古RCマンションを購入し、不動産所得を赤字化して税負担軽減
ただし安易な高額投資は資金繰り悪化リスクも伴います。キャッシュフロー計算書を作成し、融資返済や運転資金を含めた長期シミュレーションを行ったうえで実行しましょう。
専門職ゆえの控除優遇枠
医師は学会参加や専門書購入など業務関連支出が多く、「特定支出控除」を活用すると給与所得控除を上回る部分を所得から差し引ける可能性があります。控除対象となる主な費用は以下のとおりです。
- 学会参加費・参加に伴う旅費
- 専門書・雑誌の購入費用
- 白衣や医療機器の購入費用
- 勤務先から命じられた研修費・資格更新費
さらに勤務医でも条件を満たせば青色申告で65万円控除を受けられるケースがあるとされています。別途の事業(例:執筆・講演)や不動産賃貸で青色申告の要件を満たす場合に限り適用対象となります。
- 領収書や命令書を保管し、確定申告時に証明書を添付する必要があります
- 給与所得控除額の1/2超または55万円超(どちらか低い方)を超える支出のみ控除対象
このように専門職ならではの控除枠を活用することで実質的な課税所得を低減し、税率の高いゾーを回避できると考えられます。まずは年間支出を洗い出し、要件を満たすか税理士へ確認することが第一歩です。
勤務医・開業医別の主要節税メニュー

勤務医と開業医では収入形態や経費計上の自由度が異なるため、選択できる節税策も変わります。勤務医は「給与所得控除」や「特定支出控除」を軸に可処分所得を確保しつつ、iDeCo・新NISAで長期運用益を非課税化する流れが基本とされています。
一方、開業医は事業所得として幅広い経費を計上できるほか、資産管理会社を通じた所得分散や不動産投資による減価償却が大きな武器になります。
節税策を組み合わせることで、ケースによっては実効税率を20〜30%台に抑えられる可能性があります。
例えば、高額所得を法人税率の適用対象へ分散させた場合や、複数の所得控除を最大限活用した場合には、税負担軽減幅が大きくなるケースも見られます。以下では代表的なメニューを4つに整理し、それぞれの仕組みと導入ポイントを詳しく解説します。
給与所得控除と特定支出控除
給与所得控除は収入金額に応じて自動的に差し引かれるため、勤務医にとって最も基本的な節税策とされています。例えば年収1,600万円の場合、控除後の課税給与所得は約1,223万円となり、33%帯まで圧縮される計算です(参照:国税庁「給与所得控除後の給与等の金額の表」)。
さらに特定支出控除を活用すると、学会参加費や白衣購入費など業務関連支出が一定額を超えた部分を追加控除でき、可処分所得のさらなる増加が期待できます。
- 要件を満たす支出はレシート・明細を保管
- 会社が発行する証明書を確定申告書に添付
- 控除対象額=(年間特定支出額−給与所得控除額×1/2または55万円)
- 年初から家計簿アプリで経費区分をタグ管理→領収書探しの手間を削減
- 学会費や専門書はクレジットカード決済に統一→明細データが証憑になる
給与所得控除自体は自動計算されますが、特定支出控除は「証明書の添付」や「確定申告」が必須です。まずは年間の業務関連支出を集計し、控除ラインを超える見込みか早めにシミュレーションしましょう。
iDeCo・新NISAによる長期運用
iDeCoは掛金が全額所得控除になるうえ、運用益も非課税で再投資できる制度とされています。掛金上限は勤務医なら月2万3,000円、開業医が国民年金第1号被保険者なら月6万8,000円まで拠出可能です。
新NISAは年間投資枠が最大360万円(つみたて投資枠120万円+成長投資枠240万円)と拡大し、非課税期間が無期限化されたことで中長期の資産形成に適しているといえます(参照:金融庁「NISA早わかりガイドブック」)。
- iDeCo掛金→所得控除で当年の税額を即時圧縮
- 新NISA→非課税枠で運用益の複利効果を最大化
- 医療法人の役員報酬→小規模企業共済にも加入可能
- 手数料が低いインデックスファンドを中心に分散投資
- ボーナス時に新NISA枠を一括利用→ドルコストと併用で価格変動リスクを低減
iDeCoは60歳まで資金拘束されるため、生活防衛資金を確保してから上限拠出することが推奨されています。一方、新NISAは途中売却が自由なので、自身のライフプランに応じて流動性を確保しつつ非課税枠をフル活用すると効果的です。
不動産投資がおすすめ
医師は金融機関からの信用が高く、長期固定ローンを低金利で借入しやすい点が大きな強みです。物件を賃貸に出すことで家賃収入を得ながら、建物部分の減価償却費を計上すれば不動産所得を赤字化し、給与所得と損益通算できる可能性があります(参照:国税庁「減価償却のあらまし」)。
- 中古RCマンション→法定耐用年数47年─経過年数で残存年数計算
- 購入初年度→仲介手数料や登記費用も経費計上可
- 所得税節税+インフレヘッジ→二重のメリット
- 空室率が低い駅徒歩10分圏内→安定キャッシュフローを確保
- 耐用年数が短い築古物件→減価償却費を早期に計上できるため節税効果が大きい
ただし過剰な借入や高額修繕費はキャッシュフローを圧迫するリスクがあります。購入前に長期シミュレーションを行い、表面利回りだけでなく実質利回りを重視して検討しましょう。
プライベートカンパニー設立で所得分散
一定の収益規模に達した開業医や資産運用を行う勤務医は、資産管理会社(いわゆるプライベートカンパニー)を設立し、所得を法人税率へシフトさせる方法が有効とされています。
中小企業の法人税率は所得800万円以下の部分が19%、超過部分が23.2%であるため(参照:国税庁「法人税の税率」)、個人の最高55%課税に比べて大幅に軽減できる余地があります。
- 役員報酬を家族へ分散→世帯ベースでの控除枠を最大化
- 医療機器や不動産を法人名義で保有→経費計上範囲を拡大
- 退職金の積立→法人損金算入、個人側では退職所得控除
- 設立費用(定款認証・登録免許税など)や維持コスト(顧問税理士報酬)を事前に試算
- 赤字でも均等割(法人住民税)が発生→実効税率が高止まりするケースもある
法人化の目安は「年間家賃収入1,000万円超」や「不動産投資規模3物件以上」などといわれていますが、業種・家族構成により最適解は変わります。
まずは税理士に試算を依頼し、個人・法人の合算で最小税負担となるスキームを検討することが重要です。
国税庁データで見る控除・法人化の節税幅

医師が実践できる節税策の効果を定量的に把握するには、国税庁が公表する「所得税の税率表」と「法人税の税率表」を照合し、課税所得ごとに控除後の実効税率を比較することが重要です。
まず個人の場合、給与所得控除や各種所得控除を活用すると課税所得を圧縮でき、その結果として累進税率の高い帯を回避できる可能性があります。
たとえば課税所得1,800万円超の医師が寄附金控除や医療費控除を組み合わせて200万円の所得控除を得れば、課税所得は1,600万円台に減少し、最高税率45%から40%へ下がります。
さらに開業医や不動産投資を行う勤務医の場合、資産管理会社を設立し所得を法人税率へシフトすることで、個人の最高55%相当(所得税+住民税)と比べて19〜23.2%へ税負担を大幅に抑えられます。
ここでは国税庁データをもとに①所得控除別シミュレーション、②法人税率と所得分散の比較表の順に具体的な数字をご紹介します。
所得控除別シミュレーション
下表は、給与年収1,600万円の勤務医が各種所得控除を行った場合の「課税所得」と「税額」の変化を示したシミュレーションです。
| 控除パターン | 課税所得・税額の変化 |
|---|---|
| 控除なし | 課税所得約1,223万円→所得税約408万円 |
| 寄附金控除40万円 | 課税所得約1,183万円→所得税約393万円(▲15万円) |
| 医療費控除100万円 | 課税所得約1,083万円→所得税約357万円(▲51万円) |
| iDeCo拠出27.6万円+寄附金控除40万円 | 課税所得約1,056万円→所得税約347万円(▲61万円) |
【ポイント】
- 所得控除は「課税所得」を直接減少させるため、累進税率の高い帯にいるほど税額削減効果が大きくなります。
- iDeCo拠出や寄附金控除は比較的手続きが簡単で、勤務医でも導入しやすいのが特徴です。
- 年初に控除枠を把握し、早めに支出計画を立てる
- 領収書・証明書をクラウド保管し申告作業を効率化
法人税率と所得分散の比較表
資産管理会社を活用して所得を分散すると、個人課税と法人課税の差だけでなく「家族への役員報酬」や「退職金積立」などの追加メリットも得られます。
以下の比較表は、年間所得2,000万円を〈個人名義のまま〉と〈法人を設立して利益を800万円ずつ法人と個人へ分散〉した場合の概算税負担をまとめたものです。
| 区分 | 個人課税のみ | 法人+個人分散 |
|---|---|---|
| 課税所得/課税所得等 | 個人2,000万円 | 法人800万円+個人1,200万円 |
| 税率適用 | 所得税40%+住民税10% | 法人税19%+所得税33%+住民税10% |
| 概算税額 | 約1,000万円 | 法人約152万円+個人約516万円=約668万円 |
| 税負担差 | ― | ▲約332万円 |
【比較のポイント】
- 法人設立により「法人税率19%(800万円以下部分)」が適用されるため、同じ所得でも税負担が軽くなります。
- 家族を役員にして報酬を分散すると、各人の所得控除枠を有効活用できます。
- 法人から支給する退職金は損金算入でき、個人側では退職所得控除を受けられるため、さらなる節税余地が生まれます。
- 年間利益1,000万円超または不動産3物件以上
- 家族へ給与や退職金を分散できる体制がある
法人化には設立費や顧問税理士報酬など固定コストが発生しますが、シミュレーション結果のように年間で数百万円の税負担軽減が見込めるケースでは十分にペイする可能性があります。まずは試算表を作成し、個人と法人の合計税負担が最小になるラインを税理士と検討してみましょう。
減価償却&損益通算シミュレーション

減価償却とは、建物価格を法定耐用年数にわたって費用配分する会計処理であり、不動産所得を赤字化して給与所得と損益通算できる可能性があります。
特に医師は高い給与所得を持つため、初年度から大きな減価償却費を計上すると実効税率を押し下げ、キャッシュフローを改善できると考えられます。
本章では①中古区分マンションを購入した場合の年間減価償却額と税効果、②高属性ローンを活用した場合の返済負担と節税メリットを比較し、投資判断に役立つシミュレーションを提示します。
なお試算値は代表的な前提に基づくモデルケースであり、実際の効果は物件条件や個人の所得状況により変動するとされています。
中古区分マンションモデルケース
想定条件は「築20年RC造・購入価格2,500万円(建物1,800万円、土地700万円)・残存耐用年数27年・賃料年収192万円」とします。
定額法による年間減価償却費は約67万円となり、家賃収入から経費(管理費20万円・修繕積立金15万円・固定資産税12万円)を差し引くと、不動産所得は▲22万円の赤字になる計算です。
給与所得1,600万円の勤務医がこの赤字を損益通算すると、課税所得が1,223万円→1,201万円に圧縮されるため、所得税・住民税を合わせて約10万円軽減できると考えられます。
| 項目 | 金額(万円) | 備考 |
|---|---|---|
| 家賃収入 | 192 | 月16万円 |
| 経費合計 | 114 | 管理費・修繕・固定資産税 |
| 減価償却費 | 67 | 建物1,800万円÷27年 |
| 不動産所得 | ▲22 | 給与と損益通算 |
- 耐用年数が短いほど年間償却費が増え、節税効果が高まる傾向
- 土地部分は償却できないため、建物比率を確認→契約書で明示すると安全
- 赤字幅が大きすぎると金融機関審査でマイナス評価になりやすい
- 築古物件は表面利回りが高く減価償却費も大きい反面、修繕費負担が増える可能性があります。
- 損益通算は原則として3年間繰越控除できるため、翌年度以降の給与変動にも対応しやすいです。
高属性ローン活用による税効果
医師は与信力が高く、20年超の長期ローンを低金利(変動0.9%前後)で借りられるケースが多いとされています。上記モデル物件に自己資金300万円・ローン2,200万円(20年・0.9%)を適用すると、元利均等返済は月10.2万円、年間返済約122万円です。
キャッシュフローは「家賃192万円−経費114万円−返済122万円=▲44万円」となるものの、減価償却費67万円を加えると税務上の赤字は▲22万円にとどまるため、手残り資金は「−44万円+税還付10万円前後」で実質▲34万円前後と計算されます。
| 指標 | ローン利用 | 自己資金購入 |
|---|---|---|
| 初期投資 | 300万円 | 2,500万円 |
| 年間返済 | 122万円 | 0万円 |
| 税引後キャッシュフロー | ▲34万円 | +55万円 |
| 自己資本ROI | −11% | +2% |
- 返済比率が高いと金利上昇局面でCFが急激に悪化する恐れ
- 団信保険料や繰上返済手数料をシミュレーションに含める→想定外コストを防止
- 自己資本ROIは初期投資が小さいほど振れ幅が大きく、短期的にはマイナスに傾く可能性があります。
- 長期保有で家賃上昇やローン元金減少が進むと、CFがプラスに転じやすいと考えられます。
- 物件選定時は「空室率」と「修繕履歴」を確認→将来キャッシュフローの安定性を重視しましょう。
税制改正とインボイス制度の最新動向

2023年以降の税制改正では、法人課税の見直しや消費税仕入税額控除の要件強化など、医師の資産運用に直結するルールが相次いでいます。特に注目すべきは〈インボイス制度〉の開始により、課税事業者でない不動産オーナーや診療所取引先との取引コストが増大しやすくなった点です。
これに伴い、開業医や勤務医のプライベートカンパニーでも「課税事業者選択届出書」を提出してインボイス発行事業者となるケースが増えています。
さらに2024年度税制改正では、中小法人の所得拡大促進税制が延長・拡充され、スタッフの給与引上げ分を一定割合控除できる制度が続行されました。医療機関の人材確保と節税を同時に図るチャンスといえます。
加えて、電子帳簿保存法の猶予期間終了が迫り、領収書・請求書のデジタル保存要件も強化されています。これらの変更点を踏まえ、インボイス対応とデジタル保存体制を整えることは、今後の税務調査リスク低減と円滑な資産管理の鍵になります。
- インボイス登録済み事業者かどうかを取引先へ確認→仕入税額控除の損失を防止
- 給与引上げに伴う税額控除制度の適用→人件費増でも税負担を相殺
- 電子帳簿保存法の要件満たすクラウド会計ソフト導入→ペーパーレスで証憑管理を効率化
医療法人化への影響
インボイス制度は医療法人や資産管理会社を通じて外部業者へ支払う診療材料費・委託費にも影響します。課税事業者でない個人事業主から仕入れた場合、従来は仕入税額控除が可能でしたが、制度開始後はインボイス発行事業者でなければ控除が受けられず、実質コストが増大する恐れがあります。
したがって医療法人は〈取引先のインボイス登録確認〉を必須フローとし、未登録業者とは価格再交渉や契約見直しを行う必要があります。
また、法人が保有する賃貸不動産の家賃収入についても、テナントが課税事業者の場合は適格請求書の発行が求められるため、法人側の事務負担が増える点に留意しましょう。
| 項目 | 従来(免税事業者取引) | インボイス開始後 |
|---|---|---|
| 仕入税額控除 | 全額控除可 | 控除不可(経過措置あり/段階的縮減) |
| 契約書式 | 領収書・請求書のみ | 適格請求書の記載要件追加 |
| 事務コスト | 低い | 請求書保存・確認手間が増加 |
- 免税業者との取引は実質値上げになる可能性→総コストを再試算
- 家賃収入のインボイス対応→テナントとの契約更新時期を確認
- スタッフへの研修実施→請求書チェックフローを標準化
専門家に依頼すべきタイミング
税制改正の影響度合いは個々の所得形態・投資規模によって異なるため、次のような局面では早めに税理士や公認会計士へ相談することが推奨されます。
- プライベートカンパニー設立を検討し始めたとき→法人・個人合算の最適課税比較が必要
- インボイス未登録業者との取引割合が多いと判明したとき→コスト増の影響試算と契約見直し策を策定
- 電子帳簿保存法のスキャナ保存要件を満たすシステム導入が間に合わないとき→猶予申請や代替策の助言を受ける
- 給与引上げによる所得拡大促進税制の適用可否を判断したいとき→控除対象額のシミュレーションが必要
- 現在の課税区分・取引構成を一覧化→初回面談で情報共有がスムーズ
- 相談費用は経費計上可→節税効果とコストをセットで評価
- セカンドオピニオンを活用→複雑な法人スキームは複数の専門家でダブルチェック
専門家への依頼前に、自身で〈取引先のインボイス登録状況〉〈電子帳簿保存対応状況〉〈法人化による所得分散シミュレーション〉を簡易的に整理しておくと、打ち合わせ時間を短縮でき、報酬コストを抑えつつ的確なアドバイスを得やすくなります。
適切なタイミングで専門家を活用することで、税制改正リスクの最小化と節税効果の最大化を同時に達成しましょう。
まとめ
医師の節税は①各種控除の最大化②法人化による所得分散③不動産投資での減価償却活用が鍵です。国税庁データと実例シミュレーションを基に、税負担を最大50%削減しながらキャッシュフローと資産形成を同時に進める具体策を解説しました。
まずは手軽な控除チェックから着手し、専門家と連携してローン審査と物件選定を進めることで失敗リスクを抑えつつ行動に移しましょう。今こそ税金を味方にし、自由度の高い働き方を実現してください。