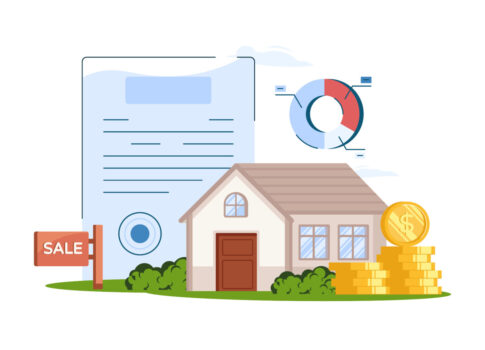毎月の給与から天引きされる税金にため息をついていませんか?制度を正しく理解し活用すれば、年間数十万円の手取りアップは誰でも狙えます。本記事ではふるさと納税やiDeCoなど定番節税対策10選を紹介し、副業・損益通算まで段階的に解説。
控除の仕組みを把握して節税プランを立て、読後にはキャッシュフロー改善へ一歩踏み出せるロードマップが手に入ります。
目次
サラリーマンが節税対策を始める前に知るべき税金の仕組み

給与明細を見るたびに「税金が高い」と感じる方も多いでしょう。日本の所得課税は超過累進税率を採用しており、額面給与が上がるほど税率が段階的に上昇します。
さらに住民税は前年の所得を基準に算出されるため、昇給の翌年に税負担が一気に重くなるケースも珍しくありません。
会社員は源泉徴収と年末調整で大半の納税手続きが完結する一方、自分で控除を申告しなければ還付を受け損ねるリスクがあります。そこで重要になるのが「課税所得=所得金額−所得控除」という公式を理解し、可処分所得を左右するポイントを押さえることです。
- 所得税:超過累進税率(5%〜45%)で算定
- 住民税:一律10%(所得割)+均等割
- 社会保険料:税額計算の前に控除対象
- 控除を増やすほど課税所得が減少し、結果的に手取りが増える
- 税額控除は算出された税額から直接差し引くため効果が大きい
所得税・住民税が決まる計算フロー
所得税と住民税は似たようで計算ステップが異なります。まず給与所得控除を差し引き「給与所得」を求めたあと、基礎控除や社会保険料控除など14種類の所得控除を合算して「課税所得金額」を割り出します。
ここに所得税の超過累進税率を適用し、復興特別所得税(所得税×2.1%)を加算したものが国へ納める税額です。
一方、住民税は前年の課税所得に一律10%を掛けて算定する「所得割」と、自治体によって決まる「均等割」を合算して確定します。
| ステップ | 具体的な内容 |
|---|---|
| 1.収入金額 | 年間の支払給与・賞与合計 |
| 2.給与所得控除 | 収入に応じて自動計算(最低55万円) |
| 3.所得控除 | 基礎控除・扶養控除・社会保険料控除など |
| 4.課税所得 | (1−2−3)で算出 |
| 5.税額計算 | 所得税率を適用し、住民税は一律10% |
控除と税額控除の違いを押さえる
節税策を検討する際にまず区別したいのが「所得控除」と「税額控除」です。所得控除は課税所得を減らす仕組みで、適用額に税率を掛けた分だけ税金が軽くなります。
例えば課税所得が330万円、税率10%の人がふるさと納税で3万円を控除すると、減税額は3万円×10%=3,000円です。
一方、税額控除はすでに算出した税額から直接差し引くため効果が大きく、同じ3万円の住宅ローン控除を受ければ税率に関係なく3万円がそのまま還付されます。
- 所得控除:課税所得を圧縮→影響度は税率次第
- 税額控除:算出税額を直接減額→影響度は一律
- 所得控除は税率の低い人ほど節税効果が限定的
- 税額控除は上限額や適用期間が定められている
さらに税額控除には「住宅ローン控除」「配当控除」「外国税額控除」などがあり、仕組みが複雑です。適用要件を誤ると全額否認されるリスクもあるため、制度内容を事前に確認し、必要書類を準備した上で確定申告・年末調整を行いましょう。
節税プランを立てる3ステップ
効果的な節税には継続的な計画が欠かせません。ここでは初心者でも取り組みやすい三つのステップを解説します。
- ステップ1:家計と税額の現状把握
- ステップ2:適用可能な控除・制度を洗い出す
- ステップ3:優先順位を決めて実行・検証
- 【ステップ1】では給与明細と源泉徴収票を用い、年間所得と社会保険料、現在の税額を整理します。支出バランスを可視化すると控除枠の余剰が見え、ふるさと納税の寄付上限額も算出しやすくなります。
- 【ステップ2】では「控除額が大きい」「手続きが簡単」「流動性を確保できる」という基準で制度を選定します。例えばiDeCoは老後資金を確保しつつ所得控除が得られる一方、60歳まで資金を引き出せない点に注意が必要です。
- 【ステップ3】では、実行した対策の節税額をエクセルシートや家計簿アプリで管理し、年度末に再評価します。年収の増減や家族構成の変化により最適な制度は変わるため、毎年の見直しが重要です。
- まずはハードルの低いふるさと納税・iDeCoから開始
- 節税額は手取りアップ分として貯蓄や投資に再投資
基本の節税対策10選|控除制度をフル活用

給与から差し引かれる税金を減らす最短ルートは「控除」の仕組みを理解し、条件に合う制度を漏れなく活用することです。
本章ではサラリーマンが今日から取り組める10の節税策をピックアップしました。いずれも国や自治体が公式に用意した制度なので安全性が高く、適切に手続きすれば年数万円〜数十万円の可処分所得アップが期待できます。まずは全体像を押さえ、自分に合うものから順に着手してみましょう。
| 対策 | 節税額の目安 | 手続き難易度 |
|---|---|---|
| ①ふるさと納税 | 年収500万円で約4〜6万円 | 寄附と申請のみ・低 |
| ②iDeCo | 掛金月2万円で年4〜6万円 | 金融機関選びが必要・中 |
| ③新NISA | 運用益20.315%分 | 証券口座開設のみ・低 |
| ④生命保険料控除 | 最大4万円 | 証明書提出のみ・低 |
| ⑤医療費控除 | 10万円超支出で数千円〜 | レシート集計・中 |
| ⑥住宅ローン控除 | 残高×0.7% | 初年度申告・中 |
| ⑦配偶者控除 | 最大38万円控除 | 年末調整のみ・低 |
| ⑧特定支出控除 | 支出額に応じる | 会社証明が必要・高 |
| ⑨損益通算 | 損失額×税率分 | 確定申告・中 |
| ⑩教育資金贈与 | 最大1,500万円非課税 | 信託契約など・高 |
※生命保険料控除:各区分(一般・介護医療・個人年金)の上限は4万円だが、3区分合計の所得税控除上限は12万円(住民税は計7万2,000円)
- まず難易度の低い①〜③で効果を実感
- 慣れたら④〜⑥で控除枠を最大化
- 状況に応じ⑦〜⑩でさらなる節税を検討
ふるさと納税で住民税を前払い
ふるさと納税は、好きな自治体に寄附を行い、その金額から自己負担2,000円を除いた額が翌年の住民税・所得税から控除される制度です。
サラリーマンの場合、年収と家族構成で決まる「控除上限額」まで寄附すれば、実質2,000円で魅力的な返礼品を受け取れるうえ、税負担そのものが軽くなります。
- ポータルサイトで寄附先と返礼品を選ぶ
- ワンストップ特例なら申請書を郵送するだけで確定申告不要
- 6自治体以内に収めると手続きが簡単
- ボーナス月に集中寄附し、年末調整前に上限額を消化
- 医療費控除など別の申告予定がある場合は確定申告で一括処理
具体例として、独身・年収500万円の場合、控除上限は約6万円です。6万円寄附すると翌年の住民税が約54,000円軽減され、返礼品(例:米20kgや高級牛肉など)が実質2,000円で手に入ります。
住民税を前払いするイメージで資金繰り計画を立てれば、家計を圧迫せずにお得さを享受できます。寄附は12月31日が締切なので、年末が近づくほど人気返礼品が品切れになる点に注意しましょう。
iDeCoで掛金を全額所得控除
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、毎月の掛金がそのまま所得控除になる強力な節税ツールです。
掛金上限は会社員の場合月1.2万円〜2.3万円(企業年金の有無で変動)ですが、仮に月2万円を拠出すると年間24万円が課税所得から差し引かれます。税率20%の人なら約4.8万円、23%なら約5.5万円の減税効果です。
- 口座管理手数料が低いネット証券を選ぶとコストを最小化
- 運用益も60歳まで非課税で複利効果が高い
- 受取時は退職金控除・公的年金控除を活用して税負担を抑える
- 原則60歳まで資金を引き出せないため生活防衛資金は別途確保
- 掛金変更は年1回まで。収支の見直しタイミングに合わせ調整
資産配分の基本は「国内外株式:債券:REIT=6:3:1」など長期成長を狙う比率です。信託報酬が年0.2%未満のインデックスファンドを中心に選び、手数料差でリターンを高めましょう。
また、企業型DC加入者でも条件を満たせばiDeCoを併用できるケースがあります。加入可否と上限額は勤務先の規約で異なるため、総務部門へ確認してから手続きを進めると安心です。
新NISAの成長投資枠を活かす
2024年から始まった新NISAは、つみたて投資枠(年間120万円)と成長投資枠(年間240万円)の二階建て構造で、運用益が非課税になる期間が無期限へと拡充されました。
特に成長投資枠では個別株や高配当ETFなどにも投資でき、売却益・配当金にかかる20.315%の税金を丸ごと節約できます。
- 非課税保有限度額は1,800万円(うち成長投資枠1,200万円)
- 売却すると枠が翌年復活するため機動的な資産運用が可能
- 配当金再投資で複利を最大化できるのがメリット
- 高配当ETFで年間利回り3〜4%を狙い、非課税メリットを享受
- 値動きの大きい個別株は分散投資し、損切りで枠を再利用
例えば、年間240万円を配当利回り3.5%のETFに投資すると、税引前配当は8.4万円。通常課税なら約1.7万円が税金として差し引かれますが、新NISAなら全額受け取れます。
10年間で累計84万円の配当を得る間、税金の節約総額は約17万円に達します。同じ商品を特定口座で保有している場合は移管できないため、買付先の口座を新NISA用に切り替えて非課税効果を最大化しましょう。
生命保険・地震保険料控除を重ねる
生命保険料控除は「一般」「介護医療」「個人年金」の3区分に分かれ、それぞれ所得税で最大4万円、住民税で2万8,000円まで控除できます。さらに、火災保険に付帯する地震保険も別枠で所得税5万円、住民税2万5,000円が上限です。
たとえば新旧契約を組み合わせて各区分の枠をいっぱいまで使えば、所得控除だけで計16万円超を確保でき、税率20%の方なら年3万円以上の減税効果が期待できます。適用には保険会社から届く控除証明書を年末調整または確定申告で提出するだけなので、手間は最小限です。
- 更新のタイミングで保障内容を見直し、控除枠を埋める
- 地震保険は一括払いにすると長期割引+控除効果で実質負担を圧縮
- 夫婦で契約者を分ければ双方の控除枠を活用できる
- 10月〜11月に証明書が届くので紛失防止のため撮影・アプリ保存
- 忘れた場合でも再発行は可能。年末調整期限前に保険会社へ連絡
医療費控除&セルフメディケーション税制
年間で自己負担した医療費が10万円(または所得の5%)を超えた場合、超過分を所得控除できるのが医療費控除です。通院交通費や市販薬も対象になるため、家族分を合算すると意外にハードルは高くありません。
領収書は自宅保管で済み、確定申告では「医療費控除の明細書」に金額を転記するだけです。もう一つのセルフメディケーション税制は、健康診断などを受けた人が指定OTC医薬品を年間1万2,000円以上購入した場合、上限8万8,000円まで控除できます。
両制度はどちらか一方しか選べないので、還付額が大きくなるほうを選択しましょう。
- レシートに対象医薬品であることをメモして集計を簡単に
- ドラッグストアのアプリやクレジット明細を活用すると管理が楽
- 通院タクシー代は経路・金額を記録すれば計上可能
- E-Taxで申告する場合も領収書の5年間保存義務は残る
- 高額療養費制度で補填された分は医療費から差し引く必要あり
住宅ローン控除で13年間の減税
マイホーム取得後、一定の要件を満たすと年末ローン残高の0.7%(入居時期によっては1%)を13年間にわたり所得税から控除できるのが住宅ローン控除です。残高4,000万円なら初年度で28万円の減税になり、2022年入居分以降の住宅ローン控除は、住民税の控除上限が9万7,500円(課税総所得×5%)に引き下げられています。13万6,500円の上限は消費税率10%で契約した2014~2021年入居の特定取得のみが対象です。
手続きは初年度のみ確定申告、2年目以降は勤務先が年末調整で対応するため一度申請すれば負担は大幅に減少します。
- 控除対象の床面積は40㎡以上(令和3年以降の新制度)
- 長期優良住宅なら借入限度額が5,000万円に拡大し節税効果アップ
- 借換え後も残存期間や要件を満たせば控除を継続できる
- 国税庁サイトの試算ツールで控除額と返済負担率を同時チェック
- 返済計画に繰上げ返済を組み込み、控除終了後の負担増に備える
配偶者控除・配偶者特別控除を最大化
配偶者控除は配偶者の合計所得が48万円以下(給与収入103万円以下)の場合、納税者の所得から最大38万円を控除できます。さらに年収が150万円未満まで段階的に控除額が減少する「配偶者特別控除」を活用すれば、配偶者の働き方を調整するだけで数万円の減税が可能です。
ポイントは年間収入の見込みを早めに把握し、103万円・130万円・150万円の壁を意識しながらシフトを組むこと。社会保険の扶養判定は130万円の壁が基準になるため、手取り額と保険料負担を総合的に比較しましょう。
- パート勤務なら年末にシフト調整を行い壁を超えないよう管理
- 扶養範囲に収めるかフルタイムで社会保険加入するかの試算が重要
- 配偶者のiDeCo掛金は所得を減らし控除枠を維持する裏技になる
- 賞与を含めると年収が壁を超えて控除額が一気に減る
- 扶養内に抑えるために労働時間を極端に減らし世帯収入が逆に減少
特定支出控除で勤務関連費を経費化
特定支出控除は、同年中の特定支出合計が「給与所得控除額の2分の1(50%)」を超えた場合に、その超過部分を追加で所得控除できる制度です。
対象となるのは転居費や単身赴任者の帰宅旅費、研修費、資格取得費、勤務に必要な書籍・衣服費(※勤務必要経費は年間65万円が上限)など幅広く、会社が「業務上必要だった」と証明書を発行すれば特定支出として認められます。
例として、年収500万円(給与所得控除144万円)の会社員が転勤に伴う引越し費60万円・帰宅旅費12万円・資格取得費13万円の計85万円を自己負担した場合、判定基準は「給与所得控除額の2分の1=72万円」なので 85万円−72万円=13万円 が特定支出控除の対象になります。
所得税率20%・住民税率10%なら 13万円×30%=約3万9,000円 が還付・減税される計算です。
- 控除対象額=(対象支出合計−給与所得控除額)
- 会社に経費精算できなかった費用が主な対象
- 領収書と会社発行の証明書を確定申告書に添付
| 主な対象支出 | 具体例 |
|---|---|
| 転居費 | 引越し業者への支払い、敷金礼金、転居に伴う交通費 |
| 研修費 | 業務に必要な外部セミナー受講料、教材費 |
| 資格取得費 | 受験料や登録料(宅建・簿記など業務関連) |
- 会社が発行する証明書が必須。発行に時間がかかるため早めに依頼
- 家族同伴の旅費や私的利用分が混在すると控除対象外になる
株式・投資信託の損益通算&繰越控除
株や投資信託で損失が出ても、正しく申告すれば税金を取り戻せます。特定口座(源泉徴収あり)で自動徴収された税金も、年間取引を確定申告で精算し「譲渡損失」として損益通算すれば、同一年内の配当や売却益と相殺できる仕組みです。
それでも控除しきれない損失は3年間繰り越して翌年以降の利益と通算可能。たとえば2025年に▲50万円の評価損、2026年に+40万円の利益が出た場合、繰越控除により2026年の課税対象利益はゼロ、余った▲10万円は2027年まで繰り越せます。
- 通算対象は「上場株式等」の譲渡益・配当・分配金
- NISA口座の損失は通算不可、特定・一般口座のみ対象
- 繰越控除は毎年の確定申告が必須(1回でも欠けると権利喪失)
| 年度 | 損益 | 課税対象 |
|---|---|---|
| 2025年 | ▲50万円 | 0円(翌年へ繰越) |
| 2026年 | +40万円 | 0円(▲10万円を2027年へ) |
| 2027年 | +20万円 | +10万円(▲10万円で相殺) |
- 源泉徴収あり口座でも還付を受けるには確定申告が必要
- 損失発生年にe-Taxで申告すれば翌年以降の手続きが簡略化
教育資金・住宅取得資金贈与の非課税枠を利用
父母や祖父母から一括で資金援助を受ける場合、相続時精算課税制度と組み合わせると大幅に贈与税を節減できます。
教育資金贈与は信託銀行や銀行の専用口座を利用し、30歳未満の子や孫へ最大1,500万円(うち学校以外分は500万円)まで非課税。授業料のほか留学渡航費や塾代も対象となり、領収書を提出するごとに口座から払い出します。
住宅取得等資金の非課税枠は、契約締結時期や住宅性能で最大1,000万〜1,500万円まで拡充。新築・中古を問わず省エネ基準適合住宅なら上限が高く設定されています。
- 教育資金贈与の払い出し期限は30歳、残高は贈与税課税対象になる
- 住宅取得資金は翌年3月15日までの入居が原則
- 両制度とも贈与者の相続発生から3年以内の贈与でも非課税扱い
- 信託契約書や贈与契約書を紛失すると税務調査で否認リスク
- 住宅資金は契約・建築・入居の各期日を過ぎると非課税枠が幻に
副業・個人事業主化で経費計上する中級編

副業収入が年間20万円を超えたら、確定申告で適正に経費を差し引くことで節税効果が一気に高まります。
会社員のままでも「雑所得」ではなく「事業所得」として申告すれば、赤字を給与所得と損益通算できる余地が生まれます。その鍵となるのが開業届と青色申告です。
開業届を提出すると屋号で銀行口座を開設でき、経費管理が明確になります。さらに青色申告承認申請書を併せて出せば、最大65万円の青色申告特別控除や赤字の3年繰越など、白色申告では得られないメリットが多数。
ここでは、開業手続きから具体的な経費計上方法、会社員でも利用できる特定支出控除までを体系的に解説し、ワンランク上の節税術を身に付けるステップを示します。
開業届&青色申告特別控除で最大65万円
開業届(正式名称:個人事業の開業・廃業等届出書)は、事業開始から1か月以内が提出の目安ですが、初めての申告年度内であれば受理されます。
合わせて出す「青色申告承認申請書」を税務署が承認すると、複式簿記で記帳・申告するだけで65万円(電子申告なら最大)が所得から控除され、課税所得が大幅に圧縮されます。
- 提出先:事業所を管轄する税務署(郵送・持参・e-Tax)
- 記帳方法:複式簿記+月次試算表・総勘定元帳を保存
- 提出期限:原則として開業日から2か月以内(翌年3月15日まで延長可)
- 複式簿記による帳簿作成と保存(7年間)
- 期末に貸借対照表・損益計算書を提出
- e-Taxまたは電子帳簿保存法に準拠した電子帳簿
青色申告では家族への給与を「専従者給与」として経費化できるほか、30万円未満の資産は一括償却可能。たとえば副業用PCを18万円で購入した場合、白色申告では減価償却に4年かかるところ、青色なら購入年に全額経費にできます。
提出書類は国税庁サイトのPDFを印刷・記入するかe-Taxでオンライン提出が基本。給与所得と損益通算することで住民税も減るため、サラリーマンの副業規模でも効果は十分です。
副業経費として落とせる代表的な6項目
副業で使った費用は「事業関連性」が証明できれば経費化できます。以下の6項目は特に認められやすく、領収書を保管しておくだけで節税額が大きく変わります。
| 費用区分 | 具体例 | ポイント |
|---|---|---|
| 通信費 | 業務用スマホ・Wi-Fi・クラウドサービス | 私用分を按分して計上 |
| 消耗品費 | プリンタ用紙・名刺・梱包材 | 10万円未満は即時経費 |
| 地代家賃 | 自宅の一室を事務所利用 | 面積按分率で家賃を按分 |
| 交通費 | 打合せ・取材の電車賃、タクシー代 | ICカード履歴を保存 |
| 研修費 | オンライン講座、業務関連セミナー | 資料代も含めて可 |
| 減価償却費 | パソコン、カメラ、デスク | 30万円未満なら一括償却 |
- 事業用クレジットカードと銀行口座を分けて仕訳を簡略化
- 領収書はスキャンしクラウド保存、電子帳簿保存法にも備える
たとえば自宅6畳を書斎として利用し、全体の居住面積が60㎡なら使用割合は10%。家賃10万円なら月1万円を経費にできます。
さらに光熱費も同じ按分率で計上可能。副業売上が月5万円でも、通信費・家賃按分・消耗品費を合計すると利益が圧縮され、所得税と住民税の合計で数万円の節税につながります。
特定支出控除で会社経費を取り戻す
会社員としての業務に必要だったが会社から精算されなかった費用については「特定支出控除」で取り戻せます。
対象は通勤費、転居費、研修費、資格取得費、帰宅旅費、図書費・衣服費(業務上着用するスーツなど)。合計が給与所得控除額の2分の1(上限ある場合あり)を超えると、その超過分を所得控除できます。
- 会社発行の証明書が必要:業務上必要だった旨と金額を記載
- 確定申告時に領収書・証明書を提出(e-Taxなら画像添付可)
- 給与所得控除が高い高収入層ほどハードルが上がる
- 私的要素が混在すると全額否認される可能性
- 年度をまたいだ支出は控除対象外。領収日付を必ず確認
例として給与所得控除額が120万円の方が、自己負担の研修費と書籍代で80万円支出した場合、控除対象額は80万円−60万円(120万円×1/2)=20万円。
税率20%なら4万円の所得税が還付されます。高額な資格試験に挑戦する際は、合否を問わず受験料・登録料まで控除可能なため忘れず領収書を保管してください。
不動産投資で“損益通算”しながら資産形成

給与所得者が不動産投資を活用すると、家賃収入だけでなく減価償却や各種経費を計上して赤字を作り、給与所得と損益通算することで所得税・住民税を圧縮できます。
とくに築古物件は帳簿上の耐用年数が短く、初期数年の減価償却費が大きくなるため節税インパクトが高い一方、長期保有ではキャッシュフローがプラスに転じやすいというメリットがあります。
ただし2021年の税制改正で融資額や物件価格が著しく高い場合、赤字が給与所得と通算できないケースも出てきました。
損益通算を最大限に生かすには、減価償却の仕組みを理解し、物件種類ごとの節税効果と出口戦略を組み合わせることが重要です。
減価償却と赤字通算の仕組み
減価償却とは、建物本体や設備の取得価額を耐用年数にわたって按分し、毎年の経費として計上できる制度です。
たとえば鉄筋コンクリート造(RC)の中古マンションを築30年で購入した場合、簡便法では「法定耐用年数−経過年数+経過年数×20%(端数切捨て)」を用いるため、47−30+(30×0.2)=23年が耐用年数となります(最低2年)。
年間1,000万円で購入し土地割合が30%なら、建物取得価額700万円÷17年≒41万円を毎年経費化できます。
賃貸経営で家賃収入が年間80万円、諸経費を除いた営業利益が20万円でも、減価償却費41万円で帳簿上は▲21万円の赤字となり、この赤字を給与所得と損益通算すれば税率20%の方で約4万円の税金が還付される計算です。
- 耐用年数の簡易計算:中古木造22年、軽量鉄骨27年、RC47年
- 定額法が原則だが、平成28年以前取得の建物は旧定率法も選択可
- 設備・内装は15年以内の個別耐用年数を適用し節税加速が可能
- 融資金利が著しく高い物件や、返済期間35年以上の過大借入は注意
- 家賃相場とかけ離れた収支計画は税務調査で否認されやすい
赤字が出る期間は物件・融資条件で異なりますが、5〜7年目以降は減価償却費が逓減し黒字化するのが一般的です。
黒字転換後は税負担が増えるため、内装リフォームや設備入替えを計画的に行い、追加償却でキャッシュフローと節税効果のバランスを保ちましょう。
区分マンション vs 一棟アパートの節税効果
同じ不動産投資でも、区分マンションと一棟アパートでは減価償却スピードや経費認定範囲が異なり、節税効果とリスクの質が大きく変わります。
以下の比較で、自身の投資スタイルに合う選択肢を検討してください。
| 項目 | 区分マンション | 一棟アパート |
|---|---|---|
| 購入価格 | 1,500万〜3,000万円が中心 | 5,000万〜1億円超も |
| 減価償却 | 建物割合が30%前後で償却額が小さめ | 土地割合20%以下も多く償却額大 |
| 管理負担 | 管理組合任せで手間少 | 外壁修繕・設備更新を自主管理 |
| 空室リスク | 1戸のみなので空室=収入ゼロ | 複数戸で空室分散が可能 |
| 出口戦略 | 売買市場が厚く流動性高い | 築古になると買い手が限られる |
- 区分マンションは自己資金300万円前後でも始められ、初回の節税効果は限定的だが流動性が高い
- 一棟アパートは高額投資で融資審査が厳しいものの、減価償却費が大きく年間100万〜200万円の赤字を作ることも可能
- 修繕積立金や原状回復費を計画的に積み立てないと、黒字化後にキャッシュアウトが急増する
- 節税インパクトより流動性重視▶︎区分マンション
- 所得税45%・住民税10%と高税率層▶︎一棟アパートで大きな損益通算
具体例として、年収1,200万円のサラリーマンが一棟アパート(木造・築25年)を7,000万円、土地割合15%で購入すると、建物取得価額5,950万円を法定耐用年数(22年−経過年数25年→残存年数=22年×20%=4年)で償却し、年間約1480万円を経費化できます。
家賃収入が年間700万円、諸経費を引いた営業利益150万円でも、帳簿上は▲1,330万円の赤字となり、所得税率45%の場合で約600万円の税金が還付される試算です。
高い節税効果が得られる一方、キャッシュフローはマイナスが続くため、自己資金に余裕を持ち、出口戦略として5年後の売却益や賃料増額プランを組み込んでおくことが成功の鍵です。
初心者向け物件選びと融資のポイント
不動産投資をスタートする際は、物件選びと融資条件を同時に検討することが成功への近道です。まず立地ですが、駅徒歩10分圏内かつ人口が増加傾向にあるエリアを狙うと空室リスクを抑えられます。
築年数は減価償却による節税効果を狙うなら築20年以上、長期保有と価値維持を重視するなら築10年以内が目安です。次に物件価格と融資比率をチェックしましょう。
金利が1%違うだけでキャッシュフローが大きく変わるため、複数金融機関に同時打診して比較することが重要です。
| 評価項目 | 見るべきポイント | チェック方法 |
|---|---|---|
| 立地 | 駅距離・商圏・大学や企業の有無 | 国勢調査・現地視察 |
| 築年数 | 耐用年数残存と修繕履歴 | 登記簿・管理組合資料 |
| 融資条件 | 金利・期間・自己資金比率 | 事前審査で3行比較 |
- 自己資金は物件価格の10〜20%を確保すると融資審査が通りやすい
- 管理会社の評判を調べ、入居率95%以上の実績があるかを確認
- 火災保険・地震保険に加入し、突発的な支出に備える
- 利回りだけでなく空室率と修繕費を差し引いた「実質利回り」を試算
- 賃料査定は周辺の成約事例を3件以上集めて裏付けを取る
節税とキャッシュフローを同時に伸ばすシミュレーション
ここでは、年収800万円のサラリーマンが築25年・木造アパート(総戸数6戸)を6,000万円、土地割合20%で購入したケースを想定します。
自己資金600万円、融資5,400万円、金利2.0%・期間25年とし、年間家賃収入は432万円(平均賃料6万円×6戸×12か月)、運営費率30%で計算します。
- 建物取得価額:6,000万円×80%=4,800万円
- 耐用年数:22年×20%=4年 → 年間償却費:4,800万円÷4=1,200万円
- 営業利益:432万円−(運営費129万円+利息約105万円)=198万円
- 帳簿上の所得:198万円−償却費1,200万円=▲1,002万円
▲1,002万円を給与所得と損益通算すると、所得税率23%、住民税10%の場合で約330万円の税金が還付されます。
キャッシュフローは営業利益198万円−元金返済約115万円=83万円の黒字を確保でき、還付金を加えると初年度キャッシュフローは実質400万円超となります。
- 減価償却で大きな赤字を作りつつ、実際のキャッシュはプラス
- 償却期間終了後は税負担が増えるため、繰上げ返済や新規物件購入で節税サイクルを継続
- 空室率が想定より悪化し家賃収入が10%減っても、営業利益が155万円確保できる設計とする
- 金利上昇リスクを踏まえ、元金返済スピードの早い短期ローンも試算しておく
- 黒字化後は設備更新費や追加投資で経費枠を確保し、税負担の急増を回避
このシミュレーションのように、減価償却を最大限活用しつつキャッシュフローを黒字に保つ設計ができれば、手元資金を殖やしながら次の投資チャンスへ備える好循環を築けます。
まとめ
10の基本控除で今すぐ手取りを増やし、副業や損益通算で中期的な税負担を抑え、最後に不動産投資で資産と節税効果を両取りする流れを示しました。
仕組みを理解し、今日からできる対策を一つずつ実行すれば、年収帯に関わらず可処分所得を高め、将来への安心資金も同時に育てられます。まずはふるさと納税やiDeCoなどハードルの低い制度から着手し、節税メリットを実感しましょう。