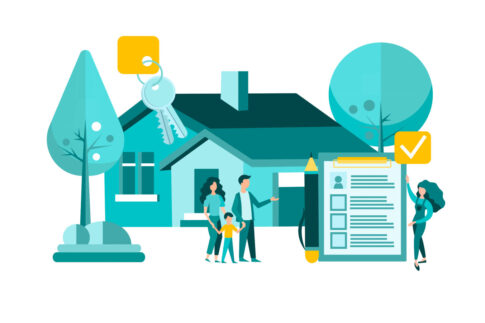年収1,500万円超の弁理士は、報酬の10.21%源泉徴収後に45%の累進課税と社会保険料が重なり、手取りが伸びにくいとされています。
本記事では青色申告65万円控除・小規模企業共済・特許業務法人への法人成りに加え、減価償却を活用した不動産投資まで網羅。合法的に税負担を半減しつつ、キャッシュフローと将来資産を同時に守る具体手順をわかりやすく解説します。
目次
高所得弁理士が抱える税負担の実態

弁理士は特許出願や調査・鑑定といった高付加価値業務を行うため、1件あたりの報酬単価が高い傾向にあります。年収が1,500万円を超えるケースも珍しくありませんが、その裏では〈源泉徴収10.21%→所得税・住民税55%〉という二重の課税構造に直面し、「働くほど手取り率が下がる」というジレンマが起こる可能性があります。
加えて、業務委託報酬を主とする場合は経費になりにくい“人的コスト”が大半を占めるため、粗利益がそのまま課税所得に反映されやすい点が大きな課題です。
さらに、登録免許税や印紙税の立替分をクライアントへ請求するタイミング次第で、消費税の納税資金を一時的に先払いするケースもあり、キャッシュフローが圧迫されやすいとされています。
これらの負担を放置すると、事務所の成長投資に充てるはずの資金が納税に流出し、将来の収益拡大を阻害するリスクが高まります。
本章では〈①源泉徴収と累進課税のギャップ〉〈②社会保険料・消費税のダブルパンチ〉という二つの観点から、弁理士特有の税負担構造を整理し、次章以降で紹介する節税スキームの重要性を明確にします。
- 源泉徴収は10.21%固定で控除対象外→確定申告で追加納税が発生しがち
- 社会保険料は報酬比例で増加→標準報酬月額の上限でも年間100万円超の負担
- 印紙税など立替費用のタイムラグ→消費税納税資金が不足しやすい
- 利益率が高い業務モデルほど税負担が表面化
- 正確な帳簿と資金繰りシミュレーションが必須
源泉徴収10.21%と累進課税のギャップを知る
弁理士報酬は、法人顧客からの委任契約が多い場合、その支払い時に10.21%の源泉所得税が天引きされる仕組みになっています。ただし、この10.21%は“前払い”に過ぎず、確定申告時には年間の課税所得に応じた所得税率(最大45%)と住民税(10%)を精算する必要があります。
たとえば、年間報酬2,000万円・必要経費400万円の弁理士の場合、源泉徴収額は200万円(2,000万円×10.21%)ですが、課税所得は1,600万円となり、所得税率33%帯に該当するとされています。
計算上の所得税はおおむね330万円、住民税160万円で合計490万円となるため、確定申告で290万円(490万円−源泉200万円)の追加納税が必要です。
このギャップを見越した資金繰りを行わないと、3月の納税時期に多額のキャッシュ流出が発生し、運転資金を圧迫するリスクがあります。
| シミュレーション項目 | 内容 |
|---|---|
| 年間報酬 | 2,000万円 |
| 必要経費 | 400万円(20%を想定) |
| 課税所得 | 1,600万円 |
| 所得税(概算) | 330万円 |
| 住民税 | 160万円 |
| 源泉徴収済 | 200万円 |
| 追加納税 | 290万円 |
- 源泉徴収は“払い過ぎ”にも“払い足り”にもなる→年間試算が必須
- 予定納税の対象になると、7月・11月にも納税キャッシュが必要
- 源泉額の過不足をe-Taxでリアルタイム把握→資金繰りを最適化
- 源泉徴収額は別口座でプールし、事業資金と分離管理
- 追加納税が読めない場合は納期特例や延納を検討
社会保険料・消費税がキャッシュフローを圧迫
弁理士が法人に雇用されず個人事業として活動する場合、国民健康保険と国民年金を全額自己負担で支払う必要があります。
所得が増えると国民健康保険料は医療分と支援金分を合わせて最大年間約100万円近くに達する可能性があり、国民年金の付加保険料を入れると負担感はさらに増します。
法人化して厚生年金・協会けんぽに加入したとしても、標準報酬月額の上限(現行65万円)まで報酬を設定すれば自己負担・会社負担を合わせた年間保険料は約240万円前後とされ、キャッシュフローに重くのしかかります。
さらに、基準期間課税売上1,000万円超またはインボイス登録により消費税の納税義務が生じると、納税スケジュールは3月(確定申告)・3月末(消費税)・5月(住民税・事業税)の三段重なりとなり、資金繰りが最もタイトになる春先に大口納税が集中します。
- 社会保険料:→報酬比例で増加し、報酬を上げても手取りが増えにくい
- 消費税:→報酬入金タイミングと納税タイミングがズレると資金ショートの要因
- 納税集中:→1〜5月は納税ラッシュ→運転資金を多めに確保
- 役員報酬を月55万円程度に設定→保険料と可処分所得のバランスを最適化
- 報酬入金用と納税専用の預金口座を分け、消費税相当額を自動振替
| 納税項目 | 納付月 | 資金繰り対策 |
|---|---|---|
| 所得税 | 3月15日 | 予定納税・延納申請・e-Tax分割納付 |
| 消費税 | 3月31日 | 簡易課税・2割特例で税額を圧縮 |
| 住民税 | 6月〜 | 普通徴収→年4回払いでキャッシュを平準化 |
- 簡易課税制度の業種区分(第5種50%)を利用すると仕入控除計算が簡略化できる可能性があります
- 電子帳簿保存法対応で経費否認リスクを防ぎ、消費税仕入控除を確実に確保
- 短期的な資金繰りには納税資金専用の当座貸越枠を確保しておくと安心です
弁理士が活用すべき節税スキーム

弁理士は案件単価が高く、売上の多くが人的サービスに帰属するため利益率が上がりやすい一方、課税所得も膨らみやすいとされています。そこで重要になるのが「所得控除を最大限に取り切る」「長期的に税負担を平準化する」「専門職ならではの経費を漏れなく拾う」という三つの視点です。
本章では〈①青色申告65万円控除+経費計上〉〈②小規模企業共済・iDeCo〉〈③知財関連経費・研究費〉の三本柱を中心に、手取りを守りつつキャッシュフローを滑らかにする実践策を解説します。
各スキームは初期コストが低く、帳簿体制が整えば小規模事務所でも導入しやすい点が魅力です。さらに、後述の法人化や不動産投資と組み合わせることで、短期の節税と長期の資産形成を同時に実現する道筋が見えてきます。
- 青色申告→帳簿と電子申告で控除をフル取得
- 掛金控除→将来資金を準備しながら今すぐ節税
- 専門経費→知財調査・翻訳費など業務直結支出を計上
青色申告65万円控除と経費計上を最大化する方法
青色申告特別控除65万円を確実に受けるには〈複式簿記で帳簿を作成〉し〈期限内に電子申告〉する二つの要件を満たす必要があります。
クラウド会計ソフトを使えば銀行・カード・電子マネーの明細を自動取り込みできるため、仕訳の手間を大幅に削減できます。
たとえば年商1,800万円・経費480万円の弁理士が控除を取得すると、課税所得は1,320万円→1,255万円まで圧縮でき、33%税率帯なら概算21万円の節税効果が見込めるとされています。
| ステップ | 具体内容 |
|---|---|
| 仕訳自動化 | 銀行API連携・AIレシート読取で入力漏れを防止 |
| 月次確認 | 月末に試算表を出力し、未分類取引をゼロにする |
| 電子申告 | マイナンバーカード方式でe-Tax送信→控除要件クリア |
- 家賃・通信費は業務使用割合を明記→合理的な按分が重要
- 10万円未満の備品は即時費用でキャッシュを守る方法があります
- 研究文献・特許庁手数料は業務関連性を示しやすく、経費計上しやすいとされています
- 紙提出や期限後申告は控除55万円へ減額→必ず電子申告
- 領収書は撮影後30日以内にアップロード→電子保存要件を満たす
小規模企業共済・iDeCoで長期的な税負担を抑える
掛金を全額所得控除にできる小規模企業共済とiDeCoは、弁理士のように将来独立や退職を見据える専門職に適した制度です。共済は月1,000円〜7万円まで自由に掛けられ、廃業時や65歳以降に退職所得扱いで受け取れるため、受取時の税率も抑えられるとされています。
iDeCoは月5,000円〜6.8万円の範囲で運用益が非課税となり、老後資金の準備と節税を両立できます。
仮に両制度へ月5万円ずつ拠出すると年間120万円の所得控除が得られ、33%税率帯なら約40万円、43%帯なら約52万円の節税効果につながる計算です。
- 【共済】→掛金を年末に増額し、その年の利益に応じ節税調整
- 【iDeCo】→低リスク型で運用し、掛金を長期で積み立てる
- 【共通メリット】→掛金全額控除+運用益非課税(iDeCo)
- 掛金設定→キャッシュフローに無理のない金額から開始
- 解約リスク→急な資金需要に備え、別口座で生活防衛資金を確保
- 金融機関選定→手数料と運用商品ラインアップで比較
- 掛金証明書を年末に受領→確定申告書Bの控除欄へ転記
- 受給時期を退職金とずらし、退職所得控除を最大化
知財関連経費・研究費を漏れなく経費化するポイント
弁理士業務では「特許庁への調査用手数料」「先行技術調査のデータベース利用料」「専門翻訳や図面作成費」など、一般的な士業と異なる独自経費が発生します。これらを漏れなく経費計上することで、課税所得を着実に圧縮できます。
ポイントは〈業務関連性の証明〉〈領収書の電子保存〉〈仕訳科目の統一〉の三つです。まず、クライアント案件との紐付けを明示した発注書や作業報告書を保存し、税務調査時に業務関連性を示せる状態を整えます。
次に、データベース利用料や翻訳費など電子請求書で受け取る支出は、電子帳簿保存法の改正要件を満たす形でクラウド保管し検索性を担保します。
最後に、仕訳科目を「研究開発費」「外注費」「図書費」などで分散させず、「知財関連費」に統一すると、年間費用の傾向が把握しやすく管理が簡便になります。
| 経費区分 | 具体例 | 証明書類 |
|---|---|---|
| 調査費 | J-PlatPat拡張検索料 | 検索ログ・請求書 |
| 翻訳費 | 特許明細書の外国語訳 | 発注書・成果物 |
| 外注図面 | 意匠図面作成 | メール発注履歴 |
- 科目統一→「知財関連費」で一元管理し管理工数を削減
- 電子請求書→改ざんリスクを抑制
- クライアント請求に含める立替費用は分けて管理し、消費税区分の混在を防止
- 自社開発案件とクライアント案件の支出を混同しない
- 私的利用があるソフトは按分率を合理的に設定
- 案件コードを仕訳に付与し、経費の紐付けを明確化
- 年度末に経費分析を行い、費用対効果を検証
- 翌期の料金設計に反映し、値決めミスによる利益圧縮を防止
法人成り(特許業務法人・合同会社)で税率を平準化

弁理士が個人事業で高収益を上げ続けると、所得税45%と住民税10%を合わせた最高55%の累進課税が適用される可能性が高まり、社会保険料を含めた実効税率はさらに膨らむとされています。
そこで検討したいのが「法人化」による税率の平準化です。特許業務法人や合同会社を設立すれば、法人税・地方法人税・事業税・住民税を含めた実効税率はおおむね23〜31%に収まり、課税所得を法人側へ移すことで個人の累進税率上昇を抑制できます。
加えて、法人名義で接待交際費・研修費・福利厚生費を計上しやすくなるほか、退職金積立や役員社宅など多様な節税メニューを選択できる可能性があります。
さらに、法人は欠損金の繰越控除期間が10年間あるため、設備投資や不動産取得で赤字が出ても長期で節税効果を享受できる点が魅力です。
以下では「①設立条件と税率引き下げのステップ」「②役員報酬・退職金スキームによる所得分散」という二つの切り口で、具体的な流れと注意点を紹介します。
- 特許業務法人→ブランド力と信頼性◯、設立費用と手続きがやや煩雑
- 合同会社→設立費用約6万円、運営コスト低めで小規模でも導入しやすい
- 法人化時は事業計画とキャッシュフロー予測を同時に作成し、銀行融資や設備投資を視野に入れると中長期戦略が描きやすくなります
設立条件と実効税率約30%への引き下げステップ
法人化による節税効果を最大化するには「設立時の形式選定」「利益配分のシミュレーション」「設立後3期の資金計画」という三段階が重要です。まず形式選定では、複数弁理士で共同経営を行うなら特許業務法人、単独または家族経営でコストを抑えたいなら合同会社が向いています。
両者とも資本金1,000万円未満に抑えれば外形標準課税を回避でき、所得800万円以下部分の法人税率15%(実効約23%)を適用できるとされています。
次に利益配分シミュレーションでは、年間利益1,200万円の例で〈役員報酬800万円+内部留保400万円〉とした場合、法人税等は概算120万円、個人側の所得税・住民税は約190万円と試算され、個人事業より50万円前後の節税が期待できます。
最後に設立後3期の資金計画では、法人住民税均等割7万円や決算申告報酬、社会保険料を織り込んだキャッシュフローを作成し、黒字倒産リスクを低減させます。
| 区分 | 800万円以下 | 800万円超 |
|---|---|---|
| 法人税等(標準) | 約23% | 約31% |
| 個人所得税等 | 5〜33% | 40〜55% |
- 内部留保を設備投資・研修費に充当し、経費化を進めると税率差のメリットをさらに享受しやすい
- 資本金を1円に抑えても信用力に不安がある場合は増資か融資実績で補完するとされています
- 簡易課税制度の業種区分(第5種50%)が適用できる場合、消費税負担も軽減可能
- 定款作成→電子定款なら印紙4万円を節約
- 登記→法務局へオンライン登録免許税支払い
- 税務署・年金事務所へ設立届と社会保険新規適用届を提出
- 売上・利益が安定して800万円超なら法人化検討のタイミングとされています
- 設立初年度は資金準備のため役員報酬を低めに設定し、2期目以降に調整する方法が安全
- 法人カードを活用し、経費支出を一本化すると帳簿管理が容易になります
役員報酬・退職金スキームで所得分散を図る
法人化後の節税効果をさらに高める鍵は「役員報酬の適正配分」と「退職金スキーム」の活用です。役員報酬は定期同額給与が原則で、期首に決めた金額を毎月同じ額支払う必要があります。
報酬を高く設定し過ぎると個人の累進税率が再び上昇するため、家族を役員に加えて報酬を分散する方法が有効です。
たとえば夫婦2名体制で〈代表600万円+配偶者360万円〉とすると、各人の課税所得を900万円以下に抑えられ、33%税率帯に収めることが可能です。さらに、退職金は勤務年数と功績倍率を基に算定し「退職所得控除+1/2課税」が適用されるため、長期的な税負担を繰り延べられるとされています。
- 【報酬分散】→家族が実働していれば給与所得控除も使え、実効税率が下がる
- 【退職金積立】→中小企業退職金共済や逓増定期保険を活用し損金算入
- 【社宅制度】→役員社宅で住宅費を法人負担し、実質手取りを増やす方法もある
- 期首に役員報酬を決定→株主総会議事録を作成
- 給与支払事務所等の開設届を提出→源泉徴収体制を整備
- 退職給与規程を作成→功績倍率や支給基準を明文化
| スキーム | 税務上の扱い | メリット |
|---|---|---|
| 役員報酬 | 損金算入可 定期同額が要件 |
給与所得控除で実効税率を抑制 |
| 退職金 | 支給時に損金算入 退職所得控除+1/2課税 |
長期繰延と税率ダウン |
| 社宅制度 | 福利厚生費で損金算入 | 個人の住宅費を法人負担にシフト |
- 資本金1億円超の大法人になると交際費損金算入枠が制限→成長ステージで制度の再設計が必要
- 過大役員報酬や功績倍率の高すぎる退職金は「行為計算否認」の対象となる可能性があるため注意
- 退職所得控除を最大化するには支給タイミングを65歳以降に調整し、他の退職金と重ならないよう管理するとされています
コンプライアンス簡易管理とインボイス対応

弁理士業務は特許庁への手数料立替や翻訳外注など証憑の種類が多岐にわたり、日々の取引を正しく記録できないと青色申告65万円控除の要件を満たせず、消費税の仕入税額控除が否認される可能性があります。
さらに2023年開始のインボイス制度により、取引先から適格請求書の発行を求められるケースが増加しており、帳簿と証憑を電子データでひも付ける作業が必須になりつつあります。
そこで重要となるのが「クラウド会計ソフトを使ったリアルタイム記帳」「AI仕訳を活用した入力ミス削減」「インボイス発行から保存までをワンストップで完結させるワークフロー」の三点です。
これらを組み込めば、領収書を探す時間や入力ミスの修正工数が大幅に減少し、税務調査時の対応負荷も最小限に抑えられるとされています。
- 証憑データを即時アップロード→入力遅延ゼロへ
- AI仕訳で科目候補を自動提示→ヒューマンエラーを削減
- 適格請求書保存要件を満たしつつ消費税仕入控除を確保
- 帳簿精度向上で65万円控除を安定確保
- 検索性が高まり税務調査での提出工数を削減
クラウド帳簿とAI仕訳で領収書管理をラクにする
紙の領収書をファイルに綴じ、月末にまとめて入力する従来型のやり方では、入力漏れや科目ミスが発生しやすく、青色申告控除の要件である「正規の簿記」に抵触するリスクがあります。
これを回避する最もシンプルな手段が、クラウド会計ソフトとスマホアプリを導入して「受取即アップロード→AI仕訳→月次検証」という三段階プロセスを自動化する方法です。
たとえばfreeeやマネーフォワードでは、銀行APIやクレジットカード明細を自動取得し、AIが仕訳候補を提示してくれるため、日次での確認作業はタップ操作のみで完結します。
月末には試算表をワンクリックで出力できるため、未分類取引をゼロにしたうえで税理士レビューに回すだけで、65万円控除の帳簿要件を満たしやすくなります。
| 手順 | 作業内容 | 効果 |
|---|---|---|
| ①即時撮影 | レシートをスマホで撮影しクラウドへ | 紛失防止・紙保管スペース削減 |
| ②AI仕訳 | 日付・金額・科目を自動推測 | 入力ミス削減・作業時間短縮 |
| ③月次検証 | 未分類取引を一括確認 | 帳簿精度向上・控除要件を確保 |
- レシートは撮影→電子帳簿保存法の真実性要件を満たす
- ChatGPT連携のメモ機能を使い、取引内容を音声入力→仕訳メモとして自動反映
- AIが誤判定した科目は即修正→学習機能で翌月以降の再発を防止
- 電子請求書のファイル名がバラバラ→「日付_取引先_金額.pdf」で統一
- 小口現金の出し入れを記帳せず残高が合わない→専用カード決済で現金取引をゼロ化
- クラウド会計に銀行・カード・電子マネーを連携し、自動取込を有効化
- レシートは撮影後すぐAI仕訳を確認し、科目が正しいかワンタップ修正
- 月末に残高試算表を出力し、未分類ゼロ・誤差ゼロを達成
源泉税10.21%の精算と資金繰りをスムーズにするコツ
弁理士報酬は受領時に10.21%の源泉所得税が控除されるため、年間を通じて源泉徴収税額が積み上がります。しかし確定申告時には累進税率で計算した所得税額との差額を精算しなければならず、追加納税や還付が発生します。
資金繰りを安定させるには「源泉税専用口座を設けて天引き額をプール」「予定納税スケジュールをカレンダー通知」「追加納税見込みを四半期決算で試算」の三つを習慣化することが効果的です。
専用口座に源泉額を自動振替しておけば、売上口座の残高は実質手取りに近い数字となり、資金繰りの誤認リスクを減らせます。
また、予定納税の対象になる場合は7月と11月に納付があるため、四半期ごとに試算表を確認して不足額を早期に把握すると、納税直前の資金ショートを防げます。
| 時期 | 主なタスク | 資金繰り対策 |
|---|---|---|
| 毎月 | 源泉額を専用口座へ自動振替 | 納税資金を見える化 |
| 四半期 | 試算表で追加納税額を試算 | 不足分を事前積立 |
| 7・11月 | 予定納税 | 一括納付か延納を比較検討 |
- 消費税も同口座で積立→3月末の大型納税に備える
- 資金繰りアプリで入出金予定を可視化→融資枠の活用タイミングが把握しやすい
- 還付が予想される場合は早期申告→キャッシュを早く取り戻す
- 源泉徴収票はPDF保存→科目「立替金」で紐付けて検索性を確保
- 追加納税が高額になりそうな年は、年末に共済掛金を増額して調整
- 報酬受領時→源泉税額自動計算→専用口座へ即時振替
- 四半期末→累計源泉額と推定税額を比較→不足分を積立
- 確定申告後→還付金が入金されたら共済掛金や設備投資に再投資
不動産投資で節税と資産形成を両立

弁理士の主な収入源は技術文書作成や審査対応など人的サービスで、経費化できる費用が限定されやすいとされています。その結果、年収が上がるほど課税所得が急増し、所得税・住民税・社会保険料が可処分所得を圧迫する構造になりがちです。
不動産投資はこの弱点を補う実物資産型の節税策であり、〈減価償却による非資金費用の創出〉と〈損益通算による納税キャッシュアウトの削減〉を同時に実現できる点が魅力です。
さらに、ローン返済により毎年元本が減少し純資産が積み上がるため、「節税メリットを得ながら資産形成も進む」というダブル効果が期待できます。
特に弁理士は契約実務や権利調査に長けているため、物件の権利関係や契約条件を自らチェックでき、リーガルリスクを最小限に抑えられる可能性があります。
本章では、①減価償却と損益通算の具体的な仕組みと注意点、②物件選定と弁理士ならではの契約・リスク管理という二つの視点から、初心者でも実践しやすいノウハウを解説します。
- 非資金費用→手元キャッシュを減らさず課税所得を圧縮
- 長期保有→ローン完済後は家賃がほぼ純利益
- 法務スキル→契約不備・瑕疵リスクを自前でチェック可能
減価償却・損益通算の仕組みと注意点
減価償却は「建物取得費用を耐用年数に応じて毎年費用化する会計処理」で、現金支出を伴わずに経費を計上できるため、弁理士のようにキャッシュフローを重視する個人事業者に適した節税手段とされています。
たとえば築古木造アパートを建物価格1,200万円で取得した場合、残存耐用年数が最短4年となり、年間300万円を経費化できます。
この償却費にローン利息や管理費を加え、家賃収入を上回る赤字が発生すると、給与所得と損益通算して総所得を圧縮できる仕組みです。
ただし、赤字幅が大きすぎると金融機関の評価が下がるほか、税務調査で「所得隠し」と指摘されるリスクもゼロではありません。耐用年数の短い設備を分離して加速償却を狙う際も、見積書や写真で資産区分を明確化し、税務署が納得する根拠を備えることが重要です。
| 構造 | 残存耐用年数(例) | 年間償却率(例) |
|---|---|---|
| 木造(築20年) | 4年 | 25% |
| RC(築25年) | 22年 | 約4.6% |
- 赤字が出ても最長3年間繰越控除→翌期の黒字と相殺可能
- 土地は償却対象外→建物割合が高い物件ほど節税効果大
- 青色申告との併用で10万円控除(白色)→65万円控除へ拡大可能
- 築古×高建物割合物件で初年度から大幅償却
- ローン元金据置期間を設定し、初期CFを厚くする
- 物件取得→建物・土地按分を適正に設定
- 減価償却計算→耐用年数を根拠資料とともに税務署へ提示
- 損益通算→確定申告書Bの赤字欄に転記し総所得を圧縮
物件選定と弁理士ならではの契約・リスク管理
節税目的の不動産投資では「キャッシュフローの安定」と「出口戦略の透明性」を両立させる物件選定が不可欠です。
具体的には〈①建物割合が高く減価償却しやすい築古アパート〉〈②空室リスクを抑えるエリア選定〉〈③法的リスクを最小化する契約条件〉の三要件を満たすと安全性が高まるとされています。
弁理士の場合、契約審査のスキルを活かし、売買契約書や賃貸借契約の特約条項を自ら交渉できる点が大きな強みです。
たとえば、瑕疵担保責任(契約不適合責任)の存続期間を長めに設定し、設備故障が発生した際の無償修理範囲を明確化しておくと、予期せぬ修繕負担を回避しやすくなります。
| 選定基準 | チェックポイント | 弁理士が活かせる強み |
|---|---|---|
| 物件属性 | 築20年以上・建物割合60%以上 | 登記簿・評価証明を自分で調査 |
| 立地需要 | 大学近接・工業団地周辺 | 人口動態統計を読み解くスキル |
| 契約条件 | 瑕疵担保期間・違約金条項 | 契約書レビュー・交渉力 |
- リーガルリスクを低減→裁判コストを事前に抑制
- 入居審査基準を文書化→トラブル時の証拠力が向上
- 出口戦略→長期譲渡税率への切り替えを待ち売却
- ①物件調査→インスペクション+権利関係の二重チェック
- ②賃貸運営→PM会社と契約書を締結し管理委託範囲を明示
- ③売却準備→3ヶ月前から市場調査し、譲渡所得計算をシミュレーション
- 購入フェーズ→手付解除期日を延長しデューデリ期間を確保
- 保有フェーズ→修繕積立シミュレーションでCFを平準化
- 売却フェーズ→法人間M&Aや区分売却で税負担を繰延べ
まとめ
本記事は、高所得弁理士が直面する税負担の構造を整理し、青色申告・掛金控除・法人化・不動産投資の四段階で課税所得を圧縮する方法を示しました。
まずはクラウド会計で帳簿を電子化し65万円控除を確実に取得。次に共済やiDeCoで将来資金を確保し、法人成りで税率を平準化。最後に減価償却効果の高い物件へ投資して節税と資産形成を両立させましょう。