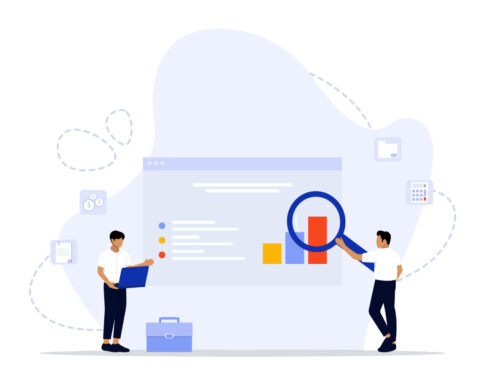年間所得が高い弁護士でも、減価償却や法人設立を駆使した不動産投資で課税所得を圧縮し、キャッシュフローを守ることが可能です。
本記事では高税率の仕組みと節税スキーム、物件選定からリスク管理まで客観データを基に解説し、実効税率が下がるシミュレーション例も掲載。節税初心者でも即実践できるステップをまとめました。知識ゼロでも読み切れば護身と将来設計が変わります。
目次
高所得弁護士が抱える税負担と節税ニーズ

年収1,500万円を超える弁護士は、所得税と住民税だけで最大55%もの税率が適用されます。そこへ健康保険・厚生年金などの社会保険料が加わり、手取りは想像以上に圧縮されがちです。
事務所経費を除いても可処分所得が残りにくく、「専門職なのに資産が増えない」と感じる声は少なくありません。不動産投資は、この課題を解決しやすい数少ない手段の一つです。減価償却やローン利息を経費化して課税所得を減らせる上、長期的な資産形成も期待できます。
【主要な悩みとニーズ】
- 累進課税で税額が急増→可処分所得が減少
- 社会保険料の上限到達→報酬増でも手取りほぼ横ばい
- 将来の独立やセカンドライフに備えた資産形成が必要
- 経費化できる投資(減価償却・利息)を選ぶ
- 法人設立で累進税率を回避し所得分散
- 入退去リスクを抑えた物件管理で安定キャッシュフロー
所得税45%+住民税10%の累進課税構造
日本の所得税は7段階の超過累進税率で、課税所得4,000万円超から45%が適用されます。住民税は一律10%のため、最高税率帯では合計55%となり、税引前1,000万円の追加利益に対して手取りは450万円しか残りません。以下の早見表でイメージをつかみましょう。
| 課税所得帯 | 所得税率 | 実効税率(所得税+住民税) |
|---|---|---|
| 1,000万円超〜1,500万円以下 | 33% | 43% |
| 1,800万円超〜4,000万円以下 | 40% | 50% |
| 4,000万円超 | 45% | 55% |
- 弁護士報酬は案件増で跳ねやすく、すぐに最高税率帯へ到達
- 累進幅が大きいため、控除や経費のインパクトが大きい
- 課税所得圧縮策なしでは“働くほど税負担増”となる
- 過度な節税は租税回避と判断される可能性があります
- 個人名義では損益通算できない投資もあるため要確認
社会保険料上限で可処分所得が圧迫される理由
弁護士が法人に雇用される場合、健康保険と厚生年金の保険料は「標準報酬月額」で計算され、現在の上限は月65万円(厚生年金)と139万円(協会けんぽ・都道府県により異なる)です。
報酬月額がこれを超えても保険料は頭打ちですが、負担額は年間約120万円に達し、所得税・住民税と並んで可処分所得を押し下げます。また、賦課限度額の引き上げが検討されており、保険料負担が今後増える可能性もあります。
- 資産管理会社設立により役員報酬を調整→標準報酬月額を抑制
- 給与所得と不動産所得を組み合わせ、社会保険料負担を最適化
不動産投資がもたらす3大節税メカニズム

弁護士のように高所得の専門職でも、不動産投資を活用すれば税負担を大きく抑えることができます。具体的には①減価償却で帳簿上の利益を減らす、②ローン利息や管理費などを必要経費に算入する、③不動産所得の赤字を給与所得と損益通算する──という三つの仕組みが中心です。
いずれも税法に明記された合法的な手段であり、正しい手順を踏めば節税と資産形成を同時に進められます。
特に減価償却は現金流出を伴わない“非資金費用”であるため、キャッシュを手元に残したまま課税所得だけを圧縮できる点が大きな魅力です。以下では各メカニズムの原理と注意点を順番に解説します。
- 減価償却→耐用年数に基づき毎年費用計上
- ローン利息・諸経費→収入を得るための支出は概ね経費化
- 損益通算→赤字を他の所得と相殺し納税額を軽減
減価償却で課税所得を圧縮する仕組み
減価償却とは、建物や建物附属設備などの取得費用を法定耐用年数に応じて分割計上する会計処理です。たとえば築20年の木造アパートを1,000万円で取得した場合、中古資産の耐用年数は簡便法により(法定耐用年数 − 経過年数)+ 経過年数 × 20%で算出します。
木造の法定耐用年数は22年のため、この場合は(22年 − 20年)+ 20年 × 0.2 = 4年となり、年間250万円を4年間にわたって償却できます。家賃収入が同額であれば帳簿上の利益はゼロとなり、その分課税所得を圧縮できます。
| 建物構造 | 法定耐用年数 |
|---|---|
| 木造 | 22年 |
| 軽量鉄骨 | 34年 |
| RC造 | 47年 |
- 築古物件ほど残存耐用年数が短く、償却スピードが速い
- 建物と建物附属設備は分けて計上→附属設備や器具備品は耐用年数表に基づき償却(例:空調設備15年、事務机8年など)
- 減価償却は現金流出を伴わないためキャッシュフローを圧迫しない
- 築古×木造で残存耐用年数を短縮→年間償却費を増やす
- 土地と建物の按分割合を適正に設定し、建物部分を増やす
ローン利息・諸経費を経費化できる根拠
賃貸経営に要するローン利息や管理費、修繕費、固定資産税などは、「不動産所得を得るために直接必要な費用」として所得税法上の必要経費に該当します。
たとえば年間家賃収入600万円、必要経費が360万円(うち利息120万円)の場合、課税対象となる不動産所得は240万円に抑えられます。利息は元金返済と異なり現金支出であるものの、経費算入により実質的な税負担を軽減できる点がメリットです。
| 費用区分 | 具体例 | 経費算入ポイント |
|---|---|---|
| ローン利息 | 投資用アパートローン利息 | 元金部分は経費不可 |
| 管理関連 | 管理委託料・清掃費 | 支払時点で全額計上 |
| 修繕費 | 給排水管交換・外壁補修 | 資本的支出に該当しない範囲は経費化可(少額資産の特例等は別途適用) |
- 借入金額が大きい初期ほど利息割合が高く、節税効果も大きい
- 建物・土地の取得に直接要した費用(仲介手数料、登録免許税、不動産取得税、登記関連費用など)は取得価額に算入し、建物は減価償却、土地は非償却となる(即時経費化は不可)
- 大規模修繕は資本的支出と判定されると減価償却扱いになる
- 自宅併用物件の利息は使用割合で按分→全額経費不可
- 領収書・契約書は電子帳簿保存法の要件を満たして管理しないと否認リスク
損益通算で給与所得と相殺する手順
不動産所得が赤字になった場合、その赤字額は原則として他の所得区分と損益通算できます。弁護士としての給与所得が2,000万円、不動産所得が▲300万円なら、総所得は1,700万円となり、課税所得も同額減少します。
これにより最高税率帯にある場合、約55%の税率が適用されるため理論上165万円の税額軽減が可能です。手順は以下のとおりです。
- 決算書と確定申告書Bを作成→青色申告の場合は65万円控除も利用
- 赤字額を損益通算欄に転記→差引後の総所得金額を計算
- 源泉徴収税額との差額を還付または追加納付で調整
- 土地部分が大きいと赤字化しにくい→築古物件で建物割合を確保
- 事務所や家族給与との混在を避け、収支管理を明確化
物件選定・購入タイミングとリスク管理で節税効果を最大化

不動産投資で大きな節税を狙うなら、物件の種類や取得時期、そして購入後のリスク管理を戦略的に組み合わせることが欠かせません。築年数や構造が異なれば、減価償却のスピードも変わり、キャッシュフローに与える影響は大きく異なります。
また、決算期直前の購入や修繕費のタイミングを調整することで、初年度の税負担を抑えやすくなります。さらに、2024年から義務化が始まった電子帳簿保存法への対応を怠ると、せっかくの節税効果が否認されるリスクもあります。
ここでは、①築古木造とRC物件の耐用年数と償却スピード、②購入・修繕のベストタイミング、③電子帳簿保存法対応と税務調査対策の三つの観点から、節税効果を最大化する具体策を解説します。
- 耐用年数の短い物件→減価償却を加速し課税所得を圧縮
- 決算前の取得・修繕→初年度の納税キャッシュアウトを削減
- 電子帳簿保存法対応→適切な証憑管理で経費否認リスクを回避
築古木造とRC物件—耐用年数・償却スピード比較
不動産の減価償却費は建物構造と築年数によって大きく変わります。木造は法定耐用年数が22年と短いため、築年数20年以上の物件を取得すれば残存耐用年数は最短4年となり、償却費を一気に計上できます。
一方、RC造(鉄筋コンクリート)は法定耐用年数が47年あり、築古であっても残存耐用年数が長めに残るため、毎年の償却費は木造より小さくなりますが、長期にわたり安定して経費を計上できるのがメリットです。
| 構造 | 法定耐用年数 | メリット・デメリット |
|---|---|---|
| 木造 | 22年 | ◎償却加速で短期節税 △老朽化リスクが高い |
| RC造 | 47年 | ◎長期安定・資産価値維持 △償却ペースは緩やか |
- 短期で税圧縮したい→築25〜30年の木造アパート
- 長期保有と出口戦略重視→築15〜25年のRCマンション
- 複数物件を組み合わせ、償却カーブを平準化するとキャッシュフローが安定
- 建物割合が高いと償却費が増える→土地建物按分を適正に設定
- インスペクションを実施し、老朽化リスクを数値で把握
決算期直前購入/修繕費計上で初年度負担を抑える
物件購入や大規模修繕のタイミングを決算期直前に設定すると、その期に計上できる減価償却費や修繕費を増やせる場合があります。
減価償却費は取得(使用開始)月に応じて月割計算されるため、期末に近い購入であっても数か月分の償却費を初年度に計上できます。また、修繕費は支出時に経費化できるため、決算前の実施により当期の課税所得を抑える効果があります。
- 決算期から逆算して金融機関審査・引渡し日を調整
- 設備更新や外壁塗装など資本的支出に該当しない修繕は支出時に全額経費化
- 資本的支出と判断される大規模修繕は減価償却扱いとなるため、早期着手で初年度償却期間を確保
【ポイント】
- ローン初回返済日は引渡し翌月末が多く、決算後の支払いに設定すればキャッシュフローが安定
- 取得時の仲介手数料や登記費用などは取得価額に算入(建物は減価償却、土地は非償却)
- 修繕工事は工事完了証明書や請求書を保存し、経費算入の根拠を明確化
- 引渡し遅延で決算を跨ぐと節税効果が翌期に繰り越される
- 無理な工期短縮は施工不良を招き、将来の修繕コスト増加につながる可能性がある
電子帳簿保存法対応と税務調査で指摘されやすい論点
2024年1月から電子データで受領した領収書・請求書は、電子帳簿保存法に基づき改ざん防止措置を講じた形で保存することが義務化されました。紙の原本をスキャン保存する場合も、タイムスタンプや検索要件を満たさないと経費として認められないリスクがあります。
特に高所得者向けの節税スキームは税務調査で重点的に確認されるため、証憑管理が不十分だと減価償却費や修繕費の否認につながりかねません。
- 入力後2か月以内+7営業日以内にタイムスタンプ付与→改ざん防止
- ファイル名に「取引日・金額・取引先」を含め検索性を確保
- 税務調査は3〜5年後に実施されることが多く、クラウド保存で長期保管が安全
- 土地建物按分が不自然に建物寄り→鑑定評価書で裏付けを用意
- 修繕費と資本的支出の区分が不明確→工事見積書と写真を保管
- 家族給与や管理委託費の相場超過→職務内容と報酬根拠を明示
資産管理会社を活用した所得分散と法人税メリット

弁護士が不動産投資を本格化する際、個人名義だけで運用すると最高55%の累進課税が重くのしかかります。一方、物件を保有する資産管理会社(合同会社や株式会社など)を設立し、家賃収入や譲渡益を法人課税に切り替えると、実効税率はおおむね30%前後に抑えられます。
さらに、役員報酬や家族給与を活用して所得を分散すれば、個人側の課税所得も低く抑えられるため、二重の節税効果が期待できます。
ただし、法人設立には設立費用や毎期の決算・申告コストが伴い、弁護士業との事業区分を明確にしないと損益通算で不利益を被るリスクがあります。
本章では、①会社形態による税率差、②役員報酬シミュレーション、③弁護士業との切り分けポイントを解説し、節税効果を最大化する手順を示します。
- 法人税率は固定なので高所得者ほどメリット大
- 家族への給与で所得を細分化し累進税率を回避
- 事業区分と証憑整理を誤ると損益通算が制限される可能性があります
合同会社・株式会社設立で実効税率約30%に下げる方法
法人課税は「所得割」と「住民税・事業税・地方法人税」から成り、資本金1億円以下の中小法人なら、所得800万円までは国税15%・地方税合わせて約23%、800万円超部分は約30%強が目安です。
例えば不動産所得1,200万円の場合、個人なら最高55%課税で手取り540万円程度にとどまりますが、法人なら総合実効税率約31%とされ、手取りは約828万円まで増えます。
| 区分 | 800万円以下 | 800万円超 |
|---|---|---|
| 合同会社 | 約23% | 約31% |
| 株式会社 | 約23% | 約31% |
- 合同会社は設立費用約6万円・維持コスト低い
- 株式会社は資本政策や信用力で優位
- いずれも役員報酬は損金算入可能
-
-
- 短期で物件数を増やすなら合同会社→コスト軽減
- 将来の売却や資金調達を見据えるなら株式会社→信用力重視
-
役員報酬・家族給与で累進税率を回避するシミュレーション
法人化すると、会社の利益を役員報酬として外部に振り分けられます。たとえば不動産所得1,200万円のうち、600万円を自分、300万円を配偶者、従事分として200万円を成年の子に給与として支給すると、個人側はそれぞれ所得控除後の課税所得が抑えられ、累進税率の上昇を回避できます。
- 会社の利益1,200万円(税前)→法人税等約372万円
- 残額828万円を家族3人で役員給与配分
- 各人の課税所得が900万円以下に収まれば所得税率は23%以下
- 同族会社で著しく不自然な報酬水準は否認される可能性があります
- 給与分散だけを目的とした名義だけの役員・従業員は避けるべきです
弁護士業との事業区分と損益通算の注意点
弁護士業務による所得は、一般に「事業所得」または「給与所得」として申告します。不動産を法人に移管した場合、以下の区分管理が必要です。
- 弁護士業務は個人または別法人A、資産管理会社は法人B
- 法人Bの不動産所得と法人Aの法務収入は損益通算不可
- 個人の給与所得と法人Bの不動産所得赤字も通算不可
したがって、法人Bが赤字でも個人側の税額を直接減らすことはできず、繰越欠損金として最大10年間で内部通算する形となります。事業区分があいまいだと、税務調査で「実質一体」と判断され連結的に課税されるリスクがあります。
- 顧客との契約書や請求書に法人名を明記し事業を分離
- 使用口座・会計ソフト・原始証憑を完全に分ける
- 共通経費(事務所家賃など)は合理的な按分基準を作成
弁護士こそ不動産投資がおすすめな理由と次のアクション

弁護士は高収入である一方、累進課税や社会保険料の負担が大きく、可処分所得が伸びにくい傾向があります。不動産投資を組み合わせると、減価償却や経費計上で課税所得を圧縮でき、長期的な資産形成も同時に進められるため、税効率の高いポートフォリオを構築しやすくなります。
さらに、弁護士は契約交渉や法的リスク管理に精通しているため、取引条件や管理体制を有利に整えやすい点も強みです。
本章では、①長期保有による節税と資産構築、②プロパティマネジメントでの収益安定化、③専門家ネットワークを活かした出口戦略の三つの視点から、次に取るべき具体的なアクションを解説します。
- 税負担を抑えながらキャッシュフローを向上
- 専門知識を活かし、リスクをコントロール
- 出口まで描くことでリターンを最大化
長期保有で節税と資産形成を両立
不動産投資を長期保有すると、減価償却による節税効果を毎年受け取りながら、ローン元本の返済で純資産が着実に増加します。例えば築古木造アパートを残存耐用年数4年で購入した場合、初期4年間は大きな償却費で課税所得を圧縮でき、その後もローン残高が減るにつれてキャッシュフローが改善していきます。
また、保有期間中に地価や賃料が緩やかに上昇すれば、含み益を得られる可能性も高まります。税制面では、長期保有することで譲渡所得の税率が下がる特例を活用できる場合があるため、利益確定時の総合的な税負担を抑えやすくなる点も魅力です。
- 減価償却で課税所得を圧縮→毎年の納税キャッシュアウトを軽減
- 元本返済で純資産が増加→バランスシートを強化
- 長期譲渡特例で売却益課税を抑制→最終リターンを最大化
- 税負担を抑えながら純資産を増やす二重のメリット
- 家賃上昇・地価上昇があれば含み益も享受
プロパティマネジメントで安定収益を確保
長期保有の前提は、空室リスクを抑えて安定収益を確保することです。プロパティマネジメント(PM)会社を適切に選定し、賃料設定や入居者管理、修繕計画を体系化すれば、キャッシュフローを予測可能な範囲に収めやすくなります。
弁護士は契約書チェックや賃貸借トラブルの法的対応に強いため、PM会社と連携してリーガルリスクを最小化できる点が強みです。
また、賃料保証やサブリースなどのスキームを採用する際は、保証料率や中途解約条項を詳細に精査し、長期的な収益性を損なわないように注意する必要があります。
- PM会社の実績・管理戸数・退去率を比較検討
- 修繕積立シミュレーションで大規模修繕費を平準化
- 家賃保証契約は免責期間や減額条項を精査
- 手数料重視で選ぶとサービス品質が低下する可能性があります
- サブリース契約は賃料改定条項を確認し、収益悪化を防ぐ必要があります
専門家ネットワークを活かした出口戦略と再投資
弁護士ネットワークを活用すると、金融機関・税理士・不動産業者・投資家との連携が取りやすく、売却や買い替え時に有利な条件を引き出せる可能性があります。
たとえば、同業者の依頼を受けた金融機関は、事案に応じた融資条件を提案しやすく、共同投資案件への参画がスムーズに進むケースもあります。
出口戦略としては、譲渡所得課税を抑えるタイミングで売却し、得た資金を次の築古物件へ再投資することで、減価償却メリットを継続的に享受できます。
1031交換のような国内版制度は存在しませんが、資産管理会社を介した売買やM&Aスキームを活用すれば、税負担を一定程度繰り延べることは可能とされています。
- 売却益の課税タイミングを調整→キャピタルゲイン課税を最適化
- 資産管理会社間で物件を移転→法人税の繰延効果を狙う
- 共同投資やクラウドファンディングでポートフォリオを分散
- 売却前に市場調査と物件価値査定を複数社で実施
- 再投資先の融資枠を事前に確保し、機会損失を防止
まとめ
本記事では、高所得弁護士が直面する高税率の仕組みと、不動産投資を中心とした合法的な節税策を解説しました。減価償却・経費計上・法人化による所得分散を活用すれば、手元資金を守りつつ長期的な資産形成が可能です。
まずはシミュレーションを行い、信頼できる専門家へ相談して一歩踏み出しましょう。早期の対策が将来のキャッシュフローとライフプランを大きく左右します。適切な物件選定と継続管理で、税負担軽減と資産拡大を両立しましょう。