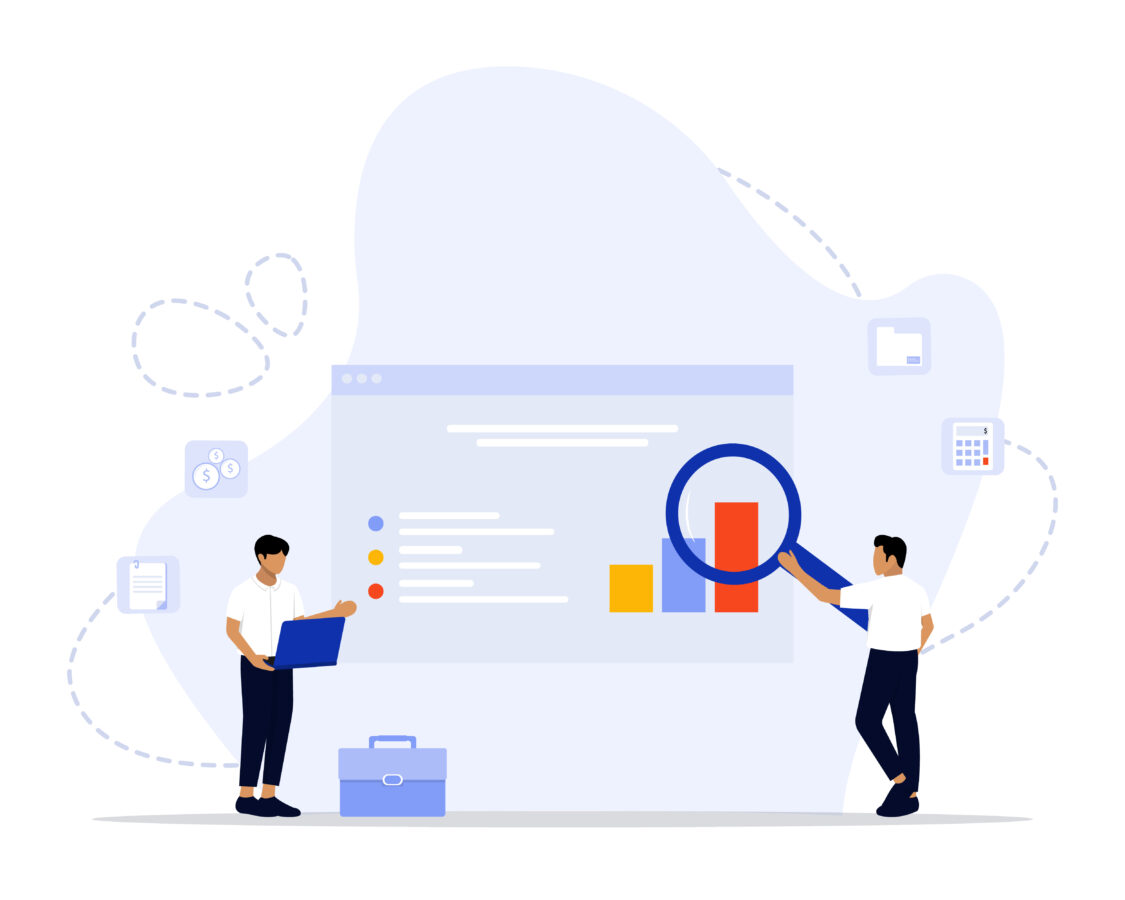高所得層でも、“損益通算”を使えば納税キャッシュを圧縮し手取りを大幅に増やせる可能性があります。本記事では損益通算の基本から、事業・不動産・金融商品の赤字を合法的に活用する4つのポイントまでを体系的に解説。
不動産投資で減価償却を加味した最強の節税モデルも紹介し、初心者でも今日から実践できるステップを提示します。
目次
損益通算とは?節税インパクトと対象所得

損益通算とは、複数の所得区分で発生した赤字と黒字を相殺し、課税所得を小さくする制度です。たとえば不動産所得の赤字300万円と給与所得の黒字1,000万円を合算すれば、課税対象は700万円になり、その分の所得税・住民税を減らせるとされています。
高所得層ほど累進税率が高いため、同じ300万円の赤字でも節税インパクトが大きく、手取りキャッシュを守りやすい点が特徴です。
さらに赤字を出し切れなかった場合は「損失の繰越控除」により最長3年間繰り越せるため、年ごとの収入変動が大きい士業や経営者でも税負担を平準化しやすいといわれています。以下では、基本ルールと対象所得を整理し、後続章で活用ステップを具体的に解説します。
- 赤字と黒字を相殺→課税所得を圧縮
- 最高税率帯では1円の赤字が55%節税につながる可能性
- 使いこなせばキャッシュフローと投資余力を同時に確保
- 納税キャッシュの即時削減
- 繰越控除で将来の税負担を平準化
損益通算の基本ルールと計算順序
損益通算は「総合課税の所得同士で相殺する」「順序を守って計算する」という2つのルールがあります。
赤字が出た場合、まず同じ総合課税グループ内で相殺し、それでも残った赤字は損失の繰越控除へ回す順序です。具体的な計算フローは次のとおりです。
- 事業・不動産・山林・譲渡所得をそれぞれ損益計算
- 赤字所得を黒字所得に充当→総所得を圧縮
- 残った赤字は翌年以降へ繰り越し
- 総合所得に所得控除を適用→課税所得を確定
| ステップ | 注意点 |
|---|---|
| 1.個別計算 | 青色申告特別控除など各所得区分固有の控除を先に適用 |
| 2.相殺 | 赤字額は黒字額の範囲まで。超過分は繰越へ |
| 3.繰越 | 確定申告書第三表に記載し、3年以内に相殺しきる |
- 分離課税所得(株式譲渡など)は原則通算不可→要注意
- 繰越控除を使う年も青色申告が必要→届出忘れで無効化の可能性
- 赤字発生年度内で相殺しきると、住民税・国保料も軽減
- 赤字計上の根拠資料が不足→税務調査で否認される可能性
- 繰越申告を失念→赤字が失効し節税機会を逃す恐れ
損益通算できる4所得とできない所得
損益通算が認められるのは「事業・不動産・山林・譲渡(総合課税分)」の4所得とされています。それ以外の所得は通算できず、分離課税か雑所得として別枠で課税される点を押さえておく必要があります。
| 区分 | 通算可否 | 主な注意点 |
|---|---|---|
| 事業所得 | ○ | 赤字額に青色65万円控除を含められる |
| 不動産所得 | ○ | 土地取得の借入利息は一部制限あり |
| 山林所得 | ○ | 5年超保有なら森林計画特例が適用される場合 |
| 総合譲渡所得 | ○ | 金地金やゴルフ会員権の譲渡損益など |
| 株式譲渡益 | × | 申告分離課税→損失は同じ上場株内でのみ相殺 |
| 先物・FX | × | 申告分離税率20.315%、損失は同区分で3年繰越 |
| 給与所得 | − | 黒字側としてのみ相殺に利用され、赤字は出ない |
- 【通算可】でも赤字を意図的に作る行為は租税回避と判断される可能性
- 【通算不可】の所得は源泉徴収や特定口座で自動精算し、別管理
- 雑所得の暗号資産損失は通算不可→注意が必要
- 通算可4所得の赤字計上は証憑と事業関連性を明確化
- 分離課税損失も繰越制度を活用し、翌期以降の利益と相殺
高所得者が損益通算で得られる節税効果

高所得層は累進税率のため、1円の課税所得減少でも大きな税額軽減につながるとされています。たとえば課税所得4,000万円超では所得税45%+住民税10%の合計55%が適用されるため、300万円の赤字を損益通算すれば理論上165万円前後の税負担を圧縮できる計算です。
また、赤字によって住民税や国民健康保険料も連動して下がるため、キャッシュフローの改善効果は単純な所得税減だけでは収まらない可能性があります。
さらに赤字を使って総所得を900万円以下に抑えられれば、ふるさと納税や児童手当などの所得制限回避にも寄与し、トータルの家計コストを抑制できる点も見逃せません。
高所得者こそ“税率差益”を最大活用できるため、損益通算は単なる節税テクニックではなく資産形成を加速させるレバレッジ装置といえるでしょう。
- 赤字300万円→最高税率帯なら実質節税インパクト約165万円
- 住民税・国保料も基礎となる所得が減るため追加効果が見込める
- 所得制限のある各種控除や補助にも好影響
- 高税率帯ほど“1円の赤字”価値が高い
- 通算後の所得に応じて社会保険料も見直される可能性
事業所得・不動産所得の赤字活用シナリオ
損益通算にもっとも利用されるのが、事業所得と不動産所得の赤字です。事業所得では、①開業初期に設備投資を集中的に行う、②売上計上を期末後にずらすなどタイミングを調整し赤字を意図的に作る手法があります。
ただし赤字目的の過度な納品遅延や故意の値引きは租税回避とみなされるリスクがあるため、実態に即した支出計画が前提となります。
一方、不動産所得は減価償却とローン利息によって“現金流出を伴わず”赤字を計上できる点が強みです。
特に築古木造物件なら残存耐用年数が4〜6年程度と短く、初年度から大きな償却費を計上できます。以下のシナリオ例では、不動産所得の赤字を活用して手取りを増やすモデルを示しています。
| 項目 | 個人事業モデル | 不動産投資モデル |
|---|---|---|
| 赤字要因 | 開業設備300万円 | 減価償却300万円 |
| 現金流出 | 300万円支出 | 0円(非資金費用) |
| 節税効果※ | 約165万円 | 約165万円 |
※最高税率55%の場合の概算
- 現金を守りつつ赤字を計上できるのは不動産所得の大きな利点
- 赤字額を調整しやすいよう、設備・修繕を期末前にまとめる方法があります
- 過度な赤字は融資審査でマイナス評価→金融機関とのバランスが重要
- 借入利息が土地取得に充当される場合は一部経費否認の可能性
- 形式的赤字は税務調査で否認されるリスクがあるため、領収書・契約書を必ず保存
【ポイント】
- 年度初めに損益計画を作成→赤字幅と納税額をシミュレーション
- 期中で収支をモニタリング→想定とズレた場合は追加投資や支出調整でリカバリー
- 期末に未払計上や修繕計画を活用→目標赤字額に着地できるよう調整
損失の繰越控除で3年先まで税負担を平準化
損益通算で相殺しきれなかった赤字は「損失の繰越控除」を使い、翌年度以降3年間にわたり総所得から控除することが可能です。これにより、景気変動や案件増減で所得が上下する職種でも、税負担を平準化できるメリットがあります。
たとえば初年度に事業所得の赤字500万円を計上し、黒字が300万円しかなかった場合、200万円の赤字が残ります。
この200万円は翌年度の黒字と自動的に相殺され、納税キャッシュを抑えられる仕組みです。さらに、赤字が3年間で使い切れない場合も「繰越控除を使いたい年度は青色申告要件を満たす」必要があるため、帳簿精度と電子申告の継続が不可欠とされています。
| 年度 | 損益状況 | 繰越残高 |
|---|---|---|
| 1年目 | ▲500万円 | ▲200万円 |
| 2年目 | +300万円 | 0円 |
| 3年目 | +150万円 | 0円 |
- 損失残高がある期間も予定納税基準額が下がるため、納税資金を他の投資に回せる
- 赤字が完全に相殺されるまで控除は自動適用→特別な手続きは不要
- 繰越控除を適用する年は青色申告要件を満たさないと赤字が失効する可能性
- 赤字発生年度に確定申告書第三表を提出
- 翌年以降も青色申告で決算→残高を自動相殺
- 控除しきれない場合は資産売却や大型案件で黒字を作り切る
【ポイント】
- 赤字額と残高を年次で記録し、利用完了までモニタリング
- 黒字が見込めない場合は繰越期間内に追加投資で赤字を活用
- 繰越期間終了前に税理士と節税シナリオを再確認し、失効を回避
不動産投資で赤字を作り課税所得を圧縮
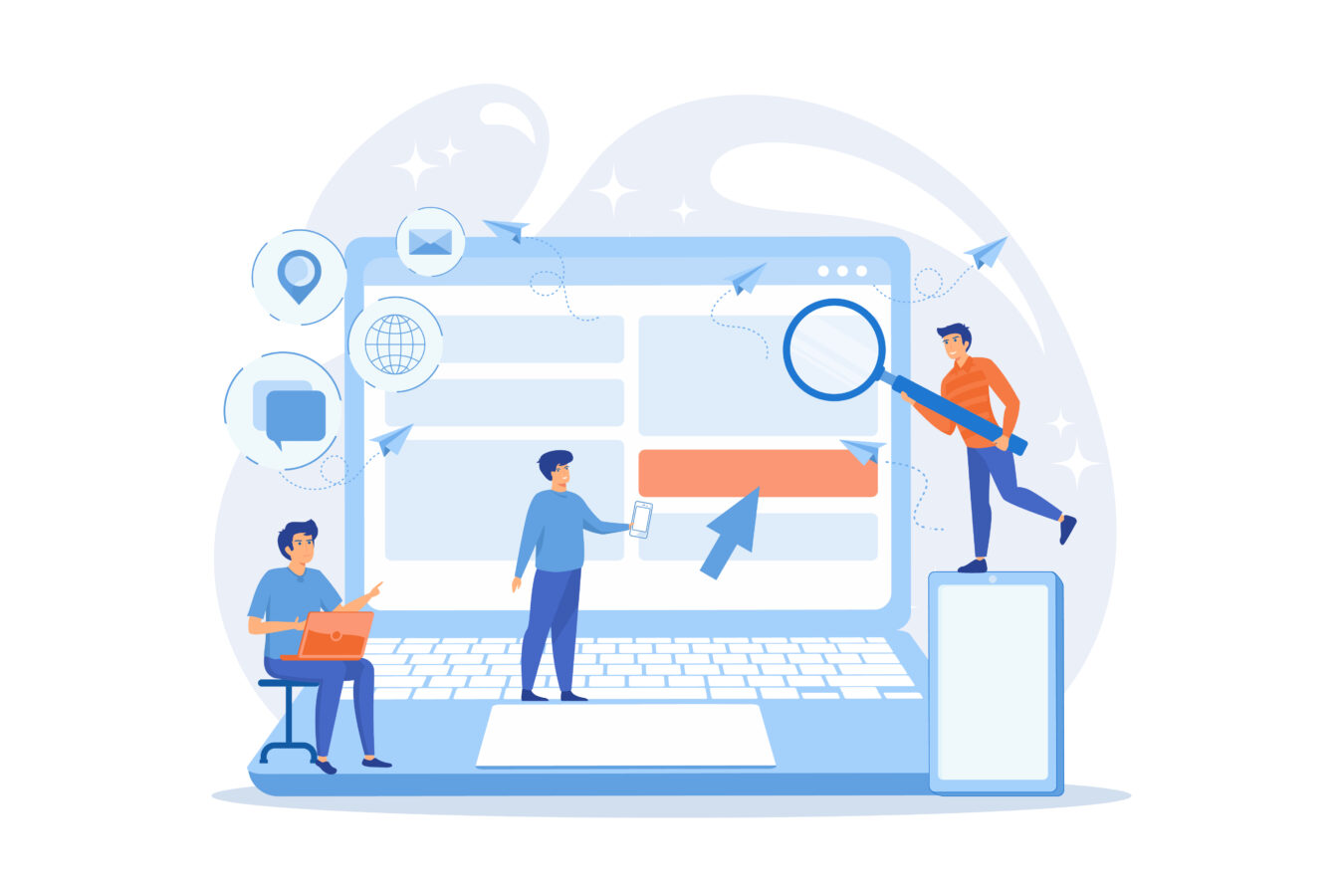
高所得者が損益通算を最大化する手段として、不動産投資は極めて相性が良いとされています。なぜなら、家賃という安定収入を得ながら、建物の減価償却やローン利息といった“非資金”または“半非資金”の費用を計上できるためです。
これにより手元キャッシュを減らさずに帳簿上の赤字を作り、給与・事業など他の黒字所得と相殺することで、実質的な税率を大幅に引き下げることが可能になります。
さらに、ローン元本の返済で純資産が積み上がるため、節税と資産形成を同時に達成できる点も魅力です。ただし、赤字計上には「金融機関の与信評価」「税務調査での合理性説明」「長期保有に耐える物件品質」という三つのハードルが存在するため、計画的なプランニングが欠かせません。
本章では、①減価償却とローン利息を活用した安全な赤字化、②築古物件を使って初年度から大きな償却を取る具体手順の二段構成で解説します。
- 非資金費用→減価償却でキャッシュを守りつつ節税
- ローン活用→利息部分のみ経費化、元本返済で資産増
- 適切な物件選定と管理→出口戦略まで視野に入れる
減価償却とローン利息で安全に赤字化
減価償却は、建物や設備の取得費を耐用年数にわたって分割計上する仕組みであり、現金支出を伴わずに経費を増やせる“非資金費用”です。
不動産所得では、この償却費にローン利息・管理費・固定資産税を加えることで、家賃収入を超える赤字を計上しやすくなります。
たとえば木造アパート(築20年・建物1,000万円)を取得し、残存耐用年数4年で償却すると年間250万円の費用が発生します。家賃収入500万円、その他経費260万円の場合、−10万円の赤字となり、給与所得と相殺できる計算です。
| 費用項目 | 内容 | 節税ポイント |
|---|---|---|
| 減価償却 | 建物1,000万円÷4年=250万円 | 非資金費用→CF影響ゼロ |
| ローン利息 | 借入5,000万円×1.5%=75万円 | 元本部分は経費不可 |
| 管理・税金 | 管理委託料80万円ほか | 領収書保存で否認防止 |
【安全に赤字化するコツ】
- 家賃収入≧ローン返済額+固定費→キャッシュフローを黒字に保つ
- ローン利息が高い初期3年で赤字幅を最大化→以降は繰越控除活用
- 青色申告により65万円控除を追加すると赤字が作りやすい
- ローン審査で「返済比率悪化」と判断される可能性
- 修繕・広告費の水増しは税務調査で否認される恐れがあります
【ポイント】
- 取得時に建物と土地を適正按分し、建物割合を高める
- 設備(エアコンなど)は最短6年で償却できるため分離計上
- 元本据置期間を1〜2年設け、初年度赤字を最大化して損益通算
金融機関には「黒字キャッシュフロー」を示し、税務署には「合理的赤字」を説明できる資料を準備しましょう
築古物件で初年度から大きめの償却をとる手順
中古資産の耐用年数は、省令の「中古資産の見積耐用年数」の簡便計算式で求めます。
- – 経過年数が法定耐用年数未満のとき:
見積耐用年数 =(法定耐用年数 − 経過年数)+(経過年数 × 0.2)〔1年未満切上げ〕 - – 経過年数が法定耐用年数以上のとき:
見積耐用年数 =(法定耐用年数 × 0.2)〔1年未満切上げ・最低2年〕
たとえば築25年の木造アパート(建物価格800万円・土地200万円、木造の法定耐用年数22年)の場合、経過年数が法定耐用年数以上なので、見積耐用年数は 22年×0.2=4.4年 → 切上げで5年。
建物は原則定額法で償却するため、年間償却費の目安は 800万円÷5年=160万円(初年度は事業供用を開始した月からの月割)となります。
| ステップ | 具体作業 | ポイント |
|---|---|---|
| ①物件選定 | 建物割合が適正に確認できる築古 | 固定資産評価証明・売買契約で按分根拠を確保 |
| ②耐用年数判定 | 木造22年・経過25年 → 22×0.2=4.4年 | 切上げで5年(最低2年) |
| ③償却費計算 | 800万円÷5年=160万円/年 | 初年度は供用開始月から月割計上(例:2月取得なら11/12) |
- 木造(法定耐用年数22年)の築古は、経過年数しだいで5年前後の短い耐用年数になるケースがある
- RC造(法定47年)は、経過年数が法定未満なら式により長めの年数(例:築25年なら 47−25+25×0.2=27年)となる点に注意
- 建物・建物附属設備は原則定額法。附属設備・構築物は2016/4/1以後取得は定額法のみ
- 建物・土地の按分は評価証明や鑑定等で客観根拠を用意
- インスペクションで修繕見積を事前把握→突発支出を抑制
- 取得年の償却は月割。決算直前取得でも12か月分一括にはならない
金融商品別の損益通算・繰越控除の注意点

損益通算を語るうえで忘れてはならないのが「金融商品ごとに課税方式が違い、通算・繰越ルールも変わる」という事実です。
株式や投資信託、FX、暗号資産(仮想通貨)などは一見似た“投資”でも、税法上はそれぞれ別枠で課税されるため、赤字が出ても他の黒字所得と相殺できない場合があります。
ここを誤解していると「赤字を出したのに税金が減らない」事態に陥りかねません。本章では〈①上場株式・投資信託〉〈②FX・暗号資産〉という代表的な金融商品のルールを整理し、繰越控除を最大限に活用するポイントを解説します。
- 金融商品の多くは申告分離課税→総合課税所得とは通算不可
- NISA口座の損失は原則通算対象外→注意が必要
- 繰越控除には確定申告が必須→e-Taxで手続き簡素化
- 同一課税区分内でしか通算できない
- 損失を翌年以降に繰り越すには各年の確定申告が前提
株式・投資信託の譲渡損と配当益の相殺
株式・投資信託の譲渡益や配当・分配金は、税率20.315%(所得税15%+住民税5%+復興特別税)で申告分離課税される仕組みです。
ここで生じた譲渡損失は「同じ分離課税区分内」でのみ相殺が可能となり、総合課税の所得(給与や不動産所得)とは通算できません。ただし、特定口座(源泉徴収あり)を利用している場合、自動的に相殺してくれる機能があるため、年間損益がプラスマイナスゼロなら追加申告は不要とされています。
問題は“複数証券会社に口座を持ち、片方で赤字・片方で黒字”というケースです。この場合、確定申告で損益通算しないと本来不要な税金を払い過ぎるおそれがあります。
さらに、譲渡損失が当年で控除しきれない場合は、翌年以降3年間繰り越して相殺できるため、急激な株価上昇局面で節税インパクトを残す効果も期待できます。
| ポイント | 解説 |
|---|---|
| 通算範囲 | 上場株式・ETF・公募投信・REITの譲渡損益/配当等 |
| NISA | 損失は通算対象外、配当益も申告不要 |
| 繰越控除 | 確定申告要、最長3年間で相殺 |
- 複数口座の年間取引報告書を集約→申告書附票に転記
- 配当控除を検討する場合は「総合課税」or「分離課税」どちらが有利か再計算
- 利益確定売りと同時に含み損株を損切り→「税金還付+ポートフォリオ見直し」が一度に実行可能
- 配当控除狙いで総合課税を選択→所得税率が高いと逆効果の場合があります
- 貸株サービス利用中の配当代替金は雑所得扱い→通算できず計算が複雑化
【手順】
- 各証券会社から電子交付された取引報告書をダウンロード
- 譲渡損益欄と配当欄を合算→通算後の数字を特定口座計算欄に入力
- 損失が残れば第三表へ繰越控除額を記載し、翌年度へ引き継ぐ
FX・仮想通貨損失の扱いと分離課税の壁
FX(店頭デリバティブ取引)やCFD、株価指数先物などは税率20.315%の申告分離課税で、株式とは異なる「先物取引に係る雑所得等」区分に位置付けられています。
このため、FXの損失は上場株式の損益とは通算できず、同区分の利益としか相殺できません。一方、暗号資産(ビットコインなど)は雑所得として総合課税扱いとなるため、所得税率が高い高所得者の場合最大55%課税とされ、損失の通算対象外という厳しいルールが適用されます。
暗号資産の損失は現行制度では繰越控除もできないため、ハイリスク・ハイリターンであることを理解しておく必要があります。
| 商品区分 | 課税方式 | 通算・繰越可否 |
|---|---|---|
| FX・先物 | 申告分離20.315% | 同区分内で通算、3年繰越可 |
| 暗号資産 | 総合課税5〜45% | 通算不可、繰越不可 |
【対策と活用アイデア】
- 【FX】→損失が出た年度に利益を意図的に確定し、相殺して税率を平準化
- 【先物】→繰越制度を利用し、翌年度の利益に充当
- 【暗号資産】→法人化して資本金1億円以下の法人税率約30%で取引するスキームも検討
- 暗号資産間の交換取引も譲渡所得扱い→取引ログを完全保存
- 海外取引所利用時はFBAR・国外財産調書など付随義務に注意
【手順】
- FX・先物の年間損益を損益計算書で集計→区分損益計算書へ転記
- 暗号資産は損益計算サイトを使い「総平均法」または「移動平均法」で計算
- 区分ごとに第三表・第四表へ記載し、繰越控除欄を漏れなく記入
損益通算を成功させる申告手続きとリスク管理

損益通算は「赤字を有効活用して納税キャッシュを守る」強力な節税策ですが、正しい申告手続きとリスク管理を怠ると、税務調査で否認される恐れがあります。
特に高所得層の場合、控除額が大きい分だけ調査対象になりやすく、帳簿不備や証憑不足が見つかれば本来の節税メリットが一瞬で消える可能性があります。
ここでは〈①確定申告書B・第三表の正しい記載〉〈②証憑整理と保存方法〉の二つの視点から、ミスを防ぎながら損益通算を成功させるための実践フローを解説します。
ポイントは「入力を自動化しヒューマンエラーを削減」「証憑をタイムスタンプ付き電子データで一元管理」「調査リスクを想定したエビデンスセットを年度ごとに整備」の三つです。
確定申告書Bと第三表の書き方
確定申告書Bでは、第一表に総所得金額を、第二表に各種控除を入力し、損益通算の実務は第三表(損失申告用)の記載で完結します。まず第三表第一面の「損失の種類」欄に事業所得や不動産所得の赤字額を転記し、「総損失額」へ集計します。
次に同じ表の「損益通算後の所得金額」欄へ黒字所得と相殺した後の金額を記入し、差引後に残った赤字は「翌年以後に繰り越す損失額」へ振り替えます。
電子申告なら会計ソフトの自動連携で転記漏れを防げるため、65万円控除の要件も同時に満たせる点がメリットです。
| ステップ | 入力ポイント |
|---|---|
| ①第一表 | 総所得金額欄に相殺後の金額を記入→住民税・国保料に直結 |
| ②第三表 | 赤字額を「損失の種類」へ記載→黒字所得と自動相殺 |
| ③別表添付 | 株式・FXの繰越損失は第四表へ、不動産減価償却は明細書を添付 |
- 【自動化】→クラウド会計とe-Tax連携で転記ミスをゼロに近づける
- 【ダブルチェック】→税理士レビュー前に残高試算表と第三表を突合
- 【提出期限】→赤字年度と繰越年度の申告を両方電子で行わないと控除が無効になる場合があります
- 電子申告+青色帳簿で65万円控除を同時取得
- 赤字額は必ず「マイナス」符号を付ける
- 繰越欄に残高を記載し、翌年も忘れずに転記
【手順】
- 会計ソフトで第三表を自動生成→PDFプレビューで形式を確認
- e-Tax送信後、受信通知と添付書類一覧をPDF保存→5年間保管
- 翌年の申告開始前に残高をインポートし、繰越損失を自動計算
税務調査で否認されない証憑整理術
税務調査は「①証憑の真実性」「②経費計上の合理性」「③損失計上の継続性」の三点を重点的に確認するとされています。最も多い否認理由は、領収書の紛失や取引の裏付けが取れないケースです。
これを防ぐには〈電子帳簿保存法に準拠したデータ管理〉〈案件コードで領収書を紐付け〉〈年度ごとに監査ファイルを作成〉の三段階で証憑整理を行うと効果的です。
- 【電子保存】→領収書撮影→30日以内タイムスタンプ→取引日・金額をファイル名に付与
- 【紐付け】→クラウド会計のタグ機能で案件コードを付与し、支払実態を検索しやすく
- 【監査ファイル】→PDFで月次フォルダを作成し、決算報告書・総勘定元帳・領収書一覧を格納
- 土地取得借入の利息分→不動産所得で経費制限があるため按分根拠を保存
- 家族給与・管理委託料→職務分掌と相場資料を添付し、独立当事者性を確保
| 資料 | 保存期間 | 保存形式 |
|---|---|---|
| 領収書 | 7年間 | PDF+タイムスタンプ |
| 契約書 | 業務終了後7年間 | 電子契約→クラウド保存 |
| 減価償却明細 | 帳簿保存期間と同一 | 会計ソフト出力PDF |
- 【手順】
- 決算月翌月までに年度フォルダを作成→証憑を一括格納
- 四半期ごとに領収書と仕訳を突合→未登録取引をゼロに
- 税務調査通知を受けたら監査ファイルを税理士と共有→質問事項を事前想定
まとめ
損益通算は「赤字と黒字を相殺して課税所得を圧縮する」強力な節税ツールです。まずは対象4所得と計算順序を理解し、赤字が出やすい事業所得・不動産所得を戦略的に組み込むことが鍵となります。
さらに損失が出なかった年でも3年間繰り越せる制度を使えば、収益変動が大きい職種でも税負担を平準化できます。減価償却が大きい築古物件への投資を組み合わせれば、節税と資産形成を同時に実現できるでしょう。行動の第一歩は、今期の収支を可視化し、赤字ポケットを設計することから始めてください。