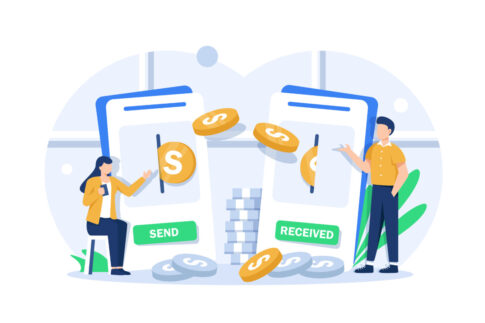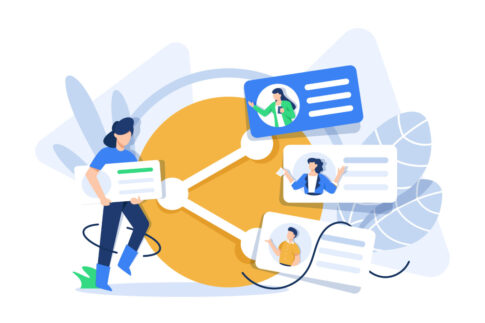「節税で手取りを増やしたいけれど、結局どれを選べばいいの?」──そんな悩みを抱える方へ。iDeCoやふるさと納税など少額から始められる制度から、不動産投資による大型節税まで15のおすすめ策を厳選しました。
控除額の仕組みとキャッシュフローへの効果を具体例で示すので、読後すぐに自分に合うプランを組み立てられます。
節税おすすめ人気トップ7

節税策は「簡単に始められるもの」「掛金が全額控除になるもの」「資産形成につながるもの」の三要素を押さえると効果が飛躍的に高まります。
本章では実践者の利用率が高く、税制面でもメリットが明確な7つの制度・手法を厳選しました。具体的には〈iDeCo〉〈小規模企業共済〉〈新NISA〉〈ふるさと納税〉〈生命保険料控除〉〈医療費控除〉〈築古マンション投資〉の7項目です。
これらは少額から始められ、掛金や投資額がそのまま所得控除や非課税枠として反映されるため、確定申告での税額がダイレクトに下がります。
まずは月数千円からスタートできる制度で節税効果を体感し、手取りが増えたら大型投資でキャッシュフローと資産形成を両立させる流れが王道です。
iDeCoで老後資金と掛金全額控除を両立
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、掛金がそのまま所得控除になる最強クラスの節税制度です。自営業者が積み立てられる上限は月6万8,000円で、年額81万6,000円すべてが課税所得から差し引かれます。
所得税率20%・住民税10%のケースなら、理論上年間約24万円が節税効果として戻ってくる計算です。さらに運用益も非課税で再投資されるため、複利が最大化しやすい点が大きな魅力です。
- 掛金は月5,000円から1,000円単位で増減でき、資金繰りも柔軟
- 運用商品の中心は信託報酬0.2%前後のインデックスファンド
- 受取時は退職所得控除または公的年金等控除が使え二重で優遇
- 開業初年度でも控除はフル適用、赤字決算でも損失繰越にプラス
- 掛金証明書は10〜11月に届くので紛失前に撮影&クラウド保存
留意点として60歳まで原則引き出せませんが、掛金停止はいつでも可能です。まずは節税額を試算し、可能な範囲で上限に近づけるのが老後資金と税負担軽減の両面で最適解になります。
小規模企業共済で退職金づくりと所得圧縮
小規模企業共済は国(中小機構)が運営する“自分専用の退職金制度”です。掛金は月1,000~7万円まで自由設定でき、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として所得控除になります。
たとえば月3万円を年間で36万円拠出すれば、税率30%の人なら約10万8,000円の節税効果を得ながら将来の退職金を積み立てられます。
- 掛金は途中で増減・停止が可能、資金繰りが厳しい月は変更手続きで調整
- 節税+掛金貸付(掛金の7~9割を低金利で借入可)が二重のメリット
- 共済金受取時は退職所得扱いで“1/2課税+控除”と大幅優遇
- 年度末の所得が想定より増えたら増額手続きを行い控除を最大化
- 受取時期を他の退職所得と重ねず、控除枠をフルに使う
加入は商工会議所や金融機関の窓口、オンライン申込で完結。iDeCoと併用しても掛金上限は別枠なので、ダブルで控除を狙うと節税スピードが一気に高まります。
新NISA非課税枠で運用益ゼロ課税を実現
2024年からスタートした新NISAは「つみたて投資枠120万円/成長投資枠240万円」の年間非課税枠と、生涯1,800万円までの非課税限度額が特徴です。
従来NISAと異なり非課税期間が無期限に延長され、売却して枠が復活する(生涯非課税保有限度額(1,800万円)の空き枠)ため長期運用の自由度が格段に向上しました。
- つみたて投資枠:金融庁基準の低コストインデックス投信のみ対象
- 成長投資枠:日本株・米国株・ETFなど幅広い商品に投資可能
- 運用益・配当金が非課税、複利効果がフルに働く
- 一般口座・特定口座と異なり譲渡損益通算や損失繰越は不可
- 非課税枠を使い切れない年はつみたて枠だけで無理なく積立
- 長期保有前提なら信託報酬0.1%台の全世界株式インデックスが鉄板
新NISAは運用益が非課税になる“攻めの節税策”で、iDeCoや共済の“守りの控除策”と組み合わせると、リスクを抑えながら税メリットと資産成長を両取りできます。毎月のキャッシュフローを確認しながら、まずは自動積立で非課税枠を埋めるところから始めましょう。
ふるさと納税で返礼品+翌年住民税減額
ふるさと納税は、好きな自治体へ寄付をすると返礼品を受取りつつ「寄付額−2,000円」が所得税と翌年の住民税から控除される制度です。控除上限は年収・家族構成によって変動するため、必ずシミュレーションサイトで確認してから寄付額を決めましょう。
たとえば課税所得400万円・扶養なしの場合、上限は約4万円。4万円寄付すると実質負担2,000円で30,000円相当の返礼品が届き、翌年の住民税が約35,800円減ります。寄付はクレジットカード払いが可能で、楽天やポイントサイト経由ならポイント還元により負担をほぼゼロに抑えられます。
- ワンストップ特例制度を使えば確定申告不要(寄付先5自治体以内)
- 6月の住民税決定通知書で控除額を確認し、翌年の資金計画に反映
- 寄付上限超過分は控除対象外になるため注意
- 年末の駆け込み寄付は決済締切(12月31日23:59)に注意
- 寄付受領証明書は確定申告・ワンストップ申請書と同封保管
住宅ローン控除で10年間の税額控除を獲得
住宅ローン控除の控除率はすべての区分で年0.7%(認定住宅を含む)。認定住宅・ZEH住宅などは借入限度額や控除期間(最長13年)が上乗せされるが、控除率は変わりません。
ローン残高上限は一般住宅4,000万円、長期優良住宅等は5,000万円。たとえば一般住宅で残高3,500万円なら、初年度に24万5,000円(3,500万円×0.7%)が所得税から控除され、控除し切れない分は住民税(一部上限あり)へ振替されます。
- 控除適用要件:床面積40㎡以上・合計所得2,000万円以下・10年以上の返済期間
- 増改築や省エネ改修でも対象になるケースあり(要リフォーム控除要件)
- サラリーマンでも初年度は確定申告、2年目以降は年末調整で控除継続
- 繰上返済を多用すると控除額が減るため、金利と控除効果のバランスが重要
- ペアローン・連帯債務で控除枠を2人分に分散し上限を拡大
- 団信保険料が金利上乗せの場合、支払利息として経費化不可なので要確認
医療費控除で急な出費を税金で取り戻す
医療費控除は、家族全員の1年間の医療費総額が10万円(または所得の5%いずれか低い方)を超えた場合、その超過分が所得控除になる仕組みです。対象は診療費・薬代・通院交通費・入院時の部屋代差額など幅広く、医療保険の給付金や高額療養費制度の補填分は差し引いて計算します。
たとえば総所得600万円の家庭で医療費が30万円、高額療養費として5万円戻った場合、控除額は(30万円−5万円−10万円)=15万円。税率20%・住民税10%なら約4万5,000円が節税額となります。
- 市販薬購入は「セルフメディケーション税制」も選択可(いずれか一方)
- 通院タクシー代は領収書、電車代は経路メモで証憑化
- 歯列矯正は審美目的だと対象外、医療的必要性の証明書で可否が決まる
- 確定申告の医療費控除明細書は領収書添付不要だが、5年間保存義務あり
- 家族分を一人に集約すると超過額を大きくしやすい
- 年内に治療完了予定がある場合は早めに支払い調整して控除枠を超える
マンション投資で減価償却と損益通算を最大化
築古マンション投資は、建物価格を短期で減価償却できるため帳簿上の赤字を作りやすく、事業所得や給与所得と損益通算して税金を還付できる“攻めの節税策”です。
たとえば築30年RC区分1,200万円(建物比率60%)を購入し、残存耐用年数9年で償却すると年間80万円の減価償却費を計上可能。家賃収入96万円、経費40万円なら損益は▲24万円となり、税率33%の高所得者なら約8万円の還付を受けられます。
- 築古木造(築20年以上)・RC(築30年以上)は残存年数が短く節税効率◎
- 建物比率は鑑定書添付で60%超を狙うと償却費が増大
- 青色申告なら65万円控除+赤字繰越3年で効果継続
- 減価償却切れ後はデッドクロス対策として繰上返済や法人移管を検討
- 保有期:減価償却費+実経費で赤字維持し損益通算
- 出口期:長期譲渡税率20%を狙い売却益の税負担を圧縮
適切な物件選定と資金計画が前提ですが、家賃収入という現金インを確保しつつ税負担を削減できるため、キャッシュフローと資産拡大を同時に狙えるのが最大の魅力です。
控除・保険テクニック5選【家計を守る】

節税には「掛金をそのまま所得控除できる仕組み」と「万一の備えを兼ねた保険活用」が欠かせません。特に生命保険料控除と地震保険料控除は、支払保険料を居住用住宅や家計防衛に直結させながら税負担を減らせる“守りの節税策”です。
加えて、医療保険・がん保険の見直しや団体信用生命保険の金利上乗せ比較など、保険料そのものの最適化も大きなポイントになります。
本章では【家計を守る控除・保険テクニック】として、生命保険料控除、地震保険料控除、医療保険見直し控除効果、団信金利差額節税、家事按分による火災保険経費化の5項目を整理します。
まずは王道の生命保険料控除と地震保険料控除を詳しく確認し、支払保険料が無駄にならないよう控除上限を意識した加入・更新フローを身に付けましょう。
生命保険料控除で最大4万円の節税効果
生命保険料控除は「一般」「介護医療」「個人年金」の3区分に分かれ、各区分の年間支払保険料に応じて最大4万円(所得税)、住民税では最大2万8,000円が所得控除になります。
たとえば一般生命保険と介護医療保険にそれぞれ年間8万円ずつ支払えば、所得控除合計は8万円。税率20%・住民税10%の方なら、単純計算で年間2万4,000円の節税効果が得られます。
- 控除計算式は旧契約(2011年以前)と新契約で異なるため、更新時に再試算が必要
- 年間払込保険料が8万円を超えると控除額は頭打ちになるので過剰加入に注意
- 不要な死亡保障を削減し、医療・介護・就業不能保障へシフトすると保険料と控除のバランスが最適化
- 保険料控除証明書は10月〜11月に郵送、紛失・未着時は再発行手続きを早めに
- 夫婦それぞれ契約し控除枠を2倍に活用(世帯全体の節税額を最大化)
- 返戻率重視の終身保険は掛金が高額になりがち→控除枠と利回りを冷静に試算
契約を見直す際は「保険証券紹介サービス」で契約一覧と控除額試算を行い、控除枠上限に合わせてリバランスすると効率的です。保険料をクレジットカード払いにするとポイント還元分も実質的な節税となり、一石二鳥の効果が期待できます。
地震保険料控除で災害リスクと税負担を同時カット
地震保険料控除は、居住用住宅に付帯する地震保険料の全額(所得税で最高5万円・住民税で最高2万5,000円)を所得控除にできる制度です。
たとえば年間保険料3万円の場合、その3万円がそのまま課税所得から差し引かれます。税率30%の世帯なら、所得税9,000円・住民税3,000円、合計1万2,000円の節税効果を得ながら地震リスクに備えられます。
- 控除対象は「地震保険料」部分のみ。火災保険料と合算契約の場合は内訳を確認
- 保険期間は最長5年。長期契約一括払いだと割引率が上がり、控除額は当年分のみ
- 建物の免震・耐震等級が高いと保険料割引が適用され、控除額との二重メリット
- 地震保険は政府再保険制度で保護されており、破綻リスクが極めて低い
- 火災保険更新の際に耐震診断証明を取得し、保険料割引+控除枠のダブル活用
- 2年払い・3年払いでも支払年分しか控除対象にならないため、一括払いか年払いを比較検討
地震保険料控除は毎年の住民税通知書で金額を確認し、控除反映をチェックすることが大切です。保険見直しのタイミングで耐震等級アップのリフォームを行えば、保険料割引・控除・資産価値向上の“三重のリターン”が期待できます。
配偶者控除と配偶者特別控除で所得分散
配偶者控除(最大38万円)と配偶者特別控除(最大38万円)は、夫婦の所得差を活かして世帯全体の課税所得を下げる代表的な節税制度です。ポイントは「だれの所得がいくら減るか」ではなく「世帯トータルで手取りがいくら増えるか」という視点で最適ラインを決めることです。
一般的には配偶者(主に扶養される側)の年収が103万円以下なら配偶者控除が適用され、年収103万円超~201万6,000円以下なら段階的に配偶者特別控除が受けられます。
控除額が徐々に縮小する「谷間」を理解し、例えばパート収入を106万円に抑えて社会保険加入を避けるか、あるいは130万円を超えて社会保険加入する代わりに配偶者特別控除を最大化しつつ厚生年金や健康保険の給付を受けるかをシミュレーションすると最適解が見えてきます。
- 基礎控除48万円を加えると配偶者の課税所得ゼロラインは給与収入約103万円
- 配偶者控除を受ける側の合計所得が1,000万円超になると控除ゼロになるため注意
- iDeCo掛金で配偶者の所得を圧縮し、控除ライン内に収める合わせ技も有効
- 社会保険扶養・税扶養の判定基準は異なるので要確認
- 年間収入の見込みを10月時点で確認し、勤務調整・在宅ワークで微調整
- 配偶者の医療費控除や生命保険料控除を合算して世帯最適化
扶養控除を使い家族全体の税率を下げるコツ
扶養控除は16歳以上の扶養親族1人につき38万円(特定扶養なら63万円)が所得控除になる制度で、大学生の子どもを持つ家庭や親を扶養する場合に大きな節税効果を発揮します。適用条件は「年間所得が48万円以下(給与収入103万円以下)」「同一生計で生活費を負担していること」の2点です。
例えば大学生の子どもがアルバイト収入90万円、仕送り120万円の場合、子どもの所得は48万円以下となり父親(又は母親)が特定扶養控除63万円を受けられます。
税率20%・住民税10%の世帯なら年間18万9,000円の節税です。さらに親を扶養に入れる場合は、介護医療保険料や医療費控除も合算でき、家族全体で税負担を引き下げる「クロス控除」が成立します。
- 仕送りは銀行振込または現金書留で証憑を残し、扶養実態を証明できるようにする
- 同居親族の医療費は世帯主がまとめて医療費控除に計上すると控除枠が拡大
- 学生のアルバイト収入が103万円を超えそうな場合は、源泉徴収額と控除額を比較し働き方を調整
- 扶養控除は年末調整で適用、家族構成の変更があれば早めに会社へ申告
- 親が年金受給者でも、老齢基礎年金のみなら扶養控除対象になるケースが多い
- 家族の医療費・保険料をまとめ、控除計算を一括で行うと還付額が最大化
家事按分で自宅家賃・光熱費を経費化
個人事業主や副業サラリーマンが自宅の一部をワークスペースとして使う場合、その家賃・光熱費・通信費を「家事按分」することで必要経費に計上できます。
按分率の決定は「使用面積比×使用時間比」を掛け合わせる方法が一般的で、たとえば自宅60㎡のうち8㎡の書斎を週5日・1日8時間使用する場合、面積比13.3%×時間比33%=約4.4%が按分率となります。
月10万円の家賃なら月4,400円、年間5万2,800円を経費化でき、税率30%なら約1万5,800円の節税効果です。光熱費やネット回線費も同じ按分率で経費化すれば、固定費の一部を事業費として落とせるためキャッシュフローが改善します。
- 按分率の根拠を示すため、部屋の平面図・使用時間記録を保存
- 家族共有スペース(リビング等)は按分対象外にし、税務調査リスクを低減
- 在宅勤務手当を受け取っている場合は、重複計上しないよう注意
- 家事按分は月次で入力し、年度末に実績比率を再計算すると精度が向上
- 電気料金はスマートメーターの時間帯別データで業務使用時間を証明
- クラウド会計にレシートを取り込み、摘要欄に「按分◯%」と明記
大型投資節税戦略3選【高所得者向け】

年収1,000万円超になると、所得税・住民税・社会保険料を合算した実効税率が30〜40%に達し、「控除系の節税だけでは手取りが頭打ち」という壁にぶつかります。
そこで検討したいのが、〈損失計上で課税所得そのものを圧縮〉〈減価償却を活用してキャッシュアウトなしで赤字を作る〉〈法人スキームで税率を頭打ちにする〉といった大型投資型の節税策です。
本章では、高所得者でも比較的少額から始められる「ソーシャルレンディング」、即時償却を狙える「太陽光発電投資」、そして総合的な税率コントロールに威力を発揮する「資産管理会社」の3本柱を取り上げます。
どの手法も一定のリスクと専門知識が必要ですが、適切なデューデリジェンスと資金計画を組めば、キャッシュフローを確保しながら年間の税負担を二桁%単位で削減することが可能です。以下で仕組み・メリット・注意点を順番に押さえていきましょう。
ソーシャルレンディングで雑所得を分散させる方法
ソーシャルレンディング(融資型クラウドファンディング)は、インターネットを通じて匿名組合出資で不動産開発や事業資金を貸し付け、利息を収益として受け取る投資スキームです。
利息収入は雑所得扱いとなるため、同じ雑所得区分の赤字(例:海外不動産投資の減価償却費、仮想通貨の評価損)と損益通算が可能です。
- 最低投資額1万円程度から始められ、複数案件に分散投資しやすい
- 利回りは年3〜7%が主流、運用期間は6〜36か月と比較的短期
- 匿名組合契約により出資額が有限責任、最悪でも出資元本までで損失が限定
- 貸倒損失が生じた場合は雑所得区分で赤字計上し、他の雑所得と相殺できる
- 毎年20万円以内の雑所得は確定申告不要枠を利用し、課税対象を最適化
- 同一プラットフォームの複数案件は「案件ごと」ではなく「合計」で雑所得を計算
損失リスクは事業者の貸付先審査に依存するため、担保評価が公開されているか、貸付残高・延滞率を定期開示しているか、貸倒補填スキーム(優先劣後出資など)があるかをチェックしましょう。利息収入が安定して発生するため、年間キャッシュフローに潤いを持たせつつ税務上の所得分散が図れます。
太陽光発電投資の即時償却と売電収入の組み合わせ
10kW以上の産業用太陽光発電設備を取得すると、「グリーン投資減税」(即時償却か10%税額控除の選択)が適用されるケースがあります。
即時償却を選ぶと、設備取得価格の100%を初年度に損金算入できるため、巨額の赤字を作り損益通算で税負担を大幅に削減できます。
- 設備価格1,000万円を即時償却→課税所得▲1,000万円、税率40%なら400万円の節税
- 売電単価はFIT制度で20年固定(案件により10〜13円/kWh程度)
- 土地を賃貸借にすると初期投資を抑制でき、利回りを高めやすい
- 設備は減価償却後も売電収入が続くため、税金還付+キャッシュフローの二重メリット
- 発電量シミュレーションは日射量データ×劣化率で保守的に試算
- メンテナンスコスト(年3〜5万円/50kW)とパワコン交換費をCFに織り込む
銀行融資はLTV70%程度までが目安で、利回り(表面10%以上)が出る案件なら自己資金3割で初年度の節税インパクトを最大化できます。即時償却後は償却費がゼロとなるため、売電益への法人税課税を見越して資産管理会社スキームと組み合わせると効果的です。
資産管理会社設立で実効税率を30%台に抑える
個人の最高税率55%(所得税45%+住民税10%)に対し、中小法人の実効税率は約30%。高所得者が不動産や高配当株、太陽光発電を複数保有する場合、資産管理会社(合同会社または株式会社)を設立し、所得を法人に集約するだけで約20%の税率差メリットが得られます。
| 課税主体 | 課税所得1,500万円の税額 | 主なメリット |
|---|---|---|
| 個人 | 約660万円(55%) | 損益通算可、社会保険不要 |
| 法人 | 約450万円(30%) | 税率頭打ち、役員報酬で所得分散 |
- 現物出資で不動産を移管すると、登録免許税・不動産取得税が発生(概ね評価額×0.4〜3%)
- 赤字は10年間繰越控除が可能、黒字期に相殺して税額を平準化
- 役員報酬を家族へ分散→給与所得控除を使い二重節税
- 累進課税を回避し、利益の内部留保で次期投資の自己資金を確保
- 資本金は1,000万円未満に抑え、消費税の免税期間2年を確保
- 設立費用は合同会社で約6万円、税理士顧問料は月1〜2万円が目安
法人化は社会保険加入で手取りが減るデメリットもありますが、所得が安定して1,000万円超となった段階で検討すると、節税効果が社会保険料増を上回るケースが多いです。
設備投資の即時償却と組み合わせれば、法人の黒字を早期に圧縮し、実効税率30%台をキープしやすくなります。
節税プランを成功させる実践ロードマップ

節税対策は「制度を知る」だけでは効果が持続しません。最も重要なのは、年間を通じてキャッシュフローと納税スケジュールを可視化し、毎年発表される税制改正を即座に反映できる運用フローを構築することです。
本章では〈ステップ1:数字の見える化〉と〈ステップ2:制度アップデート〉の二段構えでロードマップを提示します。まず月次ベースで売上・経費・投資額を集計し、予定納税や住民税の納付月をカレンダーに落とし込むことで資金ショートを防ぎます。
次に、税制改正大綱をチェックし専門家からフィードバックを受ける仕組みを整えることで、控除漏れやペナルティを回避しながら節税効果を長期にわたり最大化します。
ロードマップに沿って行動すれば、「気付いたら税金で資金が消えた」という事態を避け、安定した手残りと資産拡大を同時に実現できます。
年間キャッシュフローと納税スケジュールを可視化
キャッシュフローを正確に把握する第一歩は「売上・経費・投資・納税」を一つのシートに集約することです。
クラウド会計ソフトからCSV出力した月次データをスプレッドシートに取り込み、税額計算用の関数を組み込めば自動で納税額が更新されます。以下は最小構成のテンプレート例です。
| シート名 | 入力項目 | 可視化できるKPI |
|---|---|---|
| 月次CF | 売上・経費・ローン返済 | 営業CF・投資CF・余剰資金 |
| 税額試算 | 課税所得・控除額 | 所得税・住民税・事業税 |
| 投資計画 | iDeCo掛金・不動産投資額 | 節税額・利回り・回収期間 |
- 予定納税は6月・11月に自動リマインドを設定し資金を先取り確保
- 住民税の4期分(6・8・10・翌1月)をCFシートに反映し忘れを防止
- 所得が大きく変動する月は「前後3か月平均×90%」で保守的に予算化
- 赤字化した月でも納税資金プールは維持し、キャッシュ不足を回避
- 月末に実績値をインポートし、差異をグラフで色分け
- 金利上昇・空室率上昇など悲観シナリオを別タブで作成し耐性を確認
数字が見える化されると「いつ・いくら投資できるか」「損益通算で還付はどの程度か」が即座に分かり、繰上返済や追加投資の判断を誤りません。
税制改正チェックリストと専門家の活用で継続運用
節税効果を継続させる鍵は「税制改正のキャッチアップ」と「専門家レビュー」の二点です。税制は毎年12月の税制改正大綱で方向性が公表され、翌年の確定申告に直結します。
改正点を見逃すと還付漏れや加算税のリスクが高まるため、チェックリスト方式で運用フローに組み込みましょう。
- 12月:税理士ニュースレターで改正速報を受取り、CFシートの控除・税率セルを仮更新
- 1月:国税庁タックスアンサーの更新を確認し、シートを正式アップデート
- イス・電子帳簿保存法の要件を会計ソフトの設定で再チェック
- 3月:確定申告後、還付額をCFシートに入力し、次年度の投資計画を修正
- 年2回(6月・12月)の定例ミーティングで税理士にシートを共有
- 大型投資を検討する際は、金融機関・FP・不動産会社を交えた三者面談で資金計画を精査
改正内容が複雑な場合は税理士へスポット相談(2~3万円程度)を依頼し、シートの計算式を一緒に確認するとミスを防げます。
また、国税庁の無償ウェビナーや金融機関の税制セミナーを活用すれば、最新情報を無料で取得可能です。チェックリストと専門家レビューを年次ルーチンに組み込むことで、制度変更に左右されない堅牢な節税サイクルを維持できます。
まとめ
本記事では「即効性の高い控除・保険」「確実に家計を守る節約型」「高所得者向けの大型投資」の三層で節税策を整理しました。
まずは掛金全額が控除になるiDeCoや小規模企業共済で土台を固め、余剰資金ができたら築古マンション投資で減価償却と損益通算を狙う流れが王道です。年間キャッシュフロー表と税制改正チェックリストを活用し、今日から実践できる節税ロードマップを完成させましょう。