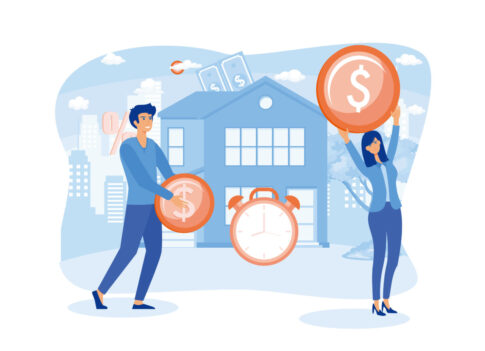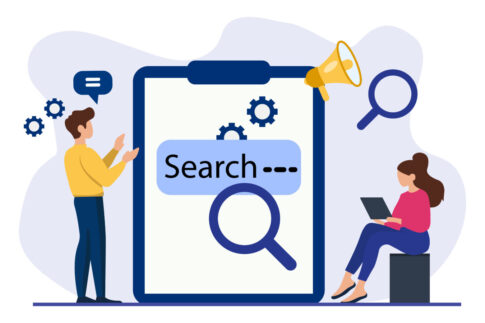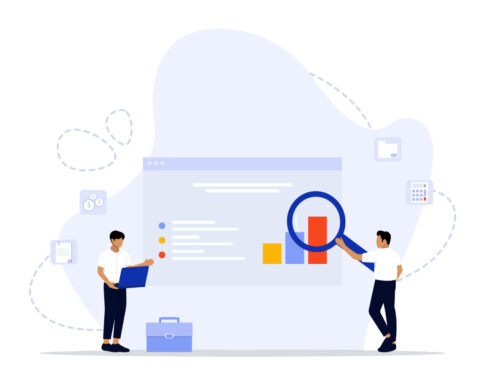「節税 マンション」で検索したあなたへ。減価償却と損益通算を軸に、購入・運用・売却の各フェーズで税負担を最小化する戦略をマップ化しました。
法人設立と相続対策の分岐点も具体例付きで解説。記事を読めば、キャッシュを守りつつ家賃収入を伸ばす実践プランがそのまま手に入ります。
マンション購入前に必ず行う節税設計

マンション投資で得られる節税インパクトの大半は、売買契約を結ぶ前の“設計段階”で決まります。物件を取得した後でも減価償却や経費処理で微調整はできますが、物件タイプ・名義形態・資金配分を誤ると、節税どころかキャッシュフローが赤字に転落しかねません。
はじめに検討すべきは 「個人名義で保有するか、資産管理会社(法人)を設立するか」です。実効税率だけでなく、損益通算の可否・社会保険料負担・手取りキャッシュの動きまでシミュレーションしておくと、将来の資金繰りが明確になります。
次に重要になるのが 売買価格のうち建物割合をどこまで高められるかです。建物割合が大きいほど毎年計上できる減価償却費が厚くなり、損益通算による還付金も増加します。
加えて、取得時の諸費用(仲介手数料・登録免許税・不動産取得税など)は取得価額に含めて減価償却の対象とするため、建物側に配分されるほど早期に費用化できる 点も押さえておきましょう。
最後に自己資金の投入割合を決めます。頭金を厚くすると借入負担は軽くなりますが、減価償却費や利息経費が薄くなり節税余地が縮小します。「諸費用+1年分の返済原資」を最低ラインとし、残りは手元キャッシュとして運転資金や将来の繰上返済に温存するのがセオリーです。
以下の検討フローを使い、ご自身の年収・ライフプランに合った節税シナリオを設計してみてください。
| 検討項目 | ポイント |
|---|---|
| 保有形態 | 個人:赤字を給与所得と損益通算◎/法人:実効税率が約30%で頭打ち・社会保険料負担増 |
| 建物割合 | 築古物件+簡易鑑定で建物50〜60%を目安に設定し、減価償却費を最大化 |
| 諸費用 | 取得価額に組み入れ、建物側へ配分して減価償却を通じて早期回収 |
法人or個人?税率とキャッシュを比較する判断軸
個人名義と法人名義では、適用される税率とキャッシュフローの流れが大きく異なります。個人の場合、所得税は累進課税(5~45%)に住民税10%が加算される一方、損益通算により不動産の赤字を事業所得や給与所得と相殺できます。
法人は実効税率およそ30%前後で頭打ちになり、高所得者ほど税率メリットが出やすい反面、赤字を本業所得と通算できず、社会保険料の加入義務で手取りが下がる点が注意点です。
- 年収900万円以上で黒字化が見込めるなら法人化で税率メリットが大
- 赤字期間に損益通算したい場合は個人名義が有利
- 法人は役員報酬を調整することで所得分散が可能
- 金融機関によっては法人の方が融資枠・期間が伸びる
- 開業3年以内で減価償却費が厚い間→個人名義
- 家賃黒字が安定し所得が増加→法人へ物件売却または現物出資
最終的には「税率差」「社会保険料」「損益通算の可否」「融資条件」の4軸で総合判断し、試算表を2パターン作成して比較するとミスを防げます。
専門家にシミュレーションを依頼する際は、5年後・10年後の黒字転換タイミングを盛り込み、デッドクロス発生年も含めて検討するとより現実的です。
建物割合と残存耐用年数を高める価格交渉テクニック
減価償却費を最大化するカギは「建物割合」と「残存耐用年数」の2点です。売買契約書の内訳で建物価格を高められれば、それだけ毎年計上できる減価償却費が増え、課税所得を圧縮できます。
また、築古物件ほど残存耐用年数が短くなり、短期間で大量の償却費を計上できるため節税スピードが加速します。
- 固定資産税評価額を根拠にしつつ、仲介会社へ建物割合60%以上を打診
- 補強工事やリフォーム履歴があると建物価値の根拠が示しやすい
- 築25年以上の木造、築47年以上のRCを狙うと耐用年数が4〜10年に短縮
- 価格交渉の際は「法定耐用年数内の融資期間延長可否」も同時に確認
- 鑑定士の簡易評価書を添付して売主に提示
- 減価償却メリットを説明し“価格据え置きで建物割合増”を提案
交渉が難航した場合でも、別途「資産総合評価書」を作成して金融機関へ建物割合の妥当性を説明すれば、融資審査でネガティブになりにくくなります。
耐用年数と融資期間のバランスが取れれば、キャッシュフローと節税効果を両立する理想的なスタートが切れます。
諸費用一括計上と自己資金配分でスタートダッシュ
物件取得時に発生する仲介手数料・登記費用・不動産取得税・印紙税などの諸費用は、取得年に一括で必要経費に計上できます。
これにより初年度から大きな赤字を作り損益通算で還付金を得る“スタートダッシュ”が可能です。さらに自己資金の投入割合を調整してローン元本返済額を抑えれば、キャッシュフローを確保しつつ繰上返済の余力も残せます。
- 諸費用は物件価格の7〜10%が目安:例)1,500万円物件なら約120万円
- 自己資金は「諸費用+1年分の返済原資」を基本ラインに設定
- 頭金を減らし現金を温存→減価償却費&経費で赤字拡大→還付金増
- 繰上返済は減価償却切れ前に集中的に行いデッドクロス回避
- 頭金10%+諸費用でローン比率を高め節税効果優先
- キャッシュリザーブは家賃収入の6か月分を確保
取得年に還付金を受け取れれば、その資金をリフォーム費用や追加投資の頭金に充当できます。確定申告後の還付スケジュール(3月中旬〜5月初旬)を逆算し、資金繰り表に組み込んでおくことで、初年度から手残りと節税の両方を体感できる投資サイクルが実現します。
保有期間に効くキャッシュフロー型節税術

マンション投資で節税効果を継続させるには、保有期間中に「帳簿上の赤字を維持しつつ現金収支を黒字化」する仕組みづくりが欠かせません。
具体的には〈減価償却で作る赤字〉〈修繕・リフォーム費の即時償却〉〈管理委託や家事按分による経費最適化〉という三本柱を組み合わせ、毎年の課税所得をコントロールします。
これらを実行すれば所得税・住民税を圧縮しながら家賃収入を手取りとして確保できるため、キャッシュフローが安定し追加投資や繰上返済の余力が生まれます。
以下では各テクニックの仕組みと実践手順を詳しく解説し、保有期間中に発生しがちな「デッドクロス」「修繕費増」「税務調査リスク」を回避しつつ、長期的に節税メリットを最大化する方法を紹介します。
減価償却フェーズで赤字を作り損益通算する方法
減価償却フェーズとは、購入後に厚い減価償却費を計上できる期間を指します。築古物件を選ぶと残存耐用年数が短くなり、年間の償却費が増えるため帳簿上の赤字を作りやすくなります。
この赤字は確定申告で事業所得や給与所得と損益通算でき、源泉徴収された所得税・住民税の一部が還付される仕組みです。
- 築25年以上の木造、築30年以上のRC物件は残存年数4〜10年で償却ペースが速い
- 建物比率60%以上を確保すると償却費が増え赤字幅が拡大
- 青色申告なら最大65万円控除も合算でき赤字効果がさらに大
- 給与所得と相殺する場合、源泉徴収票をもとに赤字額を調整
- 赤字を出し過ぎると金融機関審査で不利になるため黒字化タイミングを計画
減価償却費が尽きるとデッドクロス(税額増+返済負担)が顕在化します。対策として、償却終了年の2年前から繰上返済や新規物件購入を検討し、再度償却費を計上して税負担を平準化すると安全です。
修繕・リフォーム費の即時償却と資本的支出の見極め
修繕費は「修繕費として即時に経費化できる支出」と「資本的支出として減価償却する支出」に分けられます。区分マンションの室内リフォームや軽微な外壁補修は修繕費として一括経費計上できるため、課税所得を圧縮する強力な手段です。
- 修繕費判定の目安:①支出額が20万円未満 ②効果が3年未満 ③原状回復目的
- 資本的支出となる例:間取り変更、耐震補強、エレベーター新設など
- 資本的支出は法定耐用年数または残存耐用年数で再償却
- 大規模修繕前に「工事内訳書」を管理組合から取得し経費区分を事前確認
- 30万円未満の部材交換は「少額減価償却資産の特例」も活用
- 税務調査に備え領収書・写真・工事契約書をクラウドに保存
修繕費の計上タイミングはキャッシュフローと税額に直結します。減価償却が薄くなる年に合わせてリフォームを実施し、一括経費化で赤字幅を維持すれば、還付金を得つつ物件価値も向上させる好循環が作れます。
管理委託・家事按分を駆使した経費計上の最適化
毎年発生する経費は「漏れなく、適切な根拠で」計上することで節税効果が安定します。まず管理委託料は家賃の5〜8%が相場で、外注費として全額経費化できます。
さらに自宅兼事務所を使って物件管理や確定申告を行う場合、家賃・光熱費・通信費を家事按分して必要経費とすることが可能です。
- 管理会社選定時に「空室期間」「原状回復費の上限」「家賃保証条件」を数値で比較
- 家事按分率の例:専有面積×使用時間→家賃30%、光熱費20%、通信費70%
- スマホ料金やサブスクも業務利用割合を示せば按分可能
- クラウド会計で領収書を撮影・添付し、按分根拠をメモに残す
- 火災・地震保険料の一括払いを年払いで経費化
- 移動交通費はICカード連携アプリで自動仕訳
経費計上は税務調査で否認されると追徴課税リスクがあるため、事業関連性を示す証憑と合理的な按分根拠が必須です。月次で経費を入力し、年末にロジックを再確認することで、節税効果を保ちつつ監査リスクを最小限に抑えられます。
売却・相続フェーズの税率差逆転シナリオ

減価償却で節税してきたマンション投資も、出口戦略を誤れば「譲渡所得税や相続税で結局多く払った」という逆転現象が起こります。
そこで重要になるのが〈長期譲渡税率への持ち越し〉〈相続評価の圧縮〉〈デッドクロス後の法人移管・M&A売却〉という三つの切り札です。所有期間を5年超に伸ばすだけで譲渡税率は約39%→約20%に半減し、さらに買換えや交換の特例を活用すれば課税を翌世代へ先送りできます。
相続局面では、区分マンションなら固定資産税評価額と路線価評価を組み合わせることで実勢価格より2〜3割低い評価額に抑えられ、相続税を圧縮しながら賃貸収入を次世代に引き継げます。
また、減価償却が切れて税負担が増えるデッドクロス期には、法人へ現物出資して損益通算の制限を回避しつつM&A売却で譲渡益を低税率で受取る選択肢も有効です。これらの「税率差逆転シナリオ」を計画的に仕込むことで、売却・相続フェーズでもキャッシュを守りつつ手残りを最大化できます。
長期譲渡税率への持ち越しと買換え特例の活用
譲渡所得税は「所有期間5年以下=短期」「5年超=長期」で税率が大きく異なります。短期譲渡は39.63%(所得税30%+住民税9%+復興特別所得税)、長期譲渡は20.315%と半分以下です。
したがって、売却益が見込める物件は取得後6年目以降に売却すると税負担を一気に減らせます。
- 取得日ではなく「取得した年の翌年1月1日」からカウントする点に注意
- 交換特例(同一価値の物件同士を入替)を使えば課税を将来に繰延べ
- 自宅を投資用に転用した場合は「居住用3,000万円控除」の適用可否を確認
- 譲渡益×19.315%が運用益を超えるなら持ち越しメリット大
- 賃料下落・空室増が税負担を上回る場合は早期売却を検討
区分マンションで相続評価を3割下げるスキーム
相続税の課税評価額は、土地が路線価、建物が固定資産税評価額をベースに算出されます。区分マンションの場合、さらに「借家権控除(30%)」と「小規模宅地等の特例(200㎡まで50%減)」が組み合わさるため、実勢価格より約3割低い評価額で計算されるケースが一般的です。
| 評価過程 | 土地 | 建物 |
|---|---|---|
| 基本評価 | 路線価×面積 | 固定資産税評価額 |
| 控除適用 | 借地権割合/借家権割合控除 | 借家権30%控除 |
| 小規模宅地 | 200㎡まで▲50% | 対象外 |
- 被相続人が賃貸中なら借家権控除がフルに効き評価が大幅圧縮
- 複数戸に分散保有すると1戸あたり評価が小さく分割もしやすい
- 相続開始3年以内の生前贈与は持ち戻し課税の対象なのでタイミングに注意
- 暦年贈与(110万円非課税)を活用し持分を計画的に移転すると負担が平準化
- 固定資産税評価額の再鑑定で建物評価をさらに引下げ
- 借家権控除が適用されるよう客付けを維持し空室期間を最小化
相続が発生した後は「延納・物納」「物件売却」の二択しか残らないため、評価額を下げておくほど納税原資を確保しやすく、遺産分割協議もスムーズになります。
デッドクロス後に法人移管・M&A売却を選択する判断基準
減価償却が終了しキャッシュフローは黒字でも税負担が急増するデッドクロス期には、個人名義のまま保有し続けると実効税率が上がり手残りが減る一方です。
この段階で有効なのが「資産管理会社への現物出資(法人移管)」と「M&Aプラットフォームでの物件パッケージ売却」です。
- 法人移管:簿価で出資すれば移転税は登録免許税・不動産取得税が最小限(※)
- 株式譲渡益=20.315%課税で頭打ち、個人の所得税45%との差が大
- M&A売却:空室率改善やリノベ実績を強みに、利回り・借入条件込みで高値成約
- 金融機関のローン付替え承諾を取れるかが売却可否のカギ
(※新設法人で株式90%保有」など限定要件を満たすケースのみ)
- 実効税率が30%を超えたら法人移管を検討
- 返済比率が下がりキャップレートが改善した時点でM&A売却
法人移管後は役員報酬で所得分散できるほか、将来の相続対策として株式の贈与や持株会社化も視野に入ります。一方、M&A売却は譲渡益課税が確定するため、長期譲渡税率への持ち越しや他物件の譲渡損と通算するタイミングを合わせ、税負担を最小化するスケジューリングが重要です。
実例で学ぶ実践ポイント

節税設計やキャッシュフロー管理の理論を理解しても、実際にどの程度の効果が得られるのかを数字で把握しなければ行動には移しづらいものです。そこで本章では、年収帯別に代表的な投資シナリオを組み立て、〈節税額〉〈家賃キャッシュ〉〈デッドクロス対策〉を可視化します。
まず課税所得900万円超の高所得フリーランスが築古区分マンションを購入して50万円の税還付と年間家賃黒字を確保した事例を紹介。
続いて購入から5年後のキャッシュフロー推移をシミュレーション表で示し、減価償却切れ前に繰上返済や追加投資をどう判断するかを具体的に示します。
最後に、毎年の税制改正やインボイス制度への対応を運用手順として組み込み、知識をアップデートしながら節税サイクルを継続する方法を解説します。
課税所得900万円超の事例―年50万円節税と家賃黒字化
フリーランスエンジニアのBさん(課税所得920万円・税率33%)は、築28年RC区分マンション(購入1,500万円、建物比率65%)をフルローン(金利2.0%、期間20年)で取得しました。残存耐用年数は10年となり、年間97.5万円の減価償却費を計上できます。
- 家賃収入:月9万円→年間108万円
- 経費:管理費15万円+修繕積立金8万円+金利28万円=51万円
- 帳簿上の損益:108万円−51万円−97.5万円=▲40.5万円
【節税効果】
- 損益通算で所得920万円→879.5万円に圧縮
- 所得税:▲13.4万円/住民税:▲4.0万円
→税還付合計≒17.4万円 - 青色65万円控除で追加▲21.5万円(税額換算約7.1万円)
- 諸費用一括経費115万円が加わり初年度▲50万円還付
- 建物比率65%で償却費を最大化
- 還付金をローン元本に充当し実質利回りアップ
現金ベースでは家賃手残り57万円(108−51)と還付50万円で計107万円のプラス。ローン元本返済78万円を差し引いても29万円の黒字となり、購入初年度でキャッシュフローと節税の両方を実感できました。
5年後キャッシュフローを可視化するシミュレーション表
購入後5年間のキャッシュフロー推移を把握すると、減価償却が続く期間にどれだけ資金を蓄えられるかが明確になります。下表は家賃下落年1%、空室率5%、修繕費比率年5%の前提で作成したシミュレーション例です。
| 年度 | 税引前CF(万円) | 税還付後CF(万円) |
|---|---|---|
| 1年目 | 57 | 107 |
| 2年目 | 55 | 91 |
| 3年目 | 53 | 74 |
| 4年目 | 51 | 63 |
| 5年目 | 49 | 54 |
【チェックポイント】
- 5年間の累計税還付=169万円、キャッシュ総額=389万円
- 繰上返済:3年目に100万円、5年目に80万円で総返済期間−1.5年
- 修繕積立金増額前(6年目)に追加購入資金150万円を確保
- 年間CFが40万円を切ったタイミングで追加投資か売却を再検討
- 金利上昇1%シナリオも別タブで算出しリスク耐性を確認
Excelやクラウド財務ツールに上記ロジックを組み込み、毎年の実績値を入力して差異分析を行えば、投資判断のタイミングを逃さずに済みます。
税制改正・インボイス対応を毎年更新する運用手順
大きな節税効果を維持するには、税制改正やインボイス制度の変更点を毎年チェックし、帳簿や申告手続きをアップデートする必要があります。
- 12月:税制改正大綱を税理士ニュースレターで確認し、減価償却・損益通算の制限や延長の有無をチェック
- 1月:クラウド会計ソフトのアップデートを適用し、新控除や記帳要件を反映
- 2月:インボイスの経過措置(2割特例・簡易課税選択期限)を再確認
- 3月:確定申告完了後に還付予定額をCF表へ入力し、翌年度の投資・繰上返済計画を修正
- 四半期ごとに家賃下落率・空室率・修繕費を実績更新
- 半期ごとに税理士へCF表を共有し節税シナリオを再評価
インボイス制度の追加負担が見込まれる場合は、課税事業者選択届出書の撤回や簡易課税制度への切替を検討し、最も手残りが多い方法を選択しましょう。
これらの運用手順を「カレンダー+チェックリスト+専門家レビュー」で固定化すれば、制度変更に振り回されることなく長期的に節税サイクルを継続できます。
まとめ
マンション投資の節税効果は、購入前の設計・運用中の経費最適化・売却時の税率コントロールで最大化できます。
本記事のチェックリストとシミュレーションを活用すれば、減価償却で赤字を作り損益通算で還付を受け、最終的に譲渡益も守れる三段階の節税フローが完成。今すぐ試算表を作成し、専門家と連携して行動に移しましょう。