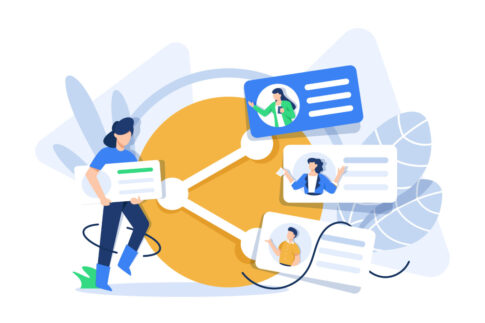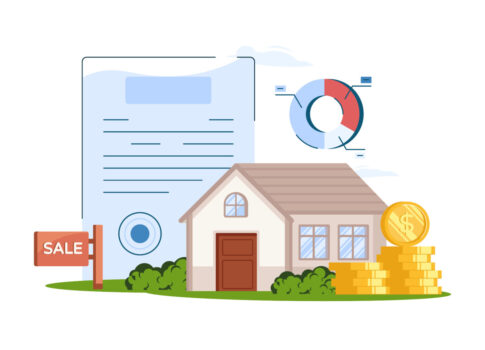個人名義で賃貸物件を保有すると、最高税率55%の総合課税が利益を圧迫しがちです。法人化すれば実効税率が約30%へ下がり、減価償却や役員報酬など経費枠も拡大できます。
本記事では「税率シミュレーション」「設立手順」「銀行評価アップ術」など高所得者が押さえるべき5大ポイントを体系的に解説。最短ルートで合法的な節税と資産拡大を実現するヒントを提供します。
目次
法人化で得られる節税メリットとデメリット

個人で不動産所得が増えると、累進課税により最高55%の税率が適用される可能性があります。一方、資産管理会社を設立すれば実効税率はおおむね30%前後に抑えられ、役員報酬や退職金、家族への給与などを経費として計上できる点が大きなメリットとされています。
さらに法人は交際費や会議費の幅が広く、損失を10年間繰り越せるため、中長期でのキャッシュフロー安定に役立ちます。
ただし、設立費用(約25〜30万円)や毎期の会計・税務顧問費用(年間20〜40万円)が発生し、社会保険への強制加入で人件費負担が増える点はデメリットです。また、法人から個人へ配当を出すと二重課税が生じるため、出口戦略も事前に検討する必要があります。
- 税率低減→実効約30%で一定
- 経費計上→役員報酬・減価償却を柔軟に設定
- 損失繰越→最長10年間控除可能
- 設立コスト→登録免許税・定款認証など発生
- 社会保険→法人役員は原則加入義務
- 課税所得900万円超・物件3棟以上で法人化を検討
- 配当より役員報酬で資金を抜くと二重課税を回避可能
法人税率vs所得税率シミュレーション
法人化を検討する際は、個人と法人で同じ手残りがいくらになるかを数値で比較することが重要です。以下は課税所得1,200万円のケースを想定し、「個人名義で賃貸経営」「法人で役員報酬600万円+利益留保600万円」を比較した概算シミュレーションです。
| 区分 | 税負担 | 手残り |
|---|---|---|
| 個人(総合課税) | 所得税・住民税 約490万円 | 約710万円 |
| 法人+役員報酬 | 法人税等 約1800万円 役員報酬の所得税等 約120万円 |
約900万円 |
結果として、同じ1,200万円の利益でも法人スキームでは約190万円の手残り増となる計算です。なお、法人は交際費800万円まで損金算入、10年間の欠損金繰越、退職金控除など追加の節税余地があります。
一方、赤字転落時でも法人は均等割(7〜21万円)の住民税が発生するほか、役員報酬を高く設定しすぎると社会保険料負担が膨らむ点に注意が必要です。
- 役員報酬は期首に決定→途中変更は原則不可
- 借入金利が個人より高くなるケースを加味
経費・減価償却・損失繰越の拡大
法人化のもう一つの強みは「経費計上の自由度」と「税務上の損失コントロール幅」が大きく広がる点です。個人の不動産所得は必要経費が家事関連費とされやすく、交際費や自家用車費用は按分が厳格になります。
これに対し法人の場合、事業遂行に合理性があれば役員車両や法人カードの出張費、取引先との会食費も経費化しやすいとされています。
- 減価償却の自由度
減価償却方法は資産区分ごとに法令で定められており、個人・法人で原則が異なるわけではありません。 - 損失繰越期間
・個人:3年
・法人:10年(中小法人等は所得金額の範囲内で100%まで控除可。 - 退職金計上
・法人役員なら退職所得控除適用→勤続20年超で年40万円控除
- 役員社宅:賃料の50%程度を経費計上
- 役員旅行:4泊5日以内・業務目的なら福利厚生費
- 管理会社への外注費:家族を従業員登録し給与分散
法人化の判断基準とタイミング

不動産を法人化するかどうかは「節税メリットが設立・維持コストを上回るか」で判断するのが基本です。
具体的には、個人の課税所得が累進課税の高税率帯(900万円超)に達している、物件数や家賃収入が増え減価償却・経費枠を拡大したい、将来の相続・事業承継対策を前倒ししたい─といった条件がそろうと法人化の効果が高いとされています。
さらに、金融機関の融資姿勢が法人名義のほうが有利な局面や、赤字繰越を10年間活用して新築・リノベ投資を計画的に行う場合もタイミングの好機です。
設立時期は〈決算月を3月→繁忙期を避ける〉〈保有期間5年経過後→長期譲渡特例を使い切る〉など、既存資産の評価と税務スケジュールを照らし合わせて決める方法が推奨されています。
- 高税率帯に突入→法人税率へシフト
- 物件3棟・家賃年1,000万円超→経費枠拡大
- 相続対策→株式評価で贈与税を圧縮
- 融資戦略→法人名義で追加枠を確保
- キャッシュフロー試算→手残りが増えるか確認
- 設立・維持コストを算定→損益分岐を把握
- 税理士と設立時期を逆算→特例適用と年度繰越を最適化
課税所得900万円超が目安?
個人所得税は課税所得が695万円を超えると33%、900万円を超えると43%、1,800万円超で50%(復興税含む)と急激に負担が上がります。
一方、中小法人の実効税率は800万円以下19%前後、800万円超でも30%前後にとどまるため、個人課税所得が900万円を超えた頃が法人化の損益分岐点とされています。ただし「役員報酬−社会保険料−所得税」の三重負担を考慮し、以下のように比較するのが実務的です。
| 課税所得 | 個人実効税率→法人実効税率 |
|---|---|
| 〜600万円 | 23%前後 → 19%(差4%) |
| 600〜900万円 | 33%前後 → 24%(差9%) |
| 900〜1,800万円 | 43〜50% → 30%(差13〜20%) |
【判断ポイント】
- 家族を役員にして役員報酬を分散→超過累進を回避
- 退職金枠を確保→長期的な所得分散に寄与
- 均等割・顧問料の固定コスト→税効果を相殺しないか確認
- 役員報酬は毎期固定→赤字でも支払いが発生
- 役員報酬を高く設定し過ぎると社会保険料が急増
資産規模別キャッシュフローシナリオ
法人化の効果は物件数・家賃収入・借入金残高によっても変化します。以下は〈木造アパート×2棟(家賃年1,200万円)〉と〈RCマンション×1棟(家賃年3,600万円)〉の2モデルで、法人化前後の年間キャッシュフローを比較したシナリオです。
| モデル | 個人手残り | 法人手残り |
|---|---|---|
| A:小規模 | 約720万円 | 約850万円 |
| B:大型 | 約1,620万円 | 約1,950万円 |
モデルAでは手残り130万円の差にとどまる一方、モデルBでは330万円の差が生じ、規模が大きいほど法人化メリットが拡大する傾向がみてとれます。
さらに法人は10年間の欠損金繰越を利用して大規模修繕の年に赤字を繰り越し、翌年以降の黒字と相殺することで税負担を平準化できる可能性があります。
- 規模が小さい場合→顧問料・均等割の固定費が重くなる
- 大型物件→減価償却を定率法で前倒し→初年度税負担を圧縮
- 借入金比率が高い→法人名義で長期固定金利へ借換え→金利上昇リスクをヘッジ
- 収支計画は5〜10年の長期で作成→大規模修繕を含める
- 繰越欠損を活用→修繕費・塗装費の年度をコントロール
- 金融機関の法人評価→自己資本比率とDSCRを重視
法人化スキームと設立手順
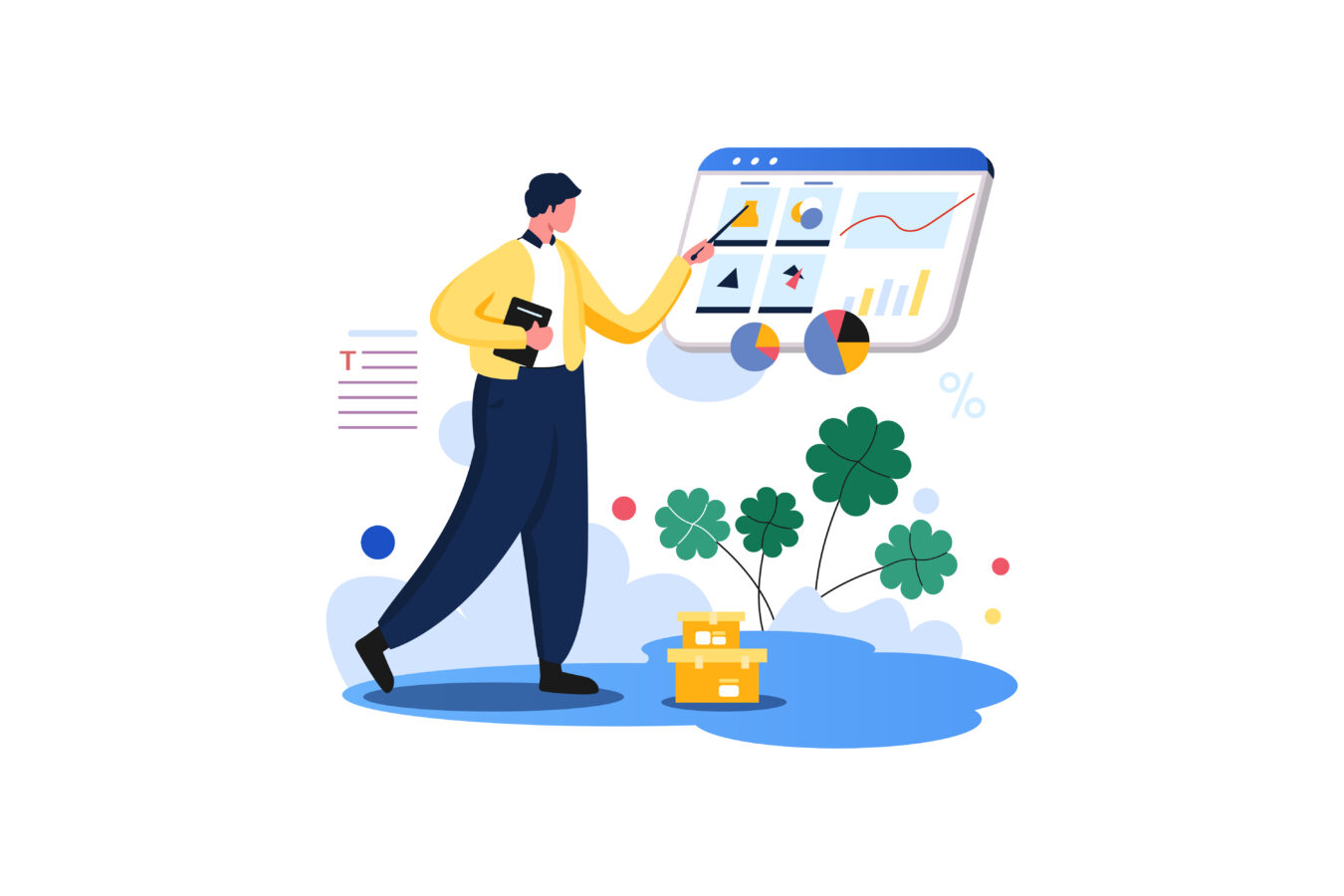
不動産投資を法人化する場合、大きく分けて〈資産移転方式〉と〈新規取得方式〉の二通りがあります。既存物件を法人へ売却または現物出資する資産移転方式は、譲渡所得税や登録免許税が発生する一方で、減価償却を新たに取り直せるメリットがあります。
新規取得方式は、今後の物件をすべて法人名義で購入するシンプルな仕組みですが、個人に残る物件と法人保有物件が混在するため、経費按分や資金移動の管理が複雑になる可能性があります。
どちらの方式でも〈設立コスト〉〈毎期の顧問料〉〈社会保険加入義務〉といった固定費が増える点を踏まえ、キャッシュフロー効果を10年スパンで試算することが推奨されています。
タイミングとしては、長期譲渡特例を使い切った翌期や大規模修繕の前年度など、税負担と資金需要が同時に高まる前に設立すると効果が高まるとされています。
- 資産移転方式→譲渡益課税のリスクを逆算
- 新規取得方式→既存ローンの個人保証に注意
- 設立タイミング→長期譲渡特例後・修繕前が好機
- 税理士と事前シミュレーション→最適方式を選定
- 設立日と決算月を確定→税務メリットが最大化
- 金融機関へ法人スキームを共有→融資姿勢を確認
不動産所有方式と管理委託方式
法人スキームには〈所有方式〉と〈管理委託方式〉があります。所有方式は法人が物件の登記名義と借入を引き受け、賃料も法人収入として計上するスタンダードな形です。
税務上のメリットは大きいものの、個人側で長期譲渡特例を使った売却が難しくなり、金融機関も追加担保を求める傾向があるとされています。
一方、管理委託方式は物件名義を個人に残し、家賃収入を管理料として法人に移転する仕組みで、所有権移転に伴う登録免許税や不動産取得税を回避できるのが特徴です。ただし、管理料率が高すぎると税務調査で否認されるリスクがあるため、〈市場相当の5〜10%〉程度に設定するのが一般的とされています。
| 項目 | 所有方式 | 管理委託方式 |
|---|---|---|
| 登記名義 | 法人 | 個人 |
| 資金調達 | 法人名義の融資 | 個人ローン継続 |
| 主なメリット | 減価償却を再取得 法人税率で課税 |
移転税が不要 長期譲渡特例を維持 |
| 主な注意点 | 譲渡所得税が発生 | 管理料率の妥当性 |
- 所有方式→売買契約書や評価額の整合性を確認
- 管理委託方式→実質負担が法人へ移転したことを示す証憑が必要
設立費用・登記・税務手続き
株式会社を設立する場合、定款認証料約5万円、登録免許税15万円(資本金200万円以下なら15万円が下限)、司法書士報酬10万〜15万円が初期コストの目安とされています。
合同会社(LLC)なら定款認証が不要なため5万円程度安く抑えられますが、金融機関によっては評価が低い可能性があります。
設立後は税務署・都道府県税事務所・市区町村役場への各種届出(法人設立届、青色申告承認申請、給与支払事務所等の開設届など)を2か月以内に提出する必要があります。
また、社会保険(厚生年金・健康保険)は設立後5日以内に加入手続きを行い、役員報酬の支給開始前に標準報酬月額を決定する流れです。
- 会社設立の流れ
- 商号・事業目的・資本金を決定
- 定款作成→公証役場で認証(合同会社は不要)
- 出資金払込→金融機関の払込証明取得
- 登記申請→法務局へオンラインまたは書面
- 税務手続き
- 法人設立届出書
- 青色申告の承認申請書
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
- 社会保険・労働保険
- 健康保険・厚生年金保険新規適用届
- 雇用保険適用事業所設置届(従業員雇用時)
- 定款は電子認証→印紙4万円が不要
- オンライン登記→登記完了まで最短3〜4日
- 税務届出はe-Tax→控え保存と二重提出防止
資金調達と銀行評価を高めるコツ

法人化後に安定的な拡大戦略を描くには、銀行からの評価を高めつつ低コストで資金を調達する仕組みづくりが欠かせません。
金融機関が最も重視するのは〈返済能力=キャッシュフロー〉と〈担保・保証〉ですが、法人ならではの財務指標――自己資本比率やDSCR(元利金返済余裕率)、さらには役員報酬の水準までも審査材料となります。
特に不動産投資法人の場合、物件の収益性だけでなく決算書の透明性や税務申告の正確性が直接スコア化される傾向があり、これらを高水準で保つことが追加融資枠の拡大に直結します。
また、金融庁のガイドラインでは「地域企業との長期的取引を支援する姿勢」が求められており、中小法人でも事業計画書を整備し実行管理を徹底することで、金利引下げや長期固定化といった優遇を受けられる可能性があります。
- 決算書→2期連続黒字・自己資本比率20%超が目安
- 事業計画→5年間の収支・返済計画・修繕予定を記載
- 銀行交渉→決算報告面談でIRR・DSCRを数値で説明
- 期中試算表を毎月提出→情報開示で信頼を獲得
- 物件別損益を開示→ポートフォリオ健全性を示す
- 代表者保証ガイドラインを活用→保証リスクを軽減
法人名義融資と保証人問題
法人で融資を受ける場合、金融機関は通常〈法人〉と〈代表者個人〉双方への保証を求めるとされています。
しかし、2023年の「経営者保証に関するガイドライン」改訂により、①財務指標が一定基準を満たす、②事業計画の信頼性が高い、③法人と経営者の資産分離が明確──のいずれかを満たせば、個人保証の解除や軽減が認められる可能性があります。
| 解除要件 | ポイント |
|---|---|
| 財務基準 | 自己資本比率30%以上または負債比率100%未満 |
| 事業計画 | 5か年計画で営業CFが元利返済額の1.5倍以上 |
| 資産分離 | 経営者と法人資産が明確に区分されている |
保証を外す交渉では、まず決算書の信頼性を担保するため税理士の「試算表レビュー報告書」や「記帳代行契約書」を提示し、次に不動産評価書・レントロールを添付した返済計画を提出します。
金利については、公的制度融資(保証協会付き)を卒業し、プロパー融資へ切り替えるタイミングで0.3〜0.5%程度下がるケースが多いとされています。
- 保証解除は一括でなく段階的→まずは債務残高の50%保証に縮小
- 金融機関を分散→メイン行と競合行で条件を比較
役員報酬設計と信用改善
役員報酬は「節税」と「銀行評価」のバランスを取る重要なパラメータです。報酬を低く設定すると法人の利益が増え税率メリットが薄れますが、逆に高くしすぎると社会保険料負担が重くなり、融資審査で「実質キャッシュフローが不足」と判断される可能性があります。実務では次の三段活用が推奨されています。
- 基本報酬:金融機関が可処分所得を評価できる水準(年360万〜600万円)
- 賞与ゼロ:不動産法人は定期同額給与が原則→賞与分は配当や退職金で調整
- 退職金枠:役員退職金規程を整備し、勤続20年超で年40万円×勤続年数+800万円控除
また、代表者個人の信用情報を改善するために、役員報酬を住宅ローン返済比率25%以内に抑え、クレジットカード残高をゼロにするなど「個人保証を外す前提条件」を整えることが重要です。
- 社会保険料→会社負担+個人負担で約30%
- 退職金積立→損金算入で法人税を圧縮
- 配当→二重課税を考慮し少額に留める
- 役員報酬÷売上高=15〜20%を目安に設定
- 期首に報酬額を決定→中途変更は臨時改定事由が必要
- 役員社宅制度で手取り増→経費と現物給与の最適化
法人化後の税務管理とシミュレーション事例

法人を設立した後は、毎期の決算・申告の正確さと資金繰りの見える化が節税効果を左右します。決算期までに領収書を整理し、月次試算表を基に納税額を早期把握していれば、役員報酬や減価償却方法の変更など年度内に打てる調整策が増えます。
さらに、銀行との定期面談でキャッシュフロー計画と修繕積立の進捗を共有すれば、追加融資時の金利や担保条件も優遇される可能性があります。
また税務調査は通知から1〜2か月後が実地とされますが、法人の場合は帳簿保存義務が7年と長く、会計ソフトでの電子帳簿保存に対応していないとペナルティが課される場合があります。
法人化直後から「証憑を電子化→クラウド共有→税理士と毎月レビュー」というサイクルを確立することで、調査リスクの低減と経営判断の迅速化を同時に図ることが望ましいです。
- 月次試算表を10日以内に作成→納税見積もりの精度向上
- 電子帳簿保存法に対応→ペーパーレスで保管コスト削減
- 四半期ごとに税理士面談→節税余地を即時反映
- クラウド会計:自動仕訳で経費漏れを防止
- ワークフロー:承認履歴を残し調査対応を簡素化
決算・申告フローと税務調査対策
決算作業は「前処理→試算表確定→税額計算→申告書作成→納税」の5段階です。まず期末2か月前までに棚卸・減価償却資産の一覧を確定し、役員報酬と経費見込みを調整します。
次に期末後1か月以内に試算表を確定させ、法人税・地方法人税・事業税・住民税の合計を早期に把握します。そのうえで節税余地が残る場合は、倒産防止共済や小規模企業共済の掛金前払いで損金を積み増し、納税額の平準化を図る方法があります。
申告期限は決算日の翌日から原則2か月以内ですが、e-Taxで申告すれば法人税はペーパーレスで納付でき、付帯税計算もソフトが自動処理します。
税務調査は「無予告型」と「事前通知型」に大別されますが、法人の大半は事前通知型で、調査対象年度と調査項目が通達されます。
調査官は帳簿と証憑の突合を重視するため、電子帳簿保存法に沿ったスキャナ保存やPDF保存が有効です。また、調査官との面談前に税理士がロープレを行い、想定質問と回答を整理しておくと修正申告や追徴課税のリスクが低減するとされています。
- 決算2か月前→棚卸・減価償却資産を確認
- 決算後1か月→試算表確定・税額概算
- 決算後2か月→申告書提出・電子納税
- 調査通知→質問事項整理・証憑整理
- 調査当日→帳簿説明・是認狙いの対応
- 電子保存要件を満たす→タイムスタンプ・検索機能を整備
- 社内ルールを文書化→調査官へ業務フローを提示
- 是認率の高い税理士を選任→交渉力を強化
法人化前後の税負担比較ケース
以下は「家賃収入3,600万円・経費1,200万円・借入金利1.5%・減価償却500万円」のRCマンションを保有するケースで、個人と法人の税負担を比較したシミュレーション例です。
| 区分 | 税額内訳 | 年間手残り |
|---|---|---|
| 個人保有 | 所得税・住民税:約920万円 | 約980万円 |
| 法人保有(役員報酬600万円) | 法人税等:約350万円 役員報酬の所得税等:約120万円 |
約1,430万円 |
| 法人保有(役員報酬300万円+退職金積立200万円) | 法人税等:約420万円 役員報酬の所得税等:約60万円 |
約1,520万円 |
個人保有に比べ、法人化+役員報酬600万円の場合で年間手残りは約450万円、役員報酬を抑え退職金積立へ振り分けると約540万円の増加が見込まれる試算です。
さらに、法人では10年間の赤字繰越を使いながら大規模修繕を実施し、その年の損失を翌年の黒字と相殺することで税負担をゼロに抑えることも可能とされています。
- 役員報酬を抑える→社会保険料減・退職金控除へシフト
- 赤字繰越で修繕費を平準化→キャッシュアウトの波を緩和
- 減価償却を定率法→前倒しで損金を計上し銀行返済能力を向上
- 個人・法人の3期分キャッシュフローを作成
- 役員報酬・退職金・配当を変数にして感度分析
- 金利上昇や空室率悪化をリスクシナリオで設定
まとめ
不動産の法人化は〈税率低減〉〈経費拡大〉〈資産承継の円滑化〉という三大メリットを同時に狙える一方、設立費用や事務負担が増える点に留意が必要です。
課税所得900万円超・保有物件3棟以上が一つの目安とされ、売却益や融資枠の将来計画を含めたシミュレーションが必須です。本記事で示した判断基準と手順を活用し、税理士と連携して最適なタイミングで法人化を進めましょう。