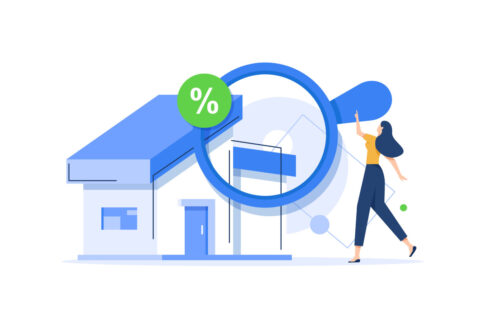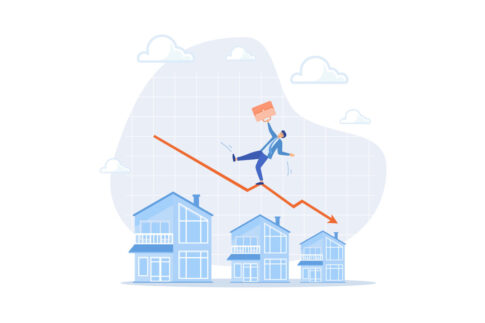この記事では、不動産投資で失敗を防ぐために重要な「リスクヘッジ」に焦点を当て、代表的なリスク要因から安全対策の具体例までを解説していきます。
資金計画や物件選び、さらには複数物件を組み合わせるなど、多彩な手法を組み合わせることでリスクを低減し、安定した収益をめざすことが可能になります。初心者でも気軽に取り入れられるポイントを踏まえながら、投資全体の成果を大きく伸ばすためのヒントを紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください。
目次
リスクヘッジの基本を押さえて不動産投資を成功させよう
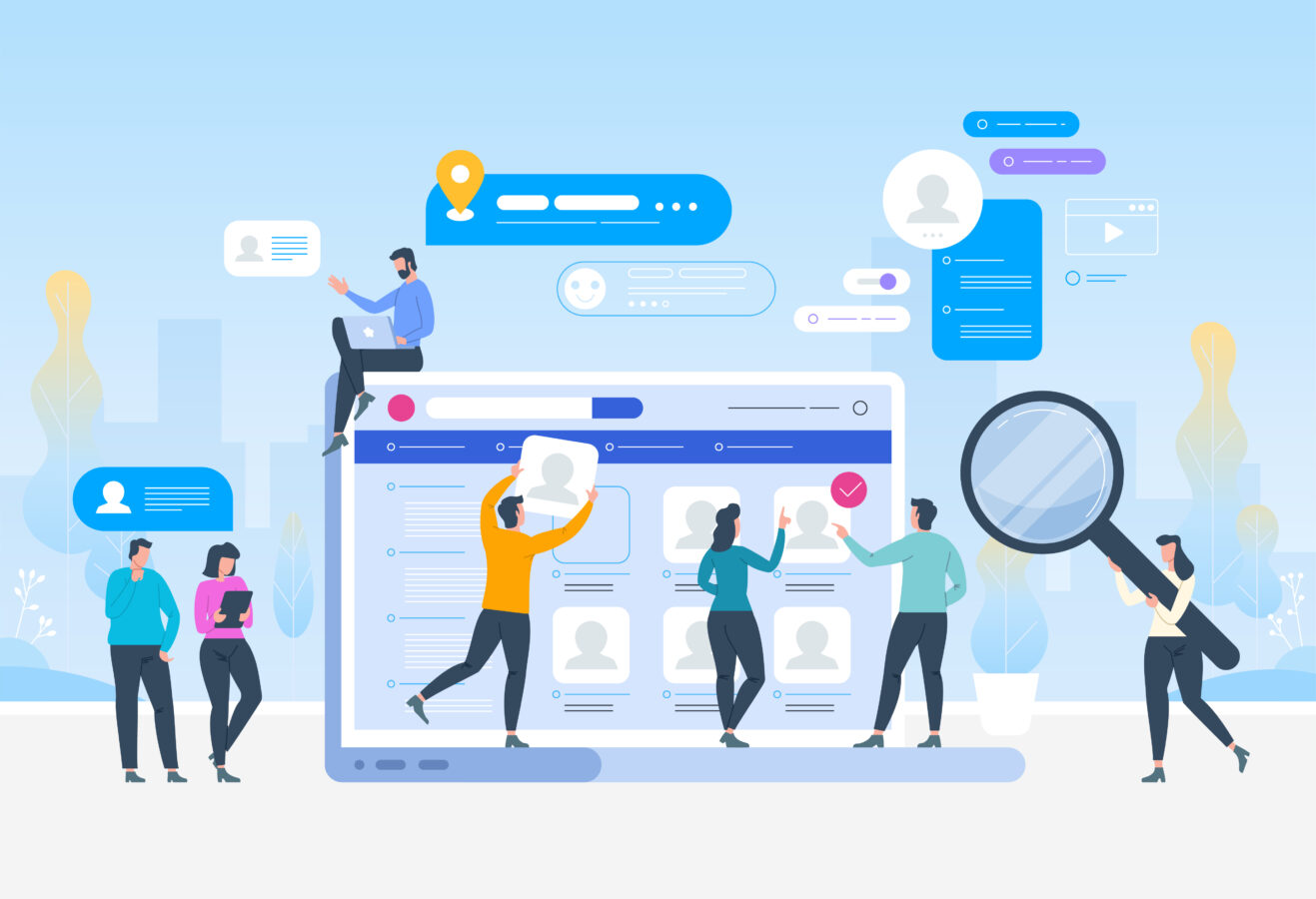
不動産投資は、物件を購入して家賃収入や売却益を得ることで資産形成をめざす手段ですが、その一方で多様なリスクも抱えています。例えば、空室リスクによって思うように家賃収入が得られなくなったり、経済状況の変化でローン金利が上昇し、返済負担が重くなってしまうケースが挙げられます。
こうしたリスクに気付かずに投資を始めてしまうと、計画通りの収益を得られないばかりか、最悪の場合は赤字経営に陥る可能性も否定できません。そこで大切なのが「リスクヘッジ」という考え方です。リスクヘッジとは、あらかじめ潜在的な問題を洗い出し、必要な対策を講じてリスクの発生確率や被害規模を最小限に抑えることを指します。
具体的には、複数の物件を分散して保有したり、借入金の返済計画をシミュレーションして金利上昇に備えたりといった手法が挙げられます。リスクヘッジをしっかり行うことで、投資成果のブレを抑えつつ、長期的に安定した収益を得る土台を作ることが可能です。
特に初心者の方は、不動産投資特有のリスク要因や現実的な対策方法を早めに押さえておくことで、大きな失敗を避けやすくなるでしょう。これからご紹介するリスクヘッジの基本を理解し、自分の投資方針や資金状況に合った取り組みを選ぶことで、成功につなげる第一歩を踏み出してください。
初心者が見落としがちな代表的なリスク要因とは
不動産投資を始める際、初心者の方が特に見落としがちなリスクにはいくつかのパターンがあります。まずは「空室リスク」です。
物件を購入する時点で賃貸需要が高いと判断していても、地域の人口減少や競合物件の増加などにより、想定よりも空室が発生してしまうことは十分に考えられます。空室が続くと家賃収入が得られず、ローン返済や維持費などが自腹での負担になり、キャッシュフローが一気に悪化する恐れがあります。
次に挙げられるのが「金利リスク」です。変動金利型のローンを利用している場合、経済情勢によって金利が上昇すると、返済額が増えて投資計画に狂いが生じるケースが珍しくありません。
また、不動産自体の評価額が下落し、売却時に想定した価格で手放せない「価格変動リスク」も大きな課題です。例えば、都市部であっても、供給過多や景気後退で地価が下がれば、売却益どころか買値を下回る価格でしか売れない可能性もあります。
さらに見落とされがちなのが、物件の老朽化リスクや修繕費用リスクです。築年数が古い物件ほど、エレベーターや給排水設備の大規模修繕が必要になりやすく、一度の修繕費用が数百万円単位になることも珍しくありません。
これらを甘く見積もったまま物件を購入すると、大幅な負担増によって投資計画が崩壊しかねないのです。下記の表では、初心者が特に注意すべき主なリスク要因をまとめています。
| リスク要因 | 具体例 |
|---|---|
| 空室リスク | 地域の競合物件増、住環境の変化による入居者減少 |
| 金利リスク | 変動金利型ローン利用時の返済額増加 |
| 価格変動リスク | 景気後退や地価下落により売却益が得られない可能性 |
| 老朽化リスク | 大規模修繕費用の高騰、築年数が進むほど改修負担が増加 |
- キャッシュフローの急激な悪化
- 想定外の修繕費やローン負担で家計を圧迫
例えば、地方の駅からバスで20分以上かかる物件を「価格が安いから」と安易に選んだ結果、思ったように入居者が集まらず、家賃収入がほとんど発生しないという事態も起こり得ます。
こうした失敗を避けるためには、地域の人口動向や利便性、物件の築年数・構造など、リスク要因を事前にチェックすることが何よりも大切です。特に初心者のうちは、物件の魅力にだけ目を奪われず、リスク面を含めて総合的に判断する姿勢を身につけましょう。
リスクヘッジの視点が変わるだけで投資成果は大きく変わる
リスクヘッジを考えるうえで大切なのは、「単にリスクを避ける」だけでなく、「リスクをコントロールしながら、どれだけリターンを最大化できるか」という視点に立つことです。例えば、空室リスクに備えるために複数のエリアに物件を分散しておけば、ある地域で需要が落ち込んでも、別の地域の物件が収益を補う形でリスクを平準化できるでしょう。
同様に、金利上昇リスクに対しては、低金利の期間に繰り上げ返済を行ってローン残高を減らしたり、一部を固定金利で組むことで返済額の変動幅を抑えたりする方法が考えられます。こうしたリスクヘッジの工夫次第で、同じ投資額・同じ運用期間であっても、最終的な収益に大きな差が生じるのです。
また、リスクヘッジの視点を変えるという意味では、物件の資産価値向上も重要なポイントです。築古物件をあえてリノベーションし、入居者のニーズに合ったデザインや設備にアップデートすることで空室リスクを下げるだけでなく、家賃を引き上げられる可能性もあります。
たとえば、都内で家賃5万円前後のワンルームをリノベーションしてお洒落な内装に変えれば、若い単身者層にアピールでき、家賃6万円以上に設定しても入居者が見つかるケースも珍しくありません。その結果、投資回収のスピードがアップし、ローン返済も計画的に進めやすくなります。
下記は、リスクヘッジを意識した投資戦略の一例と、その効果を比較したものです。
| 戦略 | 具体的な方法 | 期待できる効果 |
|---|---|---|
| 物件分散 | エリアや物件種別をバラけさせる | 空室リスクや価格変動リスクを低減 |
| ローン戦略 | 固定金利と変動金利の組み合わせ、繰り上げ返済 | 金利上昇リスクを抑え、返済計画を安定化 |
| 資産価値向上 | リノベーションや設備のグレードアップ | 空室期間の短縮、家賃アップによる収益向上 |
- 予想外のトラブルや市況変化に柔軟に対応できる
- キャッシュフローの安定化で次の投資にも積極的に取り組める
例えば、物件分散によって空室リスクを下げたうえで、ローンを固定金利と変動金利で半分ずつ組むことで、金利上昇の打撃を抑えつつ、低金利の恩恵も一部受けられるようにする投資家もいます。さらに、築古の物件に限定してリノベーション費用をあらかじめ計上し、家賃収入を相場より高めに設定することで、投資効率をぐっと高める戦略も存在します。
こうした多面的なリスクヘッジの視点を取り入れることで、不動産投資の失敗リスクを下げながら、長期的に収益を伸ばす道が開けるのです。結局のところ、成功する投資家とそうでない投資家の差は「リスクをどれだけ意識し、コントロールしようとしているか」にかかっているといえるでしょう。
物件選びでリスクを最小化するポイント

不動産投資において、物件選びは最も重要なステップと言っても過言ではありません。どれだけ魅力的な家賃収入を見込めるとしても、リスクをしっかり見極めずに購入してしまうと、後々空室や大規模修繕の費用などに悩まされる可能性が高くなります。
逆に、物件の立地や築年数、管理状況を細かくチェックすることで、空室リスクや資産価値の下落を大幅に抑えることができます。例えば、大学が近いエリアであれば、学生向け物件の賃貸需要が一定数見込めるため、家賃設定に余裕が生まれることもあります。
また、築年数が経過している物件でも、管理が行き届いているケースなら実質的な老朽化リスクが低いかもしれません。こうした情報を入手し、自分の投資目的と照らし合わせながら、適切な物件かどうかを判断することが、不動産投資の成功確率を高めるポイントとなるのです。
さらに、物件選びの際には「将来的な需要変化」にも目を向ける必要があります。人口動態や都市開発の計画などを調べることで、数年後には魅力的な投資エリアに変貌する可能性を見極めることができるでしょう。結果として、投資を通じて長期的なキャッシュフローを安定化させ、リスクを最小限に抑える土台を築くことにつながります。
立地・築年数・管理状況の見極め方
物件選びでリスクを最小化するうえで、最初に注目すべきは「立地」です。駅から徒歩何分か、周辺にスーパーやコンビニ、病院などの生活施設がどれだけ充実しているかによって、入居者の利便性が大きく左右されます。例えば、徒歩5分圏内に駅がある物件は、駅徒歩10分以上の物件に比べて空室リスクが低いとされる傾向があります。
特に社会人がメインターゲットになるエリアでは、毎日の通勤時間が短いほど人気が高まるため、家賃設定や空室期間にも大きな差がつくのです。また、大学や専門学校などが近いエリアでは学生向けの単身物件が安定的に需要を得やすく、周辺環境をよく確認することで効率的にテナントを募集できます。
次に注目すべきは「築年数」です。築年数が古い物件は購入価格が比較的安い反面、大規模修繕や設備交換のタイミングが早めに訪れる可能性があります。例えば、築30年を超えるRC造のマンションの場合、外壁補修や給排水管の更新などに数百万円規模の費用がかかることも珍しくありません。
ただし、一括でリノベーションを行い、内装や設備を大幅に刷新すれば、家賃を引き上げられるケースもあります。これにより、最終的には投資効率が高まる可能性もあるため、単に築年数だけで判断するのではなく、「必要な修繕費用と家賃アップの余地」をセットで考えることが重要です。
そして見落とされがちなのが「管理状況」です。同じ築年数や構造の物件でも、管理状態の良し悪しで資産価値や入居者からの印象が大きく変わります。
廊下やゴミ置き場など共用部分の清掃が行き届いているかどうか、一斉清掃や設備の定期点検をきちんと実施しているかといったポイントをチェックしましょう。下記の表は、立地・築年数・管理状況を見極める際に確認すべき主要項目をまとめたものです。
| 項目 | チェックポイント |
|---|---|
| 立地 |
|
| 築年数 |
|
| 管理状況 |
|
- 入居率の向上で安定したキャッシュフローを確保
- 長期的な資産価値を維持しやすく、売却時も好条件を引き出せる
例えば、駅徒歩5分圏内の築15年程度のRC造マンションは、新築と比べて購入価格が抑えられながらも、賃貸需要の安定性が高いことが期待できます。
さらに共用部の管理が行き届いていれば、空室リスクはさらに下がり、長期的な投資にも向いているといえます。このように、立地・築年数・管理状況といった視点から物件を厳選することで、リスクを最小化しながら効率的に家賃収入を得る道が開けるのです。
不動産会社や管理会社との上手な付き合い方
物件選びでリスクを最小化する際、もう一つ見逃せないのが「不動産会社や管理会社との関係づくり」です。いくら立地や物件の条件が良くても、仲介や管理を担当する業者選びに失敗すると、結果的に空室率が高まったり、急な修繕トラブルに対処しきれなかったりと、投資に悪影響が及ぶ可能性があります。
特に、管理会社が適切に業務を行わないと、入居者募集が滞ったり、修繕費用が相場以上に高くなったりするケースも起こり得ます。そこで大切なのは、業者の信頼性や実績、サービス内容をきちんと比較検討した上で、自分の投資方針に合ったパートナーを選ぶことです。
まず、不動産会社を選ぶ際には、地域密着型の業者かどうか、あるいは全国展開している大手かなど、それぞれの強みと特徴を考慮する必要があります。地域に根ざした業者であれば、そのエリア特有の賃貸需要の動向や、物件に適切なリフォームプランを提案してくれるケースが多いです。
一方、大手仲介業者は全国的なネットワークを活かし、広範囲から入居者を募集できたり、独自の集客力を持っていたりする点がメリットとなります。また、管理会社を選ぶ際には、月々の管理費や修繕の見積もり内容だけでなく、トラブル発生時の対応スピードや入居者とのコミュニケーション力もチェックポイントです。
下記の例では、不動産会社や管理会社との付き合い方で、どのようなメリット・デメリットが発生するかをまとめています。
| 業者選びの観点 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 地域密着型 | 地元情報に精通、柔軟な対応 | 全国的な知名度やネットワークが弱い |
| 大手仲介業者 | 広範囲の集客力、高度なノウハウ | 担当者によっては地域の細かい事情に疎い |
| 管理会社の体制 | 管理費に見合ったサービスを受けられれば空室リスク低減 | トラブル対応が遅いと入居者満足度が低下 |
- 修繕やリフォームの見積もりが高額になる場合がある
- 担当者のスキルや対応姿勢で入居率が大きく変動
例えば、都内で駅徒歩10分のマンションを所有している投資家が、管理会社を複数候補から選ぶ場合、月々の管理手数料や修繕費用の見積もりを比較するだけでなく、実際に担当者と面談して対応力を見極めることが重要です。
「入居者からのクレームにはどのように対応しているか」「トラブルや修繕が発生した場合、何日以内に処理を完了させるか」など、具体的な質問を投げかけることで、その管理会社の業務クオリティがある程度推察できます。
こうした上手な付き合い方を意識することで、物件運営のトラブルを減らし、空室期間や修繕コストを抑えることが期待できます。結果として、物件選びだけでなく、パートナー選びもリスク最小化に直結する大切な要素だと言えるでしょう。
資金計画と融資戦略で安定性を高める
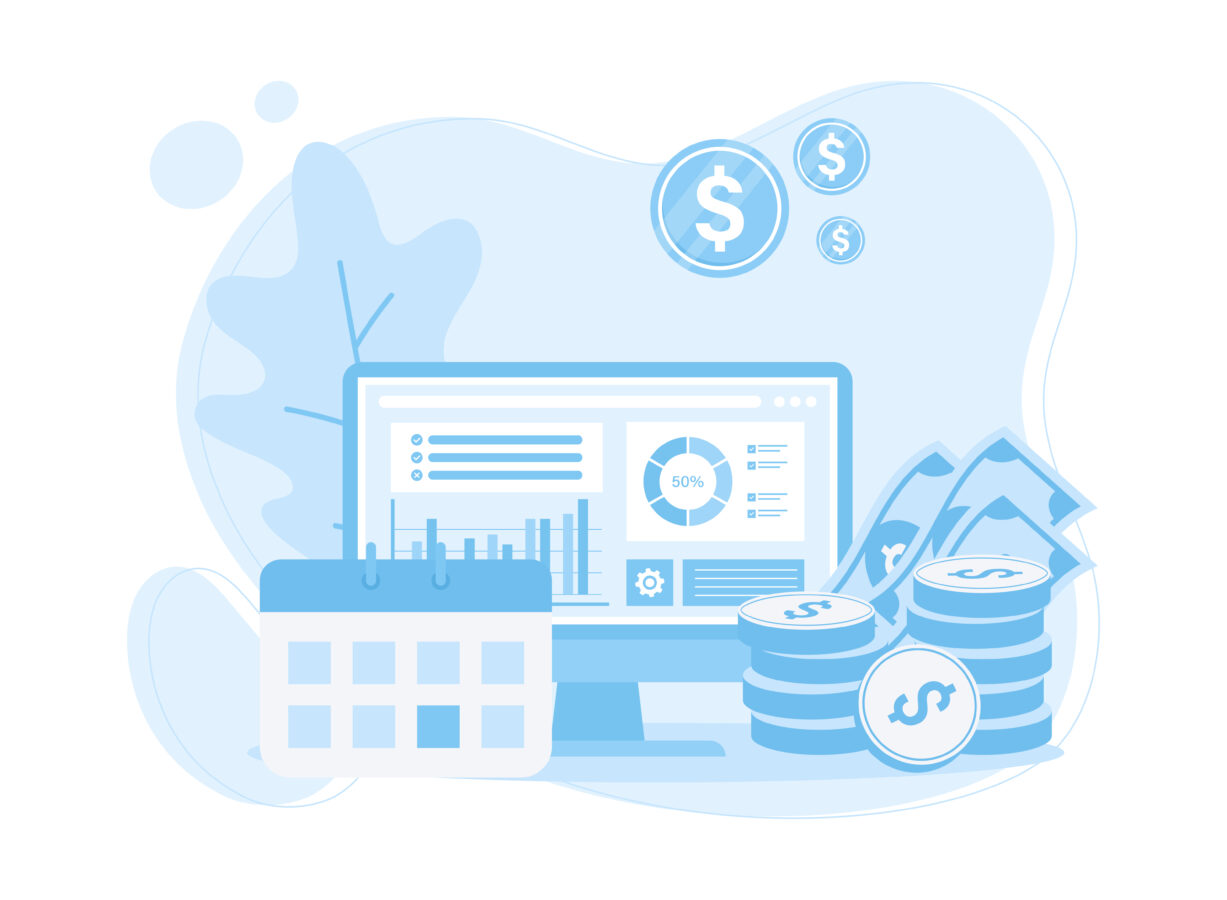
不動産投資で成功を目指すには、物件そのものの選定だけでなく、資金計画をどのように組むかが大きなカギを握ります。いくら収益力が高そうな物件であっても、キャッシュフローが不安定だったり、無理なローン返済が続く状態では、結果的に投資リスクが急増することになりかねません。
反対に、しっかりとした返済プランや自己資金の確保を行っておけば、景気変動や金利上昇といった外部要因に対しても、ある程度の耐性を持つことができます。
特に融資戦略では、固定金利と変動金利をどの割合で組み合わせるか、返済期間を長めに設定して余裕を作るかなど、複数の選択肢を検討することが重要です。例えば、低金利のタイミングを狙って固定金利で借り入れを行い、将来的な金利上昇リスクを抑えながら物件購入を進める投資家も少なくありません。
また、自己資金が手薄な状態で次々に物件を購入すると、思わぬ空室や修繕費用の発生で一気に破綻しかねないため、自分の資金状況と返済能力を正確に把握し、複数の金融機関を比較して最適な融資プランを選ぶようにしましょう。資金計画と融資戦略をしっかりと練ることで、安定性と収益性をバランス良く追求する不動産投資が可能になります。
ローン返済に潜むリスクと対処法
不動産投資において、ローンを活用することはレバレッジを利かせて規模を拡大する上で有効な手段です。しかし、返済計画を見誤ってしまうと、大きなリスクに直面する可能性があります。代表的なのが「金利上昇リスク」です。
変動金利で借り入れを行っている場合、金融情勢や政策金利の変更によって返済額が増えてしまい、当初想定していたキャッシュフローが崩れる恐れがあります。さらに、予期せぬ空室や修繕が重なったタイミングで返済額が上昇すると、運営資金に余裕がなくなり、最終的には延滞や物件売却を余儀なくされるケースもあります。
もう一つのリスクは「期間短縮による返済負担の増大」です。投資効率を高めようと短期での返済を目指す場合、月々の返済額が大きくなるため、空室リスクや経済変動が起きた際に立て直しが難しくなります。以下の表では、ローン返済のリスクとそれに対処するための代表的な方法をまとめています。
| リスク要因 | 主な対策 |
|---|---|
| 金利上昇 |
|
| 返済期間の短期化 |
|
| 空室・修繕の発生 |
|
- 低金利時の楽観的な見込みで短期返済を設定し、金利上昇で苦境に陥る
- キャッシュフロー管理が甘く、空室や修繕費で思わぬ負担を抱える
例えば、3,000万円の物件を金利1%の変動金利で借りた場合、金利が1%上がるだけでも毎月の返済額は大きく変わります。月々2万円程度の返済増でも、年間で24万円以上の追加費用となり、入居者が入れ替わるタイミングでさらに長い空室が続けば、一気に収支が悪化しかねません。
こうした状況を避けるために、あらかじめ繰上げ返済用の資金を確保したり、固定金利ローンを一部導入するなどして返済額を安定させるのは有効な手段です。大事なのは「短期的な金利水準」に惑わされず、数年後、さらに10年後まで見据えた返済計画を立案することだと言えます。
自己資金の確保とキャッシュフロー管理の重要性
不動産投資を成功に導くためには、融資だけでなく「自己資金の確保」や「キャッシュフロー管理」にも目を向ける必要があります。たとえ高い融資額を受けられたとしても、自己資金が極端に少ない状態では、空室や修繕が重なった際に一時的な資金不足に陥り、返済計画が崩れてしまう恐れがあるからです。
例えば、築年数の古いアパートを3,000万円で購入し、頭金なしでフルローンを組んだ場合、空調設備や屋根の修繕に数十万円〜百万円単位の費用が発生すると、一気にキャッシュが底をつくリスクが高まります。そうなると、賃貸経営に専念するどころか、常に資金繰りに追われるような状況に陥りやすいのです。
また、キャッシュフローを安定させるための管理方法も重要です。日々の家賃収入やローン返済、管理費や修繕費などの支出を、明確に把握しておくことで、収支のバランスをコントロールしやすくなります。
特に複数物件を運用している場合、管理が行き届かないと、どの物件がどの程度の収益を生み出しているのか分からなくなり、無駄な経費が増える原因にもなります。下記の例では、自己資金確保とキャッシュフロー管理がどのようなメリットをもたらすかをまとめています。
| 管理要素 | 具体例 | 期待できる効果 |
|---|---|---|
| 自己資金確保 | 頭金を2割程度用意してローン額を抑える | 返済額の安定、空室・修繕時の余裕確保 |
| キャッシュフロー管理 | 家賃収入や支出を月ごとに記帳・分析 | 収支の偏りを早期発見し、対策を打ちやすくなる |
| 資金計画の見直し | 数年ごとにローン条件や金利状況を再検討 | 金利上昇や物件の老朽化に柔軟に対応 |
- リスク発生時でも家計への影響を最小限に抑えられる
- 安定したキャッシュフローで次の投資にもチャレンジしやすい
例えば、都内の中古マンションを購入する際、自己資金として購入金額の2割にあたる400万円ほどを用意し、2,000万円前後の借入れにとどめる投資家がいます。こうすることで、ローン返済額が月7〜8万円程度に抑えられ、仮に家賃が10〜12万円でも空室が数カ月あれば赤字にならない余裕を確保できます。
さらに、しっかりと記帳を行い、毎月の収支を一覧化すれば、空室リスクや修繕計画の見直しに早めに着手できるため、結果として物件運用の安定度が高まります。このように、自己資金の確保とキャッシュフロー管理を徹底することで、ローン返済のリスクをコントロールし、投資全体の安全性と収益性を同時に向上させることができるのです。
複数物件・保険活用など多角的リスクヘッジの手法

不動産投資は、ただ一つの物件を購入して家賃収入を得るだけではなく、複数の物件や保険商品を活用することでリスクを複合的に分散できる点が魅力です。もちろん、一棟のアパートやマンションを所有しているだけでも収益化は可能ですが、ひとつの物件に依存していると、空室が続いたり大規模な修繕が発生した際のキャッシュフローが一気に悪化してしまいます。
そこで重要なのが、複数の物件を組み合わせる「物件分散」や、同じ物件でも火災保険や地震保険といった「保険」を積極的に活用し、想定外の支出リスクをカバーしておくことです。
実際に、2~3軒の中古マンションを地域別に所有することで、どこか一つに空室や賃料下落などのトラブルが発生しても、他の物件の収入で補填できるケースが珍しくありません。
また、不測の災害や事故に備えるための保険を適切に選んでおくと、大きな出費を強いられたときにもカバー範囲が広くなるため、経営へのダメージを最小限に抑えられます。多角的なリスクヘッジを行うことで、長期的に安定したキャッシュフローを確保しやすくなり、不動産投資の醍醐味である資産拡大への道がより現実的になるでしょう。
物件分散や地域分散でブレを抑える方法
不動産投資では、一つの物件だけに集中するよりも、複数の物件を組み合わせて投資する「物件分散」が効果的です。例えば、都心のワンルームマンションと地方のファミリー向けアパートを両方持っている場合、都心エリアでの需要が下がったとしても地方で安定的に入居が確保できたり、その逆のケースもあり得るため、全体としての空室率を低く抑えることが期待できます。
さらに、首都圏に偏らず、名古屋や大阪、福岡など複数の都市に分散投資を行う「地域分散」を取り入れると、地価下落や景気変動の影響を一点集中で受けにくいというメリットも得られます。こうした多角的な配置を行うことで、収益が大きく落ち込むリスクを回避しつつ、一定の家賃収入を確保しやすくなります。
ただし、物件分散や地域分散は、管理や運用の手間が増える点にも注意が必要です。複数の管理会社との契約や、地理的に離れた物件の状況を把握するには、一定のコストと労力を要します。
そのため、物件数が増える前に、効率的な管理体制や記帳方法を構築しておくことが大切です。下記の表では、物件分散や地域分散を取り入れる際のメリットと注意点をまとめました。
| 項目 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|
| 物件分散 | 空室リスクを分散し、キャッシュフローを安定化 | 管理コストや情報把握の手間が増える |
| 地域分散 | 地域特有の需要変化や地価下落の影響を緩和 | 地理的な距離が大きいほど管理の難易度が上がる |
- 都市部・地方部など異なる市場特性を意識して組み合わせる
- 管理やリフォーム対応を円滑にするため、業者との連携を強化
例えば、都内に築10年のワンルームマンションを1戸、地方都市に築15年のファミリー向け物件を1棟所有する投資スタイルを取っている方がいるとします。都内マンションは単身者向けの需要が比較的安定しており、家賃が下落しにくい分、土地や建物の取得費用が高いのが難点です。一方、地方物件は取得費用が安く、敷地が広いことから安定したファミリー層を取り込める反面、地域経済の状況に左右されやすいデメリットがあります。
しかし、この2種類の物件を合わせ持つことで、それぞれの弱点を相殺し合い、どちらかが不調になってももう一方でカバーできる可能性が高まります。結果的に、空室率や家賃下落リスクのブレを抑えながら、長期的に安定した収益をめざせるというわけです。
火災保険や地震保険など不測の事態に備える契約の選び方
不動産投資で多角的なリスクヘッジを行う際には、火災保険や地震保険といった保険契約の活用も欠かせません。物件を複数持っている場合でも、天災や火災などが起きたときには、修繕費用や復旧費用がまとめて発生するリスクが高まるからです。
特に日本は地震大国とも呼ばれ、地域によっては洪水や台風の被害が大きい場合もあるため、最低限の保険をかけておけば、大きな出費を防ぐ上で強い味方になります。ただし、保険を契約すればいいという単純な話ではなく、補償内容や免責金額、契約期間など細部をよく確認し、自分の投資スタイルに合ったプランを選ぶことが重要です。
火災保険の場合、火災だけでなく、風災・雪災・落雷などの補償を含む「住宅総合保険」に加入するケースが多いです。
一方、地震保険は火災保険とセットでしか契約できない仕組みになっており、建物の評価額の一定割合までしか補償されないのが特徴です。以下の例は、火災保険と地震保険でどのような違いがあるかをまとめています。
| 保険の種類 | 主な補償範囲 | 特徴 |
|---|---|---|
| 火災保険 | 火災・風災・落雷・破損汚損など | プランにより水災や盗難補償もオプションで追加可能 |
| 地震保険 | 地震による建物や家財の損害 | 火災保険とセットで契約、補償額に上限がある |
- 補償範囲を誤解し、肝心の被害が保証されない
- 免責金額や保険金の支払い条件を把握していない
例えば、海沿いの地域にアパートを保有している投資家が、台風や高潮による浸水リスクに備えるならば、水災補償を含んだ火災保険を選ぶと安心です。また、東日本大震災のように大規模な地震が発生した際には、倒壊や全壊で物件そのものが使えなくなる可能性もあるため、地震保険も検討の余地があります。
注意したいのは、地震保険は建物の評価額の50%までしか補償が受けられないなど、火災保険と異なる制限がある点です。その分、保険料を抑えられるメリットもありますが、もし地震によって全壊した場合は、建て替え費用の一部しか補填されない可能性があるので、追加資金を用意するなど事前の準備が大切になります。
不動産投資で一度に数百万円以上の損失を被ることは珍しくないので、こうした保険の活用も含めてリスク管理を多角的に行うことで、安定した運用を実現しやすくなるでしょう。
まとめ
今回の記事では、不動産投資におけるリスクヘッジの基本から、物件選びや資金計画といった実践的な対策、さらには複数物件や保険活用など多角的な方法を紹介しました。
これらの手法を複合的に取り入れることで、空室リスクやローン返済リスク、不測の災害リスクなどを効果的に低減し、長期的な投資成果の安定化が期待できます。不動産投資を成功させるために、まずは自分が想定するリスクに合わせて対策を組み立て、無理のない範囲で安全対策を進めることが大切です。