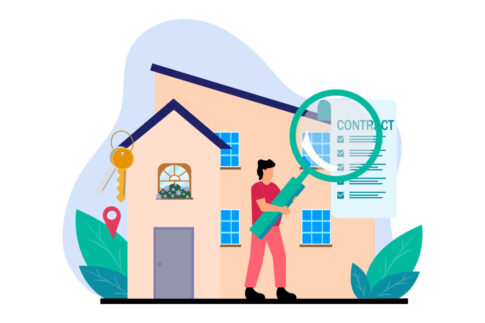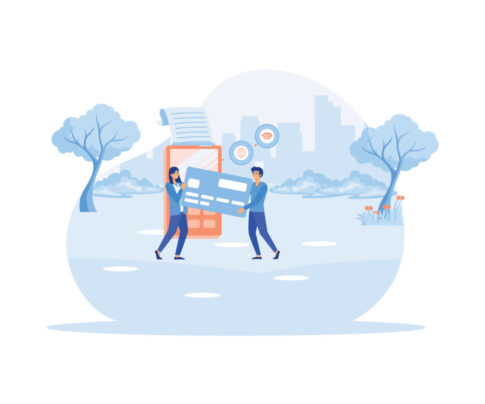私道のある再建築不可、ほんとうに大丈夫?本記事は、接道2mの判定、道路種別(42条・2項道路)とセットバック、私道の持分・通行掘削承諾、位置指定の可否までを初心者向けに整理。
購入前・売却前に必要な確認手順と、早く高く進めるための資料作りの要点も一気に把握できます。
私道×再建築不可の基礎

再建築不可かどうかは「法的に道路と認められるか」と「敷地がその道路に2m以上連続して接しているか」で大きく左右されます。ここで混同しやすいのが「私道」と「建築基準法上の道路」の関係です。
私道であっても、位置指定道路(法42条1項5号)や2項道路など、要件を満たしていれば“法の道路”に該当します。
一方、舗装されていても里道・水路跡・私設通路のように、法の道路ではないケースも多く見られます。
再建築不可の物件では、接道不足、セットバックの未実施、私道持分や通行・掘削承諾の未整備が価格と成約スピードを直撃します。
はじめに「道路種別→接道2m→後退量→私道権利」を順に確認し、資料と現地の実測を突合することで、売買・活用・是正の判断がぶれにくくなります。
【最初に押さえるチェックポイント】
- 前面通路は法42条のどれに当たるか(位置指定・2項道路等)
- 敷地の道路接面は2m以上を確保しているか(連続性を確認)
- 幅員4m未満なら後退(セットバック)の必要量はどれくらいか
- 私道の持分や通行・掘削承諾は書面で整っているか
| 論点 | 見るべき内容 | 実務のヒント |
|---|---|---|
| 道路種別 | 法42条の区分(1項・2項) | 道路台帳・指定道路図で一次確認 |
| 接道 | 連続2mの有無・角地の取り方 | 現地実測と写真で可視化 |
| 後退 | 中心線・必要後退量 | 後退線を配置図に赤入れ |
| 私道権利 | 持分・通行/掘削の承諾範囲 | 承諾書に範囲・承継・復旧基準を明記 |
- 「道路種別・接道2m・後退量・権利」の4点を一枚に集約
- 図と写真で説明可能に→内見・交渉での減額を抑制
再建築不可と私道の基本定義
再建築不可とは、原則として敷地が「建築基準法上の道路」に所定の条件で接していないため、新たな建築確認が下りない(下りにくい)状態を指します。ここでいう道路は“法の道路”であり、見た目の通路や舗装の有無だけでは判断できません。
私道でも、役所の位置指定を受けたもの(法42条1項5号)や、幅員4m未満でも一定要件を満たす2項道路は“法の道路”と扱われます。
一方、私設通路・通り抜け通路・水路/里道の敷地などは、法の道路に該当しないことがあり、接道2mを満たしていても再建築不可に該当する可能性があります。
投資の現場では、①前面通路が法42条のどれか、②敷地が連続2m以上接道しているか、③4m未満なら後退量がどれくらいか、④私道の持分・通行・掘削承諾が揃っているか、を順番に確認します。
これらを資料(台帳・図面・回答書)と現地実測で裏づけることで、価格・是正可否・出口戦略が具体化します。
【キーワードの整理】
- 位置指定道路→私道でも要件充足で「法の道路」
- 2項道路→狭あい道路。中心線からの後退で将来4m確保
- 接道2m→敷地の道路接面の連続距離。通路の有効幅に注意
- 道路台帳/指定道路図/幅員証明
- 接道実測写真(スケール写し込み)
都市計画区分と区域指定の注意点
都市計画区域内では、原則として建築確認の審査対象となり、接道要件や防火・用途などの技術基準が厳格に及びます。
準都市計画区域や区域外では、確認手続や基準の運用が一部異なる地域もありますが、だからといって自由になるわけではありません。
防火地域・準防火地域、景観・風致・自然公園・農地転用、河川・道路占用といった他法令の規制は別に及びます。
さらに、10㎡未満増築の確認不要の取扱いがある地域でも、接道義務や防火・避難・衛生の要件は消えません。
投資目線では、①どの区域か、②防火指定の有無、③用途地域・建ぺい/容積の余地、④他法令の該当、⑤上下水・ガスの整備状況、を同時に把握することが肝心です。
区域外で“仮設”のつもりでも、居住・宿泊・飲食提供など不特定多数が利用する実態に近づけば、建築物扱いの要求水準が上がり、思わぬ是正や撤去が必要になることがあります。
| 区分 | 主なチェック | 実務の着眼点 |
|---|---|---|
| 都市計画区域内 | 接道・用途・防火・斜線・日影 | 確認手続が前提。私道承諾や後退の整備が要 |
| 準都市計画/区域外 | 確認要否のローカル運用 | 他法令(景観・農地・道路占用等)の適用を別途確認 |
| 防火指定 | 防火/準防火の別と延焼ライン | 外壁・開口部・内装制限の強化に留意 |
- 確認不要でも技術基準や他法令は残る
- 居住・宿泊用途に近づくほど要求水準が上がる
見た目の道路と法的道路の違い
舗装されて車が通れるからといって、それが直ちに「建築基準法上の道路」とは限りません。
典型的には、私設の通路、里道や水路跡の敷地、開発時に整備されたが位置指定を受けていない私道などが該当します。これらは見た目が道路でも、建替えや新築の接道要件を満たさず、再建築不可の原因になります。
実務では、(1)道路台帳・路線認定、(2)指定道路図や位置指定の告示、(3)2項道路の中心線・幅員証明、のいずれかで「法の道路」に当たる根拠を確認し、現地実測で接道2mの連続性を確かめます。
角地や曲線部は有効幅の取り違いが生じやすく、旗竿地は通路の有効幅(門柱・給湯器・配管の出っ張り等で狭まる)がネックになりがちです。
さらに、私道は通行・掘削・再掘削の承諾がなければ、配管引込や舗装復旧で紛争化します。見た目に惑わされず、「根拠資料+実測」で二重に確かめる姿勢が重要です。
| 見た目 | 実態の可能性 | 確認資料・行動 |
|---|---|---|
| 舗装された細道 | 位置指定なしの私道/単なる通路 | 指定道路図・告示の有無を照会 |
| 古い路地 | 2項道路または非該当 | 中心線・幅員証明→後退量を算定 |
| 里道・水路跡 | 法の道路に非該当の可能性 | 所管へ用途・権利関係を確認 |
- “舗装=法の道路”ではない→必ず台帳・図面で裏づけ
- 有効幅は現地で実測→出っ張り・隅切りを見落とさない
接道2m・道路種別と私道の関係

再建築可否は「前面通路が建築基準法上の道路に当たるか」と「敷地がその道路に2m以上連続して接しているか」で大きく変わります。
私道でも、位置指定道路(法42条1項5号)や2項道路の要件を満たせば“法の道路”として扱われます。
一方、舗装はされていても位置指定を受けていない通路や、里道・水路跡などは法の道路に該当しないことがあります。
評価・売買・活用の順番は、①道路種別の特定→②接道2mの連続性確認→③幅員4m未満ならセットバックの有無・後退量→④私道の権利(持分・通行・掘削)の整備、の流れで進めると失敗が減ります。
とくに旗竿地や袋地は「接道の取り方」「有効幅」「角や設備の出っ張り」で条件を満たさない例が多く、現地実測と資料照会をセットで確認することが重要です。
| 確認軸 | 見るポイント | 実務ヒント |
|---|---|---|
| 道路種別 | 42条1項1〜5号/2項のどれか | 道路台帳・指定道路図・位置指定告示で裏づけ |
| 接道2m | 連続2mの有無・旗竿通路の有効幅 | メジャー撮影・曲線や隅切りの有効取り |
| 幅員 | 4m未満なら2項道路か否か | 中心線・幅員証明→後退量を算定 |
| 私道権利 | 持分・通行/掘削承諾の有無 | 範囲・承継・復旧基準を承諾書に明記 |
- 道路台帳/指定道路図/幅員証明の写し
- 接道実測写真(スケール入り)
建築基準法42条道路と私道の典型パターン
私道が常に「法の道路」になるわけではありません。法42条は、建築に使える道路を1項1〜5号と2項で定義しています。
1項1号は道路法による公道、1項2号は区画整理や都市計画事業などによる道路、1項3号は基準適用時に既に存在していた既存道路、1項4号は近く事業執行予定の計画道路、1項5号は位置指定道路(私人築造だが特定行政庁の位置指定を受けた私道)です。
さらに2項道路は、幅員4m未満でもみなし道路として扱い、建替え時に中心線からの後退(セットバック)で将来的な4m確保を図る仕組みです。
現地でよくある私道の姿は、①位置指定済みで条件が揃っている、②古い狭い路地で2項道路に該当、③見た目は道路だが位置指定も2項指定もなく法の道路に非該当、の三類型です。
③の場合は、接道2mを満たしていても再建築不可になるため注意が必要です。
| 類型 | 概要 | 実務ポイント |
|---|---|---|
| 位置指定道路(1項5号) | 私道だが位置指定の告示・図面が存在 | 幅員・排水・転回など基準確認、告示写しで根拠化 |
| 2項道路 | 幅員4m未満の狭あい道路のみなし道路 | 中心線の特定→必要後退量・隅切りを算定 |
| 非該当私道 | 見た目は道路でも法の道路でない | 通行はできても接道要件は満たせず→建替え困難 |
- 「私道=法の道路」ではない→位置指定や2項の根拠が要
- 舗装の有無は判断材料にならない→資料と実測で確認
接道2mの取り方と旗竿通路の実務注意
接道2mは、敷地と道路が接する直線距離の連続幅を指します。
旗竿地(路地状敷地)の「竿」部分は有効幅が2m以上必要とされ、門柱・給湯器・ポスト・階段・植栽・メーターボックスなどの出っ張りで実効幅が削られると、接道2mを満たさない扱いになり得ます。
角地や曲線部では、隅切りやカーブで測る位置を誤ると“2mあると思ったのに不足”という事態が起きやすいため、現地実測と図面の両方で確認します。
旗竿通路は、勾配・段差・路面状態が悪いと緊急車両や工事車両の進入に支障が出やすく、将来の建替えや売買にも影響します。
また、通路部分の所有権や地役権、通行・掘削承諾の有無はライフライン引込や舗装復旧の前提になるため、権利関係を早期に書面化しておくのが安全です。
| 確認項目 | 具体的チェック | ミス防止のコツ |
|---|---|---|
| 有効幅2m | 設備の出っ張り・塀・フェンスの厚みを差し引く | メジャーを写し込んだ写真を保存 |
| 連続性 | 途中でくびれる箇所がないか | 実測線を図面に赤入れし共有 |
| 角・曲線 | 隅切りの位置、カーブの接線の取り方 | 役所の解釈を事前照会→メモ化 |
| 権利関係 | 通路の所有形態・地役権・承諾の有無 | 承諾書に範囲・承継・復旧基準を明記 |
- 通路中央で2m確保→出っ張りで実効幅が細らないか
- 勾配・段差→搬入や緊急車両の通行に支障がないか
セットバック要否と後退面積の見極め
前面道路の幅員が4m未満でも、2項道路であれば建替え時に道路中心線から後退(セットバック)し、将来4mを確保する考え方が採用されます。
実務では、①その道が2項道路に指定されているか、②中心線の位置、③必要後退量(通常2m−現況半幅)、④隅切りや曲線部の扱い、を順に確定させます。
後退部分は原則として建築に利用できない扱いになり、門柱や塀、給湯器、バルコニー支持柱などは移設・撤去が必要です。
後退後の有効宅地面積の減少は、建物計画と価格形成に直結しますので、面積減を数量化し、復旧仕様(舗装、側溝、集水桝、縁石)と合わせて概算見積を用意すると交渉が安定します。
また、自治体によっては狭あい道路整備の補助制度や、提供方法(寄付・使用承諾)の運用が異なるため、早めの照会が有効です。
| 項目 | 見るポイント | 実務の要点 |
|---|---|---|
| 指定の有無 | その道が2項道路かどうか | 2項道路台帳・幅員証明で確認 |
| 中心線 | どこを中心とするか | 役所の図面・基準点で特定 |
| 後退量 | 2m−現況半幅(一般的な考え方) | 曲線・隅切りは別計算→図で合意 |
| 復旧仕様 | 舗装・側溝・桝・縁石の標準 | 数量表に落として見積を取得 |
- 台帳幅員と現地幅員が合わない→必ず実測で補正する
- 後退面積の見落とし→建物規模と価格に影響しやすい
私道持分・通行掘削承諾の整え方
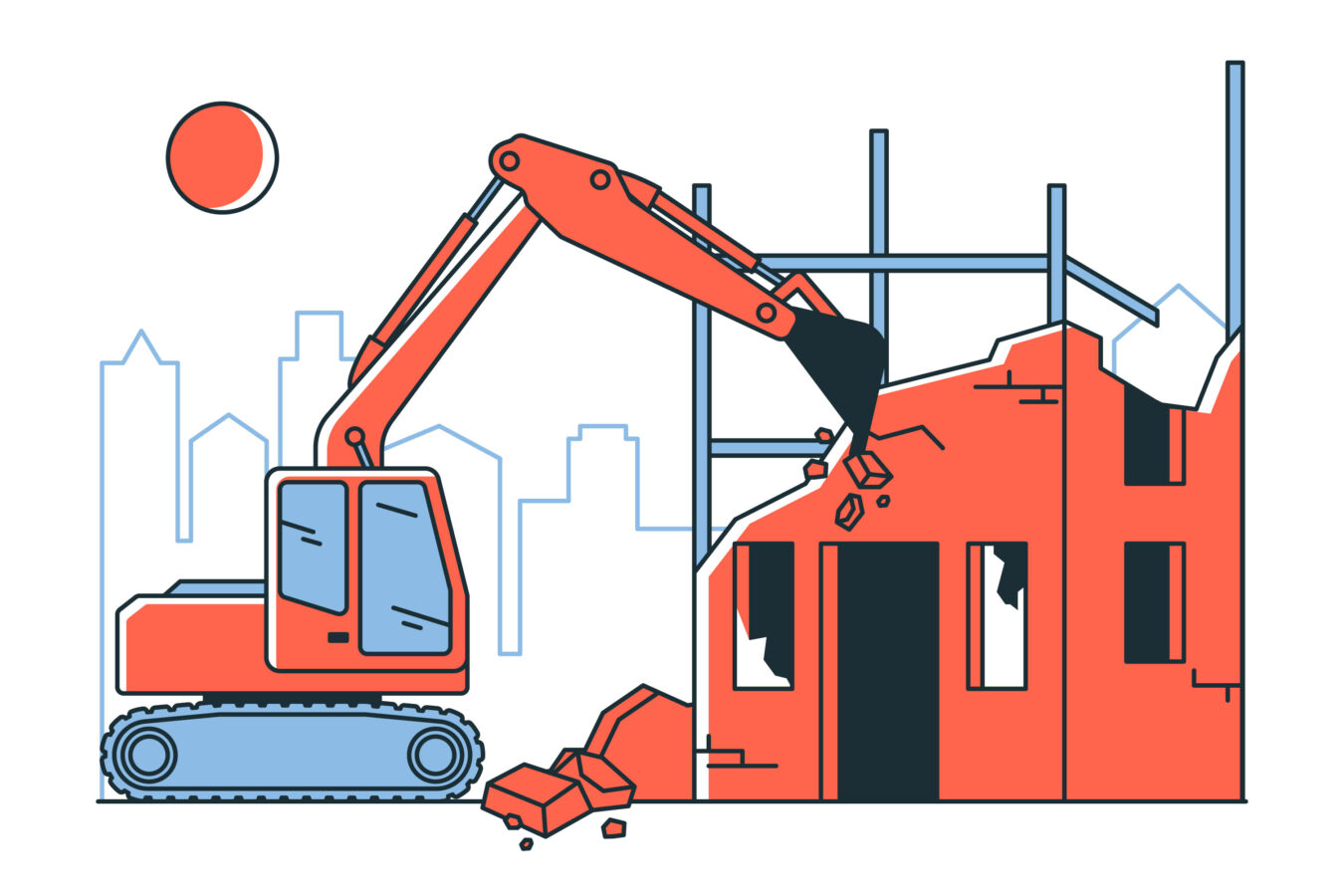
私道が絡む再建築不可の可否や価格は、「持分(オーナー権)」と「承諾(通る・掘るの許可)」をどこまで客観資料で示せるかで大きく変わります。
まずは前面通路の地番を特定し、登記事項で所有者と持分の有無・割合・共有者数を把握します。
次に、通行承諾(人・車・工事車両)と掘削承諾(上水・下水・ガス・電気・通信)の範囲、再掘削の可否、舗装復旧の基準、将来の承継までを文章化します。
共有私道では「全員の同意」や管理ルールが肝心で、同意者が多いほど段取りと文面の精度が成果を左右します。
資料は〈道路台帳・公図・登記事項・位置図〉を核に、承諾書ドラフト・数量表・復旧仕様(舗装厚・側溝・桝)を添付して、疑義を先回りで潰すと交渉が安定します。
【まず整える順序】
- 地番の特定→登記事項で所有者・持分・共有者数を確認
- 通行/掘削の範囲を定義→車種・時間・再掘削・復旧基準
- 承継条項と管理ルール→売却・相続後も効く仕立てに
| 論点 | 確認すること | 実務のヒント |
|---|---|---|
| 持分 | 有無・割合・共有者数・連絡先 | 清算金の有無・評価根拠をメモ化 |
| 通行 | 歩行・車両・工事車両の可否 | 幅員・時間帯・一時占用を明記 |
| 掘削 | 対象インフラと深さ・延長 | 復旧厚・舗装種別・再掘削を定義 |
- 図面に赤入れ→通路幅・配管位置・復旧断面を可視化
- ドラフトは短文+別紙仕様→読みやすく、誤解を減らす
私道持分の有無確認と取得・共有の実務
私道持分は「その通路の土地にあなたが何分の何を持っているか」を示す権利です。最初に公図で通路の地番を特定し、法務局で登記事項(全部事項証明)を取得して所有者・持分割合・共有者数を確認します。
持分が無い場合の通行は、通行地役権の設定や通行承諾で代替できますが、掘削や将来の再掘削まで必要なら持分取得が有利です。
取得は〈持分譲渡(売買/贈与)〉〈分筆のうえ持分付与〉〈換地的な持分調整〉などが選択肢で、共有者全員の同意が原則求められます。
価格は一律ではなく、路線価や面積、通路の機能、将来の維持費負担を踏まえて当事者間で決めるのが一般的です。
登記では原因(売買/贈与)、対価、持分割合、負担の有無を明確にし、司法書士が関与するとスムーズです。
共有後は、無断駐車・ゴミ放置・舗装破損等のトラブルを防ぐため、管理覚書で「維持管理・復旧負担・禁止事項・連絡方法」を取り決めます。
| 場面 | 実務ポイント | 注意点 |
|---|---|---|
| 地番特定 | 公図で通路の筆を確認 | 一部が他人地/里道の可能性に注意 |
| 登記確認 | 所有者・持分・共有者数を把握 | 共有者の住所変更/相続未登記に留意 |
| 持分取得 | 譲渡契約→登記申請(司法書士) | 同意者の網羅、清算金と税務の整理 |
| 管理運用 | 管理覚書で維持/復旧の基準化 | 違反時の対応・費用分担を条文化 |
- 関係者リストと持分割合の一覧化→不足持分の特定
- 清算金の考え方と管理覚書案を同時提示→合意を取りやすく
通行承諾・掘削承諾の範囲と文言
通行承諾は「人・車両が恒常的に通行できる」こと、掘削承諾は「ライフラインを埋設し、工事のために通路を掘り、舗装を復旧できる」ことを相手方が認める文書です。
文面は曖昧さを排除し、〈対象地(地番・位置図)〉〈対象者(所有者・承継人を含む)〉〈範囲(歩行・車両・工事車両・占用)〉〈掘削(上水・下水・ガス・電気・通信)〉〈再掘削の可否と回数〉〈復旧基準(舗装厚・材質・ライン)〉〈養生・事故時の責任〉〈期間(原則無期限)〉〈対価・協力金〉〈承継条項〉を盛り込みます。
とくに「再掘削可否」「工事車両の通行」「夜間・休日作業」「警備員手配」「産廃処理」など運用事項を外すと、工事段階で紛争化しやすいです。
承諾は覚書だけでなく、別紙に〈配管ルート図〉〈断面復旧図〉〈工事工程表〉を添えると相互の期待値を揃えられます。
| 条項 | 盛り込む要点 | 実務メモ |
|---|---|---|
| 範囲 | 歩行/車両/工事車両・一時占用 | 幅員・時間帯・車種制限を明示 |
| 掘削 | 対象インフラ・深さ・延長・方法 | 横断/縦断・路盤構成・夜間の可否 |
| 復旧 | 舗装厚・材質・ライン・段差許容 | 写真管理・検収方法・保証期間 |
| 承継 | 所有者・賃借人・相続人へ承継 | 所有権移転時の通知・再署名不要化 |
- 「必要な範囲で」→具体の幅員・延長・回数に置換
- 「原状回復」→断面図で舗装厚・材質を明記
承諾書ドラフト作成と承継条項の設計
ドラフトは「短く・明確に・図面で補う」が鉄則です。表題に物件住所と地番を記し、別紙に〈位置図〉〈配管ルート〉〈復旧断面〉〈工程〉を添付します。
本文では、(1)目的(通行/掘削/再掘削)と範囲、(2)期間(無期限/○年/工事期間)、(3)復旧基準(舗装厚・材質・路盤構成・側溝・桝)、(4)費用負担、(5)損害発生時の責任、(6)近隣調整(警備・騒音・時間帯)、(7)協力金の有無、(8)承継条項を章立てします。
承継条項は「本承諾は所有権移転・賃貸借・相続があっても承継し、再署名を要しない」旨を明記し、将来の売買や相続でも効力が切れない設計にします。
共有私道の場合は「共有者代表者方式+全員同意」の二段構えにし、代表が実務窓口、重要事項は全員決裁とするのが現実的です。
署名は実印・押印区分、添付書類(印鑑証明・本人確認)も明記し、原本は当事者双方が保管、写しを仲介や施工者へ配布します。
| ドラフト項目 | 記載内容 | 添付・運用 |
|---|---|---|
| 目的・範囲 | 通行/掘削/再掘削・工事車両・占用 | 位置図・ルート図で補足 |
| 復旧基準 | 舗装厚・材質・ライン・段差許容 | 断面図・検収写真・保証期間 |
| 承継条項 | 移転・相続後も効力継続 | 通知義務・再署名不要の明記 |
| 紛争対応 | 協議・管轄・違約金/実費精算 | 連絡先・期限・記録様式 |
- 再掘削を含む明確な範囲定義(幅員・延長・回数)
- 復旧断面と検収方法(写真・立会い・是正期限)
- 承継条項(移転・賃貸・相続でも有効)
位置指定道路・2項道路の判断手順

位置指定道路と2項道路は、いずれも「私道でも条件を満たせば建築基準法上の道路として扱える」仕組みですが、根拠資料と現地の突合を段階的に行わないと誤判定が起きやすいです。
まず、前面通路が法42条のどの区分に当たるかを役所資料で特定します。次に、敷地の接道2m(連続幅)の有無、道路幅員の実測と台帳値の差、4m未満なら中心線と必要後退量を確定します。
位置指定の場合は「告示・図面・検査済」の有無、2項道路は「指定の有無・中心線の根拠」を最優先で確認します。
最後に、私道権利(持分・通行/掘削/再掘削承諾)と復旧基準、外構移設や配管の干渉を整理し、図面と写真で可視化すると、売買や是正の判断がぶれません。
【全体フロー(資料↔現地を往復)】
- 道路種別の特定→位置指定/2項/非該当を確認
- 接道2mの連続性と幅員実測→台帳値と差異を補正
- 後退量・隅切り・復旧仕様を数量化→概算見積
- 私道権利と承諾の範囲・承継条項を文書化
| 段階 | 確認ポイント | よくある落とし穴 |
|---|---|---|
| 種別特定 | 42条1項5号か2項か、非該当か | 舗装=道路と誤認、告示や台帳の未確認 |
| 接道・幅員 | 連続2m、4m未満の有無 | 出っ張りで有効幅が不足、台帳と実測の差 |
| 後退 | 中心線・必要後退量・隅切り | 曲線部の扱い漏れ、面積減の見落とし |
| 権利 | 持分・通行/掘削/再掘削承諾 | 承継条項なし、復旧基準が曖昧 |
- 位置指定告示/図面または2項道路台帳・幅員証明
- 接道実測写真(スケール入り)と後退線入り配置図
位置指定道路の要件・築造フローを把握
位置指定道路(法42条1項5号)は、私人が築造する私道を特定行政庁が「建築基準法上の道路」として指定する制度です。
一般に、幅員4m以上(地区により6m指定の地域もあり)、排水(側溝・桝・勾配)、路盤・舗装構成、行き止まりの場合は転回広場、隅切りなど、自治体の要綱で細目が定められます。
新設や拡幅では、計画図(平面・縦横断・標準断面)と沿道同意、私道の権利整理(分筆・持分・通行/掘削承諾)、上下水・ガス・電力の引込計画を整え、事前協議→申請→工事→検査→位置指定の告示という流れで進みます。
既に指定済みかどうかは、告示の写しや位置指定図、検査記録の有無で確認できます。
売買・活用では、指定済みでも維持管理(補修・占用・復旧)や将来の承継ルールが曖昧だと紛争化しやすいため、管理覚書で基準を明文化しておくのが安全です。
【築造〜指定の実務ポイント】
| 段階 | 必要事項 | 着眼点 |
|---|---|---|
| 事前協議 | 標準図の適合確認、沿道同意方針 | 幅員・排水・転回の要否を早期確定 |
| 申請 | 平面・断面・構造、権利関係図 | 私道持分、承諾、占用との整合 |
| 工事・検査 | 路盤・側溝・舗装の出来形確認 | 検査済→告示写しで根拠を保管 |
- 「告示の写し」を必ず取得・保管→売買時の根拠に
- 維持管理・復旧基準を覚書化→将来の占用・再掘削に備える
2項道路の中心線確認と後退量の決定
2項道路は、幅員4m未満の既存狭あい道路を「みなし道路」として扱い、建替え時に中心線からの後退(セットバック)で将来4mを確保する制度です。
判断の核は、①その通路が2項道路に指定されているか、②中心線をどこに取るか、③必要後退量と隅切りの設定、の3点です。
中心線は、台帳図・基準点・既存工作物の位置関係などで特定しますが、道路の片側が川・崖・法面の場合や、曲線・屈曲が多い場合は、特定行政庁が別途水平距離を指定することがあります。
必要後退量は一般に「2m−現況半幅」で算定し、角や曲線部は別計算になります。後退部分は建築不可の取扱いとなるのが通例で、門柱・塀・給湯器・階段・擁壁の一部を移設・撤去する必要があります。
面積減は建蔽・容積、駐車や動線計画に直結するため、後退面積と復旧仕様(舗装・側溝・桝・縁石)を数量化し、概算見積と配置案を同時に提示すると交渉が安定します。
| 確認項目 | 実務の見方 | 注意点 |
|---|---|---|
| 指定の有無 | 2項道路台帳・幅員証明で確認 | 非該当だと接道扱い不可→方針転換が必要 |
| 中心線特定 | 台帳・基準点・境界の整合 | 曲線・屈曲は個別協議→誤差を残さない |
| 後退量 | 2m−現況半幅(一般的な考え方) | 隅切り・角度で不足が出やすい |
| 復旧仕様 | 舗装・側溝・桝・縁石の標準 | 数量表で見積→工程・占用許可も確認 |
- 台帳幅員と現地実測の差→必ず実測し赤入れ図で共有
- 後退面積の機会損失→価格・計画に反映しないと後戻り
指定・後退の証明資料と取得ルート
「法の道路であること」「必要後退量が確定していること」を第三者に示すには、公的資料の入手と整備が不可欠です。
位置指定道路は、位置指定の告示・位置指定図・検査済の写し、道路管理者が発行する幅員証明が根拠になります。
2項道路は、2項道路台帳や幅員証明、必要に応じて中心線の座標・基準点図、狭あい道路整備の協議記録が有効です。
加えて、配置図に後退線・隅切り・数量表を赤入れし、現地写真にスケールを写し込むと、内見や金融機関、買主の審査がスムーズです。
窓口は、建築指導課(道路種別・2項台帳・後退線)、道路管理者(幅員・管理区分)、上下水道局(配管・掘削承諾の要否)、法務局(登記事項・公図)など。入手に日数を要する資料もあるため、売出前に並行取得しておくと減額交渉を抑えられます。
| 資料 | 内容 | 取得先/ヒント |
|---|---|---|
| 位置指定告示/図 | 法42条1項5号の根拠 | 建築指導課で写し請求、告示番号を控える |
| 2項道路台帳 | 指定の有無・幅員・中心線 | 建築指導課/道路管理者、地番で照会 |
| 幅員証明 | 道路幅の公的確認 | 道路管理者、手数料・日数に注意 |
| 中心線座標 | 後退線計算の基準 | 自治体の基準点図/協議記録 |
| 登記事項・公図 | 私道の所有・地番・境界 | 法務局で取得、通路地番の特定が先決 |
- 図面に後退線と数量表を重ね、写真と対で保管
- 役所回答は日付・担当・要旨を明記→交渉資料に転用
価格評価・売却手段と資料準備
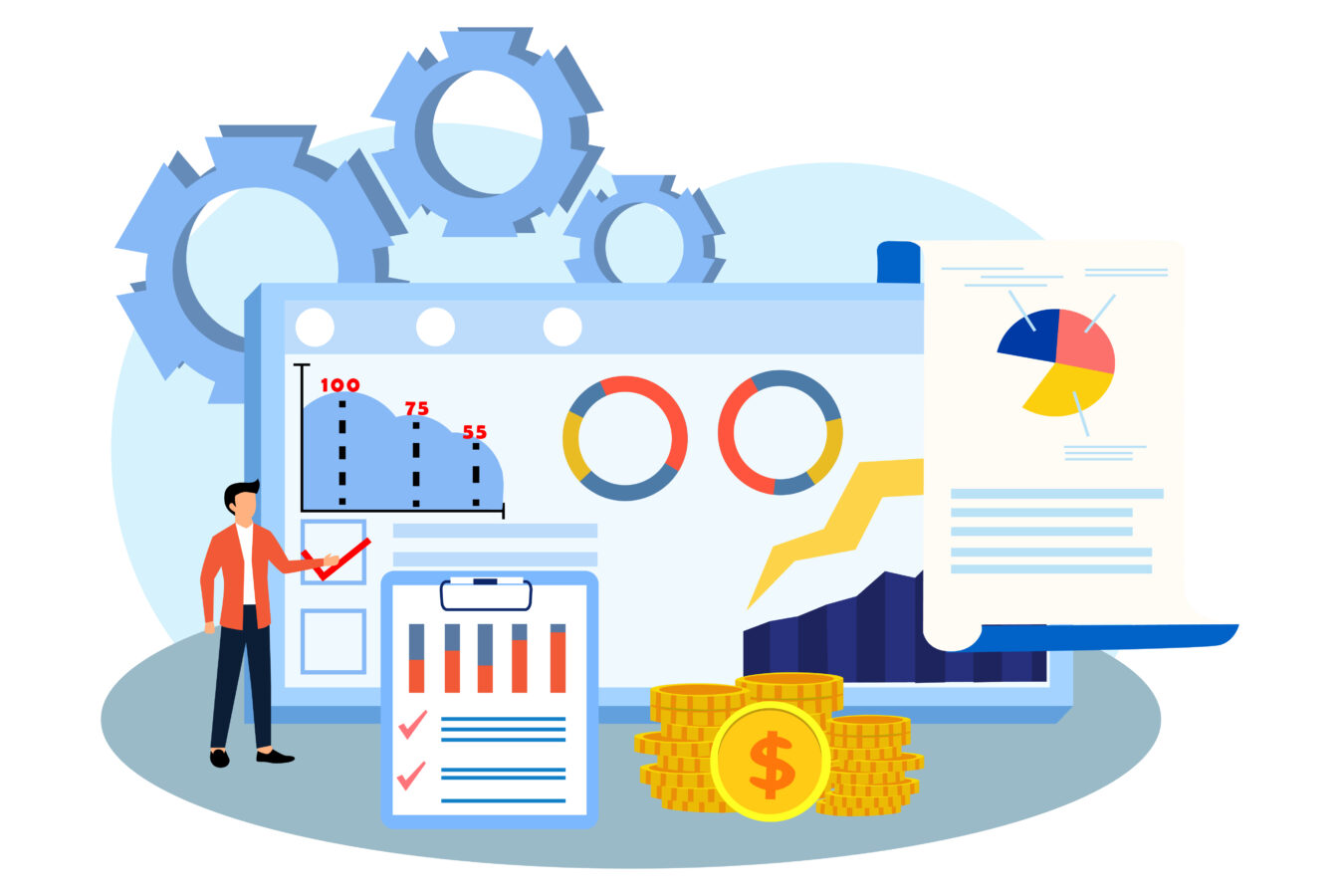
再建築不可×私道の案件は、評価と出口(売却手段)、そして資料の整備度が三位一体で成果を左右します。
まず評価では、近隣の「再建築可」相場を基準に置き、接道2m不足・セットバック面積・私道の持分や通行/掘削/再掘削承諾の整備難易度、上下水・ガスの引込可否、擁壁や高低差などを金額に置換して控除します。
次に出口選択は、現金買取・仲介・入札(買取保証含む)を「期間→確実性→価格上振れ→手間」の順に比較し、売主の制約(いつまでに現金化か、どこまで是正を先行できるか)に合わせて決めます。
最後に資料は、道路種別・接道実測・後退線・承諾の範囲・越境・数量表・復旧仕様・概算見積・工程表をワンセットにして先出しすると、指値とキャンセルが大きく減ります。
【実務の流れ】
- 評価:基準相場→個別控除→期間コストの順で手残り試算
- 出口:現金買取/仲介/入札を同条件で横並び比較
- 資料:図と写真、見積と工程を一体化→公開のタイミングを前倒し
| 要素 | 内容 | 期待効果 |
|---|---|---|
| 評価 | 個別控除(後退面積・承諾・外構移設・通路舗装 等) | 根拠ある価格→交渉でぶれない |
| 出口 | 価格×期間×条件(免責・現況有姿)で選択 | 目的に合う最短ルートを選べる |
| 資料 | 道路種別・接道2m・後退線・承諾範囲・見積・工程 | 減額抑制・検討スピード向上 |
- 手残り基準での意思決定(価格ではなく実質)
- 出口ごとの“同条件”比較(測量・残置物・是正の有無を統一)
- 先出し資料で不確実性を金額に置換→指値を縮小
現金買取・仲介・入札の比較と使い分け
現金買取は「短期・確実・手間少」の一方で、価格は控えめになりがちです。仲介は「上振れ余地」が大きい反面、資料作成・内見運用・役所照会などの準備と時間が必要です。
入札(買取保証含む)は「短期で上限価格と条件差の把握」が強みで、要項を統一すれば条件を横並び比較できます。
使い分けのカギは、売主の制約(資金化期限・居住/転居の事情)、案件の整備度(承諾と後退線の確定、数量表と見積の精度)、広告に出せる内容(弱点の正直な開示と解決案の提示)の三点です。
短期資金化が最優先→現金買取、価格の最大化が目標→是正案セットで仲介、相場の天井と条件差を素早く把握→入札、という整理が実務的です。
| 手段 | メリット | 留意点 |
|---|---|---|
| 現金買取 | 最短成約・免責/現況有姿が通りやすい | 価格は控えめ→相見積と条件(手付・猶予)比較が必須 |
| 仲介 | 上振れ余地・市場露出による競争 | 資料先出しと是正案提示が前提。期間延伸リスク |
| 入札/買取保証 | 上限探索・条件の横並び・出口担保 | 要項の精度が結果を左右。保証条件の例外条項に注意 |
- 「いつまでに現金化?」→期限を明文化し候補を絞る
- 承諾・後退線は確定済み?→未確定なら入札か保証で下限確保
路線価・成約比較と個別控除の相場化
評価の骨子は「基準相場を置き、個別控除を数値化する」ことです。
まず、近隣の再建築“可”の成約単価を、面積・駅距離・前面道路条件・築年が近い事例で複数抽出し、時点補正を加えて基準レンジをつくります。並行して路線価・公示地価・基準地価を参照し、地点間の補正を行います。
その上で、再建築不可×私道ゆえの個別控除(セットバック面積、外構移設、通路舗装、私道承諾の取得コスト、インフラ引込、越境是正、工程の長期化に伴う期間コスト)を数量×単価で積み上げ、最少/最大の二本立てで示すと交渉が安定します。
【控除の考え方】
- 物理的控除→後退面積×近隣単価、外構・擁壁・舗装の見積
- 権利的控除→通行/掘削/再掘削承諾の協力金・書式作成費
- 時間価値→売却までの月数×想定利回り(機会損失)
| ソース | 使い方 | 注意点 |
|---|---|---|
| 近隣成約 | 実勢レンジの基準化 | 広告価格ではなく成約価格を採用 |
| 路線価 | 地点差の補正・角地/側方路線補正 | 間口奥行補正も確認→机上誤差を防ぐ |
| 見積書 | 数量×復旧仕様で控除額を確定 | 最少/最大レンジでリスク許容を表現 |
- 「舗装=法の道路」と誤認→台帳/指定図で根拠確認
- 後退面積の機会損失を失念→建物計画と価格に反映
先出し資料パッケージと開示チェック
高く早く売るには、弱点の正直な開示と解決ルートの提示を同時に行うことが近道です。
資料パッケージは、①道路種別(位置指定告示・2項台帳・幅員証明)②接道実測と後退線入り配置図(スケール写し込みの写真)③私道権利(持分一覧・通行/掘削/再掘削の承諾案)④越境一覧(写真付き)⑤数量表・復旧仕様・概算見積⑥工程表(承諾→設計→工事→引渡)を基本構成にします。
広告公開と同時にダウンロード可能とし、内見前に主要論点を解消しておくと、指値とキャンセルが減ります。
開示チェックは「事実と図面・写真が一致しているか」「役所回答は日付・担当・要旨が入っているか」「承諾案は範囲・承継・復旧基準が具体か」を必ず確認します。
| 資料 | 目的 | 開示のコツ |
|---|---|---|
| 道路・接道 | 接道可否・後退量の確定 | 後退線・隅切りを赤入れ→写真と対に |
| 私道権利 | 通行/掘削の恒常性の担保 | 承継条項付きドラフトを添付 |
| 見積・工程 | 不確実性の金額化と納期感の共有 | 最少/最大レンジ・予備日の設定を明記 |
- 図と写真の不一致をゼロに→寸法を写し込み
- 承諾案は“再掘削・工事車両・復旧断面”まで明記
まとめ
要点は、①法的道路か②接道2mか③後退量と④私道権利の四点です。
まず道路台帳・指定道路図で種別確認→接道実測とセットバック面積を算定→持分と通行掘削承諾を文書化→資料一式を先出し。
役所相談の記録と是正案の概算を添えれば、判断が早まり、価格の下振れを抑えられます。