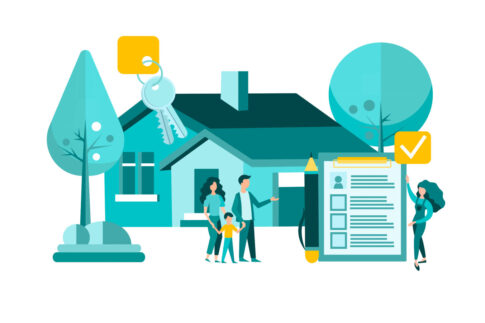不動産投資のローン返済を経費にできるかどうかは、多くの投資家が気になるテーマです。結論から言うと、元金返済は経費として計上できず、経費になるのは利息部分だけであることを押さえておきましょう。しかし、利息以外にも、減価償却や管理費、修繕費など、計上できる経費は多岐にわたります。正しい会計処理を行えば、節税効果を最大化し、キャッシュフローを安定させられるのが不動産投資の魅力です。
本記事では、ローン返済に関する正しい知識や誤った計上を避けるための注意点、さらに税務面での基本ルールや節税テクニックを詳しく解説します。銀行からの借り入れに関するリスクを適切に管理し、利息分のみの損金計上と組み合わせた賢い経費活用で、より有利に投資を進めましょう。
目次
ローン返済を経費計上する際の正しい理解

不動産投資で家賃収入を得ていると、「ローン返済を経費として落とせるのでは?」と考える投資家が少なくありません。確かに、ローン返済は毎月大きな支出となるため、経費にできれば納税額を抑えるうえで非常に魅力的です。
しかし、実際の税務上のルールでは、ローン返済の元金部分は損金(経費)として計上できず、損金処理できるのは利息部分のみという点をしっかり理解しておく必要があります。この仕組みは、不動産投資であっても個人のマイホームローンであっても基本的に同じです。
なぜなら、ローン元金の返済は「資金の借り入れを返しているだけ」であり、会計上は資産(不動産)を取得した際の元本を分割して返済している行為とみなされるためです。そのため、元金部分を経費化することはできず、実際に費用として計上できるのは金融機関に支払う利息分となります。
一方、家賃収入からローン利息を差し引いて申告する仕組みを理解しておけば、家計や投資のキャッシュフローをより正確に把握でき、資金繰りの見通しも立てやすくなるでしょう。
特に、物件を複数所有している場合や、リフォーム・修繕など他の経費がかさんでいるタイミングでは、元金返済と利息、そして減価償却などをそれぞれ分けて管理することがキャッシュフローの安定につながります。
また、このルールを誤解して元金返済まで経費に含めてしまうと、税務署からの指摘によって修正申告や加算税の対象となるリスクもあるため十分注意が必要です。
- ローン返済の元金部分は損金として計上できない
- 利息部分のみが税務上の経費となり、家賃収入から差し引くことが可能
- 元金返済を経費に含めると、税務上のトラブルを招く危険がある
- 適切な仕訳と計上で、正確なキャッシュフローを把握しやすい
- 元金返済=借入額の返済なので資産の購入費用にあたる
- 利息のみが不動産投資における支出(経費)として認められる
このように、ローン返済の内訳を把握して税務処理を行うことで、納税トラブルを回避しながら適正な不動産投資の運用が可能になります。
次の項目では、「利息のみ損金計上が可能」「元金返済がNG」と言われる理由をより詳しく掘り下げつつ、どのようにすれば効率的に経費として処理できるのかを解説していきます。
利息のみ損金計上可能!元金返済がNGな理由
不動産投資でのローン返済において、利息分だけが経費となる理由は、会計や税務の基本的な考え方に起因します。建物や土地などの不動産を購入するときにローンを組むと、毎月(または毎年)の返済額は「元金+利息」の合計ですが、元金部分はあくまで自己資産を形成する行為とみなされるのです。
会計上は、借入金によって購入した不動産という資産を、分割して買い取っている状態に近いイメージと考えるとわかりやすいでしょう。一方、利息は金融機関に対して支払う「資金を借りるためのコスト」であり、事業運営上のコストと認められるため損金として計上できます。
- 元金返済:投資用不動産の買い取り行為と見なされるため、経費扱い不可
- 利息:金融機関へ支払う資金調達コストなので、経費として算入可
- 減価償却:物件の購入費用を分割して経費計上する仕組み(元金とは別)
- 減価償却は建物の価値が減る分を経費計上する仕組み
- ローン元金返済は減価償却とは別に進めるが、資産価値の減少とは無関係
また、元金返済が経費にならないことを理解していないと、想定より大きく赤字を申告してしまう誤算や、税務上の指摘を受けるリスクが生じます。利息だけが経費化できると知っていれば、ローン返済額のうちどの部分を会計処理すべきか明確になり、キャッシュフロー管理にも役立ちます。
特に不動産投資ローンは返済期間が長期にわたるため、毎年の元金と利息の内訳をしっかり把握し、適切に仕訳を行うことが肝要です。
誤った計上でトラブル回避するための注意点
ローン返済の元金部分を経費に含めてしまうと、実際には課税されるべき所得が少なく申告されることになり、税務署から「申告漏れ」や「過少申告」と見なされるおそれがあります。こうしたケースが判明すると、修正申告や追加納税、場合によっては延滞税や重加算税が課されるリスクもあるため、十分に気をつける必要があります。
特に、元金返済と利息返済の区別を知らないまま会計処理を進めると、毎年の損益計算やキャッシュフロー予測が歪んでしまい、物件の正確な収益力をつかみにくくなるでしょう。
- ローン返済表を利用し、元金と利息の内訳を明確にする
- 利息のみを「借入金利息」の勘定科目などで経費計上する
また、減価償却と混同してしまう投資家もいますが、減価償却は建物などの資産が時間とともに価値を失うことを経費計上する仕組みであり、ローンの返済とは別の概念です。減価償却を正しく行うことで、購入した建物の費用を複数年にわたって分割して経費にできるため、結果的に課税所得を減らす効果があります。
ただし、こちらも計算方法や耐用年数を誤ると修正申告の対象になることがあるため、専門家や会計ソフトを活用して正確に処理しましょう。
- ローン利息と減価償却費を併用する形で節税効果を高められる
- 元金返済を経費化すると過少申告となり、将来的な税務調査リスク大
- 会計ソフトや税理士の助けを得て計上ミスを防止
- ローン返済額全額を経費に計上して赤字を拡大
- 元金・利息を分けずにまとめて「支出」として扱う
結果的に、ローン返済に関しては「利息のみが経費」という基本ルールを守りつつ、減価償却などの他の費用と合わせて総合的に損益を管理することが重要です。
誤った計上を避けるためにも、毎月の返済予定表や明細をもとに元金と利息を正確に仕訳し、年間のキャッシュフローを把握する仕組みを整えることが、不動産投資を長期的に安定運用するうえで不可欠となります。
不動産投資と税務の基本ルール

不動産投資では、家賃収入を得る一方でさまざまな費用がかかるため、これらを正しく仕訳し、損益計算を行うことが長期的な成功の鍵となります。特に、所得税や住民税を計算するうえでは、物件の取得コストや維持費、修繕費用をどのように経費化するかがキャッシュフローを左右します。
たとえば、物件を購入したときは、建物の購入費を耐用年数に応じて分割して計上する「減価償却」を行う必要があります。この減価償却費は、ローン返済の元金部分とは無関係に毎年の経費として計上できるため、実際のキャッシュアウトフローが起こらなくても課税対象額を下げる効果が期待できます。
また、固定資産税や都市計画税などの税金、物件管理に関する費用も経費として扱われるので、月々の家賃収入だけでは判断できない多角的な視点で収支を把握しなければなりません。
一方、誤った経費計上や処理ミスは、後から税務署の指摘を受けて修正申告や追加税の支払いにつながるリスクがあります。特にローン返済に関する元金・利息の仕分けや、修繕費と資本的支出の区別など、細かいルールを守ることが大切です。
修繕費は一度に経費化できますが、建物の価値を高めるような工事は「資本的支出」とみなされ、減価償却で時間をかけて経費にしていく形となります。
また、青色申告や法人化を利用すると、より大きな控除や損益通算のメリットを得られる一方、複式簿記での帳簿作成や税理士との連携が不可欠になります。こうしたルールを踏まえて正確な仕訳と会計処理を行えば、納税面でのトラブルを避けながら合理的な節税策を打ち出すことが可能です。
さらに、不動産所得は給与所得や事業所得などと合算され、総合課税の対象となるため、他の所得とのバランスを見ながら納税額をコントロールする視点も重要です。年収の多い会社員や自営業者の場合、不動産投資で発生した経費や減価償却費を差し引いて赤字が出れば、損益通算を行って他の所得を減らす(結果的に支払う税金を軽減する)仕組みが活用できます。
ただし、この赤字計上がローン元金返済や不適切な資本的支出によるものだと、税務署に否認されるおそれがあります。投資家としては、常に最新の税制改正や会計ソフトなどを利用して正確な仕訳を実施し、税務リスクを極力抑える努力が求められます。
- 減価償却や固定資産税など、複数の経費を総合的に管理
- 修繕費と資本的支出を区別し、正しいタイミングで経費化
- 青色申告や法人化を使って節税メリットを拡大
- 損益通算で他の所得とのバランスを最適化
- 納税リスクを抑えつつ、キャッシュフローを最大限確保できる
- 複数物件運用時に減価償却や修繕費を戦略的にコントロールしやすい
このように、不動産投資には多岐にわたる税務処理が関わりますが、基本ルールを押さえておけば、適切な経費計上とリスク管理を通じて効率よく資産形成を進められます。
次項では、減価償却など他の経費との組み合わせでどのように節税効果を高められるか、そして法人化や青色申告を活用した方法について詳しく解説します。
減価償却など他の経費との組み合わせで節税効果アップ
不動産投資の節税を考えるうえで、ローン利息以外にも見逃せない経費として「減価償却」が挙げられます。減価償却とは、建物や設備などの資産が時間とともに価値を失う分を毎年少しずつ経費として計上する仕組みです。
たとえば、RC(鉄筋コンクリート)造のマンションなら法定耐用年数47年、木造アパートなら22年など、構造によって異なる耐用年数をもとに計算が行われます。耐用年数の残りが短い中古物件を購入した場合は、さらに減価償却期間が短縮され、大きな額を短い期間で経費化できるため、課税所得を圧縮しやすくなるのです。
- 減価償却:建物や設備の価値低下分を毎年の経費に計上
- 法定耐用年数は構造によって異なり、中古物件は短縮される場合あり
- 減価償却とローン利息を組み合わせることで所得圧縮効果が高まる
- 法定耐用年数や残存年数を正確に把握して計算を行う
- 資本的支出と修繕費の違いを理解し、適切に処理
また、その他にも固定資産税や管理費、修繕費、火災保険料などの費用が経費として計上できるため、これらを組み合わせることで大きな節税効果を得られます。特に、ローテーションを組んで計画的に修繕を行えば、毎年の経費をある程度均等化し、キャッシュフローを安定させることが可能です。
さらに、投資家側でDIYを行う場合でも、材料費や工具費用を適切に証明できれば経費計上する余地があります。ただし、プライベートな支出と投資用支出を明確に区別しないと、税務署から否認されるリスクもあるため、領収書や明細書の保管が肝心です。
- 固定資産税、管理費、火災保険料なども組み合わせて節税効果を高める
- DIYやリフォームの材料費などは、投資用支出と証明できるなら経費化可能
- 支出の根拠を明確に示すために、領収書・契約書を保管
こうした経費計上を総合的に活用すれば、家賃収入に対して大きく課税されるのを抑えられ、ローン返済の負担を軽減しつつ資金を積み増すことができます。
結果的に、繰り上げ返済や新規物件の取得に投資家自身が自由に使える余剰資金を確保しやすくなるでしょう。次に、そうした税務上のテクニックをさらに活かす法人化や青色申告の手段について詳しく見ていきます。
法人化や青色申告の活用で負担を減らす方法
不動産投資で本格的に資産形成を目指す場合、個人投資家として活動するか法人を設立するか、あるいは青色申告を導入するかによって税負担が大きく変わってきます。まず、青色申告を選択すると最大65万円(不動産所得の場合は10万円または55万円などの場合もあり)の特別控除が受けられ、一定の条件を満たせば赤字を3年間繰り越せるなど、多彩な特典があります。
ただし、複式簿記で帳簿をつけるなど手間が増えるのがデメリットです。年収や物件数が多い場合は、その手間をかけるだけの節税効果を得られる可能性が高いため、導入を検討する価値があります。
- 青色申告:帳簿の整備が必要だが、特別控除や損失繰越など節税メリット大
- 白色申告:手続きが簡易的だが、控除が少なく節税効果も限定的
- メリット:法人税率の活用、社会保険料のコントロール、相続対策など
- デメリット:設立・維持コストがかかり、決算書作成や社会保険手続きの手間が増える
一方、法人化すると、個人事業とは異なる税率(法人税)で課税されるため、所得が一定以上増えた場合に有利になることがあります。さらに、役員報酬を設定すれば社会保険料や所得税の面で調整ができるなど、多角的な税務戦略が可能です。
ただし、設立費用や維持コスト、決算申告の手間もかかるうえ、法人として借り入れを行うには法人実績や代表者個人の信用力も考慮されるため、融資条件が変わってくる点に留意が必要です。
特に、不動産投資専業の法人を立ち上げると、物件数や収益規模に応じて税理士や社労士など専門家との連携が欠かせなくなりますが、成功すれば大きなスケールメリットを得ることができます。
- 法人税率を活かして、個人より低い税率で利益を残すことが可能
- 役員報酬や退職金などを用いた柔軟な資金管理ができる
- 物件数が増えるほど節税・拡大メリットが大きくなる反面、管理コストも上昇
- 物件数や投資規模が増えたら検討
- 専門家のサポートを得つつシミュレーションを行う
まとめると、ローン返済の元金部分が経費に含められない中でも、利息や減価償却、管理費などを組み合わせて大きな節税効果を得る方法は多々あります。
さらに青色申告や法人化で税務を最適化すれば、手残りが増え、追加物件の取得や繰り上げ返済などの選択肢が広がるでしょう。最終的に、年収や投資目的、物件数などを踏まえて、自分に合った申告方法や法人形態を選ぶことが、長期的に成功するためのカギとなります。
ローン返済と経費管理のポイント

不動産投資を長期的に成功させるには、ローン返済と経費管理をしっかりと行い、キャッシュフローを安定させることが不可欠です。ローン返済は毎月一定額の支出が発生し、利息部分のみ経費として認められるため、資金計画を誤ると空室や突発的な修繕費が重なった際に資金繰りが苦しくなるおそれがあります。
そのため、適切に金利タイプや返済期間を選んだうえで、経費として計上できる減価償却や管理費、修繕費などと合わせて全体の収支バランスを調整していくことが肝心です。特に、繰り上げ返済による利息軽減や借り換えによる金利低減を意識しつつ、修繕積立金の確保や空室リスク対策を同時に行うことで、より安定した投資運用が可能になります。
また、複数物件を同時に運用している場合は、それぞれの収支を分けて考え、リスクが集中しないようコントロールするのも重要です。
結果として、ローン返済計画と経費管理をセットで考慮すれば、税務リスクや資金ショートの可能性を最小限に抑えながら、長期的に安定利益を追求できるでしょう。
- ローン返済の利息部分は経費化できるが元金返済は不可
- 繰り上げ返済や借り換えで金利負担を削減
- 修繕・管理費や減価償却など、多角的に経費を組み合わせる
- 複数物件を運用する際はリスク分散を意識
- 返済計画に空室リスクや修繕費の発生を織り込む
- 月々の返済額と経費を合算し、キャッシュフローを定期的に再点検
金利タイプと返済計画の見直しでリスクを抑える
ローン返済を長期間続けるうえで避けては通れないのが「金利変動リスク」です。特に変動金利で借り入れをしている場合、市場金利の上昇によって返済額が増え、キャッシュフローを圧迫する可能性があります。
一方、固定金利を選択すれば、返済額を一定に保って安定運用を実現しやすいものの、変動金利よりも当初の利息負担が高くなるデメリットが考えられます。したがって、金利タイプを選ぶ際には、投資期間やリスク許容度、今後の金利動向への見通しなどを総合的に検討する必要があります。
- 変動金利:当初の返済額が低めだが金利上昇時の負担増に注意
- 固定金利:返済額が変わらず見通しを立てやすいが、金利は高めに設定される
- ミックスローン:変動と固定を組み合わせ、メリットを両立
- 繰り上げ返済で元金を早期に減らし、金利上昇リスクを軽減
- 借り換えで低金利の商品に乗り換え、総支払利息を圧縮
また、返済計画の見直しを定期的に行うことも重要です。繰り上げ返済で利息負担を抑えられるタイミングがあるなら、余剰資金を投入して返済期間を短縮するか、月々の返済額を軽減するかを選択する形でキャッシュフローを最適化できます。
ただし、繰り上げ返済により手元資金が減少すると修繕や空室時のリカバリー余力が低下するため、慎重なバランスが求められます。定期的な計画見直しを行い、金利タイプや返済期間を修正することで、金利変動リスクと安定運用を両立しやすくなるのです。
空室リスクへの備えと同時運用でバランスを図る
ローン返済と経費管理のバランスをとるには、空室リスクの対策も重要な課題です。いくら返済計画が安定していても、物件が空室になれば家賃収入が途絶え、キャッシュフローが一気にマイナスに転じる恐れがあります。
そこで、まずは物件選定時に立地や需要を見極め、空室が起きにくい環境を確保することが大切です。駅近や商業施設の充実したエリア、大学や企業が集中する地域など、賃貸需要が安定している場所を狙うことで、空室リスクを低減しやすくなります。
- 立地選定:駅徒歩圏や商業施設が近いエリアを優先
- ターゲット分析:学生向けやファミリー向けなど需要層を明確に
- リフォームや設備投資で物件価値を向上し、長期入居を促す
- 複数物件を運用し、一方の空室を他方の収益で補う
- 物件タイプやエリアを分散することで、一時的な経済変動を吸収しやすい
さらに、複数物件を同時に運用している場合は、物件ごとの収支バランスや空室率を一元管理し、リスク分散を行うことが効果的です。たとえば、都心区分マンションと地方一棟アパートを組み合わせれば、需要特性やリスク要因が異なるため、いずれかが不調でも他方でカバーできる可能性があります。
もちろん、同時運用では管理費や修繕費も複数分発生するので、管理会社や賃貸仲介会社との連携を密にして効率的な運用体制を構築することが不可欠です。
結果として、空室リスクへの備えと複数物件の同時運用を組み合わせれば、キャッシュフローの乱高下を抑えながらローン返済を着実に続け、安定した資産形成につなげることができます。
正しい会計処理で長期的に成功する不動産投資

不動産投資を安定して続けるには、正しい会計処理と継続的な見直しが欠かせません。特に、ローン返済の元金と利息、物件ごとの減価償却費や修繕費などを正確に仕分けし、毎年の損益計算を適切に行うことは、長期的なキャッシュフローの安定化につながります。
元金返済は経費に含めることができず、利息だけが経費になるという基本ルールを踏まえつつ、減価償却や管理費、火災保険料など、他の経費を組み合わせて「どのタイミングで、どの程度の税金が発生するか」を予測しておくことが重要です。
また、物件の構造や築年数によって耐用年数が異なるため、減価償却を正しく計算しないと納税額が過大・過少になるリスクが高まります。こうした会計処理のミスが後々の税務調査で発覚すると、追徴課税や修正申告が必要となり、投資計画そのものが大きく狂ってしまう可能性もあるでしょう。
さらに、不動産投資は事業規模が大きくなるほど多面的な管理が必要になります。複数物件を保有する場合は、家賃収入や修繕費、管理費などの経費を物件ごとに把握し、それぞれの収益率をチェックすることで、リスクが集中しないよう分散を図ることも大切です。
ローン返済と組み合わせたキャッシュフロー管理には、定期的な繰り上げ返済や借り換え検討なども有効ですが、これらの手段を使う際にも正確な会計処理に基づく損益把握が前提となります。
- 元金返済は経費にならず、利息だけが損金計上可能
- 減価償却や修繕費など他の経費とのバランスを考慮
- 複数物件の場合、物件ごとの収支を分けて管理しリスクを分散
- 適切な会計処理があってこそ繰り上げ返済や借り換えの効果が正確に見極められる
- 毎年の損益計算と納税額を細かく見直し、必要に応じて戦略を調整
- 税制改正や金利変動の情報をキャッチし、柔軟に対応できる体制を整える
結局のところ、正確な会計処理を土台にしてこそ、リスクを最小限に抑えながら最大限の利益を得ることが可能です。
次のセクションでは、より具体的に「繰り上げ返済や借り換えを活用して利息を削減するテクニック」と「税理士・コンサルタントを使った安定した資産拡大」について掘り下げ、投資家が長期的に成功するための実践的なノウハウを紹介します。
繰り上げ返済や借り換えを活用して利息を削減
不動産投資ローンの利息支払いは、経費として計上できる一方、実際には投資家のキャッシュフローを圧迫する大きな要因です。そこで大きく利息負担を減らすテクニックとして挙げられるのが「繰り上げ返済」と「借り換え」です。
繰り上げ返済では、毎月の返済とは別にまとまった資金を投入して元金を早期に減らすことで、返済期間全体の利息総額を圧縮できます。
特に、投資物件からの家賃収入とサラリーマンなど本業の給与を組み合わせて十分な余剰資金を確保できる場合は、積極的に繰り上げ返済を行うことで将来的な利息支払いを大幅に削減できるでしょう。ただし、繰り上げ返済手数料や手元資金の確保とのバランスをしっかり考える必要があります。
- 繰り上げ返済で元金を減らし、利息計算ベースを下げる
- 手数料やキャッシュフローへの影響を考慮し、計画的に実施
- ボーナスや家賃収入の一部を繰り上げ返済に回す戦略が効果的
- 借り換え先の金利がどれだけ低いか(差が1%以上あると有利な場合が多い)
- 借り換えに伴う諸費用(抵当権抹消・設定費用、事務手数料など)
- 借入期間をどう設定するかで毎月の返済額や総利息が変動
一方、借り換えでは、現在のローンよりも低金利の商品や優遇金利を打ち出している金融機関に切り替えることで、月々の返済額や支払利息を抑える狙いがあります。
たとえば、固定金利で契約した時点の金利が高いままになっている場合に、金利が下がったタイミングで変動金利や別の固定金利商品に借り換える方法が考えられます。ただし、借り換えには新たな諸費用が発生し、ローン審査を再度受ける必要があるため、借り換え前後の総費用を見比べて本当にメリットが大きいか慎重に判断することが大切です。
結果として、繰り上げ返済や借り換えは、利息負担を減らすだけでなく、金利上昇局面に備えたリスク管理としても有効な手段となります。
特に、複数物件を運用している投資家や、金利上昇が進みそうな局面では、早めにシミュレーションを行い、返済計画を見直すことで安定したキャッシュフローを確保しやすくなるでしょう。
税理士や専門家の協力で安定した資産拡大を目指す
不動産投資を長期的に継続し、ローン返済と経費管理を上手に行うには、税理士や不動産コンサルタントなどの専門家を活用するのも有力な選択肢です。税理士であれば、会計処理や税務申告のプロとして、ローン利息や減価償却、修繕費、青色申告特別控除などを総合的に最適化し、節税効果を最大限に引き出してくれます。
特に複数物件を所有している場合、どの物件でいくら経費が発生したかや、赤字と黒字をどのように損益通算するかなど複雑な処理が増えるため、プロの助けがあればミスを防ぎやすいです。
- 税理士:会計・税務処理を正確に行い、節税や損益通算を最適化
- 不動産コンサルタント:物件選定や賃貸管理、リスク分析に精通
- 法人化や青色申告の選択肢を提案し、将来の拡大戦略をサポート
- 帳簿ミス・仕訳ミスを回避し、税務リスクを抑える
- 複数物件の収支を一元管理し、管理効率を高める
- 相続税や法人設立など、将来的な展開にも対応しやすい
また、不動産会社や管理会社との連携も重要です。投資家が現地で物件の入居状況や修繕計画を逐一把握できないケースも多いため、信頼できる管理会社を選ぶことで、空室リスクや家賃滞納の初期対応、修繕時期のモニタリングなどを効率的に行えます。
結果的に、オーナー自身が会計・税務を中心とした戦略立案に集中できるため、追加投資や繰り上げ返済などの意思決定をより早く正確に行えるのです。
このように、専門家との連携を強化し、正しい会計処理・税務対策を行うことで、ローン返済と経費管理の両立が容易になり、不動産投資を長期的に続けていくための基盤が築かれます。
時には税理士から提案される法人化やコンサルタントによる物件売買のアドバイスなどを取り入れつつ、投資規模を拡大する戦略も模索していけば、より安定した資産形成とキャッシュフローが期待できるでしょう。
まとめ
ローン返済の元金部分が経費として認められず、利息だけが損金計上できるのは、不動産投資を成功させるうえで知っておくべき重要ポイントです。とはいえ、減価償却や管理費、修繕費、法人化や青色申告の活用など、適切に計上できる項目は多く存在します。正しい会計処理を行えば、税金負担を抑えながらキャッシュフローを高めることが可能です。
また、繰り上げ返済や借り換えといったローン戦略、専門家との連携を組み合わせれば、長期的なリスク対策と資産拡大を同時に実現できます。自分の投資目的やリスク許容度を踏まえ、賢く節税しながら堅実に不動産投資を続けていきましょう。