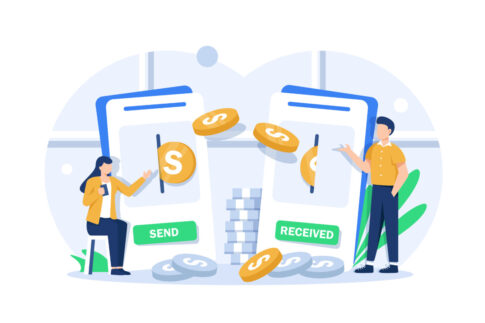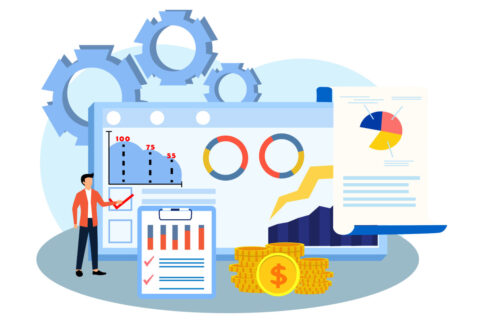高所得ながら税負担の重さに悩む公認会計士へ。本記事では給与所得控除の活用から法人化による所得分散、事務所経費・保険によるキャッシュコントロールまで、具体例でわかる節税術を体系化。
終盤では副収入と節税を両立できる不動産投資のメリットも紹介し、手取り向上と資産形成を同時に実現する方法を解説します。税務リスクを低減しながら、将来の事務所拡大やライフイベントに備える資金計画まで網羅した完全ガイドです。
目次
公認会計士が節税で得られる3つのメリット

公認会計士は高い専門性を武器に独立・開業や資産運用を行いやすい一方、年収が1,000万円を超えるケースも多く、累進課税による税負担が重くなるとされています。
たとえば給与所得だけで1,800万円の課税所得がある場合、所得税40%・住民税10%の合計50%帯に達し、税金で半分近くが差し引かれる可能性があります。
しかし、公認会計士であれば〈専門知識を生かした所得控除の最大化〉〈事務所経費や倒産防止共済を活用したキャッシュコントロール〉〈法人化による所得分散〉など、幅広い節税策を実践できる強みがあります。
これらを段階的に組み合わせることで、実効税率を20〜30%台へ抑えられる可能性が高まり、事務所の成長資金や将来の資産形成に回せる余力を確保できます。以下では、高累進課税の圧縮効果、キャッシュフロー再投資の余力、プロ視点の税務リスク低減という三つのメリットを詳しく解説します。
高累進課税の圧縮効果
公認会計士は顧問契約や監査報酬により高収入を得やすく、そのままでは所得税・住民税を合わせて最大55%を負担することになりかねません。そこで最初に押さえたいのが「所得控除」と「課税所得圧縮」です。
- 給与所得控除の把握:勤務会計士の場合、年収1,200万円なら給与所得控除は約195万円→課税所得1,005万円まで圧縮
- 特定支出控除の活用:専門書・研修費・学会参加費などが給与所得控除額の1/2超となる場合、超過額を追加控除できるとされています
- 青色申告65万円控除:独立開業後は複式簿記と電子申告を満たすことで基礎的な節税を確保
- 年初に経費計画を立て、領収書をクラウド保存→申告漏れを防止
- 倒産防止共済の掛金(年240万円上限)を経費算入→実効税率の高い年度に集中拠出
これらの控除をフル活用するだけでも、課税所得が数百万円単位で下がり、税額が年間100万円以上軽減されるケースがあると考えられます。圧縮後に残るキャッシュを次節で紹介する再投資に回すことで、さらなる資産拡大が期待できます。
キャッシュフロー再投資の余力
節税で生まれたキャッシュフローは「再投資」に振り向けることで複利的に資産を増やす原動力になります。公認会計士の場合、専門家ネットワークや金融リテラシーを活かし、以下のような再投資先を組み合わせるのが効果的とされています。
【再投資アイデア】
- iDeCo・新NISAで長期インデックス運用→運用益が非課税
- 倒産防止共済解約返戻金を事務所拡張資金に充当→掛金時の経費化と将来の資金確保を両立
- 不動産投資で減価償却と家賃収入を確保→節税+インフレヘッジ(二重メリット)
| 投資先 | 期待利回り | 節税ポイント |
|---|---|---|
| iDeCo | 年3〜5% | 掛金全額所得控除 |
| 新NISA | 年3〜6% | 運用益・配当非課税 |
| 不動産 | 年4〜8% | 減価償却で所得圧縮 |
- 短期資金→新NISA、長期資金→iDeCoと期間で分ける
- 物件購入前に20年CFシミュレーション→返済比率と修繕費を確認
キャッシュフローを再投資に回すことで、単なる節税にとどまらず「手取り増→再投資→収益増」の好循環が期待できます。特に不動産投資は減価償却による節税と家賃収入によるインカムが同時に得られるため、後述の資産運用章で詳述します。
プロ視点の税務リスク低減
公認会計士は税務知識が豊富とはいえ、自身の申告においては〈主観的判断〉が入りやすい点がリスクとされています。
税務調査で指摘を受けると、追徴課税や加算税が発生し、節税どころかペナルティがキャッシュフローを圧迫する可能性があります。そこで重要なのが〈監査的アプローチ〉を自分の経理にも適用し、チェックリストで客観性を担保することです。
【チェックリスト例】
- 経費区分があいまいな領収書→月次レビューで要否判定
- 倒産防止共済など多額支出→契約書・払込記録をクラウド保存
- 家族役員報酬→職務内容と合理性を議事録に記録
- 節税保険の解約返戻金を雑所得計上し忘れる
- 青色申告特別控除の条件(適時仕訳)を満たさず控除返還を指摘される
さらに、法人化で所得分散を行う場合は「実態が伴う業務委託」「適正な役員報酬」を文書で残すことが重要とされています。
国税庁の法人税率を参考に、個人・法人合算で最小負担となる報酬設計を毎期見直しましょう。こうしたプロ視点のリスク管理を徹底することで、節税効果を長期的に維持し、税務調査リスクも最小限に抑えられると考えられます。
勤務会計士・独立開業会計士別の節税策

勤務先に所属する会計士と独立開業会計士では、収入区分・経費計上範囲・社会保険の扱いが異なるため、選択できる節税メニューも大きく変わります。
勤務会計士は給与所得者として「給与所得控除」や「特定支出控除」を軸に課税所得を圧縮しつつ、iDeCoや新NISAで非課税運用枠を確保するのが基本とされています。
一方、独立開業会計士は事業所得者として青色申告を行い、事務所家賃や業務用ソフト購入費など幅広い経費を計上できます。
また、倒産防止共済や節税保険を活用してキャッシュフローを守りつつ、法人化による所得分散や小規模企業共済による退職金準備も選択肢に入ります。以下では〈給与所得控除と特定支出控除〉〈青色申告・事業経費の最大化〉〈退職金制度と小規模企業共済〉の三つに分け、勤務形態別の実践ポイントを詳しく解説します。
給与所得控除と特定支出控除
勤務会計士は会社からの給与を受け取るため、まず自動的に適用される「給与所得控除」で課税所得を下げることが基本となります。年収1,200万円なら約195万円が控除され、年収1,800万円でも約195万円が圧縮額の上限です。
控除額は給与テーブルに基づくため変動の余地は小さいものの、「特定支出控除」を組み合わせると追加で所得を減らせる可能性があります。
特定支出控除は〈研修・専門書の購入費〉〈学会参加費・旅費〉〈業務だけに利用するスーツや作業服〉など、職務遂行のために支払った費用のうち給与所得控除額の1/2超を追加で差し引ける仕組みです。
- 経費計画を年初に立て、領収書を原則電子保存→証憑不足を防止
- 勤務先の証明書発行フローを確認→確定申告時に提出漏れを防ぐ
- キャッシュレス決済を活用→利用明細が電子データとして残る
- 控除判定額を超えるか四半期ごとに試算→必要経費を前倒し購入する判断材料に
- iDeCoと合わせて所得を二段階で圧縮→手取りを最大化
これにより、実効税率が数ポイント下がるだけで年間数十万円の節税になる可能性があります。余力が生まれた資金は後述の再投資や自己研鑽費用に充当し、長期的な収入向上を図りましょう。
青色申告・事業経費の最大化
独立開業会計士は事業所得者に該当するため、帳簿を複式簿記で作成し期限内に電子申告を行うことで「青色申告特別控除65万円」を受けられます。
さらに、業務用パソコンやクラウド会計ソフト代、広告宣伝費、事務所家賃の按分などを経費計上することで課税所得を大幅に圧縮できます。
| 代表的な経費 | 節税ポイント |
|---|---|
| 事務所家賃 | 自宅兼用の場合、専有面積比で按分計上→固定費を経費化 |
| 業務ソフト | クラウド月額モデル→少額減価償却資産として即時費用化 |
| 通信費 | スマホ・Wi-Fiは業務使用割合で按分 |
- 年間30万円未満の備品は一括償却も検討→減価償却の手間を削減
- 出張先の宿泊費はビジネスプラン選択→私的要素を排除し税務リスクを低減
青色申告の65万円控除と経費計上を組み合わせることで、課税所得を数百万円単位で抑えられる可能性があります。また、月次で試算表を確認し、利益が増えすぎる期は倒産防止共済や設備投資を前倒しすることで所得を平準化できる点も独立開業会計士の強みです。
退職金制度と小規模企業共済
勤務会計士の場合、企業年金や確定拠出年金で退職金制度が整っていることが多いものの、独立開業会計士は自ら将来資金を準備する必要があります。
そこで有力なのが「小規模企業共済」です。月額1,000円〜7万円まで掛金を設定でき、全額を所得控除に算入できるため、掛金の負担を即時節税効果として享受しつつ、将来の退職金資金を積み立てられます。
- 共済契約期間が20年以上で元本割れリスクが解消→長期視点で加入
- 任意解約時でも掛金の7〜8割が戻る→資金流動性を確保
- 受取時は退職所得控除の適用→課税負担を大幅に抑制
- 短期解約は元本割れの可能性→最低でも10年超の加入を想定
- 掛金増減は年1回のみ→キャッシュフロー計画と連動させる
さらに、資産管理会社を設立して役員退職金規程を設ければ、法人損金算入と個人側での退職所得控除を同時に活用できるメリットもあります。
退職金準備を制度化することで、老後資金不足リスクを抑えつつ、現役時代の所得控除で節税効果を享受できるため、独立開業会計士は早めに制度設計を行うことが望ましいとされています。
事務所経費&保険を活用したキャッシュコントロール

公認会計士が長期的に安定したキャッシュフローを確保するには、毎月出ていく固定費を丁寧に管理し、利益が伸びた年度には節税型の保険や共済で資金をプールする二段構えが有効とされています。
まず経費面では〈家賃・通信費・ソフト使用料〉など固定コストを定点観測し、変動費である外注費や広告費は案件単位で収益性と連動させると、利益のブレを抑えられます。
一方、保険・共済は税制優遇が大きく、利益が想定以上に出た年度に掛金を拠出することで課税所得を平準化できます。
倒産防止共済や長期平準定期保険、そして最新の電子帳簿保存法に対応した経費処理フローを組み合わせれば、「納税資金は確保しつつ税負担を押さえる」というバランスの良いキャッシュコントロールが実現できます。
| 対策 | 主な効果 |
|---|---|
| 固定費の棚卸し | 赤字リスク低減・資金繰り安定 |
| 倒産防止共済 | 掛金全額経費計上・40か月経過後は解約返戻金で運転資金確保 |
| 節税保険 | 一時的な利益圧縮と退職金原資の確保 |
| 電子帳簿保存 | 証憑管理コスト削減・税務調査対応を効率化 |
- 月次で固定費をチェック→ムダな支出を排除
- 利益が想定超過の期は保険・共済へ資金移動
- 電子帳簿保存でペーパーレス化→証憑紛失リスクを解消
租税特別措置法を活かす倒産防止共済
倒産防止共済(正式名称:中小企業倒産防止共済制度)は、取引先の倒産など不測の資金ショートに備える経済産業省所管の制度です。
加入できるのは常時使用する従業員が50人以下の士業事務所などで、公認会計士の個人事務所や資産管理会社でも加入可能です。
掛金は月5,000円から20万円まで自由に設定でき、年間240万円を上限に全額を損金または必要経費として計上できるため、利益が大きく出た年度にまとめて拠出することで課税所得を大幅に圧縮できます。
掛金は40か月以上納付すると100%戻ってくるため、節税と資金準備の二つの効果を同時に期待できるとされています。
- 加入要件→中小企業者の範囲に該当する公認会計士事務所
- 掛金→月5,000円〜20万円(変更は年2回まで)
- 経費計上→掛金は納付時点で全額損金算入
- 資金調達→取引先倒産時に掛金総額の10倍・8,000万円まで無担保融資
- 利益が大きい期に月額上限へ増額→即効性の高い節税
- 40か月経過後の解約返戻金を事務所移転資金へ充当→資金繰りの柔軟性アップ
なお、短期での解約は掛金の80%未満しか戻らない場合があり、数年単位での利用が前提となります。加入前にキャッシュフローシミュレーションを行い、余裕資金の範囲内で掛金を設定しましょう。
節税保険の最新ルール
2019年の税制改正で「高返戻率の短期払い定期保険」が規制されて以降、保険を使った節税はルールが大きく変わりました。
現在は長期平準定期保険や逓増定期保険など、返戻率を抑えつつ保険期間を長く設定した商品が主流となっています。保険料の損金算入割合は保険種類や契約年数に応じた細かな区分に基づき、一定の合理性が求められます。
たとえば長期平準定期保険では払込期間が10年以上かつ返戻率が70%程度に設定されている商品であれば、保険料の1/2を損金算入できるケースがあります。
また、逓増定期保険は保険期間の前半で保険金額が逓増する設計に改められ、全額損金算入が可能なパターンは限定的です。
- 契約形態→法人名義で加入し、解約返戻金を退職金原資へ充当
- 損金算入割合→保険種類と期間で変動(1/2または1/3など)
- 解約返戻率→70〜80%が目安、高すぎると税務否認リスク
- 保険金受取時→益金算入されるため出口戦略が必須
- 解約返戻金を事務所運転資金に充当すると益金計上→税負担の先送りに過ぎない
- 高返戻率商品の勧誘には慎重に対応→税務否認リスクが残る
加入前には保険会社のシミュレーションだけでなく、税理士と共に法人・個人合算の税負担や資金繰りを確認し、出口時の税金とキャッシュインまで設計することが重要です。
電子帳簿保存法対応でペーパーレス経費管理
電子帳簿保存法改正により、2024年1月以降は紙証憑のスキャン保存や電子取引データの完全電子保存が義務化されました。
公認会計士事務所では、クラウド会計ソフトと連携した証憑管理システムを導入すると、証憑の検索性が高まり、税務調査時の対応スピードが向上します。
電子データ保存に必要な要件は〈真実性〉と〈可視性〉の二つで、電子取引データは改ざん防止措置としてタイムスタンプ付与や事務処理規程の整備が求められます。
- スキャナ保存→解像度200dpi以上・タイムスタンプ付与で紙領収書を破棄可能
- 電子取引→PDF・CSVなど元データを所定フォルダで7年間保存
- 検索要件→取引先・日付・金額で即時検索できるシステム設計
| 導入ステップ | 具体的作業 | 期待効果 |
|---|---|---|
| ①システム選定 | クラウド会計+証憑管理ツールを比較 | 連携コストと操作性を最適化 |
| ②社内体制整備 | 事務処理規程を策定・共有 | 法令順守を徹底 |
| ③運用開始 | 月次で証憑アップロードを確認 | データ漏れを防止 |
- 紙保管スペース削減→固定費を圧縮
- 証憑検索時間短縮→生産性向上と税務調査リスク低減
電子帳簿保存法に対応することで、経費精度が向上し、証憑紛失による経費否認リスクを大幅に下げられます。結果として課税所得の正確性が担保され、突発的な追徴課税リスクも抑えられるため、キャッシュコントロールの要として早期導入が推奨されます。
法人化と資産管理会社で税率を下げる

公認会計士が年間利益1,000万円を超え始めると、個人で受け取るよりも〈法人化〉や〈資産管理会社〉の設立により税率を引き下げる選択肢が現実味を帯びます。
個人課税では最高55%(所得税45%+住民税10%)帯に達する可能性がありますが、中小法人の実効税率は19〜23.2%台にとどまるため、同じ利益でも税負担差が拡大しやすいとされています。
さらに法人を活用すると給与所得控除とは別に〈役員報酬〉〈退職金〉〈福利厚生費〉など多様な経費化ルートが使え、資産管理会社を介して不動産や金融資産を保有すれば、所得区分ごとに最適税率を適用しながら資産を階層的に防衛することも可能です。
本章では〈法人税率と所得分散シミュレーション〉〈家族役員報酬と退職金〉〈消費税インボイス対応のコスト最適化〉の3テーマに分け、公認会計士が取り組みやすい節税スキームと実務注意点を解説します。
法人税率と所得分散シミュレーション
まずは「個人一本」か「法人+個人の分散」かで、年間税負担がどの程度変わるかを数値で確認しましょう。前提として〈年間純利益2,000万円〉を想定し、次のように比較します。
| 区分 | 課税対象 | 概算税額 |
|---|---|---|
| 個人のみ | 所得税40%+住民税10% | 約1,000万円 |
| 法人800万円 +個人1,200万円 |
法人税19%+所得税33%+住民税10% | 約668万円 |
- 法人化により差額約332万円が手取りに残る可能性
- 法人利益800万円以下は軽減税率19%→大幅に低い
- 個人側は課税所得1,200万円→33%帯にとどまる
- 決算前に試算表を作成→利益が急増する期は役員報酬や賞与で調整
- 法人利益800万円ラインを超過しすぎないよう複数法人化も検討
シミュレーションは「実際の経費」を差し引いた後の利益で行う点が重要です。
決算期直前に慌てて経費を積み上げるより、月次で利益をモニタリングし、必要に応じて報酬や共済掛金で早めに平準化すると税率メリットを最大化しやすいとされています。
家族役員報酬と退職金
法人化の節税効果をさらに高めるのが〈家族への役員報酬〉と〈退職金制度〉です。適正な職務内容と勤務実態があれば、家族に役員報酬を分散することで、それぞれの所得控除枠を活用できます。
たとえば配偶者へ年間500万円、成人した子へ年間300万円を支給すると、個人側では給与所得控除等が適用され、法人側では損金算入が認められるため、世帯合算での実効税率を大きく引き下げる効果が期待できます。
- 役員報酬は事業年度開始時に定時総会で決議→期中変更は原則不可
- 勤務実態を示すタイムカード・議事録を保存→税務調査時の証憑
- 扶養控除とのバランス→配偶者が控除対象外になる場合の再計算が必要
退職金については〈役員退職金規程〉を整備し、勤続年数と最終報酬月額に応じて支給額を算定することで、法人側は全額損金算入、個人側では退職所得控除(在職20年超部分は1年あたり70万円)を適用できます。
- 支給額=報酬月額×功績倍率×勤続年数→功績倍率は2.0〜3.0で妥当性を確保
- 退職時期を複数年に分散→大口支給で資金繰りが逼迫するリスクを防止
こうした分散スキームは節税メリットが大きい一方、形式だけで実態が伴わない場合は否認リスクがあります。毎期議事録を残し、役員の業務実績や報酬水準が合理的か第三者目線で再確認することが安全策になります。
消費税インボイス対応のコスト最適化
2023年にスタートしたインボイス制度により、課税売上1,000万円以下でも〈適格請求書発行事業者〉にならなければ仕入税額控除が受け取れない取引先が増えています。
公認会計士事務所が顧客から「インボイス発行」を求められるケースは多く、免税メリットが薄れる一方、登録に伴う事務コストと消費税納税義務が発生します。
- 売上高に占める非課税業務(監査証明料など)比率を算定→インボイス登録判断の材料に
- 簡易課税か本則課税かを選択→控除対象経費が少ない事務所なら簡易課税が有利な可能性
- システム投資→クラウド請求書発行ツールで発行業務を自動化
| 登録区分 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 免税事業者 | 納税義務なし→納付資金不要 | 取引先が仕入税額控除できず値下げ交渉リスク |
| 課税事業者 (本則) |
控除対象経費が多い場合に有利 | 記帳と申告が複雑→事務負担増 |
| 課税事業者 (簡易) |
記帳が簡単→みなし仕入率で計算 | 経費が多い場合は税負担が割高 |
- クラウド請求書ツールを共同利用→顧問先にも導入を促し業務効率を共有
- 期首に課税方式を検証→見込利益に応じて本則⇔簡易を切替
適格請求書の発行体制を整えることで顧客満足度を維持しつつ、最適な課税方式選択で消費税負担を抑えることが可能です。インボイス登録の可否は顧問先の属性や経費構造で変動するため、毎期シミュレーションし、納税額と業務コストのバランスを見極めることが鍵になります。
資産運用で広がる節税の可能性

公認会計士は収入水準が高く、累進課税の影響を強く受けやすい職業です。その一方で、金融リテラシーや決算書読解力が高いという利点を活かし、さまざまな資産運用手段を組み合わせれば「節税しながら資産を増やす」という二重のメリットを得られる可能性があります。
まず基本となるのが〈iDeCo〉や〈新NISA〉を活用した長期インデックス投資です。これらは運用益が非課税で再投資でき、掛金や投資額の全額もしくは運用益部分が税制優遇を受けるため、毎年の所得税・住民税を圧縮しながら複利効果を享受できます。
さらに倒産防止共済や長期平準定期保険などの共済・保険商品を組み合わせることで、利益が伸びた年度の課税所得を平準化し、将来の運転資金や退職金を準備するキャッシュリザーブも確保できます。
最終段階では〈不動産投資〉を組み入れ、減価償却費による所得圧縮と安定した家賃収入を得ることでキャッシュフローを補強しつつ、インフレ耐性を高めるポートフォリオを構築できます。
| 資産種別 | 主な節税メリット | 留意点 |
|---|---|---|
| iDeCo | 掛金全額所得控除・運用益非課税 | 60歳まで原則引き出し不可 |
| 新NISA | 運用益・配当が恒久非課税 | 投資枠の上限管理が必要 |
| 倒産防止共済 | 掛金全額損金算入 | 40か月未満で解約すると元本割れ |
| 長期平準定期保険 | 保険料の1/2損金算入が目安 | 出口時課税に注意 |
| 不動産投資 | 減価償却による所得圧縮 | 空室・修繕リスクを把握 |
- iDeCo・新NISAで基礎を固める
- 共済・保険で利益を平準化
- 不動産投資でキャッシュフローと資産価値を両立
このように、資産運用を段階的に組み合わせることで節税効果と資産形成を同時に拡大できる可能性があります。特に減価償却を通じて課税所得を圧縮できる不動産投資は、公認会計士のような高所得者にとってポートフォリオの核となりやすく、次項で詳しく解説します。
公認会計士に不動産投資がおすすめな理由
不動産投資は「節税」「資産保全」「安定収入」の三拍子がそろった運用手段といわれていますが、公認会計士にとっては以下の理由で特に相性が良いと考えられます。
まず第一に〈高い信用力〉です。金融機関は会計士の安定収入と専門知識を評価しやすく、長期固定金利ローンを低金利で組める傾向があります。
この与信メリットを活かせば、自己資金を抑えても複数物件を効率的に取得し、レバレッジ効果を高められる可能性があります。第二に〈減価償却費による所得圧縮〉です。
築年数が経過したRC造マンションを購入すると、残存耐用年数で建物価格を償却できるため、家賃収入の黒字を上回る減価償却費を計上して不動産所得を赤字化し、給与所得と損益通算できるケースがあります。
第三に〈決算書読解力・税務知識〉という専門スキルを活かせる点です。物件の収支計算書や管理費、修繕履歴などを精査し、税務上のリスクを事前に把握できるため、一般投資家より精度の高い判断がしやすいとされています。
- 与信力→低金利・長期ローンで資金調達しやすい
- 減価償却→所得圧縮で実効税率を引き下げる
- 専門知識→収支分析・税務処理を自力で行える
- 駅徒歩10分圏内かつ築古RC→安定稼働と高償却費を両立
- 金利上昇リスクに備え固定or長期固定金利を優先
- 修繕積立金の残高と長期修繕計画を必ず確認
不動産投資を開始する際は、税理士と連携して減価償却シミュレーションを行い、給与所得と損益通算した場合の実効税率を試算することが第一歩です。
また、家賃収入が黒字化した後は法人化して資産管理会社へ物件を移管することで、法人税率の恩恵を受けながらキャッシュフローをさらに最適化できる可能性があります。専門知識と与信力を最大限に活かし、長期的な資産形成と節税を同時に進めましょう。
まとめ
公認会計士が節税を成功させる鍵は、①給与所得控除や特定支出控除で課税所得を圧縮、②事務所経費と保険でキャッシュを守る、③法人化と資産管理会社で税率を引き下げる、の三段階にあります。
さらに自己資金とレバレッジを両立できる不動産投資を組み合わせることで、税負担を減らしつつ長期の資産形成を加速できます。まずは控除額の棚卸しと法人化シミュレーションから着手しましょう。