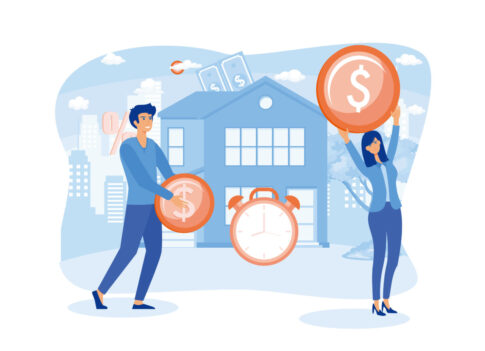高所得ゆえ税率の高さを痛感する税理士のあなたへ。減価償却・損益通算を駆使した不動産投資は、自身の専門知識を活かしながら税負担を最適化できる有力手段です。
本記事では、税理士が実践すべき投資スキームや申告手続きの注意点、リスク管理まで体系的に解説。忙しい実務の合間でも実行できるステップ別チェックリストも掲載――ぜひ最後までご覧ください。
不動産投資で得られる主要な税メリット

不動産投資には、税理士のような高所得者が抱えがちな「税率負担の高さ」と「キャッシュフローの硬直化」という二つの課題を同時に和らげる力があります。
最大の特徴は〈経費計上できる費目が多い〉ことです。建物部分の減価償却費、ローン利息、管理費、固定資産税などが毎年の不動産所得から控除でき、課税所得を計画的に圧縮できます。
また、赤字が発生した場合は一定要件のもと他の所得と損益通算を行えるため、本業収入にかかる所得税を実質的に引き下げることも可能です。
さらに、相続・贈与の局面では土地建物の評価額が時価より低く算定されやすく、節税しながら次世代へ資産を移転できる点も見逃せません。ここからは代表的な三つのメリットを具体的に見ていきます。
減価償却による所得圧縮とキャッシュ維持
減価償却とは、建物という高額資産を耐用年数にわたって少しずつ費用化する会計処理です。手元のキャッシュは減らさずに帳簿上の費用だけが増えるため、課税所得を下げながらキャッシュフローを維持できる効果があります。
たとえば中古木造アパート(耐用年数22年)を築23年時点で取得した場合、法定耐用年数は4年となり、購入価格の建物部分を4年間で均等償却することが可能です。年間の減価償却費が大きくなるぶん所得税・住民税が軽減され、本業収入で納税に回る現金を手元に残せる仕組みです。
【減価償却を活用するポイント】
- 耐用年数が短い中古物件ほど初期の節税効果が高まる
- 区分所有より一棟物件の方が建物割合を高く設定しやすい
- ローン返済額と償却費のバランスを把握し、過度な赤字を避ける
- 購入前に「税引後キャッシュフロー」を確認することで、実際に残る手取りを把握できます。
- 耐用年数終了後の税負担増に備え、次の投資や繰上返済プランを早めに検討しましょう。
青色申告・損益通算で所得税を削減
賃貸事業として開業届と青色申告承認申請書を提出すると、最大65万円の青色申告特別控除を受けられます。加えて、家族を専従者給与として計上すれば給与の一部を必要経費化でき、所得を家族へ分散させる効果も期待できます。
さらに不動産所得が赤字になった場合、給与所得や事業所得と損益通算が可能です(ただし土地取得に伴う負債利子など一部制限あり)。
たとえば本業の事業所得が1,500万円、不動産の赤字が▲300万円の場合、課税対象となる所得を1,200万円まで引き下げられる計算となり、税率区分が一段階下がるケースもあります。
【青色申告の主なメリット】
- 65万円控除→複式簿記+貸借対照表の提出で適用
- 家族給与→実務内容・金額が相当であれば経費算入可
- 30万円未満の資産→少額減価償却資産として一括経費化
- 土地購入のための借入金利息は通算対象外となることがあります。
- 別荘など居住用割合が高い物件は、不動産所得ではなく雑所得に区分される場合があります。
相続・贈与対策としての評価額引下げ効果
土地や建物は相続税評価額が〈路線価×補正率〉や〈固定資産税評価額〉で算定されるため、時価よりも低い評価になりやすい傾向があります。たとえば都心部のマンション一室を5,000万円で購入しても、相続税評価額はおおむね時価の7割前後になるケースが多いです。
さらに賃貸中であれば借家権割合(原則30%)と借家人控除(概ね▲30%)が適用され、評価額が実質的に半分程度まで下がる可能性があります。
その結果、現預金で保有すると大きな相続税課税対象となる資金を、賃貸不動産に組み替えることで評価を抑えつつ家賃収入も得られる二重のメリットが生まれます。
【評価額を下げる三つの視点】
- 居住用より賃貸用→借家権割合で評価減
- 整形地より不整形地→地積補正で評価減
- 共有持分化→持分評価減だが管理コスト増に注意
- 評価額が下がりすぎると、売却時の譲渡所得税が想定より大きくなる場合があります。
- 相続人の納税資金確保のため、収益性と流動性のバランスを重視しましょう。
税理士が押さえるべき不動産投資スキーム

不動産投資と一口にいっても、投資対象の種類や所有形態、資金調達方法によって節税インパクトは大きく変わります。
税理士の立場であれば、①物件タイプ(区分マンションか一棟アパートか)②所有形態(個人か法人か)③レバレッジ(融資比率や金利)の三つを組み合わせ、所得圧縮とキャッシュフローのバランスを最適化する視点が欠かせません。
たとえば中古の一棟アパートを法人名義で取得し、短い耐用年数で一気に償却しつつ、低金利長期ローンを活用する構成は「減価償却+所得分散+金利経費化」の三重効果が狙えるため、高所得層には定番のスキームとされています。
本章ではそれぞれの要素を順番に整理し、実務で活かせるポイントを紹介します。
区分マンション vs 一棟アパート—償却年数とキャッシュフロー比較
区分マンション投資は購入価格が比較的抑えやすく、立地を厳選すれば空室リスクを低減できます。しかし建物割合が小さくなる傾向があるため、減価償却費による所得圧縮額は限定的となりやすいです。
一方、一棟アパートは土地より建物割合を高く設定しやすく、築古物件なら残存耐用年数が短くなるため、4〜8年程度で大きな償却費を計上できるケースがあります。その代わり、修繕費や管理コストが区分より高く、空室が複数室同時に発生するリスクも考慮が必要です。
| 項目 | 比較ポイント |
|---|---|
| 取得価格 | 区分は1,500万〜3,000万円前後が中心。 一棟は7,000万〜2億円超まで幅広い。 |
| 償却スピード | 区分:耐用年数残存多く10年以上の場合も。 一棟:耐用年数超過なら4〜6年で償却可。(躯体による) |
| 管理手間 | 区分は管理会社任せで少ない。 一棟は共用部修繕や入居付けで負荷増。 |
- 初期キャッシュを抑えたい→区分で立地重視
- 短期で所得を圧縮したい→築古一棟で償却重視
- 分散投資を図りたい→区分と一棟を組み合わせる
法人設立による所得分散と所得税・住民税の最適化
個人名義で保有する場合、所得が累進課税の最高税率帯に達していると、家賃収入のほとんどが高税率で課税される可能性があります。
そこで物件購入と同時に資産管理会社を設立し、法人名義で物件を保有するスキームが選択肢となります。
法人を活用するメリットは、①法人実効税率が概ね30%前後で頭打ちになる、②家族を役員にして役員報酬を分散できる、③損益通算はできないものの繰越欠損金で将来の法人税を圧縮できる、の三点です。
設立時には資本金1,000万円未満に抑えて消費税免税期間を確保するなど、初期の税負担を軽減する工夫も重要です。
- 役員報酬→適正額であれば経費算入可
- 給与所得控除→個人側の課税所得を下げる効果
- 退職金→損金算入しつつ個人の税負担を抑制
- 会計・税務顧問料が年間数十万円発生します。
- 決算公告や社会保険加入など事務負担が増えます。
レバレッジを活かすローン活用と金利経費化
レバレッジとは、自己資金より大きな投資規模を実現するために金融機関から借入を行うことです。不動産投資ローンの金利は、個人でも法人でも全額を必要経費に算入できます。
そのため、金利支払分が実際のキャッシュアウトでありながら、税務上は所得を引き下げる効果があります。たとえば年利2.0%、残債1億円のローンであれば年間200万円の利息が経費となり、最高税率45%の場合は約90万円の税軽減インパクトが期待できます。
ローン活用のポイントは「長期固定金利でキャッシュフローを安定化させつつ、返済期間中に償却が終わるよう資金計画を組む」ことです。返済額がフル償却期間と重なれば、税引後キャッシュを黒字に保ちやすくなります。
一方、過度なレバレッジは空室や金利上昇時に資金繰りを圧迫するため、返済比率(DSCR)は最低でも1.2倍以上を目安に設定すると安心です。
- 自己資金:物件価格の20%以上を投入し金利優遇を狙う
- 金利タイプ:変動より固定→長期安定を優先
- 繰上返済:償却終了後の税負担増に備えてタイミング調整
- 直近の確定申告書・決算書を整備して返済能力を示しましょう。
- 物件の収益性だけでなく自己資金割合も重視されます。
実践フロー:物件選定から申告までのステップ

物件を購入して減価償却を計上するだけでは、安定した節税と資産形成は実現しません。投資家である税理士が成果を最大化するためには、①投資目的の明確化、②物件・資金調達・管理体制の整備、③帳簿作成と申告プロセスの精度向上という三段階を抜けもれなく踏む必要があります。
まず、家賃収入でキャッシュフローを厚くするのか、減価償却で課税所得を圧縮するのかといったゴールを設定し、目標利回りとリスク許容度を数値化しましょう。
次に、目的に合致したエリア・築年数・利回り帯の物件をピックアップし、金融機関ごとの金利や融資条件を比較しながら資金計画を組み立てます。
最後に、青色申告の承認申請、簿記ソフト設定、証憑整理フローを整え、確定申告へスムーズに接続する仕組みを作ります。以下の各項目では、実務的な手順を詳細に解説します。
投資目的設定と収支シミュレーション法
投資の成否は「なぜ買うのか→いくら残るのか→いつ回収できるのか」を数値で把握できるかどうかに左右されます。
まずは〈節税額〉〈年間キャッシュフロー〉〈想定利回り〉を三本柱にシミュレーションを行いましょう。具体的には、物件価格・諸費用・借入条件・減価償却費・経費を入力し、税引後の手取りを試算できるシートを作成します。
| 入力項目 | チェックポイント |
|---|---|
| 購入価格 | 建物割合を高められるか→減価償却額に直結 |
| 借入条件 | 金利・期間・元利均等/元金均等の違いを確認 |
| 空室率 | 周辺平均+リスク加算で保守的に設定 |
- 月間キャッシュフローが赤字なら節税額で補填可能か確認しましょう。
- 減価償却終了後の税負担増を二期分以上シミュレーションし、出口戦略を検討しましょう。
専門家ネットワーク活用(不動産業者・金融機関)
独自で融資交渉や物件調査を行うよりも、実績豊富な専門家と連携したほうが条件は好転しやすく、情報精度も高まります。まず物件選定では、仲介手数料や管理委託料だけでなく、リフォーム費用や家賃設定の妥当性を合わせて提案できる業者をパートナーに選びましょう。
金融機関については、地銀・信金・ノンバンクで融資審査の着眼点が異なるため、物件種別と借入目的に合った先を複数打診することが重要です。
- 仲介会社→レントロール・修繕履歴・近隣賃料相場を必ず提出してもらう
- 管理会社→管理委託契約書の内容を事前に精査し、修繕積立金の要否を確認
- 金融機関→融資期間が耐用年数を超えると金利が上がる傾向があるため要注意
- 仲介会社の試算は売却目線が強く、収支が楽観的になることがあります。
- 金融機関の審査通過実績を過度に優先すると、金利や担保条件が割高になるおそれがあります。
確定申告での減価償却計上と留意点
物件を取得したら、当期から適切に減価償却を開始するための帳簿設定が必要です。まず購入時の建物・設備・土地を明確に区分し、建物は「構造×築年数」で耐用年数を算定して償却率を決定します。
法定耐用年数を超える中古物件は「(耐用年数×20%)」または「残存耐用年数=耐用年数−経過年数+経過年数×20%」の短い方を選択可能です。
確定申告では、家賃収入・経費・減価償却費を集計し、不動産所得を算出した後に青色申告特別控除や専従者給与を反映して最終所得金額を決定します。
- 取得原価を建物・設備・土地に区分→減価償却計上の基礎
- 資産残高を転記→固定資産台帳を作成
- BS・PL完成→青色申告決算書へ反映
- 損益通算→必要に応じて給与所得と相殺
- 償却費の計算で千円未満を切り捨てて誤差を避けましょう。
- 期中に取得した場合、月割計算を適用し損金算入額を調整しましょう。
節税効果を最大化するためのリスク管理と出口戦略

不動産投資は減価償却や損益通算で強力な節税ツールになりますが、空室・修繕・市場変動といったリスクを軽視すると本業収入まで圧迫する恐れがあります。
そこで重要になるのが「定量的なリスク管理」と「税負担を最小化する出口戦略」の併用です。まず保有期間中はCF(キャッシュフロー)・稼働率・修繕積立金を月次でモニタリングし、マイナスが見えた時点で早期に打ち手を講じる体制を整えます。
次に、譲渡益課税が低くなる長期保有を基本としつつ、償却終了後や大規模修繕前など税率と収益性が交差するタイミングを「売却候補期」としてあらかじめ想定します。
最後に税制改正やインボイス制度といった法制度のアップデートを定期チェックし、必要に応じて保有法人の見直しや管理委託契約の更新を行うことで、節税効果を中長期で維持しやすくなります。ここでは具体的なリスクごとの対策と、売却時の税金比較、制度対応のチェックリストを順に解説します。
空室・修繕リスクへの備えと税務的影響
不動産投資の最大のリスクは、空室や突発的な修繕による収益低下です。空室が続けば家賃収入が減り、損益通算による節税額は増えるものの、キャッシュフローが赤字化して本末転倒となります。
また修繕費は即時経費化できる半面、計画外の出費が続くと資金繰りを圧迫します。そこで投資初期に「空室率◯%上昇」「修繕費◯円発生」といったシナリオを設定し、CFがマイナスにならないラインをシミュレーションしておくことが不可欠です。
- 空室対策→賃料帯の柔軟変更・ターゲット層の再設定・募集写真の刷新
- 修繕対策→屋根・外壁など高額部位は5年ごとに積立計画を作成
- 税務対応→修繕費は「資本的支出」判定に注意し、誤れば減価償却扱いで節税効果が遅延
- 家賃値下げで稼働率改善を図っても収益悪化が加速する場合があります。
- 赤字が大きいと金融機関の追加融資審査に不利な材料となりやすいです。
保有・売却タイミング別の税金比較(譲渡所得税)
物件を売却する際の譲渡所得税率は「5年以下=短期」「5年超=長期」で大きく異なります。短期譲渡は所得税30%+住民税9%、長期譲渡は所得税15%+住民税5%が基本です。
| 保有期間 | 税率(所得税+住民税) | 活用可能な主な制度 |
|---|---|---|
| 5年以下 | 39% | 控除なし。赤字繰越による相殺を検討。 |
| 5年超 | 20% | 控除なし。 |
- 減価償却済み後は簿価が低下→譲渡益が大きく課税所得増。
- 保有法人で売却→法人税+個人側の配当課税を二段階計算。
- 大規模修繕直後の売却→資本的支出を含めた簿価アップで譲渡益圧縮。
- 償却終了年+2期を目安に、税率・修繕・賃料下落の三要素を合わせて再評価しましょう。
- 法人保有なら分配方法を役員報酬・配当・退職金で比較し、全体の実効税率を算出しましょう。
税制改正・インボイス制度への適応チェックリスト
不動産投資は税制改正の影響を受けやすく、特にインボイス制度導入後は課税売上1,000万円以下のオーナーでも消費税の取り扱いを再確認する必要があります。
軽減税率の対象外である賃貸住宅は不課税ですが、事業用テナント物件を所有している場合、適格請求書発行事業者の登録有無で仕入税額控除の可否が変わります。
また減価償却制度や損益通算の制限が将来的に見直される可能性もあるため、毎年の税制改正大綱をチェックし、影響度を早期に把握することが大切です。
- インボイス登録→賃貸が課税売上の場合は原則必須
- 青色承認→電子帳簿保存法改正へのシステム対応を確認
- 損益通算→新たな制限案が提示された場合に備えて代替節税策を準備
- 毎年12月公表の税制改正大綱を読込み、影響項目を抜粋しましょう。
- 管理会社・税理士・金融機関の合同ミーティングを設定し、実務対応を分担しましょう。
まとめ
本文では、高所得税理士が自らの税負担を減らしつつ資産形成を図るための不動産投資戦略を解説しました。減価償却や損益通算を用いることで課税所得を圧縮し、キャッシュを確保できます。
法人設立や物件種別の選択、出口戦略まで段階的に示したチェックリストを実践すれば、限られた時間でも効率的に節税効果を最大化可能です。次の決算までに行動を起こし、安定したキャッシュフローと将来のリスクヘッジを同時に実現しましょう。