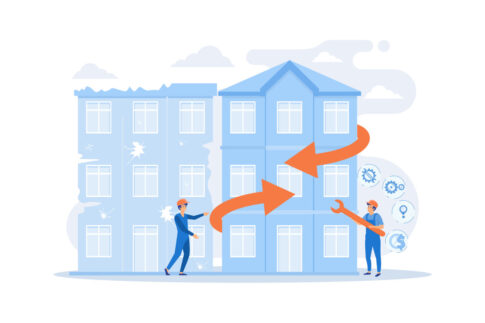再建築不可は「接道2m・道路幅4m」を満たさず新築できない土地のこと。
本記事では、建築基準法42・43条の要点、見分け方と調べ方の3手順、リフォーム可否、売買・評価の注意点までを、公式情報に基づき平易に整理。購入前や売却検討時の失敗回避に役立つ実務チェックリストとしてご活用ください。
再建築不可の基礎知識と見分け方

再建築不可とは、原則として「建築基準法上の道路」に所定の条件で接していないため、新たな建物の建築確認が下りにくい(または下りない)土地を指します。
よくある原因は、敷地が法定の道路に面していない、敷地と道路が細い通路でつながるが幅が不足している、道路自体が法的な道路に該当しない、などです。
初めての方は専門用語に戸惑いがちですが、基本は「道路の種類」と「接している長さ・幅」を順に確かめれば迷いにくくなります。実務では次の流れで確認を進めると効率的です。
【確認の流れ】
- 公図で敷地形状と隣接地の概況を把握する
- 道路台帳や指定道路図で「法42条の道路」かを確認する
- 役所窓口で接道長さやセットバック要否を照会する
| 判断ポイント | 要点 | 主な確認資料 |
|---|---|---|
| 道路の種類 | 法42条のいずれの道路に該当するか | 指定道路図・道路台帳・位置指定図 |
| 接道の状態 | 敷地が道路に2m以上接しているか | 測量図・求積図・現地実測 |
| 道路幅員 | 幅4m以上か、2項道路でセットバック要か | 道路幅員証明・現地確認 |
- 「法42条の道路」かどうか
- 敷地の道路への接道長さが2m以上か
- 道路幅が4m未満ならセットバックが必要か
対象エリアと基本的な考え方
再建築不可の考え方は全国で共通の枠組みですが、影響の出方は地域の状況で変わります。
市街地では路地状敷地(旗竿地)や袋地、古い私道沿い、川跡・水路跡に沿った細い通路などで「接道不足」になりやすいです。
郊外や集落部では、昔からある細道や農道が「建築基準法上の道路」に該当しないケースが見られます。
また、用途地域や市街化調整区域のように、道路要件に加えて別の許可や基準が絡むこともあります。
重要なのは、地目や見た目ではなく「法的に道路と認められているか」と「敷地が必要な幅で接しているか」を客観的に確かめることです。
購入前であれば、測量図や越境の有無、共有私道の持分、通路部分の地権関係も合わせてチェックすると、後戻りが減ります。
【対象になりやすいパターン】
- 旗竿地で通路部分の幅が2m未満
- 行き止まりの私道で位置指定が未了
- 側溝・水路・農道を介しているだけで法的道路と接していない
- 共有私道だが通行・掘削等の承諾が不明確
- 舗装や白線があっても、法42条の道路に該当しないことがある
- 古い里道・水路敷は権利関係や用途が異なる場合がある
接道2m・道路幅4mの原則
原則として、建築物の敷地は「建築基準法上の道路」(法42条)に接し、その接している部分の幅が2m以上必要とされます。
さらに、道路自体は幅員4m以上が基本です。幅員が4m未満でも、施行前からある道で「2項道路」に該当すれば、道路中心線から所定の後退(セットバック)を行うことで扱いが認められる場合があります。
接道長さの測り方は、敷地と道路が接する直線距離で判断するのが一般的で、曲がった細い通路や他人地の角をかすめるような接し方は認められないことがあります。
敷地延長(旗竿)の通路部分は有効幅2m以上が目安で、門柱や塀・給湯器等の出っ張りが有効幅を削ることもあるため、現地実測が欠かせません。
| 条件 | 概要・実務の見方 |
|---|---|
| 接道2m以上 | 敷地が法42条道路に連続して2m以上接する。路地状通路は有効幅を確保。 |
| 道路幅4m以上 | 原則4m以上。4m未満は2項道路の可能性を確認し、必要ならセットバック。 |
| 角地・曲線 | 隅切りやカーブでは有効接道の取り方に注意。測量図で線形を確認。 |
- 旗竿地の通路幅が1.8m→接道不足になり再建築不可の可能性
- 前面道路3.6mの古道→2項道路なら0.2mずつ後退し有効4mを確保
公図・道路台帳・指定道路図
書類での下調べは、ムダな現地調査や契約トラブルを減らします。公図は土地の大まかな区画や隣地との位置関係を把握する資料で、正確な面積や境界線は確定測量図で補います。
道路台帳や道路管理者の資料、自治体の「道路種別図・指定道路図」などで、前面路が法42条のどの道路に該当するか、幅員や管理者を確認します。
私道の場合は、位置指定道路の図面や告示、私道掘削・通行承諾の要否もあわせて確認します。
最後に、建築指導担当で接道長さの取り方やセットバックライン、将来の整備計画の有無を照会すると、再建築可否の見通しが立てやすくなります。
【よく使う資料と入手先】
| 資料 | 内容・入手のヒント |
|---|---|
| 公図・地積測量図 | 筆界の概況と形状を確認。法務局で取得、過去測量図があれば精度向上。 |
| 道路台帳・幅員証明 | 道路の管理者・幅員を確認。市区町村や道路管理者で発行依頼。 |
| 指定道路図・位置指定図 | 私道が法42条の「位置指定道路」かを確認。告示・図面の写しを入手。 |
- 公図は精度に限界→境界は確定測量で補う
- 台帳幅員と現地幅員が異なることがある→実測で再確認
法的根拠と道路種別の要点

再建築不可かどうかは、「どの種類の道路に、どう接しているか」でほぼ決まります。根拠は建築基準法で、道路の定義は第42条、接道の義務は第43条に規定されています。
第42条では、幅員4m以上(地域指定により6mの場合あり)の道路のうち、1項1号〜5号および2項(いわゆる2項道路)を「建築基準法上の道路」として列挙しています。
特に、1号(道路法による道路)・5号(位置指定道路)・2項道路(狭あい道路のみなし道路)は実務で頻出です。
まずは、前面道路が以下のどれに当たるかを役所資料(道路台帳、指定道路図、位置指定の告示)で確認し、次に「敷地がその道路に2m以上接しているか」「幅員不足ならセットバックが必要か」を順に点検すると、判断を誤りにくくなります。
| 区分 | 要点 | 典型資料 |
|---|---|---|
| 42条1項1号 | 道路法による道路(国道・都道府県道・市区町村道等/幅員4m以上) | 道路台帳・路線認定 |
| 42条1項2号 | 都市計画法、土地区画整理法、密集市街地整備法等による道路 | 事業計画図・換地図 |
| 42条1項3号 | 基準適用時に現に存在していた道(既存道路) | 指定道路図・公告 |
| 42条1項4号 | 2年以内に事業執行予定として指定された計画道路 | 特定行政庁の指定公告 |
| 42条1項5号 | 位置指定道路(私人が築造し、位置の指定を受けた道) | 位置指定図・告示 |
| 42条2項 | 幅員4m未満の狭あい道路(みなし道路)→中心線からの後退が必要 | 2項道路指定図・幅員証明 |
建築基準法42条の道路種別
第42条は、建築に使える「法の道路」を6区分(1項1〜5号+2項)で定義しています。
1項1号は道路法による公道、2号は都市計画・区画整理・再開発・密集市街地整備など各事業法に基づく道路、3号は基準適用時に既にあった道、4号は2年以内に執行予定の計画道路、5号は位置指定道路です。
2項道路は幅員4m未満でも一定条件を満たせば「みなし道路」として扱われ、建替え時に後退して将来4m幅を確保する考え方です。
現地では「舗装されている=法の道路」とは限らず、私道や水路敷、里道などは個別確認が必要です。
物件調査では、指定道路図や位置指定の告示、2項道路の指定の有無を役所(建築指導)で確認し、地積測量図や実測で接道長さ・有効幅員を詰めていきます。
- 前面路が1項1〜5号か、2項道路かの区分
- 幅員4m以上か(地域指定で6mの場合あり)
- 私道の場合→位置指定や通行・掘削承諾の要否
建築基準法43条と接道規制
第43条は「接道義務」を定め、原則として建築物の敷地は建築基準法上の道路に2m以上接する必要があります(自動車専用道路等の一部を除外)。
一方で、接道がない・不足する敷地でも、43条2項により例外が設けられています。2項1号は、通路等を「道路とみなす」認定(自治体が基準を定め、維持管理の誓約などを要件化)。
2項2号は、一般の通行に供される道路状空地に有効に接続する通路などが確保され、交通・防火・衛生上支障がないと特定行政庁が判断する場合の「許可」(多くの自治体が一括許可同意基準を整備)です。
現実には、2項1号は恒常的な通行確保や工作物の制限、2項2号は幅員2m以上の通路確保や近隣同意など、地域基準に合わせた実務対応が鍵になります。
- 「但し書き」の呼称に引きずられ、現行の2項2号手続と混同する
- 自治体ごとの基準差を見落とし、図書や同意の不備で差し戻し
- 通路の私権関係(通行・掘削承諾)や管理責任の整理漏れ
2項道路のセットバック
2項道路は、幅員4m未満でも「みなし道路」として扱う制度で、建替え時に道路中心線から2m(6m区域では3m。
状況により1.35m〜2m等の範囲指定可)を境界線とみなし、敷地を後退させることで将来的に4m(または6m)を確保します。法文上は、がけ・河川・線路敷に沿う部分の特例線や、特定行政庁による水平距離の別指定も規定されています。
実務では、セットバック部分は建築不可の扱い(構造物撤去や塀の移設等が必要)となり、自治体ごとに助成・補助制度(狭あい道路整備)や取り扱いが用意されることがあります。
調査では、2項道路指定の有無、中心線の位置、必要後退量、提供方法(寄付・使用承諾等)を事前に確認しておくと安全です。
- 中心線の把握→役所の2項道路台帳や現地基準点で確認
- 後退部分の工作物→門柱・給湯器・外構の移設計画を検討
- 隅切りや曲線部→有効幅員が不足しないか測量図で再確認
- 敷地後退で有効宅地が減る→建物規模・配置の再設計を前提に
- 自治体の狭あい道路整備支援の対象・手続を早期確認
再建築可へ向けた例外手続き

再建築不可の土地でも、法の要件を満たす通路整備や手続きを行うことで、建築の可能性を高められる場合があります。
代表的なのは、建築基準法43条に基づく許可(通称:ただし書許可)、法42条1項5号の位置指定道路の新設・変更、既存の狭あい道路に対するセットバックの計画づくりです。
どの方法が適切かは、前面通路の法的地位、幅員、接道長さ、私権関係(通行・掘削承諾、持分)で決まります。
実務では、早い段階で役所(建築指導・道路管理)とルート案を擦り合わせ、図面・写真・権利関係を整理してから意思決定すると後戻りが減ります。
費用と期間は案件差が大きいため、複数案の概算見積とスケジュール比較を行い、金融機関や売主・隣地所有者との調整計画も同時に用意しておくと安心です。
【検討ルートの整理】
- 43条許可の適用可能性→通路確保条件、交通・防災・衛生の観点を満たせるか
- 位置指定道路の築造→幅員4m以上・排水構造・転回広場等の技術基準を満たせるか
- セットバック活用→2項道路指定の有無、必要後退量、外構移設や寄付方法の検討
- 現況と権利関係の可視化(測量図・公図・持分・承諾の棚卸)
- 技術案の叩き台(平面図に幅員・後退線・転回を仮配置)
- 関係者マップ(隣接地・私道共有者・インフラ管理者・消防)
43条ただし書許可の要件
43条許可は、敷地が法42条の道路に接していない、または接道が不足している場合でも、交通・防災・衛生の面で支障がないと特定行政庁が判断すれば建築を認める制度です。
要件や審査基準は自治体ごとに細かく定められており、通路幅や構造、通行の恒常性、消防活動の支障有無、排水経路、管理責任の明確化などが確認されます。
通路は一般に有効幅2m以上を求められることが多いですが、距離や用途により別基準(有効1.5m以上や短距離限定など)が設定されることもあります。
私道・共有地を通る場合は、通行・掘削・舗装・ライフライン敷設に関する承諾書や覚書を整え、恒常的に利用可能であることを示す必要があります。
審査では、平面図・縦横断図・現況写真・権利関係図、維持管理や照明・排水の計画を添えて、建築審査会の同意が必要となる類型ではその手続も並行します。
【典型的に求められるポイント】
- 有効幅の通路確保(一般に2m以上を目安、段差・門柱等で幅を欠かないこと)
- 消防活動の確保(接近経路・消火栓位置・ホース延長距離の整合)
- 衛生面の確保(雨水・汚水の排水経路、集水桝・勾配)
- 権利の恒常性(通行・掘削・舗装・ライフライン承諾、管理主体の明確化)
- 自治体基準に幅・距離・用途の細則がある→早期に適用条文を確認
- 「ただし書」という俗称に惑わされず、現行基準の類型と図書要件を整理
- 承諾書の範囲(掘削・舗装・占用等)を具体化→後の工事差し止めを予防
位置指定道路の整備検討
位置指定道路(法42条1項5号)は、私人が築造する私道を特定行政庁が「建築基準法上の道路」と認める制度です。
新設・拡幅により幅員4m以上(地区により6m)を確保し、行き止まりの場合は所定の転回広場を設けるなど、自治体の築造基準に適合させます。
排水側溝・舗装構造・縁石・照明・高さ制限工作物の後退など、細目は地域で異なるため、標準図や要綱を参照して設計します。
私道の権利関係は、敷地所有者全員の同意や分筆・持分移転、将来的な維持管理(共有持分の管理規約や通行掘削承諾の枠組み)まで見据えるとトラブルが抑えられます。
工事に先立ち、上下水・ガス・電力の引込計画や道路占用との整合を取り、検査済通知を経て位置指定の告示がされると、当該道路に接する敷地は原則として接道要件を満たせます。
【築造基準の例(地域により差あり)】
| 審査項目 | 一般的な目安 | 手続・資料 |
|---|---|---|
| 幅員 | 4m以上(地区により6m指定) | 平面図・断面図・標準構造図 |
| 行き止まり | 転回広場の設置(直径5〜6m相当など) | 車両軌跡図・消火活動検討 |
| 排水 | 側溝・桝・勾配の確保 | 排水計画・上下水道事前協議 |
| 権利関係 | 敷地所有者の同意・持分整理 | 同意書・境界確定・分筆図 |
- 恒常的な「法の道路」を確保→将来の建替え・増築の自由度が上がる
- 資産価値・流通性の改善が見込める(金融評価の改善につながることがある)
事前相談と行政協議の進め方
例外手続きは、技術・権利・近隣調整が絡むため、事前相談の質が成否を左右します。
最初に現況を可視化し、複数ルート案(43条許可・位置指定・セットバック)を持参して、建築指導課・道路管理者・上下水道・消防と段階的に協議します。
相談時は、所有・借地・通行権などの私権関係を図示し、承諾取得の見込みや想定コスト、工期感を添えると具体的な助言を得やすくなります。
行政協議は議事録を取り、指摘事項は図面に反映→再相談のサイクルで詰めていきます。隣地との合意形成は、通路の清掃・照明・騒音・工事時間帯など運用面の取り決めまで含めると、着工後のトラブルを減らせます。
融資予定がある場合は、金融機関にも並行して計画図と行政回答を提示し、資金手当とスケジュールリスクを早期に共有します。
【持参すると有効な資料】
- 公図・地積測量図・求積図・現況写真・案内図
- 前面通路の法的根拠資料(道路台帳・指定道路図・2項道路台帳)
- 計画案(平面図・断面図・通路幅員・後退線・転回・排水計画)
- 権利関係図(共有者一覧・承諾の取得計画・覚書フォーマット)
- 質問事項を1枚に整理→可否判断の基準条項を指名して確認
- 指摘は図面に追記→再相談までの対応期限と担当窓口を明記
リフォーム・増改築の可否

再建築不可の土地に建つ建物でも、すべての工事が禁止されるわけではありません。ポイントは、建築確認の要否と、工事によって法令違反を拡大しないことです。
一般に、内装の模様替えや設備の交換など「構造や規模を変えない工事」は進めやすい一方、構造耐力上主要な部分に手を加える工事や、床面積を増やす増築はハードルが高くなります。
また、既存不適格(当時は適法だが現在の基準に合わない)建物の大規模改修では、適法性の是正を求められる場面があり、無確認工事は将来の売買や融資で不利になります。
まずは工事内容を整理し、建築確認の要否、接道・セットバック・建蔽率・容積率・用途地域などの影響を洗い出してから進めると安全です。
| 工事項目 | 進めやすい例 | 注意が必要な例 |
|---|---|---|
| 内装・設備 | 床・壁・天井仕上の更新、キッチン交換(同位置)、給湯器交換 | 耐力壁の撤去、開口拡大、スケルトン化で構造に影響 |
| 外装 | 塗装、屋根材の葺き替え(下地・架構を変えない) | 屋根形状変更、バルコニー新設で荷重・防火に影響 |
| 増改築 | なし(原則慎重に判断が必要) | 床面積の増加、庇・デッキの恒久化で増築扱い |
- 判断の流れ→工事内容の列挙→構造・規模・用途の変化有無→建築確認要否→関係法令(防火・斜線・日影・接道等)の再点検
- 売買予定がある場合→工事前後の図面・写真・契約書を保存→適法性の説明資料に活用
確認不要の軽微工事の範囲
「確認が不要な工事」は、一般に建物の規模や構造耐力に影響を与えない軽微な修繕・模様替えが対象です。
たとえば、壁紙の貼替え、床材の更新、住宅設備(キッチン・洗面・浴室機器など)の同位置交換、劣化した外壁・屋根の表層修繕などは進めやすい領域です。
窓の交換も既存開口の範囲内なら検討できますが、開口を拡大して梁・柱・耐力壁に影響する場合は慎重な検討が必要です。
給排水や電気の配線・配管も、経路や機器が同等で防火区画や避難経路を損なわない範囲なら進めやすいですが、用途変更に当たるようなプランや、区画貫通部の防火措置が必要な変更は事前相談が安全です。
- 軽微の考え方→規模・構造・防火・避難への影響が小さいこと
- 同位置・同等更新→設備の性能向上は可だが重量増は構造影響に注意
- 窓・ドア→既存開口内の交換は進めやすい。拡幅は構造検討が前提
- 耐力壁や梁・柱をいじらないか(→構造図・筋交い位置を確認)
- 防火区画・避難経路を変えないか(→建具の防火性能や開閉方向)
- 床面積や用途を変えないか(→増築・用途変更の扱いに注意)
大規模改修時の適法性是正
間取りの全面変更、耐震補強を伴う構造改修、外壁や屋根の大幅更新などの大規模改修では、建築確認の対象となる可能性が高まり、現行基準への適合や既存不適格部分の是正が課題になります。
再建築不可の背景に「接道不足」や「セットバック未了」がある場合、増築や外構の恒久化によって違反が拡大すると、確認が下りない、または是正を求められることがあります。
既存の無確認増築がある物件では、当該部分の撤去や現況復旧が前提になることもあります。
着手前に現況図面と法適合状況(建蔽率・容積率・高さ・斜線・日影・防火・用途)を棚卸しし、改修範囲ごとに必要手続・必要図書・工程影響を整理すると、後戻りが減ります。
| リスク | よくある背景 | 対策の方向性 |
|---|---|---|
| 確認不可 | 接道不足、2項道路の後退未整備、無確認増築 | セットバック整備、違反部分の是正、計画縮小 |
| 構造不適合 | 開口拡大・間取り変更で耐力壁不足 | 構造設計で補強計画を作成、壁量・耐力壁線の再配分 |
| 防火・避難 | 防火戸の性能低下、避難経路の変更 | 仕様の適合確認、避難動線の確保、区画の復元 |
- 無確認増築の放置は売却時に減点→是正か現況明示で早期合意
- 構造に触れる間取り変更は先に構造検討→意匠の手戻りを防止
耐震等の支援制度の活用
再建築不可の物件でも、耐震性や安全性を高める改修には各種支援が活用できる場合があります。
多くの自治体が、木造住宅の耐震診断・補強設計・耐震改修工事に対する補助制度を用意し、加えて狭あい道路の整備(セットバック)やブロック塀撤去など、防災性向上策への助成を設定しています。
税制面でも、一定の耐震改修を行った住宅に対する固定資産税の減額や、所得税の特例が設けられることがあります(適用要件・期間は自治体や制度ごとに異なります)。
支援の可否は、建築時期や構造種別、改修内容、耐震基準の達成度、施工者・設計者の要件などで左右されるため、事前に募集要項と手引きを確認し、見積書・図面・工程を制度の書式に合わせて準備するとスムーズです。
- 確認の順序→自治体の住宅・建築・防災担当の補助メニュー→要件・申請時期→設計・見積の整合
- 診断→補強設計→工事まで一体で支援するメニューの有無を確認
- 狭あい道路整備・ブロック塀撤去の併用で安全性と資産性を同時に向上
- 着工前に申請→交付決定前の工事は対象外になりがち
- 実績書類(写真・領収書・検査記録)を工程ごとに整理→完了検査に備える
売買・評価の注意ポイント
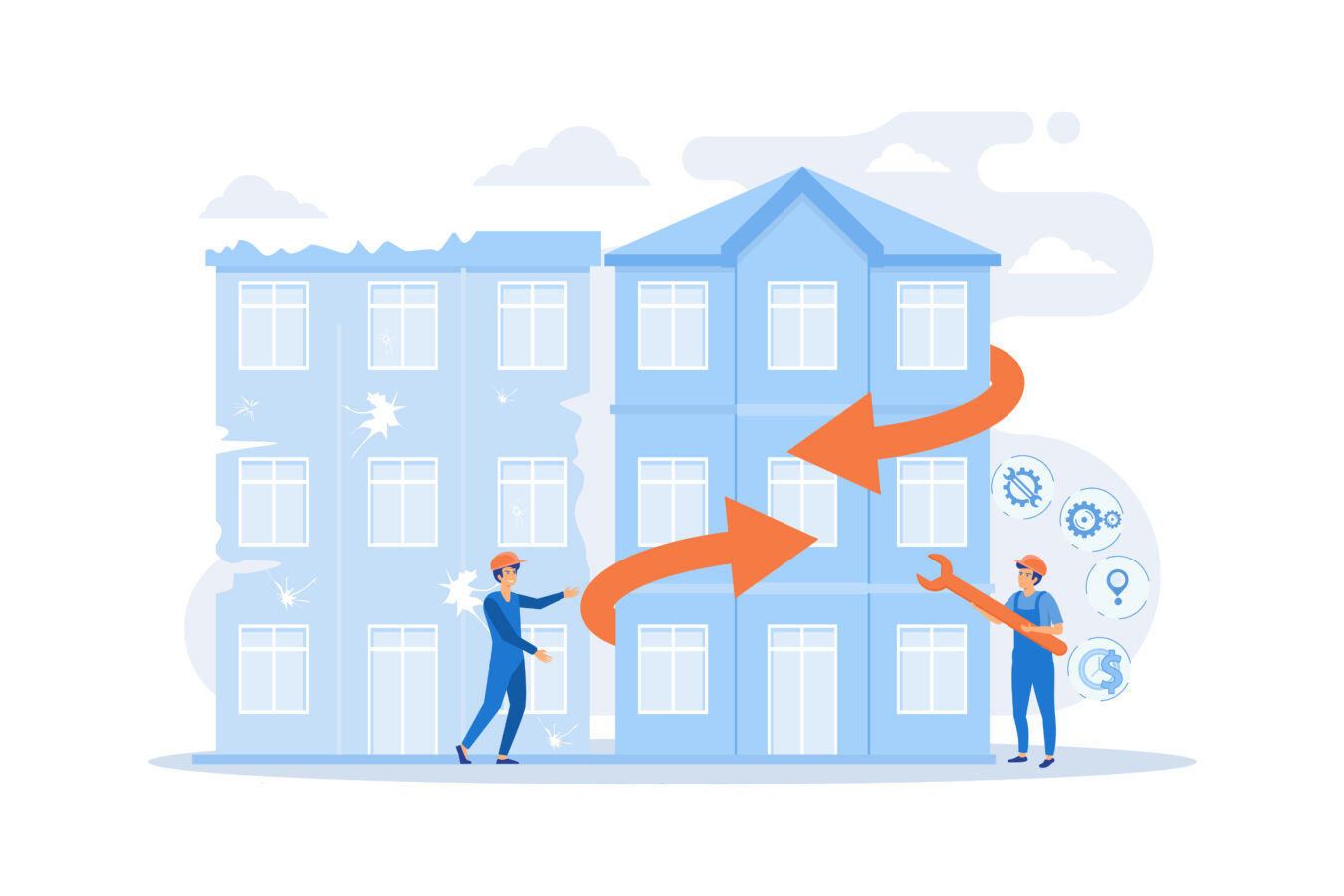
再建築不可の取引では、通常の居住用よりも「法的・物理的・権利的」な不確実性が価格と成約スピードに強く影響します。
評価を誤らないためには、前面通路の法的地位(法42条のどれに該当するか)、接道長さ・有効幅員、セットバックの要否・後退量、私道の持分や通行・掘削承諾、越境や無確認増築の有無を、書面と現地の両面から突合することが重要です。
買主側は「将来の建替え・増改築の自由度」「是正に必要な費用・期間」「資金調達の可否」を織り込んで価格を判断します。
売主側は、事前に入手できる資料を揃えて透明性を高めることで、価格の下振れや交渉の長期化を抑えられます。
| 確認軸 | 見るポイント | 主な資料 |
|---|---|---|
| 法規 | 道路種別、接道2m、セットバック要否 | 指定道路図・道路台帳・幅員証明 |
| 権利 | 私道持分、通行・掘削承諾、越境 | 登記事項・同意書・測量図 |
| 物理 | 有効宅地面積、がけ・擁壁・高低差 | 現地写真・配置図・点検記録 |
- 事前に資料を開示→疑義を減らし買い手の不安を解消
- 是正案(セットバック・通路整備)の概算と工程を提示
- 契約条件(現況有姿・責任範囲)の整理で交渉を短縮
調査で判明しやすいリスク
再建築不可では、調査を進めるほど潜在リスクが顕在化しやすく、価格や条件に直結します。
典型は、接道長さが2m未満、前面路が法の道路に該当しない、2項道路だが中心線が不明で後退量が確定できない、私道持分が無い・通行や掘削承諾が未取得、越境(庇・塀・排水管)や無確認増築の存在などです。
さらに、擁壁の適法性、がけ条例の該当、浸水・土砂・液状化などのハザード、上下水・ガスの引込経路やメーター位置の不整合も、是正費用と期間を押し上げます。
売主・買主とも、書面上の台帳・図面と現地の実測に齟齬がないかを丁寧に突合し、是正の可否とコストを早い段階で見立てることが、余計な値引き・キャンセルの回避につながります。
| 項目 | 起こりやすい問題 | 対処の方向性 |
|---|---|---|
| 接道 | 有効2m不足、角地の有効取り違い | 測量・境界確定、取り方の再確認 |
| 2項道路 | 中心線不明、必要後退量が確定不可 | 台帳照会・役所協議・仮杭で線形確認 |
| 私道 | 持分欠如、掘削・舗装承諾が未整備 | 同意取得、覚書締結、代替ルート検討 |
| 建物 | 無確認増築、越境、既存不適格の拡大 | 是正・現況明示、工事範囲の線引き |
- 資料と現地が一致しない(幅員・境界・工作物)
- 承諾の範囲が曖昧(通行は可だが掘削は不可 等)
- 是正工事の実現性が低い(地権者が多い・崖地)
現金買取など売却手段比較
再建築不可の売却は、大きく「現金買取」「仲介流通」「入札方式」「買取保証(一定期間仲介→未成約なら買取)」の選択肢があります。
現金買取はスピードと確実性が強みで、契約不適合責任の免責・残置物の原状渡しなど柔軟に交渉しやすい半面、価格は抑え目になりがちです。
仲介流通は、再建築不可のリスクを理解する買主に広くアプローチでき、是正案や活用案(賃貸・倉庫・駐車場等)を提示できれば価格の最大化が狙えますが、調査や内覧対応に時間を要します。
入札方式は、期日を切って複数の買取業者・投資家から同条件で提示を受けるため、透明性と市場感の把握に優れます。
買取保証は、販売期間を確保しつつ最終出口を担保でき、資金計画を立てやすいのが利点です。
| 手段 | スピード・確実性 | 価格傾向・留意点 |
|---|---|---|
| 現金買取 | 早い・確実。現況有姿・免責が通りやすい | 価格は控えめ。相見積と条件比較が有効 |
| 仲介流通 | 時間は要する。買主の理解形成が鍵 | 是正案提示で上振れ余地。情報開示が必須 |
| 入札方式 | 短期で相場を把握。条件の横並び比較が容易 | 募集要項の精度が価格と実行性を左右 |
| 買取保証 | 販売猶予を確保しつつ出口を担保 | 保証価格・期間・適用条件の精査が必要 |
- 時間重視か価格重視か(資金繰り・住替えの事情)
- 開示できる資料と是正案の質(買主の安心材料)
- 契約条件(現況有姿・免責・残置物)の許容範囲
価格形成要因と事例の探し方
再建築不可の価格は、「建替え可能性」と「是正コスト・期間」「代替活用の収益性」の3要素で形づくられます。
具体的には、前面道路の種別と幅員、接道長さ、セットバックの必要面積、私道の持分と承諾取得の難易度、通路整備の現実性、建物の状態(無確認増築・劣化度)、地形(高低差・がけ・擁壁)や災害リスク、近接インフラ(上下水・ガス・電柱・桝)の条件が、ディスカウントや成約速度に反映されます。
事例収集では、近隣の成約事例・公示・基準地の地価動向をベースに、再建築可の近似物件との乖離を把握し、是正後に再建築可となるケースと、是正しても困難なケースを分けて比較すると、妥当なレンジを掴みやすくなります。
| 要因 | 評価の見方 | 確認資料・ヒント |
|---|---|---|
| 道路・接道 | 種別・幅員・接道2m、後退量の確定性 | 指定道路図・幅員証明・役所回答 |
| 権利・承諾 | 私道持分・通行掘削承諾・越境の解消性 | 同意書案・境界確定・覚書 |
| 是正コスト | 通路整備・外構移設・撤去費・期間 | 概算見積・工程表・施工者見解 |
| 活用余地 | 賃貸・駐車場・倉庫等の収益見込み | 賃料相場・需要調査・配置図 |
- 半径・行政区を揃えて時期を近づける→外れ値を除外
- 是正後に再建築可となる仮定ケースと併走比較→価格の上限・下限を把握
- 成約価格だけでなく条件(現況有姿・免責・残置物)も併記
まとめ
再建築不可は接道要件と道路種別の理解が肝心。42条の種別確認、2項道路のセットバック、43条ただし書許可の可否、位置指定道路の整備可能性、リフォームの範囲を順に押さえれば、価格判断と交渉材料が明確になります。
まずは公図・道路台帳・指定道路図で現況を確認し、疑義は役所相談と専門家調査でリスクを減らしましょう。