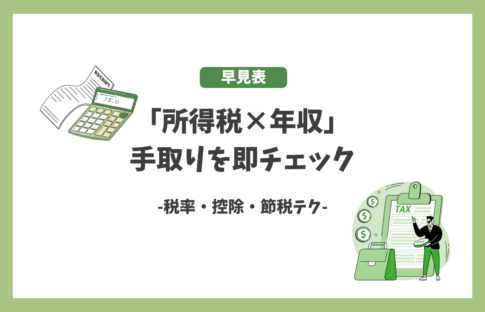年収1,000万円を超えると、所得税と住民税だけで手取りが大きく目減りします。アパート経営は減価償却や損益通算を活用し、課税所得を合法的に圧縮できる有力な選択肢です。本記事では、物件取得から運用・相続対策までの節税ノウハウを時系列で整理。
減価償却費の最適化、青色申告特別控除、法人スキームによる株価コントロールなど、多段階で税負担を最小化する具体策を解説します。
短時間で全体像をつかみ、実践に移せるロードマップを手に入れましょう。さらに固定資産税対策や保険・共済を組み合わせた長期戦略も紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
アパート経営×節税の基本メカニズム

アパート経営が節税に有効とされる理由は、賃貸収入を得ながら各種の必要経費を柔軟に計上できる点にあります。
建物部分は取得価格を耐用年数で割って毎年減価償却費として計上でき、ローン利息・管理委託料・固定資産税・火災保険料なども経費扱いにできるため、課税所得を大幅に圧縮する余地が生まれます。
さらに、賃貸運営が赤字となった場合には損益通算によって給与所得など他の黒字所得と相殺できる可能性があります。青色申告を選択すれば最大65万円の特別控除と専従者給与を組み込むことで、現金支出を伴わずに帳簿上の経費を拡大し、手元資金を温存しながら節税効果を高めることができます。
加えて、土地部分は時間が経っても価値が落ちにくい資産であるため、長期保有による資産形成と節税を両立しやすいこともアパート経営ならではのメリットといえます。
- 減価償却費→建物価格を分割して経費化
- ローン支払利息・管理費→実費を経費計上
- 青色申告→特別控除と専従者給与で課税所得をさらに圧縮
- 損益通算→赤字を他の所得と相殺し税負担を軽減
アパート経営が節税になる理由
アパート経営による節税効果は、所得税法が採用する実現課税の考え方と必要経費控除のルールに基づいています。
実現課税とは、キャッシュの支出がなくても法定耐用年数に従い建物価格を費用化できる仕組みを指し、これにより発生する減価償却費は非現金経費として帳簿に計上できます。たとえば築浅の鉄骨造アパート(耐用年数34年)を1億円で取得した場合、毎年約294万円を経費として計上できる計算です。
さらに、支払利息や共用部の電気代など実際に支出したコストも必要経費に含められるため、課税ベースのさらなる圧縮が可能です。
青色申告を採用すると、複式簿記の帳簿作成と期限内申告を条件に65万円(電子申告で55万円)もの特別控除が得られます。
| 経費区分 | 代表例 | 効果概要 |
|---|---|---|
| 減価償却費 | 建物・設備の償却費 | キャッシュアウトを伴わず所得圧縮 |
| 支払利息 | アパートローン金利 | 実支出を全額経費化 |
| 維持管理費 | 管理委託料・修繕費 | 長期的に設備保全しつつ節税 |
- 耐用年数が短い物件ほど減価償却費の計上額が大きく、早期の節税効果が見込める
- 青色申告特別控除の適用には、帳簿整備と期限内申告が必須
損益通算と所得分類の仕組み
損益通算とは、不動産所得などで生じた赤字を給与所得など他の黒字所得と相殺できる制度で、アパート経営を行う高所得者にとって極めて有効な節税手段とされています。
不動産所得は所得税法上の総合課税に分類されるため、年間の家賃収入から必要経費を差し引いた結果が赤字の場合、その赤字を給与所得や配当所得といった他の所得区分と相殺することが可能です。
赤字が通算しきれない場合でも、青色申告者であれば繰越控除によって最長3年間の持ち越しが認められています。
一方で、別荘貸付の赤字や土地取得ローン利子のうち一定部分など、損益通算の対象外となる項目も存在するため、経費の区分と適用可否を事前にチェックすることが大切です。
また、赤字が恒常的に続くと税務調査で経費性を否認されるリスクがあるため、節税目的だけでなく事業としての収益性を確保する運営計画が求められます。
- 通算対象所得区分→不動産所得・事業所得・譲渡所得・山林所得
- 赤字の繰越控除→青色申告なら3年まで適用可
- 通算不可例→別荘貸付の赤字、土地取得ローン利息の一部
- 恒常赤字は経費否認リスク→収益計画と空室対策を重視
- 短期売却益との相殺は不可→所得区分が異なるため適用外
- 赤字目的の過大借入は「租税回避」と判断される可能性がある
運用期に使える所得税節税テクニック

運用期のアパート経営では、家賃収入を確保しながら「経費枠を最大化しキャッシュを温存する」ことが節税の基本方針とされています。
具体的には、①建物や設備を適正に減価償却し、②計画的な修繕で突発コストを平準化し、③青色申告と専従者給与で所得分散を図る、という三段構えが効果的です。
帳簿上は減価償却費や修繕費を計上して課税所得を下げつつ、手元の現金は運転資金として保持できるため、突発的な空室や金利上昇に備えた安全余裕資金も確保しやすいといわれています。
また、税務上は「合理的な計算方法」と「継続適用」が求められるため、一度策定した償却・修繕ポリシーを年度ごとにぶれなく運用し、税務調査でも説明できる体制を整えることが推奨されています。
- 経費の3本柱→減価償却費・修繕費・青色申告控除
- キャッシュセーフティ→税金を減らし流動性を維持
- 継続適用→毎期同じ基準で処理→税務調査リスクを低減
減価償却費と修繕費の計上ポイント
減価償却費は、建物・設備の取得価額を耐用年数で按分し、毎年費用化できる非現金経費です。RC造(法定耐用年数47年)の中古アパートの場合、簡便法では〔法定耐用年数 − 経過年数〕+〔経過年数 × 0.2〕で見積耐用年数を計算します。
築20年なら 47 − 20 +(20 × 0.2)=31年となり、1年未満は切り上げます。経過年数が法定耐用年数以上なら、法定耐用年数 × 0.2(最低2年)が適用されます。
これにより年間償却費を早期に多く計上し、所得圧縮効果を前倒しできる可能性があります。一方、修繕費は資本的支出か費用かの判定が要となります。
原状回復や小規模改善は修繕費として一括経費化できる一方、耐用年数を延ばす大型改修は資本的支出となり、減価償却で按分する必要があるとされています。
| 費用区分 | 判定基準 | 税務処理 |
|---|---|---|
| 修繕費 | 機能維持・軽微な改善 | 支出年度に一括経費 |
| 資本的支出 | 価値向上・耐用年数延長 | 取得価額に計上→償却 |
- 100万円未満または取得価額の10%以下の修繕→概ね修繕費計上が認められる傾向
- 同一内容を毎年計上すると恒常赤字と判断される可能性→修繕計画は3〜5年サイクルで策定
- 耐用年数短縮は「簡便法」と「個別評価法」から有利な方を選定→取得前に試算
- 減価償却方法は定額法が主流→一度選択すると変更には届出が必要
- 修繕前後の写真・見積書・工事契約書を保存→税務調査で説明資料として活用
青色申告特別控除と専従者給与の活用
青色申告は、複式簿記による帳簿作成と期限内申告を条件に、最大65万円(電子申告以外は55万円)の特別控除が受けられます。控除額は現金支出を伴わない直接的な所得圧縮であり、高所得者ほど税率が高い分、節税効果が大きいとされています。
さらに家族を専従者として業務に従事させ、妥当な範囲で給与を支払えば、所得を家族間で分散できる仕組みです。
専従者給与は「従事月数×合理的な報酬水準」の範囲内であれば全額必要経費に算入できるため、家計全体の可処分所得を保ちつつ課税所得を抑えられる可能性があります。
- 青色申告特別控除→帳簿整備+期限内申告が条件
- 電子帳簿保存+e-Tax→控除65万円フル適用
- 専従者給与→生計同一配偶者や子の労務提供に対して支給
- 給与水準→地域相場や業務内容に基づき「第三者基準」で設定
- 形だけの専従者給与は否認対象→タイムカードや業務報告書で実態記録を残す
- 帳簿不備や期限後申告→控除額縮減や適用不可のケースがある
【ポイント】
- クラウド会計ソフトを活用し、仕訳データを自動連携→入力ミスと作業時間を削減
- 年末調整や源泉所得税の納付を忘れると罰則対象→給与支払報告書の提出スケジュールを管理
- 家族間での給与は銀行振込を徹底→現金手渡しは経費性を疑われる可能性がある
相続税・固定資産税を抑える長期戦略

相続税や固定資産税を抑えるカギは、アパート経営を「取得→運用→承継」の全ライフサイクルで最適化することにあります。
まず相続税では、土地と建物の評価額をいかに下げるかが大きなポイントです。賃貸中の土地は貸家建付地として評価額が下がりやすく、さらに小規模宅地等の特例を活用すると大幅な減額が期待できます。
一方、固定資産税は保有コストとして毎年発生するため、長期修繕計画やエネルギー効率化投資を通じて課税標準額の上昇を抑える工夫が重要とされています。
これらを総合的に管理するには、①土地評価減・借入金残高・減価償却累計額を毎年度チェックし、②固定資産税の通知書を比較して不当な上昇を早期に把握し、③相続開始前に遺言・家族信託など承継スキームを固める、という三段階管理が推奨されます。
- 賃貸経営で貸家建付地評価+小規模宅地等の特例を組み合わせ→評価額を圧縮
- 固定資産税は修繕・用途変更で課税標準を調整→保有コストを平準化
- 借入金残高を維持→債務控除により相続税評価総額を引き下げる
- 3〜5年ごとに資産棚卸し&評価額シミュレーション→税制改正に対応
| 節税フェーズ | 主要対策 | 期待効果 |
|---|---|---|
| 取得時 | 耐用年数短縮物件・ローン活用 | 早期償却、債務控除残高の確保 |
| 運用期 | 貸家建付地評価・修繕最適化 | 評価額低減、固定資産税の抑制 |
| 承継期 | 小規模宅地等の特例・家族信託 | 相続税圧縮、争族リスク低減 |
- 評価減と債務控除はセットで検証→単独施策より効果が大きい
- 固定資産税の審査請求は3年間の猶予期間内に判断→早期対応が鍵
小規模宅地等の特例と住宅用地評価減
小規模宅地等の特例は、一定の要件を満たす宅地の評価額を最大80%減額できる強力な制度とされています。アパート経営の場合、貸付事業用宅地として200㎡まで50%減額が可能であり、自宅兼用部分があれば特定居住用宅地として330㎡まで80%減額を併用できるケースもあります。
適用要件は①相続開始直前に賃貸事業を継続していること、②相続人が申告期限まで賃貸を続けること、③相続税申告で適用を選択すること、の三点が基本です。
併用適用の可否や面積配分は「特定事業用」との重複排除ルールがあるため、土地を分筆するなど事前の権利調整が欠かせません。
また、住宅用地評価減は固定資産税の優遇措置で、アパートが共同住宅用地に該当すると、200㎡まで6分の1、超過部分は3分の1に課税標準が減額されるとされています。運用期にこの優遇を受けることでキャッシュフローに余裕が生まれ、その分を修繕や繰上返済に充当できる点も大きなメリットです。
- 貸付事業用宅地→200㎡まで50%減額
- 特定居住用宅地→330㎡まで80%減額
- 事前に土地分筆→区分ごとの限度面積をフル活用
- 住宅用地特例→固定資産税を1/6〜1/3へ軽減
- 相続開始直前から継続的に賃貸運営しているか
- 相続人が申告期限まで賃貸・居住を継続できるか
- 特定事業用宅地との重複を整理し限度面積内に収めたか
アパートローンと債務控除で評価額を圧縮
アパートローンを活用すると、相続時には土地建物の評価額から借入残高を差し引く債務控除が適用されます。債務控除は「相続開始日時点の未払元本」が対象で、ローン残高が大きいほど課税遺産総額を圧縮できると考えられています。
たとえば、評価額1億2,000万円のアパートにローン残高7,000万円が残っていれば、実質課税対象は5,000万円まで下がる計算です。
ここに貸家建付地評価や小規模宅地等の特例を組み合わせることで、さらに評価額を引き下げる多段階減額が可能です。ただし、返済が進みすぎると債務控除の効果が弱まるため、返済スピードと評価額のバランスを見極める必要があります。
| 項目 | 一般例 | 債務控除後 |
|---|---|---|
| アパート評価額 | 1億2,000万円 | ― |
| ローン残高 | 7,000万円 | ▲7,000万円 |
| 課税評価額 | ― | 5,000万円 |
- 連帯保証人の負債は被相続人名義外→控除対象外になる可能性
- 繰上返済で残高を減らし過ぎると節税効果が薄れる→返済計画を税額試算と連動
法人スキームと共済・保険による出口戦略
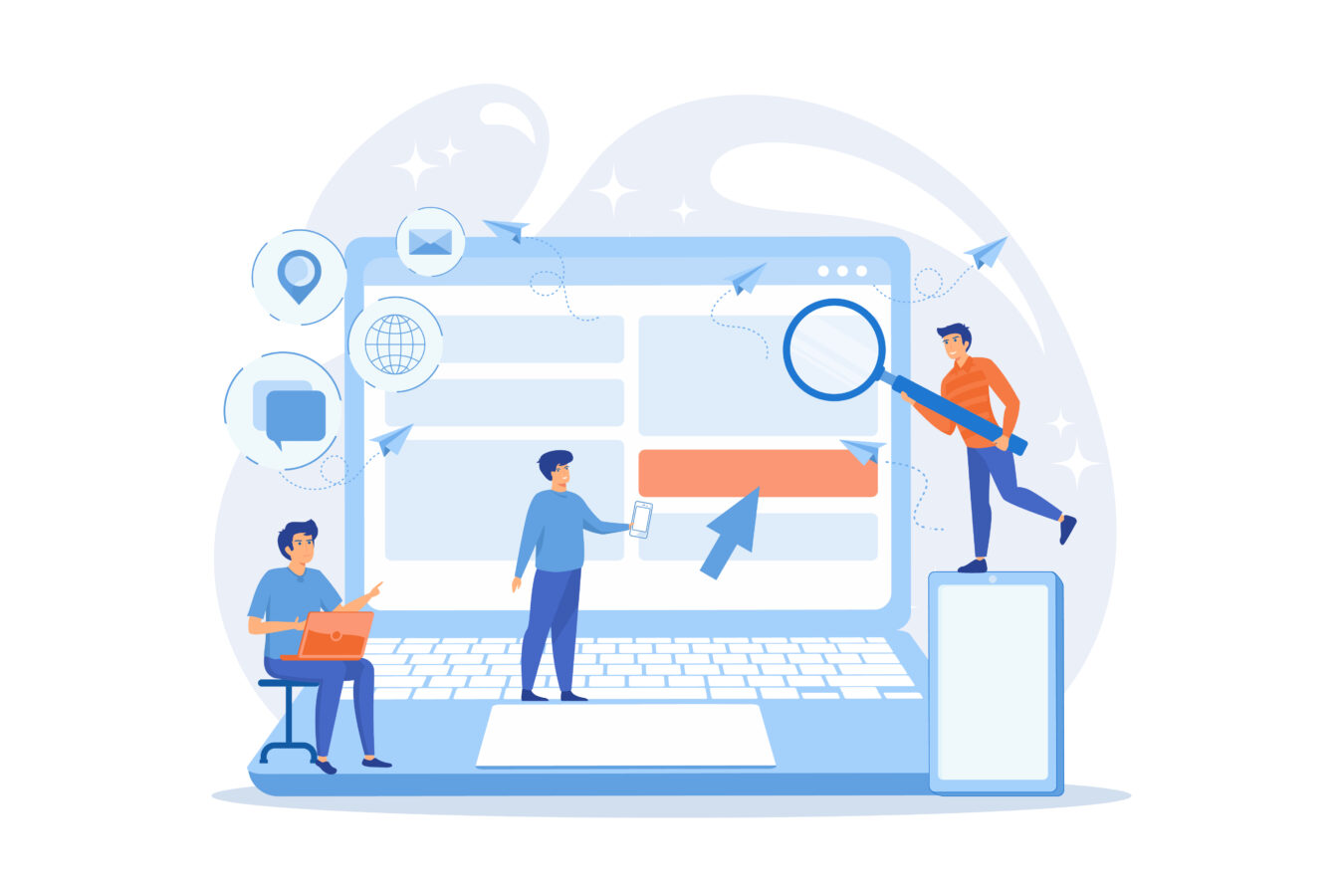
個人名義で拡大してきたアパート経営を最終的に「どう承継するか」は、相続税だけでなく所得税・法人税・住民税の総合最適化に直結します。
一般的に①資産管理会社への移管、②退職金や共済を活用した資金抽出、③生命保険で納税資金を確保──という三段階で出口を設計するモデルが採用されることが多いとされています。
まず法人化で株式に資産をまとめることで、株価評価を通じた相続税コントロールが可能になります。
さらに小規模企業共済や経営セーフティ共済、長期平準定期保険を組み合わせれば、退職金や解約返戻金を「損金算入しつつ資金プール」できるため、納税資金を外部に準備せずとも自前で用意できる可能性があります。以下のフローで出口戦略を構築すると、資産移転と税負担抑制を両立しやすいと考えられています。
| フェーズ | 主な施策 | 期待効果 |
|---|---|---|
| 法人化前 | 出資スキーム設計・簿価移転 | 含み益を抑え株価上昇を制御 |
| 運用期 | 役員報酬最適化・共済掛金支払い | 損金で当期所得を圧縮 |
| 承継期 | 退職金・生命保険受取 | 退職所得控除・みなし相続財産非課税枠で節税 |
- 三税(所得・法人・相続)の合計最小化を常に試算
- 株価算定方式と保険契約形態を毎期レビュー
資産管理会社設立による株価コントロール
資産管理会社を設立し、不動産を現物出資あるいは適正価格で売却して移転すると、相続時には「株式評価=純資産価額または類似業種比準価額」で課税されるため、借入金や減価償却累計額を活用して株価を抑えられるとされています。
たとえば純資産5,000万円・利益1,000万円・配当0円の管理会社であれば、類似業種比準方式の評価額は大幅に低下する可能性があります。加えて、役員報酬や社宅制度を利用して所得を法人と個人で分散することで累進税率の山を回避できます。
- 現物出資は登録免許税・不動産取得税が不要→コスト圧縮
- 借入金を法人側で引き受け→株価評価を圧縮
- 役員社宅や福利厚生→生活費を法人経費へシフト
- 過大な役員報酬や資本取引は第三者算定が必要→税務否認リスク
- 株式分散を避けるため、種類株式や家族信託で議決権集中を検討
【ポイント】
- 現物出資時は相続時精算課税の活用も検討→贈与税負担を平準化
- 毎期決算前に株価試算→配当・借入・修繕計画を調整
- 定款に相続人以外への譲渡制限条項を設定→経営権分裂を予防
小規模企業共済・退職金で資産移転
小規模企業共済(以下、共済)は経営者の退職金準備を目的とした制度で、掛金は全額所得控除、退職時の共済金受取は退職所得扱いとなるため、所得控除+低税率の二重メリットがあるとされています。たとえば月7万円を20年間掛けると総掛金1,680万円が全額所得控除となり、受取時の課税所得は退職所得控除と1/2課税で圧縮される計算です。
さらに法人が経営者に支払う退職金は法人側損金・個人側退職所得となるため、株価を維持しつつ現金を個人へ移転できる可能性があります。
生命保険(長期平準定期や逓増定期)を契約し、解約返戻金を退職金の原資に充当するスキームを組めば、保険料損金化と納税資金準備を同時に達成しやすくなります。
- 共済掛金→月1,000〜70,000円の範囲で自由設定
- 退職所得控除→40万円×勤続年数(20年以上は800万円+70万円×超過年数)
- 長期平準定期→保険料の2分の1損金算入が一般的
- 逓増定期→短期で高額返戻金を形成→出口時に資金化しやすい
- 保険契約は「適正返戻率」かつ「長期払込」でないと否認リスク→設計書を保存
- 退職金は功績倍率・勤続年数で妥当額を算定→過大支給は損金不認定の可能性
【ポイント】
- 共済金受取時期を相続開始前に調整→相続財産への加算を回避
- 保険金の受取人を遺留分に配慮して設定→争族リスクを低減
- 退職金支給後に役員復帰すると「退職金の否認」事例も→完全退任か非常勤報酬へ変更
実践フローと専門家の選び方

アパート経営による節税効果を最大化するには、物件取得から相続・申告までの各フェーズで適切な意思決定を時系列で積み上げることが欠かせません。
とくに高所得層の場合、物件購入時点での融資条件や耐用年数の短縮可否、運用期における修繕計画や青色申告体制の整備、承継段階での小規模宅地等の特例・債務控除適用可否など、判断ポイントが多岐にわたります。
ここでは「タイムラインを可視化して抜け漏れを防ぐ」、「フェーズごとに関与する専門家を明示しワンストップ化する」、「毎年の決算時に税制改正と資産評価を同時レビューする」という三つの視点で、長期プロジェクトを最適化する実践フローを提示します。
また、専門家の選定は節税の成否を大きく左右します。税理士は申告書作成だけでなく、物件購入前のキャッシュフロー試算や法人スキームの組み立て段階から関与させることで、計画と実務のギャップを最小化できます。
管理会社は空室率・修繕費・クレーム対応など運用コストの変動要因を抑える役割があり、結果として節税余地を安定化させる効果が期待されます。
| フェーズ | 主な課題とアクション |
|---|---|
| 取得前 | 耐用年数・融資条件・減価償却シミュレーションを税理士と共有→購入可否を判定 |
| 運用期 | 修繕サイクルの策定・青色申告体制の整備・家族専従者の業務割り振り |
| 承継準備 | 土地分筆・家族信託・法人スキーム導入可否を検討→専門家チームで分業 |
| 相続発生 | 小規模宅地等の特例申告・債務残高証明書の収集・延納物納の要否を判定 |
- 毎年決算月に資産棚卸し→評価額・債務残高・修繕計画を更新
- 税理士・司法書士・管理会社で月次オンラインミーティングを実施
- 税制改正アラートを受け取れる情報サービスを活用→即時プラン修正
【ポイント】
- 物件選定時に「修繕履歴」「法定耐用年数残」を必ず確認→減価償却計画に直結
- 融資審査は設備更新資金を含めた長期プランで申し込む→追加借入を回避
- 承継フェーズでは遺留分や家族間バランスを考慮→争族リスクを軽減
物件取得から申告までのタイムライン
アパート経営の節税効果を確実に享受するには、購入前のシミュレーションから相続税申告までの全行程を逆算し、各マイルストーンで「誰が」「いつまでに」「何を完了させるか」を明文化する必要があります。
下記オリジナルタイムラインは築15年・鉄骨造アパート(残存耐用年数19年)を取得したケースを想定した一例です。
- 購入前6か月〜3か月
物件調査・融資仮審査・建物診断 → 税理士へ減価償却試算を依頼 - 購入契約〜引渡し
重要事項説明・登記手続き → 管理会社選定・賃貸募集準備 - 購入後1年目
青色申告承認申請書を提出・会計ソフト導入 → 減価償却開始 - 購入後3年目
長期修繕計画アップデート・資本的支出判定 → 修繕積立金を積増し - 購入後5年目
不動産鑑定士に時価評価を依頼 → 法人スキーム導入可否を再検討 - 相続開始前3年〜1年
土地分筆・家族信託契約を締結 → 小規模宅地等の特例適用条件を確認 - 相続開始
財産目録作成・債務残高証明書取得 → 申告書作成フロー開始 - 申告期限10か月
各種特例を適用し相続税申告 → 延納・物納の要否判断
- クラウドタスク管理ツールで担当者と期限を可視化
- 税務上の届出は「提出月末しばり」に注意→1日遅れでも控除不可となる可能性
【ポイント】
- 家族全員が閲覧できる「相続ノート」を作成→共有ストレージで随時更新
- 定期的にローン残高と鑑定評価を照合→債務控除効果をシミュレーション
- 税制改正に備え、毎年1月に専門家からアップデートを受ける体制を構築
節税に強い税理士・管理会社のチェック項目
アパート経営の節税ノウハウを最大限活用するには、専門家選びが成果を分ける決定要因になります。税理士については「相続税申告実績」「不動産所得の節税提案力」「レスポンス速度」の三つが評価軸とされています。
管理会社は「空室率の実績」「修繕・保守ネットワーク」「家賃滞納保証体制」が重要です。以下のチェックリストを用いて面談時に聞き取りを行い、複数社比較のうえで最適パートナーを選定するとリスクを抑えられます。
| 専門家 | ヒアリング項目 | 合格ラインの目安 |
|---|---|---|
| 税理士 | 年間相続税申告件数・法人化スキームの提案件数 | 相続税20件以上/年、法人化提案例10件以上 |
| 管理会社 | 平均空室期間・修繕一次対応時間・家賃滞納率 | 空室期間1か月未満、一次対応24時間以内、滞納率2%以下 |
| 司法書士 | 家族信託・遺言執行件数・オンライン対応可否 | 信託案件50件以上、全国リモート対応 |
- 「節税できます」と断言するだけで詳細試算を提示しない→試算根拠を必ず確認
- 管理手数料の安さだけで選定→隠れコスト(広告料・更新料)を比較する
【ポイント】
- 税理士の報酬体系は「顧問料+決算料+申告料」の総額で比較→追加オプション有無を事前に特定
- 管理会社のSLA(サービス水準合意書)を契約前に入手→対応速度と賠償責任範囲を確認
- 専門家同士が情報共有できるクラウド環境を構築→資料重複提出の手間を削減
まとめ
アパート経営は、減価償却・修繕費・青色申告控除による所得税圧縮から、債務控除・小規模宅地等の特例を踏まえた相続税軽減まで、段階的に節税メリットを得られる手法です。
本記事で示したロードマップに沿って、①物件選定と収支シミュレーション、②運用期の経費最適化、③法人化・保険を使った出口戦略、④相続発生前の承継準備を実行すれば、キャッシュフローを維持しながら税負担を大幅に軽減できる可能性があります。まずは信頼できる税理士や管理会社に相談し、今日から行動に移しましょう。