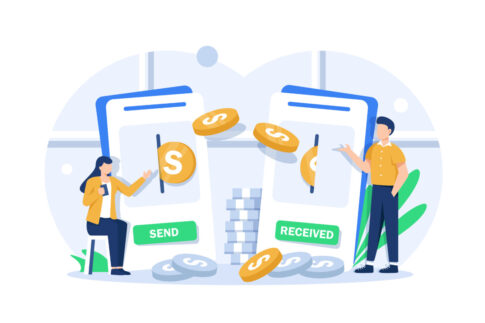高所得ゆえ税率の高さに悩む社労士のあなたへ。本記事では、役員報酬の最適化や助成金活用による社会保険料・所得税削減術から、減価償却を活かした不動産投資まで、専門家ならではの視点で節税手順を体系化します。
実践フローに沿って読み進めれば、キャッシュを守りつつ長期的な資産形成を両立できるヒントを得られます。忙しい業務の合間でも実行しやすいチェックリスト付きなので、読み終える頃には具体的なアクションプランが描けるはずです。
目次
社労士が自ら行う節税戦略の全体像

社労士は労務と社会保険の専門家ですが、自身が高所得帯になると所得税や住民税に加え、報酬月額上限まで到達した社会保険料の負担が家計を圧迫するケースが増えます。
そこで注目されるのが、①役員報酬構成や福利厚生制度を調整して「課税ベース」を下げる方法、②助成金や非課税手当を活用して「実効コスト」を抑える方法、③減価償却や損益通算を利用して「投資型の節税」を行い、長期的に資産を形成する方法の三本柱です。
それぞれの手法を単独で行うよりも、ライフプランに合わせて組み合わせることで節税効果を最大化しやすくなります。まず年間の可処分所得目標を設定したら、制度面と投資面で採用できる施策を洗い出し、最後にリスク管理と出口戦略を設計する流れが推奨されています。
【節税フローの流れ】
- 現状把握→年間所得・社会保険料・キャッシュフローを数値化
- 制度活用→給与構成・福利厚生・助成金で課税ベースを圧縮
- 投資導入→減価償却と損益通算を活用して資産形成
- 出口戦略→税率が上がるタイミングで売却や法人移行を検討
- 労務報酬と投資収益を両立させると、節税と資産形成を同時に狙えます。
- 長期計画を立てることで税制改正リスクを緩和できます。
高所得社労士の税負担特徴とリスク
高所得帯に入る社労士は、累進課税と社会保険料の二重負担で実効税率が急上昇しやすい特徴があります。たとえば年収1,800万円の場合、健康保険・厚生年金で年間150万円前後を負担しつつ、所得税と住民税で約600万円が差し引かれる計算となり、手取りは55%程度まで下がる可能性があります。
さらに報酬月額は毎年4〜6月の平均額で等級が決定されるため、繁忙期に臨時報酬を受け取ると次年度の社会保険料が上がるリスクもあります。
また役員報酬を一本化していると、退職金や医療費などライフイベント費用を上手く経費化できないため、突発的な支出が家計にのしかかります。
- 報酬月額上限→4〜6月の残業増や賞与支給で保険料が跳ね上がることがあります。
- 所得税最高税率→45%に達する前に報酬分散や退職金準備で課税所得を調整しましょう。
- 扶養控除漏れ→家族の年収判定ミスは控除額減につながるので定期確認が必要です。
- 高額療養費制度の上限を超える医療費は自己負担になるため、節税効果を相殺するリスクがあります。
- 厚生年金の標準報酬月額上限が引き上げられた場合、社会保険料負担はさらに増える可能性があります。
投資型節税を採るべき理由
給与や社会保険の調整だけでは節税額に天井があるため、長期的には投資を組み合わせた「投資型節税」が欠かせません。中でも不動産投資は、減価償却を通じてキャッシュアウトを伴わず課税所得を圧縮でき、損益通算が認められる場合は給与所得と相殺して税率を下げる効果が期待できます。
たとえば築20年・建物割合60%の木造アパートを法人名義で購入し、残存耐用年数4年で償却すると、年間数百万円規模の償却費を計上できるシナリオがあります。
これにより法人実効税率を抑えたうえで、個人側へ役員報酬や配当を調整して所得を分散し、全体の平均税率を低減するスキームが構築可能です。
【投資型節税のメリット】
- 減価償却→キャッシュアウトのない費用計上で所得を圧縮
- 損益通算→不動産所得の赤字を給与所得と相殺し税率を引下げ
- 資産保全→相続時に評価額が下がるため次世代への移転コストも抑制
- 減価償却シミュレーションで税効果とキャッシュフローを確認しましょう。
- 空室リスクや金利上昇リスクに備えた資金計画を立てましょう。
給与設計・社会保険料の最適化術

社労士が自分の給与を設計するときは、「標準報酬月額の等級」と「年間賞与額」のバランスを調整することで社会保険料をコントロールできます。
とくに報酬月額は4〜6月の3か月平均で等級が決定されるため、この期間を“報酬設計のゴールデンタイム”として位置付けると効果的です。
加えて、役員報酬と賞与を分割することで、厚生年金・健康保険の計算対象を抑えつつ、所得税の累進負担も平準化しやすくなります。
さらに退職金規程や企業型DC(確定拠出年金)を整備すれば、将来の資金準備をしながら課税を繰り延べられる点も見逃せません。以下では役員報酬のバランス調整と退職金・DCによる課税繰延の2つの具体策を詳しく解説します。
| 調整項目 | 最適化ポイント |
|---|---|
| 報酬月額 | 4〜6月を基準に残業・賞与を抑制し、等級アップを防ぐ |
| 賞与額 | 年2回に分割し、月額と合わせて課税所得を平準化 |
| 退職金 | 退職所得控除を活用し、実効税率を大幅に低減 |
役員報酬バランスと社会保険料削減
役員報酬は「定期同額給与」が原則とされていますが、年1回の改定で金額をリセットできる点を活用すると、社会保険料の負担を調整しやすくなります。
たとえば期首の4月に報酬を抑え、ボーナスを9月と3月に分ける設計を取れば、報酬月額の算定期間(4〜6月)では等級上限に届かず、社会保険料の年間負担を抑えられる可能性があります。また手当を複数に分散し、車両手当や通信手当の範囲内で業務実態に合わせた非課税精算を行うと、課税所得そのものを圧縮できます。
【役員報酬バランス調整の手順】
- 4~6月の月額をシミュレーションし、上限等級を避ける金額に設定する
- 賞与を年2回にし、月額と合算した年間総額が目標年収となるよう調整
- 車両手当・出張日当など合理的な手当を設計し、法定福利費を削減
- 定期同額給与のルールを外れる改定は損金否認リスクがあるため避けましょう。
- 手当新設時は就業規則や取締役会議事録に明記し、税務調査に備えましょう。
退職金・企業型DCを使った課税繰延
退職金は『退職所得控除』(20年まで40万円/年、20年超は70万円/年)を差し引き、残額の1/2を課税対象とする取り扱い(退職所得)です。記載の算式は国税庁の退職所得控除・課税関係に整合します。
たとえば勤続30年の場合、退職所得控除は1,500万円となり、退職金3,000万円を受け取っても課税対象は半分の1,500万円です。
さらに退職所得は1/2課税が適用されるため、実質的な課税所得は750万円となり、通常の給与課税と比べて実効税率を大幅に低減できます。
同時に企業型DCを導入して拠出上限まで掛金を積み立てれば、掛金全額が損金算入され、運用益も非課税で積み上がるため、課税を将来に繰り延べる効果が期待できます。
【退職金・DC活用の流れ】
- 退職金規程を作成し、支給要件と算定式を明確化する
- 企業型DCを導入し、掛金を報酬総額の上限まで設定する
- 毎年の役員報酬を抑えつつ、退職金積立とDC掛金で老後資金を形成する
- 退職金の一括支給額が多すぎると資金繰りを圧迫し、法人税節税効果が薄れる場合があります。
- DCの拠出上限超過や運用商品のリスク管理不足が、将来受取額に影響を与える恐れがあります。
助成金・福利厚生制度を活かす節税アイデア

社労士は助成金申請や労務管理の専門家である分、制度活用による節税余地が大きいとされています。とくに雇用維持を目的とした国の助成金や、従業員の満足度を高める福利厚生制度は、条件を満たせば会社の実質負担を抑えつつ課税所得を圧縮する手段になり得ます。
たとえばキャリアアップ助成金を使って正社員化を進めれば、1人あたり数十万円規模の助成が見込め、人件費増による社会保険料負担を相殺できる可能性があります。
また福利厚生費として非課税手当を適切に支給すれば、従業員の手取りを増やしながら法人側の損金算入枠を広げられる点も魅力です。以下では、雇用関連助成金を活用した負担圧縮策と、非課税手当・インセンティブの導入法を具体的に解説します。
雇用関連助成金で実質負担を圧縮
助成金は返済不要の公的給付であるため、人件費増や教育コストを実質的にカバーできるとされています。
代表例としてキャリアアップ助成金、特定求職者雇用開発助成金、人材開発支援助成金が挙げられ、それぞれ正社員転換・高年齢者雇用・職業訓練などの要件を満たすことで数十万〜数百万円の助成を受け取れる可能性があります。
助成金は課税所得に算入されますが、同時に支給要件を満たすための賃金加算・研修費用・社会保険料が経費になるため、法人の実効税負担はトータルで下がりやすい構造です。
申請フローとしては、①支給要件の事前確認、②計画書の提出、③実施後の支給申請、の3段階を押さえることが重要です。
| 主な助成金 | 要件と最大支給額の目安 |
|---|---|
| キャリアアップ助成金 | 一般:1人あたり最大40万円、重点分野:最大80万円(加算要件あり) |
| 人材開発支援助成金 | OFF-JT実施→賃金助成・経費助成の二本立て |
| 特定求職者雇用開発助成金 | 高齢者・障がい者を雇用→1人あたり最大240万円 |
- 着手前に計画届を提出しないと受給できないケースが多いです。
- 受給後5年間は雇用維持などのフォローアップ調査が行われる可能性があります。
非課税手当・インセンティブ導入法
給与の一部を非課税手当やインセンティブに置き換えると、従業員の手取りを維持しつつ会社負担の社会保険料と源泉所得税を抑えられるとされています。
具体例として通勤手当(月15万円まで非課税)、出張日当、永年勤続表彰金(一定額まで非課税)、社宅貸与制度などが挙げられます。
またカフェテリアプランや選択制確定拠出年金(選択制DC)を導入すると、従業員が税制優遇メリットを享受しながら福利厚生費として損金算入できる可能性があります。
導入手順は、①就業規則や賃金規程に手当の定義を追加、②非課税枠を超えない金額設定、③支給実態を証憑で管理、の3ステップを守ることで税務調査への備えが強化されます。
- 通勤手当→公共交通機関の定期代が原則、ガソリン代は距離に応じて非課税枠
- 出張日当→合理的金額なら課税されないが、業務実態の証明が必要
- カフェテリアプラン→上限ポイントを設けるとコストコントロールしやすい
- 非課税枠を超える支給は給与扱いとなり、社会保険料と所得税が課税される場合があります。
- 社宅家賃が著しく低いと「経済的利益」と見なされ、課税対象となる可能性があります。
不動産投資で継続的に節税と資産形成

税務メリットが長期にわたって継続する不動産投資は、社労士のように安定したキャリアを持つ専門職に向いた節税手段とされています。
毎年の減価償却費で課税所得を圧縮しつつ、家賃収入でキャッシュフローを確保できるため、所得税・住民税の軽減と資産形成を同時に進められる点が大きな魅力です。
また損益通算や相続時評価額の引下げ効果により、将来的な税負担や相続コストを抑えやすいのも特徴です。まずは「節税額」「安定収益」「出口戦略」の三つを指標に投資プランを立て、保有期間中は賃貸管理と税務申告をスムーズに行う体制を構築しましょう。
【不動産投資が提供する3つのメリット】
- 減価償却で毎年の所得を圧縮
- 家賃収入で安定的なキャッシュフローを確保
- 物件評価額の引下げで相続・贈与税を軽減
減価償却と損益通算の実務ポイント
減価償却は「建物取得価額×償却率」で計算し、耐用年数内で費用配分する手続きです。中古物件の場合は法定耐用年数を超えていても「残存耐用年数(例:木造22年×20%=4年)」を採用できるため、短期間に大きな償却費を計上できます。
経費計上の際は、建物・設備・土地を明確に区分し、固定資産台帳を整備することが基本です。
| 費目 | 即時経費 | 減価償却 |
|---|---|---|
| 修繕費 | 軽微な修繕→全額費用 | 資本的支出→耐用年数で償却 |
| 家具家電 | 30万円未満→一括償却 | 30万円以上→法定耐用年数 |
【損益通算のポイント】
- 給与所得と相殺できる赤字は「土地の借入金利息を除外後」の額です。
- 赤字幅が大きいと翌期以降に繰越控除できる可能性があります。
- 購入時に建物割合を高める交渉を行い、償却費を最大化しましょう。
- 空室リスクを織り込んだうえで黒字化できる賃料設定を確認しましょう。
社労士が選ぶべき物件タイプと購入手順
社労士は本業で多忙なため、管理負担の軽い区分マンションを選ぶケースが多いものの、節税効果を重視するなら短期償却が可能な築古一棟アパートも有力候補です。
物件タイプ選定では「建物割合」「修繕コスト」「管理工数」の3点を天秤にかけ、自身のキャッシュフロー計画に合ったポートフォリオを組むことが重要です。
| 物件タイプ | メリット | 留意点 |
|---|---|---|
| 区分マンション | 低管理負担・流動性高い | 建物割合が低く償却額は限定的 |
| 一棟アパート | 建物割合高く短期償却可 | 修繕・空室が一度に発生しやすい |
【購入手順】
- 投資目的を明確化→節税額と利回り目標を設定
- 融資打診→金利・期間・自己資金比率を比較
- 物件調査→レントロール・修繕履歴・近隣賃料を確認
- 売買契約→建物割合を売主と交渉し、鑑定書で裏付け
- 決済・引渡し→管理会社と賃貸募集・設備点検の計画を策定
- 築古物件は大規模修繕費が読みにくく、キャッシュフローを圧迫する可能性があります。
- 管理会社選定を怠ると空室率が高止まりし、節税効果を上回る損失を招く恐れがあります。
節税効果を守るリスク管理と出口戦略

節税効果を長期にわたり維持するには、物件保有中のリスク管理と、売却や法人移行といった出口戦略を事前に設計することが重要です。
減価償却が終わる頃には帳簿価額が大幅に下がり、譲渡益課税が増える可能性があります。また、税制改正により損益通算や青色申告特別控除の条件が変更されるケースも想定されるため、定期的なポートフォリオの見直しが欠かせません。
さらに空室・修繕・金利上昇といった外部要因がキャッシュフローを圧迫すると、節税どころか追加資金が発生するリスクがあります。
リスクシナリオごとに対応策を用意し、出口局面では保有・売却・法人移行の選択肢を比較検討することで、節税メリットを最大化しながら資産を守る体制を整えましょう。
【リスク管理の3ステップ】
- キャッシュフローの月次モニタリング→赤字化前に対策
- 修繕積立・空室率の見直し→回復計画をシミュレーション
- 税制・金利動向のチェック→制度変更時に即座に対応
税制改正に備えるポートフォリオ見直し
税制改正は償却率や損益通算の可否など、節税効果を根底から変えることがあります。とくに赤字通算の制限強化や賃貸用不動産の評価方法変更が検討されると、保有物件の税務メリットが縮小する可能性があります。
そのため、少なくとも年1回は物件ごとの税効果とキャッシュフローを再計算し、想定改正シナリオを当てはめて感度分析を行うとされています。加えて、エリア分散や物件タイプ分散を行うことで、制度変更の影響を平準化できる点もメリットです。
| 改正項目 | 想定影響 | 見直しアクション |
|---|---|---|
| 損益通算制限 | 赤字圧縮効果が低下 | ローン返済期間の延長でキャッシュ確保 |
| 耐用年数延長 | 償却費が減少 | 設備投資で新たな償却枠を確保 |
| 固定資産税評価改定 | 保有コスト上昇 | 資産売却や用途変更を検討 |
- 税制改正大綱を毎年12月に確認→影響度をシミュレーション
- 必要に応じて管理会社と家賃改定・設備更新計画を協議
売却・法人移行で税負担を最小化
減価償却終了後や大規模修繕前は、キャッシュフローと税負担がクロスする転換点となり得ます。そのタイミングで売却して長期譲渡税率20%を適用すれば、累進課税最高税率より低い水準で利益を確定できる可能性があります。
いっぽう法人に移行して保有を続ける方法では、個人から法人へ物件を売却または現物出資する形を取り、法人実効税率約30%で所得を封じ込めるスキームが検討されます。
ここでは譲渡所得税・登録免許税・不動産取得税などのコストを比較し、最終的な税負担の軽減幅を試算することが不可欠です。
| 選択肢 | メリット | 留意点 |
|---|---|---|
| 個人で売却 | 譲渡益を低税率で確定 | 翌期以降の家賃収入が消失 |
| 法人へ移行 | 法人税率で所得封じ込め | 登録免許税・取得税のコスト |
| 持ち株会社化 | 事業承継・相続対策を両立 | 設立コストと運営管理が増 |
- 個人→法人売却の場合、売買価格の妥当性が低いと寄附認定リスクがあります。
- 現物出資による移行では、簿価と時価の差額に譲渡益課税が生じる可能性があります。
まとめ
本記事では、社労士が自ら活用できる節税手法を、給与設計・助成金・福利厚生から不動産投資まで段階的に整理しました。役員報酬や社会保険料の見直しで即効性を、減価償却で継続的な節税を図り、出口戦略でリスクを抑える全体像がわかったはずです。
チェックリストを参考に、まずは目標所得圧縮額の試算から着手しましょう。次の決算前に準備を進めれば、税負担を抑えつつ手元資金を確保し、将来の資産形成へ大きな一歩を踏み出せます。