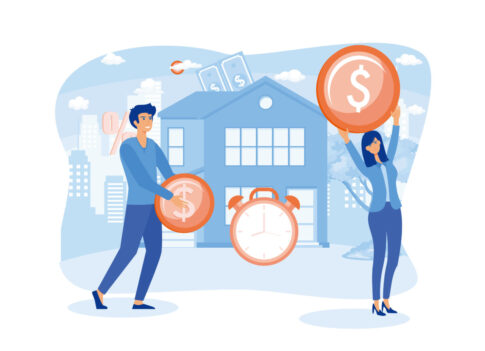毎年の税金に悩むなら、不動産を使った「減価償却」と「損益通算」で節税する方法を知っておくと安心です。本記事では仕組みから物件選び、修繕タイミングや出口戦略までを具体例で解説。読めば税負担を抑えつつ安定したキャッシュフローを得る道筋がつかめます。
目次
不動産節税の仕組みとメリット

不動産投資で節税できる最大の理由は「帳簿上の利益」と「実際のキャッシュフロー」がズレる構造にあります。家賃収入は毎月入金されますが、建物や設備は減価償却として時間をかけて費用計上できるため、キャッシュを手元に残したまま課税所得だけを小さくすることが可能です。
さらに赤字が出た場合は給与所得など他の所得と損益通算でき、所得税・住民税を直接カットできます。このように〈節税〉と〈資産形成〉を同時に狙えるのが不動産投資の大きな魅力です。
- キャッシュを残しながら帳簿上の利益を圧縮
- 損益通算で給与所得の税金も削減
- ローン返済は家賃収入で賄えるため自己資金負担が少ない
- 長期保有でインフレヘッジと相続対策にも有効
減価償却と損益通算で税負担を圧縮
減価償却とは、建物や設備の取得価額を耐用年数にわたり分割して経費化する会計ルールです。たとえば築25年の木造アパート(法定耐用年数22年超)を購入すると、簡便法により残存耐用年数は「4年」となり、建物価格を毎年25%ずつ損金にできます。
これにより不動産所得は帳簿上で赤字化しやすく、給与所得や事業所得と損益通算が可能です。例として家賃収入500万円に対し、通常経費150万円に加えて減価償却費250万円を計上したケースを示します。
| 項目 | 減価償却前 | 減価償却後 |
|---|---|---|
| 経費総額 | 150万円 | 150万円+減価償却250万円 |
| 不動産所得 | 350万円 | ▲100万円 |
| 所得税・住民税 (合計税率20%の場合) |
約70万円 | 約40万円減 (給与天引き分から還付) |
- 中古物件は耐用年数短縮で償却スピードUP(木造4年、RC9年など)
- 赤字の繰越控除は青色申告に限り3年間有効
- 土地は償却不可。建物割合は固定資産税評価額や鑑定書で客観的に按分
住宅ローン控除・固定資産税軽減の活用法
自宅購入でも節税メリットは大きいです。住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の控除率は現在0.7%。
令和4年以降の入居者は原則13年間適用され、住宅区分ごとに年末残高と控除限度額が定められています(例:認定長期優良住宅は残高上限5,000万円・控除限度額35万円/年)
さらに、新築住宅(120㎡以下の居住用部分)なら固定資産税が3年間半額、認定長期優良住宅等は5年間半額となる特例があります。都市部の木造住宅であれば年間10〜15万円の節税効果になるケースも珍しくありません。
- 住宅ローン控除は「認定住宅」等で借入限度額と期間が優遇(控除率は同じ0.7%)
- 固定資産税の減額は家屋完成翌年度から。通知書が届いたら期限内に市区町村へ申請
- 中古住宅は築年数要件(木造20年・耐火25年)を超える場合、耐震基準適合証明が必須
- 転勤などで賃貸に出すと控除が停止されるため、将来プランを事前にシミュレーション
- 購入前に住宅性能証明・登記情報を確認し、控除要件を満たすか精査
- 初年度の確定申告は提出書類が多いため、国税庁サイトの入力ガイドや税務署の事前相談を活用
戦略的な物件選びと投資スキーム

同じ1,000万円を投資しても、物件の築年数・構造・購入主体によって減価償却スピードや損益通算の幅は大きく変わります。
節税を最大化するには、建物割合が高く短期償却できる中古物件を狙う、木造・RCなど構造ごとの耐用年数を把握しキャッシュフローに合う償却年数を選ぶ、将来の売却益課税も見据えて法人か個人かを決める――という3ステップで意思決定することが重要です。
さらにフルローン・オーバーローン・現金購入など資金調達スキームまで組み合わせれば、手元資金を温存しながら税負担を抑えることも可能になります。
- 短期償却で当期利益を圧縮するか、長期償却で安定CFを狙うかを選択
- 融資条件(期間・金利・返済比率)と耐用年数の整合性を必ず確認
- 出口戦略(売却・相続)まで含めた総合税負担を試算
新築vs中古・木造vsRCで節税効果はこう変わる
新築は設備トラブルが少なく賃料も高めに設定できますが、法定耐用年数が長いため減価償却費は小さく、節税インパクトは限定的です。一方、中古は購入価格に占める建物割合が大きく、耐用年数短縮特例で4~15年程度で償却できるため、初年度から大きな経費計上が期待できます。
構造別では木造が最短4年、RC造でも最短9年で償却できるケースがあり、金利1.5%・返済比率50%以内の条件であればキャッシュフロー黒字と節税を同時に実現しやすいです。
| 区分 | 耐用年数(短縮後) | 節税インパクト |
|---|---|---|
| 新築木造 | 22年 | 減価償却が少なく節税効果は小。長期安定運用向き |
| 中古木造 | 4〜6年 | 償却スピード大。初年度から大幅節税が可能 |
| 新築RC | 47年 | 減価償却が緩やか。耐用年数長く融資期間を取りやすい |
| 中古RC | 9〜12年 | 節税と資産価値のバランスが良好。都市部で人気 |
- 所得が高い人→中古木造で早期節税、キャッシュ重視
- 長期安定派→新築RCで修繕リスクを抑えインカム重視
- キャッシュフロー黒字でも帳簿赤字にできる中古物件は融資審査で返済比率を要確認
- 木造は保険料・修繕費がRCより高くなりやすいのでランニングコストを試算
- RCは固定資産税が高め。都市計画税も合わせてコストを織り込む
法人購入と個人購入どちらがお得?
高所得者が中古物件を個人名義で購入し損益通算を行うと、最大55%の累進税率を緩和できるメリットがあります。しかし家賃収入が増え課税所得が900万円を超えるあたりから、法人実効税率(約23%)のほうが有利になるケースが多くなります。
法人購入では役員報酬や社宅スキームで所得分散が可能なほか、家族を役員にして給与を支給すれば相続税対策にも効果的です。ただし均等割7万円や社会保険料の負担増、設立コストが発生するため、キャッシュフローとのバランスが重要です。
| 購入形態 | 主なメリット | 主なデメリット |
|---|---|---|
| 個人名義 | 損益通算で給与所得を直接圧縮。手続き簡単。 | 累進税率が高くなると節税メリットが薄れる。 |
| 法人名義 | 税率フラット+所得分散が可能。退職金・保険活用◎。 | 設立費用・均等割・社保で固定費UP。赤字でも申告義務。 |
- 家賃+本業所得900万円超→法人スキーム検討
- 利益500万円未満・フルローン→まずは個人名義でCF重視
- 将来の相続対策を重視→早めに法人化→株式承継がスムーズ
- 融資金利は法人のほうが高めに設定される傾向。返済比率をシミュレーション
- 設立後2年間は消費税免税を活用し、3年目以降の納税資金をプール
- 所得分散を目的に家族へ役員報酬を支払う場合は実態業務と金額相当性を必ず確保
実践テクニックでキャッシュフロー最大化

節税効果を高めても、手元資金が枯渇すれば投資は継続できません。ここでは「支出をコントロールしながら収入を安定させる」ことに焦点を当て、修繕費のタイミング調整、ローンの繰上返済・借換という2大テクニックを紹介します。
これらは決算対策と資金繰り改善の両方に効くため、減価償却や損益通算と組み合わせるとキャッシュフローが飛躍的に向上します。
- 修繕費を計画的に実施し、黒字と税負担を平準化
- ローン条件を見直して利息削減と節税を同時に実現
- 資金クッションを厚くし、次の投資チャンスに備える
リフォーム・修繕費の時期調整術
修繕費は「資本的支出」と「修繕費」に分かれ、税務上の取り扱いが大きく異なります。資本的支出は建物価値を高めるため減価償却になりますが、修繕費は発生年度に全額経費化できるため、黒字が膨らんだ期に実施すると即効で課税所得を圧縮できます。
たとえば決算3か月前に外壁塗装150万円を実施し、損益通算で法人税率23%とすると、約35万円の税金が削減できる計算です。判断に迷う場合は国税庁タックスアンサー「資本的支出か修繕費か」を参照し、金額の30%基準や3年周期など客観根拠を整えましょう。
| 費用区分 | 税務処理 | 節税インパクト |
|---|---|---|
| 修繕費 | 当期全額損金 | 利益圧縮即効性◎ |
| 資本的支出 | 耐用年数で減価償却 | 長期節税・資産価値UP |
- 決算4〜6か月前:年度利益を予測し修繕候補をリスト化
- 決算3か月前:見積り取得→税理士と経費区分を確認
- 決算直前:資金繰りを確認し施工時期を最終決定
- 大規模修繕は一括支出が難しい場合、分割施工で年度をまたがせ利益平準化
- 火災保険の満期更新時に付帯補償で実質コストを下げる工夫も有効
繰上返済と借換で利息と税金を同時削減
ローン金利は経費計上できる一方で、キャッシュアウトが多いと手元資金を圧迫します。繰上返済は利息負担を減らしつつ元金を早期に圧縮できるため、金利差引き後の実質利回りを押し上げる効果が大きいです。
具体的には金利2.0%の残債3,000万円を100万円繰上返済すると、総支払利息が約60万円減少し、返済期間も短縮されます。
ただし利息=経費が減るため節税額も下がる点に注意が必要です。そこで借換で金利を0.8%下げつつ返済期間を据置けば、利息負担を抑えながら経費枠を維持でき、キャッシュフロー改善と節税を両立できます。
- 金利差1%以上 or 残存期間10年以上で借換効果が大
- 諸費用は借換後3年以内に回収できるか試算
- 団信・火災保険の再加入条件を確認し、総コストで比較
- 金利交渉は「他行仮審査の金利提示→メインバンクと交渉」が王道
- 元金均等返済への変更で後半ほどキャッシュフローが厚くなる
- 繰上返済は「返済額軽減型」を選ぶと毎月CFが即改善し投資余力が増加
長期視点での出口戦略と注意点

不動産投資の節税効果は「買った瞬間」にピークを迎え、その後は減価償却が尽きるにつれて帳簿上の利益が増え、納税額も徐々に上がります。さらに売却益や相続が発生すると、譲渡所得税・相続税という新たな課税フェーズが待ち受けます。
そこで大切なのが⟨いつ・いくらで売るか⟩、⟨誰に・どう継ぐか⟩を早い段階から決め、総合税負担を最小化することです。
具体的には〈保有期間5年超の長期譲渡税率20.315%の活用〉、〈相続時精算課税や家族信託で課税評価額を引き下げる〉など複数の選択肢があり、物件ごとに最適解が異なります。出口を戦略的に設計すれば、節税メリットを最後まで最大化しながら次の投資や事業承継にスムーズにシフトできます。
- 減価償却が切れる3年前から売却or組み換えを検討
- 所得の高い時期は法人スキーム、リタイア後は個人名義で税率調整
- 相続税評価額を下げるには「賃貸中に相続」を狙う
譲渡所得税・相続税を見据えた節税計画
譲渡所得税は、物件の売却価額から取得費と譲渡費用を差し引いた「譲渡所得」に課税されます。保有期間が5年以下だと39.63%、5年超なら20.315%と税率が大きく異なるため、最低でも5年以上保有して長期譲渡に切り替わるタイミングで売却を検討するのが基本です。
また、減価償却累計額は取得費から控除されるため、早期に償却を取り過ぎると売却益が膨らむ点に注意が必要です。相続税対策としては、生前贈与や家族信託で所有権を分散させたり、物件をあえて賃貸に出して評価額を約70%まで圧縮する方法が有効です。
| 施策 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|
| 長期譲渡売却 | 税率20.315%で納税額を大幅軽減 | 減価償却後は帳簿価額が低くなり譲渡益が拡大 |
| 相続時精算課税 | 2,500万円まで贈与税ゼロ、将来の相続税を前倒し計算 | 制度選択後は暦年贈与が使えない |
| 家族信託 | 認知症リスクを回避しつつ受益権分割で評価額を抑制 | 信託契約・登記費用がかかる |
- 保有5年超→長期譲渡税率へ切替
- 売却前に譲渡費用(仲介手数料・解体費など)を漏れなく計上
- 相続2年前から贈与・信託で評価圧縮+納税資金を確保
- 地価上昇期は売却益が大きくなるため、買換え特例を活用し税を繰り延べ
- 親族間売買は時価取引証明を取得し、みなし贈与課税を防止
ポートフォリオ見直しで税リスクを最小化
物件を複数保有している場合、資産規模が拡大するほど空室・修繕・金利上昇などのリスクが累積し、税負担も複雑化します。
そこで年1回の「資産ポートフォリオ健診」を行い、 NOI(純営業収益)・LTV(ローン残高比率)・減価償却残高をチェックしながら、売却・追加投資・法人化再編を判断することが重要です。
たとえば築古木造の減価償却枠が尽き、キャッシュフローも横ばいになった段階でRCや戸建てへの組み換えを行えば、再度償却枠を確保しつつ耐用年数長期化で安定収入を得られます。
また金利上昇局面では変動金利物件を縮小し、固定金利物件を増やすことでキャッシュフローを平準化し、利息経費の変動による税リスクを小さくできます。
- NOI利回りが5%未満→売却または賃料改定を検討
- LTV75%超→繰上返済または低LTV物件へ組み換え
- 減価償却残高0→新規物件購入で償却リレー継続
- 変動金利比率50%超→借換で固定化し金利リスク低減
- 法人再編(合併・分社)は登録免許税・不動産取得税に注意し、トータル税負担で判断
- 物件売却で大幅譲渡益が出る場合は、同年度内に赤字物件を減損処理し利益相殺を図る
- 海外不動産を含む場合は、為替差損益と現地税制の二重課税を事前にシミュレーション
まとめ
不動産節税は①減価償却で利益を圧縮し②損益通算で税額を下げ、さらにローン控除や固定資産税軽減を組み合わせて効果を高めます。
物件タイプや購入主体、修繕時期、売却時期を戦略的に選ぶことでキャッシュを残しながら資産を増やせます。まずは自分の所得と目標から最適な投資プランをシミュレーションしましょう。