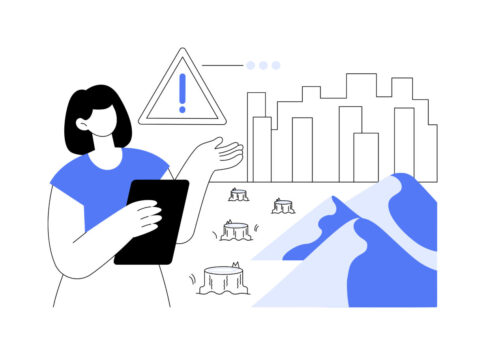再建築不可の土地は「安い」で片づけず、根拠ある評価が重要です。
本記事は、路線価と近隣成約で基準相場を作り、セットバックや私道承諾など個別控除を数量化。さらに収益還元で下支えし、出口(買取・仲介・入札)別の手残りまで一気に整理します。
再建築不可×土地評価の基礎と流れ

再建築不可の土地評価は、「基準相場づくり→個別控除の数量化→収益・代替活用での下支え→出口(売却手段)と手残りの確認」という流れで進めるとブレが少なくなります。
まず、路線価や近隣成約で“再建築可の基準相場”を置き、次にセットバック面積、私道の持分や通行・掘削承諾、擁壁・がけ・インフラ是正などを数量×単価で控除します。
さらに、駐車場・貸地・倉庫などの収益可能性を試算して下限値を把握し、最後に現金買取・仲介・入札の違い(期間・条件・価格)を同じシートで手残り比較します。
評価は「一次資料+現地実測」で裏づけることが重要で、後退線・数量表・写真を一体で揃えると説明力が高まります。
【評価の基本ステップ】
- 基準相場の設定→路線価・成約の整合
- 個別控除の数量化→後退・権利・是正費
- 収益還元の下支え→駐車場等の収支
- 出口比較→価格×期間×条件で手残り判断
| 段階 | 主な作業 | 成果物 |
|---|---|---|
| 基準相場 | 路線価・公示・近隣成約の突合 | 基準単価レンジ |
| 個別控除 | 後退面積・承諾・是正数量の拾い出し | 数量表・概算見積 |
| 収益還元 | 賃料・稼働・費用の設定 | 還元価(下限目安) |
| 出口設計 | 買取/仲介/入札の横並び | 手残り比較表 |
- 「根拠は一次資料・実測を最優先」と明文化
- 控除は最少/最大のレンジで表示→交渉を安定化
評価の目的と前提条件を整理する
評価の精度は、目的と前提条件を最初に固定できるかで大きく変わります。目的は大きく、売却価格の決定、投資意思決定(購入可否)、金融機関への説明、相続・組替えの内部評価に分かれます。
目的が違えば、許容できる期間・リスクも変わるため、基準相場や控除の「強さ」を調整します。前提条件は、法的道路の種別(法42条のどれか)、接道2mの連続性、2項道路の中心線と後退量、私道の持分・通行/掘削/再掘削の承諾、越境の有無、有効宅地面積(後退後)、地形(がけ・擁壁・高低差)、区域指定(防火・用途・高度地区等)、インフラ(上下水・ガス・電気)、市場・金利(時点補正)などです。
これらを資料と実測で固め、抜けや曖昧な点は「未確定」と注記したうえで控除をレンジ表示にします。
【目的別に重視する指標】
- 売却価格の決定→基準相場の整合と控除の妥当性
- 投資意思決定→収益還元・出口(売却手段)での手残り
- 金融機関説明→一次資料・見積の網羅性、工程の実現性
| 前提 | 確認内容 | 証拠・出典 |
|---|---|---|
| 道路・接道 | 法42条の種別、連続2m、後退量 | 道路台帳・指定道路図・幅員証明・実測写真 |
| 権利 | 私道持分、通行/掘削/再掘削、越境 | 登記事項、承諾書案、越境一覧 |
| 物理・区域 | 擁壁・高低差、防火/用途/高度地区 | 点検記録、都市計画図、配置図 |
- 「確定」「未確定」を色分け→控除はレンジで表示
- 写真・図・数量・見積を一体化→誰が見ても同じ結論に
三手法の使い分け(事例・収益・原価)
評価は基本的に〈事例比較法〉〈収益還元法〉〈原価法(造成・残余)〉を併用し、目的に応じて重み付けします。
事例比較法は「近隣の再建築可」を基準に、再建築不可の個別控除(後退面積、承諾取得、外構・舗装・擁壁、インフラ敷設など)を差し引く考え方で、実勢連動性が高いのが利点です。
収益還元法は、現況活用(駐車場、資材置場、倉庫、貸地など)の賃料、稼働率、維持費、CAPレートで下限値を把握します。
原価法は、開発・是正を行って「再建築可」に近づけるための費用(通路拡幅、位置指定、排水整備、擁壁補強等)を計上し、残余法で土地値を逆算する使い方が現実的です。
再建築不可は不確実性が高いため、事例比較を主軸に、収益還元で底を固め、原価法・残余で“可に近づけた場合の上限”を検討する三点支持が有効です。
| 手法 | 強み | 留意点 |
|---|---|---|
| 事例比較 | 市場連動・説明容易 | 控除の数量化が甘いとブレが拡大 |
| 収益還元 | 下限値の把握・逆風時に有効 | 賃料・稼働の根拠が必要、用途に制約あり |
| 原価/残余 | 「整備後の可能性」を金額で比較 | 工期・同意形成の不確実性をレンジ化 |
- 事例=中心、収益=下限、原価=整備後の上限で三点支持
- CAPレート・控除単価は出典明記→恣意性を排除
調査資料と算定シートの作成手順
調査では、道路台帳・指定道路図・幅員証明、2項道路台帳・中心線資料、登記事項(通路地番含む)、私道持分一覧、通行/掘削/再掘削の承諾案、越境一覧、確定測量図(なければ地積測量図+実測)、配置図(後退線・隅切り赤入れ)、数量表(後退幅×延長、撤去・復旧数量)、概算見積(2〜3社)、都市計画図、防災ハザード、周辺賃料データ、近隣成約の抜粋をそろえます。
算定シートは「入力→計算→結果」の三階層で、入力欄に面積・後退量・単価・承諾費・復旧仕様・賃料・稼働・CAP・出口条件(買取/仲介/入札)を並べ、計算欄で〈基準相場−個別控除〉と〈還元価〉を同時に出し、結果欄で価格帯と手残り、期間コストを表示します。
未確定値は仮置き色で区別し、最少/最大のレンジ出力をデフォルトにすると、交渉時の“あと下がり”を防げます。
| 項目 | 入力例 | 備考 |
|---|---|---|
| 基準単価 | ○万円/㎡(路線価×係数、成約補正) | 路線価・成約の出典を併記 |
| 後退面積 | 10㎡(後退幅0.5m×延長20m等) | 数量表・赤入れ図と一致させる |
| 承諾・復旧 | 掘削/再掘削協力金、舗装・側溝見積 | 単価は最少/最大の二本立て |
| 収益条件 | 月極P×台数・賃料、費用率 | CAPは近傍の実勢レンジ |
| 出口条件 | 買取/仲介/入札の期間・特約 | 手残りと時間価値で比較 |
- 入力セルに出典欄を設ける→裏取りの効率化
- 未確定値は色分け→更新履歴を残し“あと下がり”防止
基準相場づくり|路線価と成約の整合

再建築不可の評価は、まず「市場が許容する単価レンジ」をつくることから始めます。起点は〈地点の地価水準〉を示す路線価・公示地価・基準地価と、〈実勢〉を示す近隣成約の二本柱です。
前者で位置の強弱(幹線/生活道路、角地、側方路線 など)を大づかみに捉え、後者で駅距離・前面道路の種別と幅員・用途地域・防火指定・面積規模・築年など条件をそろえて“同じ土俵”の成約だけを抽出します。
次に、路線価等で得た地点の力と、成約で得た実勢の水準が矛盾していないかを相互にチェックし、差があれば要因を分解(時点、面積、道路条件の差)して整合させます。
こうして作った「再建築可の基準相場」をベースに、個別控除(セットバック・私道承諾・擁壁・インフラ等)を差し引くのが再建築不可の王道です。
【整合の考え方】
- 位置の強弱は路線価・公示・基準地で確認→駅距離や幹線影響をメモ
- 実勢の中心は成約で確認→募集価格は参考程度にとどめる
- 食い違いは「時点」「面積規模」「道路条件」の三点で説明づけ
| 情報源 | 役割 | 使うときの注意 |
|---|---|---|
| 路線価 | 地点間の比較・角地/側方路線補正 | 相続税評価ベース→実勢との乖離は成約で補正 |
| 公示/基準地 | 時点ごとの指標でトレンド確認 | 標準地条件と対象の違いを注記 |
| 近隣成約 | 実勢の中心値・レンジの把握 | 条件を揃える(駅距離・道路種別・面積規模) |
- 「位置(指標)→実勢(成約)→整合(差の説明)」の順で固定
- 整合後は単価をレンジで管理→控除のレンジと相性が良い
路線価・公示・基準地の読み方
路線価(相続税路線価)は毎年の評価基準日における道路ごとの指標で、同一路線でも角地・側方路線・間口奥行・不整形などの補正項目が設定されています。
まず対象の前面道路と隣接路線の値を取り、角地・側方路線の影響がありそうなら補正の有無をメモします。
さらに、奥行や間口が極端な場合は「標準的な宅地」からどれほど逸脱しているかを現地写真と図面で整理しておきます。
公示地価(毎年の基準日評価)と基準地価(年央の基準日評価)は、路線価よりも“市場時点”に近い動きを示すため、近年の上昇/下落トレンドや周辺との相対位置を読むのに適します。
評価では、路線価で位置の強弱を、公示/基準地で時点トレンドを押さえ、両者を近隣成約の実勢とつなぐ橋渡しに使います。
数値の絶対比率で強引に換算するのではなく、「なぜ違うか」を条件差で説明する姿勢が重要です(幹線接面、駅力、商業系/住居系の混在など)。
【指標の読み解き手順】
- 路線価→前面/側方路線の値を取得し、角地等の補正可能性を記録
- 公示/基準地→対象近傍の標準地を抽出し、時点の方向性を把握
- 対象の形状・奥行・間口を図と写真で可視化→標準との差を明示
| 指標 | 読み方のポイント | 整合での役割 |
|---|---|---|
| 路線価 | 道路ごとの地点強度。角地/側方の補正有無 | 位置の基礎値を提示し、実勢差の説明材料に |
| 公示地価 | 年次ベースのトレンド把握 | 成約の時点補正の根拠に活用 |
| 基準地価 | 年央の時点評価で補助線に | 上期/下期の市況差の説明に有効 |
- 指標は“位置と時点の羅針盤”、価格決定は最終的に成約で検証
- 単純な換算率に頼らず、条件差(道路/駅/用途)で整合させる
近隣成約の抽出と時点補正
実勢の芯を作るには、条件をそろえた近隣成約の抽出が欠かせません。半径・行政区・最寄駅・徒歩分数・用途地域・防火指定・前面道路の種別と幅員・接道長さ・面積規模・築年(建付地の場合)をそろえ、極端な外れ値は除外します。
募集価格や未成約の事例は参考にとどめ、必ず「成約価格」を基準にします。時点補正は、市況トレンド(公示/基準地の方向性)、金利・融資姿勢、供給量の変化などを踏まえて、基準時点に引き直します。
規模の経済(小区画は単価が上がり、大区画は下がる傾向)や、駅力・生活利便施設の差も補正候補です。
再建築不可評価に使う成約は、原則「再建築可」のものを母集団にし、後段の位置補正で「不可」に落とし込みます。これにより、地点の力(駅距離・用途・道路階級)と市場の水準を安定して反映できます。
【抽出と補正の実務手順】
- 条件合わせ→駅距離・道路種別・面積・用途・防火を揃える
- 成約のみに限定→募集や未成約は除外し外れ値を排除
- 時点補正→基準時へ引き直し、規模・駅力差を調整
| 項目 | 抽出/補正の観点 | 実務ポイント |
|---|---|---|
| 駅距離 | 徒歩分数・坂/高低差の有無 | 地形メモを残し体感差を数値に寄せる |
| 前面道路 | 法42条の種別・幅員・接道長さ | 「幹線/生活道路」の違いを注記 |
| 面積規模 | 規模の経済で単価差が出る | 母集団を近い規模で揃える |
- “似ている”ではなく“同条件”を徹底→母集団の質を上げる
- 時点は基準日に統一→増減は指標(公示/基準地)で説明
再建築可→不可の位置補正
整合した「再建築可の基準相場」を、対象の「再建築不可」に落とし込むのが位置補正です。やることは二つ。
第一に、〈物理的控除〉としてセットバックに伴う有効宅地の減少、外構・設備移設、通路舗装や側溝復旧、擁壁やがけの対策、上下水・ガス等の新設ルート整備を数量×単価で金額化します。
第二に、〈権利的控除〉として、私道持分の取得や通行/掘削/再掘削の協力金、管理覚書の整備コスト、同意形成にかかる期間コスト(時間価値)を織り込みます。
未確定が多い項目は最少/最大のレンジで提示し、どの条件でどこまでブレるかを明示します。
さらに、現況活用(駐車場・貸地・倉庫等)の収益還元で下限値を算出しておくと、控除のやり過ぎを防ぐガードレールになります。
【控除の設計図】
| 控除項目 | 数量化の方法 | 根拠資料 |
|---|---|---|
| セットバック | 後退幅×延長→面積減+復旧数量 | 後退線入り配置図・数量表・見積 |
| 私道承諾 | 通行/掘削/再掘削・占用の範囲ごとに計上 | 承諾書ドラフト・協力金合意メモ |
| インフラ/擁壁 | 配管延長・桝・側溝、補強/更新の数量 | 配管図・点検記録・施工見解 |
| 期間コスト | 売却までの月数×想定利回り | 工程表・金融条件メモ |
- 控除は“数量×復旧仕様”で客観化→根拠資料を添える
- レンジ(最少/最大)で幅を示し、収益還元で下限を確認
個別控除の体系化と数量化

再建築不可の土地評価では、控除を「勘」で丸めず、数量化→単価設定→根拠資料添付の順で客観化します。考え方はシンプルです。
まず再建築“可”の基準相場を置き、そこから〈物理的控除〉(セットバックで減る有効宅地、外構・設備の撤去と復旧、通路舗装や側溝の復旧、擁壁補修・がけ対策、上下水・ガスの新設)と〈権利的控除〉(私道持分取得、通行/掘削/再掘削承諾、管理覚書の整備コスト)、さらに〈時間価値〉(取得〜売却までの月数に応じた機会損失)を差し引きます。
各控除は「数量×復旧仕様(または権利メニュー)×相場単価」で算定し、未確定は最少/最大レンジで示します。
数量は配置図へ赤入れ、単価は見積や公的単価、相場メモを出典付きで管理すると、第三者への説明が通ります。
【控除の全体マップ】
| 区分 | 主な項目 | 数量化の要点 |
|---|---|---|
| 物理 | セットバック、外構移設、舗装・側溝、擁壁、配管 | 面積・延長・個数・厚みを数量表化、復旧仕様を明記 |
| 権利 | 持分取得、通行/掘削/再掘削承諾、覚書作成 | 範囲(人・車・工事車両・占用)と承継条項で区分 |
| 時間 | 承諾交渉・工事・検査の所要 | 月数×想定利回りで期間コスト計上 |
- 控除は必ず“数量×仕様×単価”で計算し、出典を併記する
- 未確定はレンジ表示(最少/最大)にして交渉のぶれを吸収
セットバックと有効宅地減の金額化
セットバックは「面積が減る」だけでなく「復旧工事が発生する」点まで金額化するのが実務です。
手順は、①2項道路の中心線を特定し、必要後退量を図面に赤入れ、②後退幅×延長で〈面積減〉を算定、③門柱・塀・フェンス・ポスト・給湯器・階段・カーポート柱などの撤去/移設対象を数量表に落とし、④舗装・縁石・側溝・集水桝・勾配の〈復旧仕様〉を決め、⑤見積を2〜3社から取得して最少/最大レンジにします。
面積減は近隣の再建築“可”相場(基準単価)を掛け合わせて機会損失として控除します。旗竿通路では、門柱・メーターボックスや植栽の出っ張りで「有効幅」が2mを割るケースが多いため、入口・中間・接点の3点で実測し、最も狭い値を採用します。
角地・曲線部は隅切りの取り方で後退面積が変わるため、役所協議のメモを写真付きで保存しておくと後日の異論を抑えられます。
【数量化のチェックリスト】
| 項目 | 数量化の方法 | 根拠/注意点 |
|---|---|---|
| 面積減 | 後退幅×延長=後退面積 | 基準単価を掛け、機会損失として控除 |
| 撤去・移設 | 門柱・塀・設備の個数/延長 | 再利用可否を明記、仮設費も計上 |
| 舗装復旧 | 面積と厚み(t)、縁石延長 | 材質(アスファルト/インターロッキング)を指定 |
| 側溝・桝 | 側溝延長、桝個数 | 規格(U字・可変側溝)、勾配を図示 |
- 「面積減(価値)+復旧(工事)」の二層で控除を作る
- 角/曲線は役所回答の写しと赤入れ図で固定→後戻りを防止
私道持分・通行掘削承諾のコスト化
権利系の控除は“範囲の定義”が甘いと金額が暴れます。まず前面通路の地番を特定し、登記事項で所有者・持分・共有者数を確認。
〈持分なし〉なら、持分取得(売買/贈与)か通行地役権の設定を比較します。コストは、清算金+登記費用(登録免許税・司法書士)+場合により測量・分筆費で構成します。
承諾は、通行(歩行/車両/工事車両)、掘削、再掘削、一時占用、復旧基準(舗装厚・材質・段差許容)、期間(原則無期限)、承継条項(所有権移転・相続・賃貸でも効力継続)を条項化し、協力金の相場レンジを提示します。
承諾の範囲が「通行のみ」だと配管新設や更新のたびに再交渉が必要になり、実質的なボトルネックになります。
覚書は短文+別紙(位置図・配管ルート・復旧断面・工程表)で可読性を上げ、協力金は“初回掘削”と“再掘削”を分けて合意するのが実務的です。
【コスト化のフレーム】
| 区分 | 内訳 | 金額設計のポイント |
|---|---|---|
| 持分取得 | 清算金+登記費+測量/分筆 | 面積×基準単価、共有者の同意コストも見込む |
| 承諾(通行) | 工事車両・占用の可否 | 時間帯・幅員制限を明記、警備員費も別建て |
| 承諾(掘削) | 上水/下水/ガス/電気/通信 | 再掘削回数、復旧断面と検収方法を条文化 |
| 承継条項 | 移転・相続後も効力継続 | 通知義務と再署名不要を明記 |
- 「通行のみ」承諾→掘削・再掘削の協力金が後出しで増額
- 承継条項なし→所有者交代のたびに再取得が必要
擁壁・がけ・インフラの是正費用
物理的な是正は、数量の拾い漏れが最終価格に直結します。擁壁は種別(RC/ブロック/石積)と高さ、延長、控え壁、排水(透水・水抜き)の有無を採番し、補修/更新の範囲を数量表に落とします。
がけ条例の離隔不足は、配置転換や規模縮小、法枠工・アンカー・裏込め排水などの選択肢を比較し、工法ごとに概算をレンジ化します。
インフラは、上水・下水・ガス・電気・雨水の各配管延長、掘削深さ、桝数、道路占用の可否、復旧厚みを設定し、私道では承諾範囲(掘削/再掘削/占用)と復旧断面を承諾書に反映します。道路との高低差がある場合は、段差解消やスロープ、U字溝接続の費用も忘れずに。
最後に、是正の要否×費用×工期を一覧化し、売却戦略(現況売り+是正案提示/整備済み売り)で手残り比較を行うと、意思決定が速くなります。
【数量拾いの例】
| 項目 | 数量化のポイント | 実務メモ |
|---|---|---|
| 擁壁補修 | 高さ・延長・控壁・排水の有無 | 配筋探査・点検写真を添付 |
| がけ対策 | 離隔、法枠/アンカーの面積・本数 | 地盤条件で工法を分岐、予備費を設定 |
| 上下水 | 配管延長、深さ、桝数 | 占用許可・復旧厚、接続先を確認 |
| ガス/電気 | 導管/配線ルート、引込柱・メーター | 管理者協議の記録を保存 |
- 数量表+復旧断面図+写真の“三点セット”で見積依頼
- 不確定は予備費と最大レンジを提示→交渉の“あと下がり”防止
収益・代替活用で下支え評価

再建築不可の土地評価では、「今すぐ建て替えられない」前提でも、現況で生むことができるキャッシュフローを見積もることで“下支え(フロア)”の価格を把握できます。
具体的には、月極駐車場・時間貸駐車場・資材置場・コンテナ倉庫・貸地(菜園・ドッグラン等)といった建物を伴わない、または軽微な施設で成立する用途を候補にし、予想収入から維持費・管理費・固定資産税相当・保険・清掃・照明・舗装の減価・空き損(稼働率)等を差し引いた年間純収益(NOI)を算出、地域のCAPレートで還元して下限値を求めます。
並行して「将来、接道是正や位置指定が実現した場合の上振れ価値」も別計算し、現況価値(収益還元)と改善後価値(是正費控除後)を二本立てで比較すると、投資可否や売却戦略の判断がぶれにくくなります。
【下支え評価の流れ】
- 候補用途の選定→法令・騒音・動線・近隣合意の可否を事前確認
- 収支の素案→賃料相場と稼働・費用率を仮置き(レンジで想定)
- NOIの算定→CAPレートで還元しフロア価格を把握
| 要素 | 主な内容 | 評価の要点 |
|---|---|---|
| 収入 | 月極/時間貸料金、台数/区画数、保管料 等 | 需要の季節性・近隣競合・アクセシビリティ |
| 費用 | 舗装・区画線・照明・フェンス、管理/清掃、税・保険 | 初期投資と更新サイクルを費用化 |
| 資本化 | CAPレート(地域×用途×リスク) | 近傍の実勢とリスク調整で設定 |
- 「収益性」だけでなく「近隣許容」と「出入口の安全」を同時検討
- 賃料・稼働・CAP・費用はレンジで置き、上下振れに備える
賃貸・駐車場・倉庫の収支試算
駐車場・簡易倉庫・資材置場は、建築行為を伴わずに運用できる可能性があるため、再建築不可の下支えとして有力です。
収支試算は「シンプルな式」で統一すると比較しやすくなります。年間賃料収入=(単価×区画/台数×稼働率×12)±付帯収入(広告・自販機 など)。
年間費用=(管理委託+清掃+照明電気+巡回/監視+保険+税金+軽微補修)+初期投資の償却相当(舗装・区画線・フェンス・ゲート等の耐用年を按分)。NOI=年間賃料収入−年間費用。
【例:月極駐車場の収支ひな形】
| 項目 | 設定の考え方 | 実務メモ |
|---|---|---|
| 賃料・台数 | 近隣相場×区画数(軽/普通/大型で幅) | 敷地形状で有効台数が変動→実測で確定 |
| 稼働率 | 平日/週末 差、季節性を加味 | オープン直後の立上り期間は控えめに |
| 費用率 | 管理・清掃・照明・保険・税金 | 照明は防犯と近隣配慮のバランスを |
| 初期投資 | 舗装(厚み)・区画線・フェンス等 | 砂利運用の是非は泥跳ね・粉じんで判断 |
- 倉庫/コンテナは「防犯・騒音・夜間搬出入」「消防・保険」の条件を先に確認
- 資材置場は「大型車両の進入・地耐力・粉じん対策」が費用に直結
- 出入口の視距不足→事故リスクで稼働/賃料が下振れ
- 近隣合意不足→クレームで運用制限(台数・時間)が発生
貸地等のCAPレート設定の考え方
CAPレートは「期待利回り=リスクの総和」という視点で決めます。
再建築不可×貸地・駐車場・置場は、建替え自由度や流動性が低いぶん、再建築可の宅地より高めのレートを求められやすいのが一般的です。設定は次の三段で考えると整理されます。
①市場の実勢:近隣の貸地・月極P・低層倉庫の利回りレンジを収集。②個別リスク:接道是正の不確実性、私道承諾の恒常性、災害・地形(がけ・浸水)などを加点/減点。③運用条件:契約期間(短期/中期/長期)、用途の転換可能性、撤去・原状回復コストの重さ。
これらを合算してCAPのレンジを設定し、NOIを割り戻して還元価を求めます。なお、CAPは一つの数字に固定せず、最少/中位/最大の三点で示すと、投資の頑健性が見えやすくなります。
【CAP設定のチェック表】
| 要因 | 上げ要因(CAP↑) | 下げ要因(CAP↓) |
|---|---|---|
| 市場流動性 | 取引が少ない・競合多い | 需要が安定・代替用途が豊富 |
| 法規・権利 | 承諾が限定・更新困難 | 恒常的承諾・位置指定/是正の見込み |
| 物理・災害 | がけ・浸水・狭あい動線 | 平坦・角地・出入口良好 |
| 契約条件 | 短期・原状回復重い | 長期・原状回復軽い |
- 市場実勢→個別リスク→運用条件の順で積み上げる
- レンジ提示と感度分析→賃料±・稼働±・CAP±で再計算
43条許可・位置指定の価値反映
収益還元で現況の下限価値を押さえたら、「接道是正が実現した場合」の上振れ価値を別枠で評価します。手順はシンプルです。
①是正後シナリオを定義(43条許可で建築可、位置指定道路で1項5号化、2項道路セットバック完了 等)。②是正後の開発余地(有効宅地面積・想定建物規模・想定賃料/分譲単価)から“整備後価値”を試算。
③必要コスト(通路拡幅・排水・転回広場・舗装・側溝・外構移設・承諾取得・設計申請・工期による期間コスト)を見積化。④差引価値=整備後価値−総コスト(+リスクバッファ)を算出し、現在価値に割り戻して採用します。
こうして「現況(収益還元)」「改善後(差引価値)」を並べると、是正に踏み込むべきか、現況活用・現況売却を選ぶべきかの判断が明瞭になります。
【二本立ての比較フォーマット】
| 項目 | 現況(収益還元) | 是正後(差引価値) |
|---|---|---|
| 前提 | 月極P/貸地 等・NOI・CAP | 建築可・想定規模・賃料/単価 |
| 価値 | NOI÷CAP=還元価 | 整備後価値−是正/期間コスト |
| リスク | 稼働・賃料・近隣許容 | 同意形成・工期・費用超過 |
- 「現況フロア」と「改善プレミアム」を別表で明示
- 同一スケールで比較(㎡・円/年・月数)→曖昧さを排除
手残りと出口設計で価格を決める

再建築不可の価格は「表面の希望価格」ではなく、「手残り(ネットプロシード)」で意思決定するのが安全です。
手残りは、想定売却代金から〈是正・撤去・測量/登記・残置物〉などの直接費、〈仲介手数料・広告〉などの間接費、〈税金〉、そして見落とされがちな〈期間コスト(売却までの月数×想定利回り)〉を差し引いた金額です。
出口(現金買取・仲介・入札)は価格・期間・条件のバランスが異なるため、同じ前提条件(測量範囲・残置物・是正の有無・免責の幅)で横並びに比較し、どのルートが最も高い“手残り/リスク比”を出すかで選びます。
さらに、最初から単価を一発提示するのではなく、控除や期間コストをレンジ(最少/中位/最大)で表示し、交渉の着地点を事前に共有すると、減額交渉やキャンセルの確率を下げられます。
【設計の基本フロー】
- 出口の候補を3案に絞る→買取/仲介/入札の前提条件を固定
- 費用は数量×仕様×単価で見積→最少/最大レンジで管理
- 期間コストを加味→手残りで意思決定(価格ではなく実質)
| 要素 | 内容 | 実務の要点 |
|---|---|---|
| 価格 | 各出口の提示レンジ | 同条件で横並び比較、免責・現況の扱いを統一 |
| 費用 | 是正/撤去/測量/広告/登記など | 数量表と出典付き単価で裏づけ |
| 期間 | 承諾・役所協議・工事の月数 | 時間価値を利回り換算で計上 |
- “価格→手残り→期間→条件”の順で比較してブレを防ぐ
- 整備済み案/現況案を併記→柔軟に舵切りできる体制に
買取・仲介・入札の比較と使い分け
現金買取・仲介流通・入札(買取保証含む)は、それぞれ強みが異なります。現金買取は「短期・確実・負担軽め」で、契約不適合責任の免責や残置物の現況渡しなど、条件面の柔軟性が得やすい一方、価格は抑えめになる傾向です。
仲介は「上振れ余地」が最も大きく、資料の先出し(道路種別・接道実測・後退線・私道承諾・越境一覧)と、是正案+概算見積の提示により、投資家/実需双方の検討スピードを上げられます。
入札は「短期で上限価格と条件差を把握」でき、要項(免責・承諾・是正・引渡猶予・残置物)の統一により、条件の横並び比較が可能です。
使い分けは、売主の期限(いつまでに現金化か)、前提資料の整備度(承諾・後退線・数量表・見積の精度)、近隣合意/工事可否などの運用条件で決めます。
| 手段 | メリット | 留意点 |
|---|---|---|
| 現金買取 | 最短で資金化・条件がシンプル | 価格は控えめ→相見積と特約比較で補正 |
| 仲介流通 | 上振れ余地・広い買い手層 | 先出し資料と是正案が前提→期間は長め |
| 入札/買取保証 | 短期で上限探索・出口担保 | 要項精度が結果を左右→例外条項に注意 |
- 期限が厳しい→買取/保証。時間に余裕→仲介で上振れ狙い
- 資料が未整備→保証で下限確保。整備済み→入札で上限探索
見積レンジと期間コストの織り込み
見積は“1本値”ではなく、最少/中位/最大のレンジで管理すると交渉の安定性が高まります。
セットバック・外構移設・通路舗装・側溝・擁壁補修・私道承諾(通行/掘削/再掘削)など、数量×復旧仕様×単価で積み上げ、未確定な部分は予備費を別枠で置きます。
期間コストは、売却までの月数に想定利回り(例:年率◯%)を掛け、手残りから控除します。これにより、「仲介で100万円高く売れるが半年長い」ケースと「買取で早期決済」ケースを同一スケールで比較できます。
金融コスト(既存ローンの利息)や機会損失(次案件への投資遅延)も期間コストに含める発想が有効です。
| 項目 | レンジ設計 | 織り込みポイント |
|---|---|---|
| 是正費 | 最少/中位/最大(数量・仕様・単価で差) | 見積2〜3社、出典併記、予備費を別枠 |
| 権利費 | 承諾協力金・登記費・地役権設定費 | 承継条項や再掘削有無で幅が出る |
| 期間コスト | 月数×年率(利回り/金利/機会損失) | 買取と仲介の所要月数差を反映 |
- “最少値”だけで売出→後半の追加費用で目減り
- 期間コストの未計上→高値成約でも実質手残りが逆転
価格帯提示と内見用開示パッケージ
価格は「一点」ではなく「帯」で提示し、帯の根拠を資料で同時に開示すると、買い手の納得感とスピードが上がります。
具体的には、〈基準相場〉〈個別控除(最少/最大)〉〈期間コスト〉を並べた価格分解表を用意し、整備済み案(是正後)と現況案の二本立てで価格帯を提示します。
内見用の開示パッケージは、道路台帳・指定道路図・幅員証明、接道実測写真、後退線入り配置図、数量表、是正見積(レンジ)、私道承諾のドラフト(通行/掘削/再掘削/承継/復旧断面)、越境一覧、工程表(承諾→設計→工事→引渡)をワンセットにし、PDFで事前配布します。
写真にはメジャーやチョークで寸法を写し込み、図面は赤入れで後退・隅切りを明示。広告原稿は「弱点→解決案→費用レンジ→工程→手残りの考え方」の順で構成すると、終盤の減額交渉が起きにくくなります。
| 資料 | 目的 | 開示のコツ |
|---|---|---|
| 価格分解表 | 価格帯の根拠を可視化 | 基準/控除/期間の三層構造で提示 |
| 後退・承諾セット | 接道/権利の確からしさを提示 | 赤入れ図+ドラフト+工程で実現性を示す |
| 見積レンジ | 不確実性を金額化 | 最少/最大の二本立て、出典を併記 |
- “帯+根拠資料”を同時提示→判断が速く、指値が縮小
- 現況案/整備案の二表運用→買い手の資金・時間に合わせて選べる
まとめ
評価は①基準相場(路線価+成約)→②個別控除(後退・権利・是正費)→③収益還元→④出口別手残り比較の順で進めるとぶれません。
数量表と見積レンジを添え、価格帯と開示パッケージを同時提示すれば、交渉が短くなり納得感のある決定に近づきます。