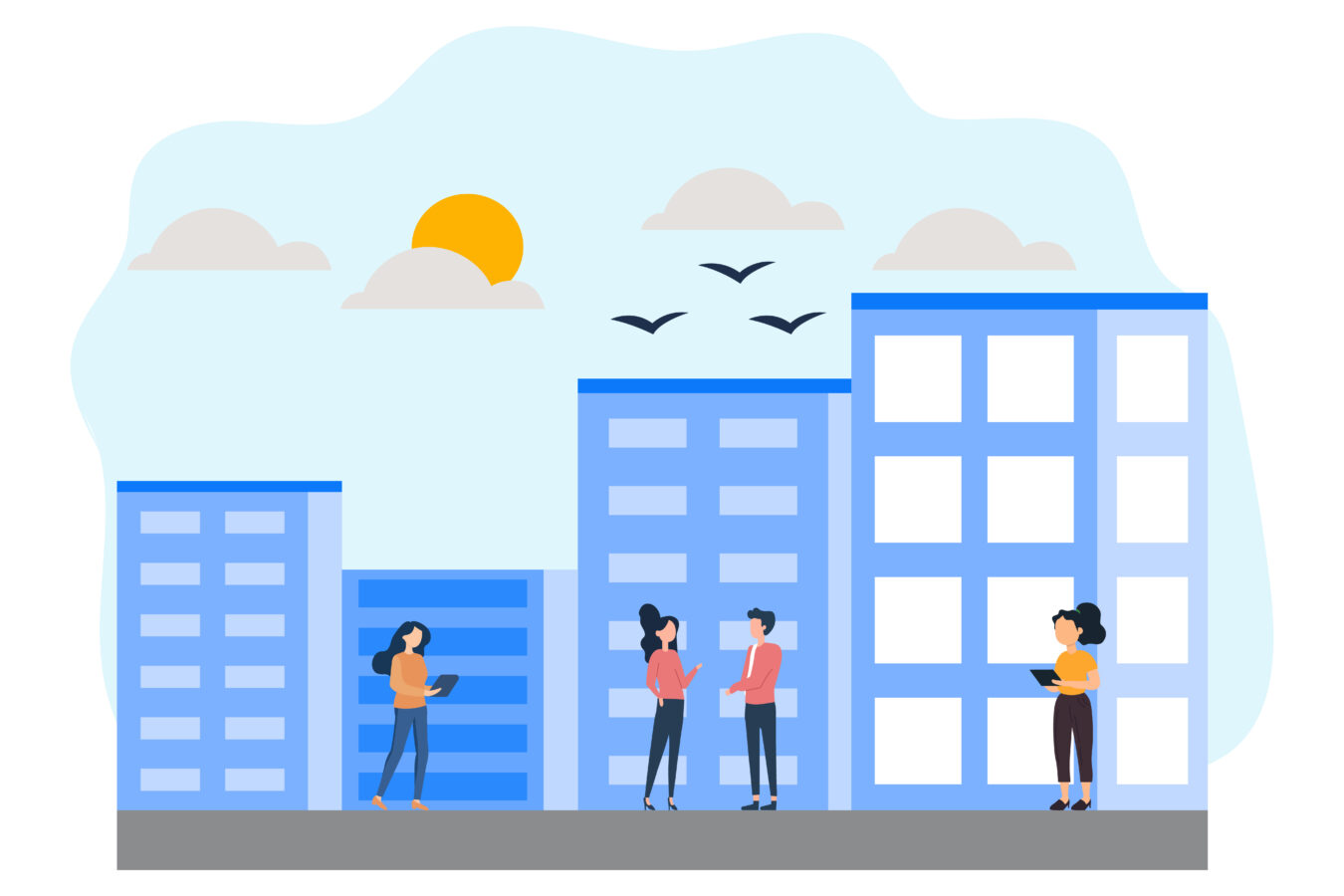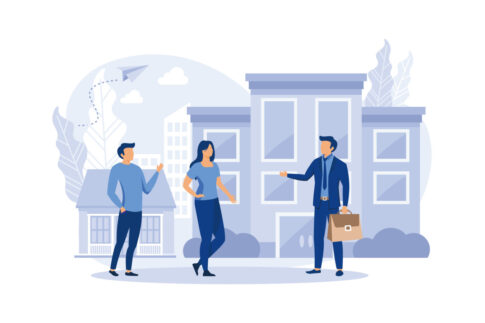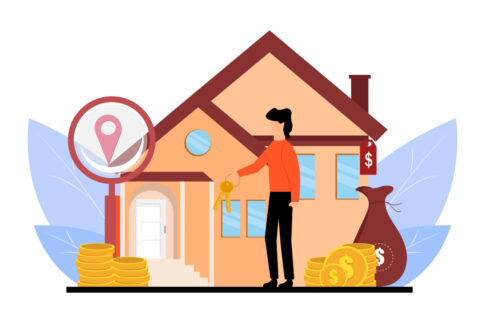築古の一棟アパートは、安く購入してリフォームを加えることで高利回りを狙える魅力があります。しかし、築年数が古い分、大規模修繕や設備更新など手間と費用がかかる点は否めません。
本記事では、築古物件ならではのメリット・デメリットから、購入前のチェックポイントや運営費用の考え方、さらには立地を活かした建て替え戦略までを幅広く解説しています。成功のカギとなるリスク管理と、長期的な資産価値向上へのヒントをお届けします。
目次
築古一棟アパートのメリット・デメリット

築古一棟アパートは、比較的リーズナブルな価格で購入できる点や、リフォーム次第では高い利回りを狙える点が魅力的です。一方で、築年数が古いために大規模修繕や設備交換が必要になるケースが多く、将来的な運営費用がかさんでしまうリスクも否めません。
さらに、老朽化した物件は金融機関の融資審査が厳しくなる場合もあり、思うように資金計画を組めない可能性があります。それでも、エリアの需要が十分に見込める場所であれば、初期投資を抑えつつ家賃収入を得られるメリットは大きいです。
たとえば、築30年以上のアパートを相場より安く手に入れ、その浮いた資金をリフォームや設備更新に充てることで入居付けをスムーズにし、高稼働率を維持できる可能性が高まります。
とはいえ、築古物件の購入には慎重な下調べが欠かせません。周辺の家賃相場と照らし合わせて、購入価格とリフォーム費を加味した上でも利益が出るのかを見極める必要があります。
特に、物件自体が耐震基準を満たしているかどうか、老朽化による雨漏りやシロアリ被害の有無など、建物の構造面での不安要素を洗い出すことが重要です。また、築古物件の魅力を存分に活かすためには、長期的な視点で修繕プランを組み、賃貸需要を保つ工夫が求められます。
周辺住民の生活環境に合わせて、部屋数や間取り、設備を最適化すれば、築年数のハンデをカバーできる可能性は十分にあります。以下のリストに、築古一棟アパートを検討する際の代表的なメリット・デメリットをまとめました。
- 【メリット】購入価格が安い分、初期投資を抑えられる
- 【メリット】リフォームで物件価値を高め、高利回りを目指せる
- 【デメリット】老朽化に伴う修繕費が大きくなる
- 【デメリット】融資審査が厳しく、借入条件が悪化する可能性
このように、築古一棟アパートには魅力とリスクの両面が存在します。物件選びや修繕計画、そして資金調達方法を慎重に検討することで、デメリットを最小限に抑えつつ安定した収益を得る道が開けるでしょう。
低価格と高利回りの魅力
築古一棟アパートの大きな魅力の一つが「低価格でも高利回りを狙える」点です。新築や築浅物件と比較すると、物件価格が大幅に抑えられるため、自己資金が少なくても投資に踏み切りやすいメリットがあります。
たとえば、都心部で築浅アパートを購入しようとすると1億円前後の物件も珍しくありませんが、築古であれば5,000万円台やそれ以下で購入できる可能性もあります。さらに、空室リスクを適切にコントロールすれば、取得価格に対する年間家賃収入の割合(利回り)が高まるため、結果としてキャッシュフローを潤沢に確保できるケースがあるのです。
この低価格と高利回りの組み合わせは、特に資金に限りのある個人投資家にとって非常に魅力的ですが、一方で「安い物件には安いなりの理由がある」ことを忘れてはいけません。
築年数が古いということは、建物の基礎部分や構造体、給排水管などが劣化しているリスクが高いです。実際には購入後すぐに大規模な修繕が必要になる場合もあり、その分コストがかさんで利回りが下がってしまう可能性も考慮する必要があります。
| 要素 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|
| 物件価格 | 初期投資を抑えやすい | 築古は修繕費が高額になる可能性 |
| 利回り | 高い利回りが期待できる | 実質利回りは修繕費で下がるケースも |
さらに、エリアによっては築古でも高い需要が見込める場所があります。たとえば、学生が多い地域やビジネス街へのアクセスが良いところなら、多少古い物件でもリーズナブルな家賃を設定すれば入居者が集まりやすい傾向にあるのです。
こうしたエリア選定とリフォームの工夫によって、外観や設備を改善しつつ適正な賃料を維持できれば、大きな収益を得るチャンスを手にできます。一方、人口減少が著しい地方では、いくら物件価格が安くても賃貸需要自体が低迷している可能性があるため、投資判断には十分な調査が欠かせません。
- 需要が安定しているエリアをリサーチ
- リフォーム費用も含めた総投資額で利回りを計算
- 耐震性能や水回りの状態など構造面を慎重に確認
結局のところ、築古一棟アパートを安く手に入れるだけでなく、どのように改修・運営していくかが高利回りを実現するカギとなります。
購入前の調査段階でリフォームのコストや予想される修繕費をしっかりと織り込んだうえで、シミュレーションを行うことが不可欠です。初期費用を抑えて高収益を狙うという魅力は大きいものの、リスクマネジメントを怠ると予想外の出費に苦しむことにもなりかねません。
避けられない修繕リスク
築古物件を購入する以上、避けて通れないのが修繕リスクです。築年数が経過しているため、屋根や外壁の傷み、給排水設備の老朽化、防水シートの劣化など、多岐にわたる箇所でトラブルが発生しやすくなります。
たとえば、築30年を超えるアパートの場合、木造ならシロアリ被害や腐朽、鉄骨造でも錆や腐食といった問題が起こりやすいです。こうした修繕を放置すれば、雨漏りや耐久性の低下につながり、入居者からのクレームが増えて空室率が高まる恐れがあるでしょう。
また、オーナー自身の費用負担が一時的に大きくなるだけでなく、入居者の退去が相次ぐとキャッシュフローの悪化を招き、最悪の場合は融資返済に支障が出るリスクも考えられます。
修繕リスクに対処するためには、あらかじめどの程度の修繕費が必要になるのかを見積もっておくことが大切です。具体的には、大規模修繕の頻度を10年に一度、もしくは15年に一度など一定のサイクルで想定し、その間にも計画的なメンテナンスを行うプランを立てます。
特に水回りや共用部、外壁や屋上などの劣化は建物全体の印象や機能性に直結するため、早期発見・早期対応が肝心です。空室期間を活かして部分的にリフォームを実施する方法もありますが、工事期間中の騒音や配置の問題など、入居者への負担にも気を配る必要があります。
- 老朽化した給排水管や防水シートは高額修繕の可能性大
- 屋上の雨漏り対策などを怠ると建物全体に悪影響が及ぶ
また、修繕費の負担を抑えるためには、複数の業者から見積もりを取り、内容と費用を比較検討することが重要です。中には「安い工事費を提示して実際の仕上がりが不十分」というケースもあるため、業者の実績や評判をしっかり確認しましょう。
さらに、タイミングよくリフォームを行えば家賃を上げられる可能性もあります。たとえば、水回りや内装を一新することで入居者の満足度が高まれば、賃料引き上げと同時に空室対策にもなるという好循環を生み出せるのです。いずれにせよ、築古一棟アパートを手がける際には、修繕リスクを「いかにコントロールするか」が投資成功の大きな鍵を握るといえます。
購入前に確認したい築古物件の要注意ポイント

築古物件は、魅力的な価格と高利回りの可能性がある反面、建物の老朽化や設備の劣化など、購入後に大きな負担が発生するリスクがあります。そのため、契約前の段階で「どの部分にどの程度の修繕が必要なのか」を把握し、想定されるコストをなるべく正確に見積もっておくことが大切です。
特に、一棟アパートは部屋数が多い分、修繕箇所が増えやすく、躯体構造から水回りまで複数の要素をチェックする必要があります。
たとえば、築年数が古ければ外壁塗装の剥がれやクラック、屋上の防水シート破損などが見られるかもしれませんし、構造そのものが耐震基準を満たしていない場合もあります。これらの不備がある物件は購入価格が安い傾向にありますが、その分、思った以上に改修費用がかかるリスクが高いです。
また、購入後すぐに大規模修繕が必要となれば、賃貸経営の初期段階からキャッシュフローが圧迫される可能性があります。逆に、事前の調査で問題が少ないようであれば、最小限のリフォームで稼働率を高められるでしょう。
その差は非常に大きいため、必ず専門家に依頼して建物診断(インスペクション)を実施するのがおすすめです。購入の直前までに内見やヒアリングを重ね、共用部の状態や過去の修繕履歴などをチェックしておくと、不意のトラブルを回避しやすくなります。以下では、築古物件で特に注意したいポイントをまとめました。
- 耐震性の有無(新耐震基準を満たしているか)
- 雨漏りやカビの発生など屋上・外壁の状態
- 躯体構造(木造・鉄骨造・RC造)の傷み具合
- 設備関連(給排水管やガス管など)の使用年数
- 過去の修繕履歴や費用の有無
このような情報を総合的に判断し、どの程度の追加投資が必要か試算することで、購入後の収益シミュレーションをより正確に組み立てられます。
仮に大きな修繕が必要とわかっていても、物件価格とのバランスが取れていれば十分に投資価値があるケースもあるため、安直に「築古はリスクが高い」と避けるのではなく、メリットとデメリットを客観的に見極めることが重要です。
大規模修繕とリフォームの見極め
築古の一棟アパートを購入する際は、「大規模修繕が必要な状態なのか、それとも部分的なリフォームで対応可能か」を見極めることが収益性を大きく左右します。大規模修繕とは、屋上防水や外壁塗装、階段や共用廊下の補修など、建物の安全性や耐久性に直結する改修を指します。
これらを怠ると、雨漏りや構造の劣化が進行し、賃貸経営どころか資産価値そのものが大きく下がりかねません。一方、リフォームは部屋の内装や設備の更新、間取り変更など、入居者目線で住み心地を向上させる工事が中心となります。
- 外壁のひび割れや塗装剥がれの修繕
- 屋上やベランダの防水シート貼り替え
- 給排水管の交換・補修
大規模修繕の費用は数百万円から数千万円にのぼるケースが多く、建物の構造や築年数によっては、購入価格よりも高くなることもあり得ます。たとえば、築30年超の木造アパートでは、外壁の修繕や耐震補強、基礎部分の補修などをまとめて行う必要がある場合も珍しくありません。
こうした作業を一度に行うか、段階的に進めるかによって費用や入居者への影響も変わるため、購入前に全体像を把握しておくことが欠かせません。また、金融機関によっては大規模修繕の資金を別途融資してくれるケースもありますが、計画や見積書の提出を求められるため、準備に時間がかかることを覚悟しておきましょう。
一方で、リフォームは家賃アップや空室率の低減に直結する場合が多く、施策次第では投資リターンを大きく伸ばすチャンスとなります。たとえば、浴室やキッチンなどの水回りを最新設備に交換する、部屋の壁紙を明るいトーンに変える、フローリングをリニューアルするといった工事は、入居者から見れば「古いアパート」ではなく「手入れが行き届いた住まい」という印象を与えやすくなります。
特に単身者向けの物件では、洗濯機置き場やインターネット環境などの機能面も重視されるため、最低限の設備投資だけで意外なほど人気物件に変身する可能性もあるのです。
- リフォーム工事をどの範囲まで行うか明確に決める
- コストと見込める家賃アップのバランスを検討
- 競合物件よりも優位性を確保できる内容かを確認
このように、大規模修繕とリフォームを正しく見極められれば、築古物件でも充分に高い収益を狙うことができます。購入前の段階で建物診断をしっかり行い、必要な改修リストと予算を洗い出したうえで、「どこまで費用をかければ利回りが上がるのか」を具体的に試算することが肝心です。
水回りと内装の劣化状況
築古物件を検討する際、多くの投資家が最も気にするのが「水回りと内装の状態」です。なぜなら、これらは直接的に入居者の快適性に影響し、物件の印象を大きく左右するからです。
例えば、キッチンや浴室、トイレなどが古いタイプの設備だと、若い世代の入居者から敬遠されがちですし、汚れやカビが目立っている場合は内見時点で契約をためらわれる可能性が高くなります。一方、しっかりと清掃やリフォームが施されている物件は、「築古だけど住んでみると快適そう」というポジティブな印象を与えられます。
| 項目 | チェックポイント | 対策例 |
|---|---|---|
| キッチン | 水漏れや油汚れ、換気扇の動作 | シンク・コンロの交換、収納スペースの追加 |
| 浴室 | カビの発生、排水の詰まり、浴槽の劣化 | 浴槽・壁材の交換、防カビコーティング |
| トイレ | 水漏れ、臭いの有無、タンクの劣化 | 便器・ウォシュレットの交換 |
また、内装に関しては壁紙の剥がれや床のきしみなど、経年劣化が進行しているケースも珍しくありません。こういった軽微なトラブルであっても、入居者に与える印象は決して良いものではないため、ある程度のリフォーム予算を組んでおくのがおすすめです。
特にリビングや玄関など、部屋の第一印象を左右するエリアは入念にチェックしましょう。明るい色合いのクロスやフローリングを採用するだけで、築古物件のイメージを大きく変えられる場合もあります。
- 汚れやカビが目立つと空室リスクが高まる
- 設備のグレードアップで家賃アップが狙える
さらに、水回りや内装の不備は、トラブルが起きるとすぐにクレームや修繕費用につながる傾向があります。特に集合住宅では、漏水や排水管の詰まりが階下へ被害を及ぼす可能性もあるため、厄介な問題に発展しかねません。
したがって、購入前に専門家とともに現地調査を行い、配管の耐用年数や劣化状況を把握することが欠かせないのです。このように、築古物件だからこそ水回りと内装の点検・改善が重要な意味を持ち、適切な対応をすることで入居者の満足度を高め、安定した賃貸経営につなげられるでしょう。
築古アパートの運営費用と資金計画


築古アパートを購入する場合、物件価格は安く抑えられることが多い一方、長年の使用による劣化が進んでいるため、定期的な修繕費やメンテナンス費が増える傾向にあります。とりわけ、屋根や外壁、防水シート、給排水管といった建物の基礎部分に関わる修繕が必要になると、大きな資金負担が一度に発生する可能性があるのです。
そのため、築年数や状態に合わせて、運営費用がどの程度かかるのかをシミュレーションし、資金計画をしっかり立てることが欠かせません。また、空室リスクを考慮すると、入居者が退去してからのリフォームや設備更新のための予備費を予め確保しておくと安心です。
さらに、築古物件は銀行の融資審査で評価が低くなる場合があり、貸し出し条件が厳しくなる傾向も見られます。金利が高めに設定されることもあるため、購入後のキャッシュフローを圧迫しやすいです。その一方、築古ならではのリフォーム効果によって家賃アップが見込めるケースも少なくありません。
外観や共用部の印象を大きく変えられる大規模修繕を実施して、エリア内の競合物件よりも魅力的な状態にアップグレードすれば、家賃相場から少し高めの設定でも入居率を維持できる可能性があります。こうしたリスクとリターンを冷静に見極めながら、長期的な運営費用と収益バランスを考慮した資金計画を組み立てることが、築古アパート投資の成功を左右するのです。
- 融資金利や返済期間を複数パターンで試算
- 予想外の修繕費に備えてリフォーム積立を設定
- 家賃アップの施策が実行可能かを事前に調査
また、オーナーのライフスタイルや投資目的によって、どの程度の期間保有するかが変わるため、運用プランに合わせた計画を立てることも大切です。短期売却を視野に入れるなら、設備投資を最小限に抑え、表面利回りを魅力的に見せる戦略が有効な場合もあります。
逆に長期保有を前提とするなら、初期の段階でしっかりと大規模修繕を行い、安定的な賃貸経営で継続的にキャッシュフローを得る方が結果的にリスクを抑えられるでしょう。こうした運営費用と資金計画のバランスを上手にコントロールできれば、築古アパートでも十分に魅力ある投資案件に仕上げることが可能です。
築浅よりコストが増える理由
築古アパートは、その名のとおり建物の老朽化が進んでいるため、実際に運用を始めてみると築浅物件よりもコスト面で不利になることが多いです。最も分かりやすい例が修繕費で、屋根や外壁、防水シートなどのメンテナンスはもとより、空調や給排水などの設備更新にもお金がかかります。
特に築30年を超える木造アパートだと、シロアリ被害や腐朽が見つかるリスクがあり、補修工事が思いのほか大掛かりになるケースが少なくありません。さらに、古い建物は入居者が敬遠しがちというデメリットもあり、家賃を下げて入居促進を図る必要がある場合には、収益性が低下してしまう可能性があります。
こうした追加コストは、購入直後から発生することも珍しくなく、融資を受ける際にこれらのリスクを考慮した資金計画を組まないと、資金繰りが苦しくなる危険性が高いです。
そもそも築古アパートは金融機関の評価が低くなりがちで、融資を受けにくかったり、金利が高めに設定される場合もあります。つまり、投資家が想定していたよりも月々のローン返済額が増え、キャッシュフローの確保が難しくなるリスクを織り込んでおく必要があるのです。
| 項目 | 築浅物件 | 築古物件 |
|---|---|---|
| 修繕費 | 当面は軽微 コストも少ない |
高額になる 急な出費が発生 |
| 融資条件 | 評価されやすい 金利低め |
審査厳しい 金利高め |
| 家賃設定 | 比較的高めでも需要あり | 相場よりやや下げる必要も |
ただし、このようにコストが増えがちな築古アパートであっても、適切な修繕やリフォームを行うことで家賃アップを狙えたり、購入価格が安いことから高い利回りを確保しやすいというメリットも見逃せません。ビジネス街や大学が近い人気エリアであれば、築年数の古さよりも家賃の安さを求める入居者が多く、満室を維持しやすい可能性もあります。
最終的には「どの程度リスクを取れるか」と「どのエリアで物件を運用するのか」によって、築古アパートの運営コストと収益力のバランスが大きく変わってくるのです。したがって、築古アパート特有のコスト増を正しく理解し、その分を補うだけのリターンを狙えるプランを立てることが、失敗を避けるための鍵となります。
購入価格とのバランスを考える
築古アパートを検討する際に最も重要なのが、「購入価格と運営コストのバランスをどう取るか」という点です。物件が安く購入できれば、その分、利回りを高く設定しやすい反面、老朽化した建物の修繕費やリフォーム費用で初期コストが想定以上に膨らむ可能性があります。
特に、大規模修繕が控えている場合は、建物の耐震補強や給排水管の交換など、数百万円〜数千万円の出費になることも珍しくありません。こうしたコストをすべて加味しても、「最終的なキャッシュフローがプラスになるか」を検証するのが投資家としての責務といえます。
- 購入価格と修繕費用を合わせた総投資額の試算
- 利回り計算時に空室率・修繕予算を保守的に設定
- 周辺相場より高めの家賃設定が可能か調査
一方、物件の立地や需要状況によっては、築古でも家賃を下げずに高稼働率を維持できるケースもあります。例えば、駅から徒歩5分以内の好立地だったり、学校や病院が充実しているエリアは、人の流入が見込めるため、多少の築年数を気にしない入居者も多いです。また、近隣に競合となる新築物件が少なければ、外観や内装を適切にリフォームするだけで、競争力を確保できる可能性があります。
逆に、立地条件が悪い物件や人口減少が進むエリアでは、購入価格が安くても、空室率が高止まりしてしまうリスクが考えられます。
その結果、毎月の家賃収入が期待ほど伸びず、修繕費やローン返済に苦労する事態に陥る可能性もあるのです。こうした観点から、購入価格の安さだけに飛びつくのではなく、「総投資額から得られる収益が長期的にプラスになるか」を見極めるのが一棟アパート投資のポイントといえます。
- 周辺の家賃相場と需給バランスを調査し、キャッシュフローをシミュレーション
- 築古物件の改修工事で家賃アップを狙えるかを見極め
- 人口動態や再開発計画など将来のエリア変化も視野に入れる
このように、購入価格だけでなく、修繕・リフォーム費用や将来的な空室率、家賃設定を総合的に判断することで、築古アパートでも十分に利益を狙うことが可能です。
最終的には、投資期間やリスク許容度に応じて、どの程度の資金を改修や管理に回せるかを考える必要があります。安価な購入価格と長期的な運営コストを天秤にかけながら、計画的に投資判断を進めることが成功への近道といえるでしょう。
立地を活かして建て替えも視野に入れる

築古アパートといっても、立地によっては建て替えを含めた新たな活用方法が大いに期待できます。特に都市部や需要が高い駅近エリアでは、築古物件をそのまま運用するだけでなく、「将来的に建て替えて資産価値を高める」という選択肢が有力です。
例えば築40年を超える木造アパートであれば、耐震性能や管理コストの観点から、いずれは新築への建て替えを検討せざるを得ない状況になる可能性があります。このタイミングをどう捉えるかが、投資成果を左右する大きなポイントとなるのです。
ただし、建て替えには多額の資金と時間を要するため、安易に着手するとキャッシュフローが途絶えるリスクもあります。
入居者の退去が進んだタイミングや、ローンの完済時期などを見計らって計画を練ることが大切です。また、建物を新築するにあたっては法的な規制(建ぺい率や容積率など)や近隣住民との協議が絡んでくることも多いため、事前に自治体や専門家に相談しておくとスムーズに進められます。
- 現在の建物の耐震性能や修繕費の負担状況
- 建て替え後の需要と賃料相場の見込み
- ローン返済計画と自己資金の確保
一方で、立地が良くない場合は、建て替えによる家賃アップを期待しても、需要不足のため思ったほど収益が伸びない可能性もあります。
そうした場合は、リフォームや小規模改修で地道に入居率を維持しつつ、ローン返済が進むのを待つほうが堅実かもしれません。結局のところ、建て替えが有効かどうかは物件の所在地や周辺環境、将来的な都市計画など多岐にわたる要素を総合的に判断しなければならないのです。
将来性の高いエリアの選び方
築古アパートでも高い賃貸需要を維持し、場合によっては建て替えを視野に入れて大きな収益を得られるかどうかは、エリア選びにかかっているといっても過言ではありません。
具体的には、人口が増えている都市圏や再開発が進んでいる地域、大学や大企業がある場所などに注目すると、長期的に需要が続くケースが多いです。例えば、地方であっても県庁所在地や交通の要衝となる駅周辺は一定の集客力がありますし、大型ショッピングモールの進出などで生活の利便性が向上しているエリアも狙い目です。
- 人口動態:市区町村の人口移動データをチェック
- 再開発計画:自治体や地元新聞の情報で把握
- 主要企業・大学:通勤通学で需要が安定
- 交通インフラ:駅や高速道路の整備状況
さらに、将来性の高いエリアを見極めるためには、公的資料や統計データだけでなく、現地に足を運んで街の雰囲気や住民の動向を肌で感じることが欠かせません。
たとえば、コンビニやドラッグストア、飲食店など日常の利便施設が充実しているエリアは、単身者やファミリー層を問わず人気が高まる傾向にあります。逆に、空き店舗が目立ったり、シャッター商店街化が進んでいる地域では、たとえ築浅物件であっても空室リスクが高まる可能性があるのです。
- 都心部でも地域差が大きいため、細かい区画単位で分析
- 過去の地価動向だけでなく今後の開発計画も把握
また、将来性が高いエリアであっても、物件そのものが古すぎる場合は大幅なリフォームや建て替えを検討しないと入居者を確保しにくいケースが生じます。
こうしたポイントをきちんと押さえ、購入時の価格と将来的な改修費用、そして期待される家賃アップを総合的に見極めるのが重要なのです。結果として、築古アパートでも好立地を選べば十分に高い収益を期待できるうえ、将来的に建て替えを行うことでさらなる利回り向上を狙うことも可能となります。
出口戦略と再投資プランの重要性
築古アパート投資では、入口である「購入時点」の判断だけでなく、「出口戦略」をどのように描くかが成功に大きく影響します。
例えば、築年数がさらに進んで耐震性能の問題や修繕費の負担が無視できなくなってきた段階で売却を検討するのか、それとも思い切って建て替えを行い、新築物件として再投資を進めるのか、といった選択肢を早めに整理しておくと慌てずに対応できるでしょう。特に、ローン返済が完了した後や不動産市況が上向きのタイミングで売却すれば、物件の価値が高まっている分、大きな利益を得られる可能性があります。
一方、建て替えを選ぶ場合は、建設期間中に家賃収入が途絶える点や、新たな融資枠をどう確保するかなど、資金面でのハードルが高まることを意識しておく必要があります。
さらに、建物を新築するなら、単に同じアパートを再建築するだけでなく、需要が高い間取りや先進的な設備を取り入れることで、賃貸市場での競争力を一段と強化できるでしょう。
| 出口戦略 | 概要 | メリットと課題 |
|---|---|---|
| 売却 | 築古のまま、または軽度のリフォーム後に売りに出す | 利益確定が早いが 修繕リスクを抱えたまま売ると価格が下がる |
| 建て替え | 新築物件として再投資 高い家賃収入を狙う |
家賃収入が止まる 資金調達のハードルが上がる |
| リノベーション | 大規模改修で設備を一新 家賃アップと空室率低減 |
費用が嵩む 工事期間中の家賃収入が減少 |
また、出口戦略を考える際には、投資期間やライフステージに合わせて適切な手を打つことが求められます。例えば、老後の安定収入を確保するために長期保有を目指すなら、早めに大規模修繕を行って築古でも魅力的な物件へ改良することが重要になりますし、一方で短期間で売却益を狙いたいなら、立地条件が良く需要が高いエリアを選ぶ必要があるでしょう。
このように、最初から「いつ、どうやって物件を手放すか」「再投資のタイミングはいつか」を明確にしておくことで、築古アパートのリスクをコントロールし、長期的な資産形成を有利に進めることができるのです。
まとめ
築古の一棟アパート投資は、物件価格を抑えて高利回りを狙える反面、修繕費やリフォーム費など運営コストが増大しやすいのが特徴です。入念な物件調査や将来の大規模修繕を視野に入れた資金計画が不可欠といえます。
また、立地条件が良ければ、建て替えや再投資を通じてさらなる価値向上を目指すのも有効な手段。築古物件を賢く選択し、適切にメンテナンス・運用することで、長期的に安定した収益を確保する可能性が高まるでしょう。